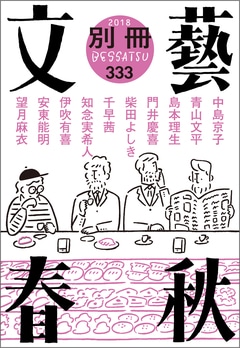1
「胃袋、ふたつあるみたいね」
「そうですか」
村上沙月は軽く受け流して、残った稲荷寿司を口に放り込んだ。
「これも食べてくれない?」
向いに座る古城美沙巡査部長が浮かない顔で、ソースのかかったコロッケを箸で指す。
「ラーメンと稲荷寿司って、食べ合わせが悪い気がするけどな」
「そうですか、わたし好きですけど」
げんなりした顔で見つめる古城の視線を気にもとめず、沙月は残った麺をひと息にすすった。
正午前なので、食堂はまだ半分ほどしか埋まっていない。
「あの、まだ落ちませんか……?」
沙月は上目遣いで訊いてみた。
とたんに古城の顔が曇った。
四日前、暴力団員に恐喝されたと歌舞伎町のホストが、新宿署に駆け込んできた。任意で呼び出された暴力団員の事情聴取を、オジョウこと古城が買って出た。土日も出勤して聴取を続けているが、月曜日のきょうになっても、男は恐喝を認めていないようだった。
恐喝していた男は、被害者の川島がかつて同棲していた女の知り合いで、その女からも事情聴取しているようだ。男女間のドロドロした事情もあるらしい。
古城は刑事課の先輩で同じ係だ。ブラウンのワンピースの上に、テーラードジャケットをふんわり肩に載せている。三十三歳にしては、肌がきめ細かい美人だ。取調室でこんな刑事と向き合う被疑者は何を思うのだろう。
古城の話に相づちを打っていると、はたと気づいたように、
「あっ、ごめん、ミヤちゃんに愚痴っちゃったね」
と口にした。
三宅島の二文字を取って、ミヤと呼ばれたりもする。正式にはまだ刑事見習いの身だ。
「とんでもないです」
そう言って、沙月は窓の外を見やった。
新宿の高層ビルが目に入ってくる。
故郷の三宅島には三階建て以上のビルはない。日本一の繁華街の歌舞伎町を抱え、人口密度は何と四百倍――。その狭いエリアで人が押し合いへし合い生きている。都会といえばそれまでだが、それだけではない。ここは人を吸い寄せる磁力のようなものを発している街なのだ。
新宿署の刑事課に配属されてまだ五カ月あまり。茨城の国立大学を出て、警視庁に入庁し一年と二カ月。半年間の警察学校を無事卒業したものの、卒配(卒業配置)の希望先として書いた五つの警察署ではなく、新宿署に配属になった。
古城が食堂横の入り口に目を向けた。エレベーターの前に、筒見康太巡査部長がいた。首をかしげ、しきりとこちらに来いというような仕草をしている。
「何かあったみたいよ」
古城に促され、沙月はトレーもそのままに席を立った。
筒見と合流すると、ちょうど隣のエレベーターが開いた。あわてて、乗り込む。
「ホテルで変死。見分に行くから」