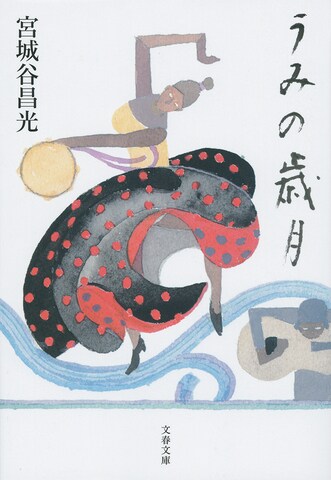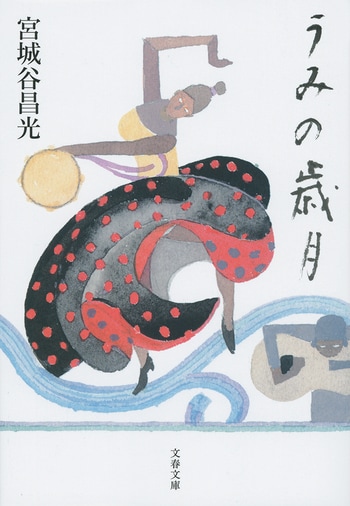著者は「小さな回想」のなかで、「四十歳をすぎたあと、もう小説家志望をやめようと深刻に考えはじめ」、「志を棄てるための支度(したく)」としてこれを書いた、といっている。そして、この作品は、「人の精神に活力を与えるものではないが、生活者として私がぎりぎりのところに立っていた証左(しょうさ)になろう」とも。
一行一節に本物のリアリティがこもっているから、小説としてはいかにも重苦しい。明敏な宮城谷氏はそのことに十分に気がついていながら、これを書いた。その機微が右のような回想の言葉になったのだろう。
「バラの季節」は、読むことが不思議な体験だった。著者は、ツルと美緒、二人の女性が悟の前に現れるその場面(シーン)に文章を集中する。時間を無視したかのようなその場面はなんともいえず艶やかで、読者を魅了せずにはおかない。
しかし、ツルも美緒も、悟の知らない現実の時間の流れに生きている。悟がそれを知ろうとしないことで、恋情は不思議な抽象性をおびる。二人の女性の時間による変化をたどらない大胆さに、私は驚き、不思議な魅力を覚えた。
「秋浦」は、芸妓である藤子の立ち居ふるまいがひとつひとつ肉体をもっていて、そのリアリティがみごとである。何か思い屈することあって河三三谷(みかわみや)に戻ってきた「彼」が、藤子とつきあうとき、藤子のその肉体がふっと薄れて、幻像のように抽象性をおびるときがある。藤子は、日常と非日常の、二つの世界を往ったり来たりするかのよう。著者が、「小さな回想」のなかで、「よくよく読んでみると、この作品は泉鏡花的である」というのは、さすがに正確な見方であると思われた。
ただし文体としては、意味をはっきりと現さないまま人間の生理や感情を包んで表現するところが、川端康成的。その点を別にすれば、虚と実が往き来するこの作品は、きわどいだけに魅力的であり、むろん凡手のできることではない。ただこの世界をつきつめてゆくかどうかは、作家の精神のありようにかかっている。置屋で身をもて余している芸妓の、いわば薄明の世界にいる姿に私はたしかに心惹かれた。
「みずうみ」は、「オール讀物」(一九九二年二月号)に掲載された掌篇である。
高倉夫妻が、二月中旬、奥浜名の猪鼻湖の宿に一泊する話である。何も起らない。風景が滑るように変化し、ところどころにある花の姿が語られるだけ。夫妻が運営する学習塾について語られているから、宮城谷夫妻のその時期の小さな旅が映っているのだろう。
静かすぎるほど、静かな散文。一組の夫婦が生きている世界の深さが、その静けさをつくりだしているに違いない。私はこの掌篇に感動した。