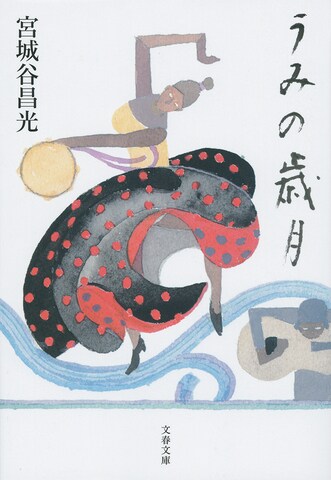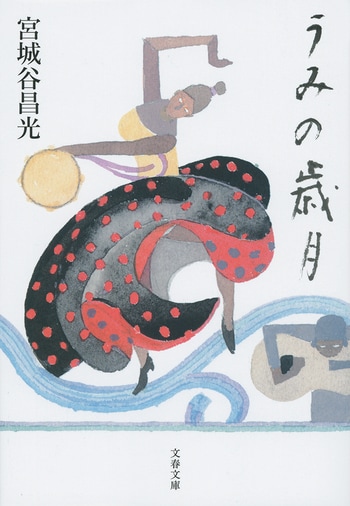一九六三(昭和三十八)年、早稲田大学文学部英文科に入学。そして六七年に大学を卒業するのだが、大学在学中に小説を書かなかった。書かなかったと特記するのは、郷里・蒲郡に近い豊橋市の時習館高校一年のとき、十五歳の少年は将来作家になろうと決心したからである。
それにもかかわらず、大学のときは小説を書かなかった。読むことに専心しようと、これまた心に決めたのである。といっても、関心の中心は詩と批評にあり、「小説というのは面白くない」と思っていたと、かつてインタビューで語っている。
といっても作家になる決心が崩れてしまったわけではない。大学を卒業して一年後に出版社の新評社に就職、月刊誌「新評」編集部に配属される。そして卒業後は自ら予定していたように小説を書きはじめた。同人誌に「春潮」(のち「春の潮」と改題)を発表したのが早大教授で仏文学者の新庄嘉章の目にとまり、新庄教授に紹介されて立原正秋と知りあうことができた。立原の推挙もあって「早稲田文学」に「天の華園」が掲載される。立原正秋に師事することにもなり、まずは順調なスタートを切ったと、他人には見えるかたちである。ところが、この若い作家志望者は、想像を越えるような一種の徹底した精神の持ち主だった。
《この恐れは、立原正秋といると、自分の小説の嘘を感じてしまうというもので、そのことにたえがたくなった私は、嘘と感じた自分の文体をたたきこわすために、東京を去った。》(「新田次郎賞を受賞して」)
ひかえ目に、さっと通り過ぎるように書いているが、若い宮城谷氏がそのときにいた位置を考えてみると、これは大変なことなのである。
敬愛する師といったんは離れなければならない。真に自分のものであると確信できない文体をいったんこわさなければならない。この二つを実現するために、自分が落ち着ける場所、郷里の蒲郡に帰ってしまう。七二年に新評社を退社、七三年に蒲郡に帰るというかたちで、それを実行した。私はこの経緯を想起するたびに、なにか苛烈な文学精神がひそかに動いている姿を感じてしまうのである。
東京にいるとき、立原正秋の紹介で白川正芳主宰の同人誌「朱羅」に加わった。「朱羅」には、小説家の岡松和夫、批評家の遠丸立などすぐれたメンバーがいた。郷里に身を落ちつけた青年は、一日一枚もいかないという遅々としたペースではあったが、自分自身の文体を身につけるため、実験的な作品を書き、それを「朱羅」に寄稿した。「無限花序」「石壁の線より」などがそういう作品である。
その間の生活についていうと、七三年に聖枝(きよえ)さんと結婚。結婚後、夫婦で母の土産物屋を手伝っていたが、八〇年に蒲郡で学習塾をひらいて、英語を教えた。