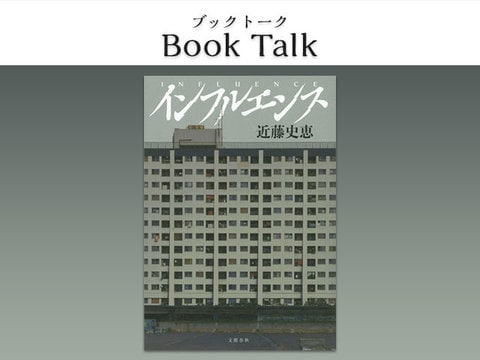「本当に会ってくださるとは思いませんでした」
目の前の彼女はそう言った。おとがいの尖った小さな顔をした女性だった。座っているから身長まではわからないが、痩せている。
会うこと自体は別にたいしたことではない。普通の人程度に忙しく、普通の人程度に遊ぶ時間もある。ちょうど、単行本の直しを抱えているだけだ。
「でも、ご期待に添えるかどうかわからないですよ。小説の題材にできるかどうかも保証はできないです」
「わかってます。それはお話を聞いていただいてからでかまいません」
ウエイターが注文を聞きにきたから、ふたりともコーヒーを頼む。
ふと、ここの勘定はどちらが払うのだろうかと考える。割り勘でいいような気もするが、話を聞かせてもらうのだから、わたしが払うべきかもしれない。
まあ終わってから考えればいい。そもそも、この出会いが和やかに終わる保証などない。
わたしが何度も思い出す風景は、夕陽の当たる団地だ。
箱のような同じ建物が、十棟以上並んでいた。団地の中に公園もあり、幼稚園もあり、スーパーや雑貨屋やクリーニング屋もあった。雑誌や絵本を売っている本屋もあった。すぐ近くには総合病院もあった。
小学生くらいまで、わたし──戸塚友梨(とつかゆり)は一生をこの団地の中で過ごすのだと思っていた。
たぶん、そうしようと思えば、それは決して難しいことではない。中学や高校だって歩いて行ける場所にある。大学はちょっと離れてはいるが、団地から通える場所で選ぶことはできる。
そして、この近くのスーパーかお店などで働けばいいのだ。
わたしの住んでいた地域は、いわゆるニュータウンと呼ばれる場所で、まわりには団地ばかりが建っていた。少し離れた場所には、一戸建てが並ぶ住宅地もあったが、幼稚園や小学校の同級生は、ほとんどが団地の子供たちだった。
今思えば簡単なことだ。一戸建てには、古くからこの地域に住んでいる人たちが多い。団地はまだできて新しく、引っ越してきた人たちはたいていは若い夫婦だった。同じ年頃の子供たちが自然と集まることになる。
友達は団地の中だけで事足りた。どこの家に遊びに行っても同じ間取りで、家具が少し違うだけだったから、誰がお金持ちだとか、誰が貧乏だとか考えなくて済んだ。お姉ちゃんがいる子はいつもお下がりを着ているとか、あの子はリカちゃんだけでなく、リカちゃんハウスを買ってもらえるのだとか、そういうわずかな差に過ぎなかった。
わたしには、田舎もなかった。
生まれたのはこの団地で、父方の祖父母もすでにいなかった。唯一、母方の祖父母だけが大阪市内に住んでいた。母の妹は若くして亡くなり、父の兄はタイで働いていて、めったに帰ってはこなかった。
夏休みやお正月にどこかに帰省することもなく、大家族が集まるようなこともなかった。小学生になって、お年玉をいくらもらったかという話になったとき、いつもわたしがいちばん少ないのだった。
大人になってから気づいた。たぶん、わたしの人生にはもともと縁というものが欠けていたのだ。孤独になるべくして、孤独に生まれたのだと思った。
そして、その団地にはそんな子供が他にもいたのだ。
日野里子(ひのさとこ)との最初の出会いがいつだったかは覚えていない。