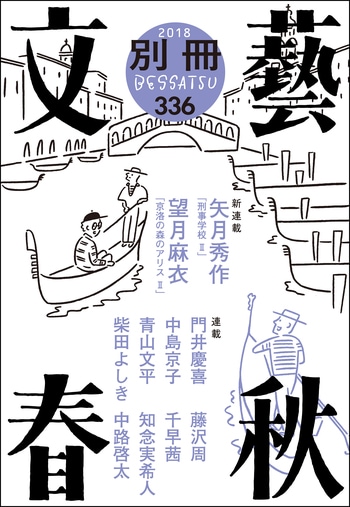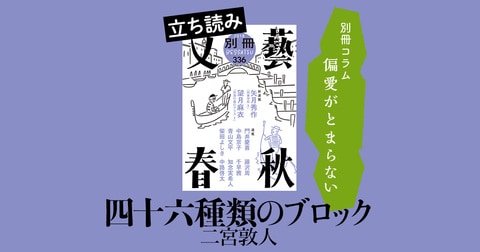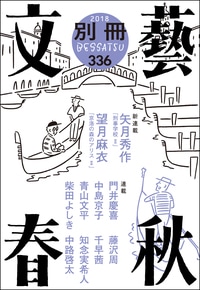
二歳から十八歳までの間、海のない土地で暮らしていた。北関東、栃木県。その中でも関東平野ってなんすか? と言いたくなるほど平らな土地がほとんど無い山間の小さな町に我が実家はあり、視界を阻む山と森に囲まれて子供時代を過ごした。
そんな町だが一応スーパーやコンビニは存在し、はるか遠くの海から運ばれてきた鮮魚がお手頃価格で手に入った。ブラボー流通革命、海なし県の山奥で刺身が食える世界。なので子供のころから魚介類は大好きだし、苦手な魚もほとんどない。
それどころか、死ぬ前の最後の晩餐は絶対に海鮮にすると心に決めている。メニューは蕎麦焼酎雲海のロックと、筋子とあん肝と白子ポン酢と、そして“アレ”だ。
アレに初めて出会ったのは、母方の祖父母が住む仙台に遊びに行ったときだった。夏で、まだ十歳にもなっていなかったと思う。昼過ぎになるとダイニングのテーブルにちょっと豪勢なお昼ご飯が並べられた。そうめん、天ぷら、茄子の煮浸し、焼き鳥、刺身。どれも好物で、名前を知っているメニューばかり。
しかしその中に、ひとつだけ、正体不明のものがあったのだ。
それは、ナマ物のようだった。なのに刺身の皿とは別の八角形の小鉢に盛られており、大根とわかめのツマの上にぐんにゃりと不定形に横たわっていた。異様なのはその色で、普段果物かキャンディでしか見ないような鮮やかなオレンジ色をしていた。
「ホヤだよ」
小鉢を凝視していた私に気付いたのか、母がそう言った。ホヤ。初めて聞く言葉だった。色だけでなく、その響きまで食べ物とはかけ離れていると感じた。
「子供には美味しくないかも」
続いてそう言われ、子供扱いされるのが大嫌いな子供だった私は即座にぐにゃぐにゃのホヤを一切れつまみ、口に入れた。
海だった。
口の中に、海が瞬時に広がった。正確には、海で溺れたときの味がした。濃縮された磯くささが味覚と嗅覚を覆い尽くし、その奥に苦味としょっぱさ、そしてほんの僅かな甘みを感じた。なんだ、これは。海の持つ荒々しさや物悲しさをそのまま噛み締めているような気持ち。
美味しいとか美味しくないとかそういう尺度では測れない。それは、食を通り越した強烈な経験だった。
以来、私はホヤにのめり込んだ。毎夏仙台に行くのを待ちわび、酒が飲める歳になってからはさらに熱く激しくホヤを求めた。時には鮮魚店で殻のままのホヤを買っては自宅でそれを緊張しながら脱がせ、一対一の逢瀬を楽しんだ。ホヤは万人に好かれるタイプとは言い難く、私たちの関係を揶揄されることもあった。そうなると余計に燃え上がってしまう。愛とはそういうものだ。
愛してるわりにはホヤのことを何も知らなかったのに気付き、これを書く前に図書館に出向いていろいろ調べてみた。しかしホヤにボリュームを割いている書物は少なく、その生態に関しては「じっさい、わけのわからない謎を秘めた動物である」と投げ出している本まであった(『世界大博物図鑑 別巻2 水生無脊椎動物』荒俣宏著 平凡社)。荒俣先生にまでわけがわからないと言われるのは、相当なわけのわからなさだ。ホヤ、なんてミステリアス。でもそんなところも、また惚れちゃう。今年もそろそろ夏が来る。