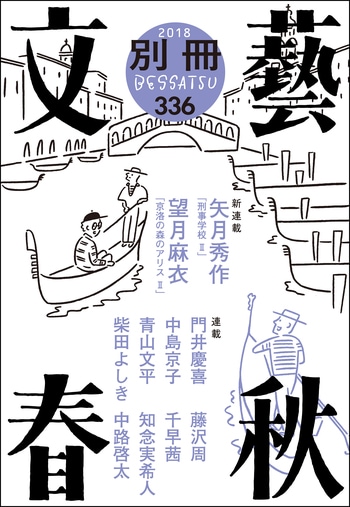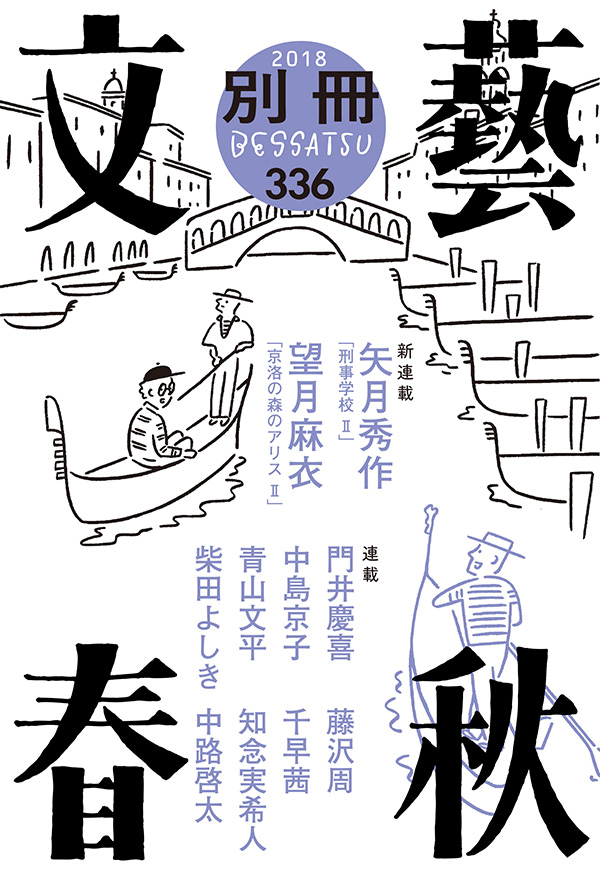
プロローグ
「ご乗車ありがとうございました。終点、大分駅前です。お降りの際はお忘れ物のないようご注意ください」
奥村耕史はマイクで声をかけ、前扉を開いた。乗客がぞろぞろと降りていく。
バックミラーで乗客がいなくなったことを確認して、ドアを閉じた。
前後左右をしっかりと確認し、ゆっくりとクリープでバスを動かす。
奥村は大分中央交通バスの運転手をしていた。三十歳での結婚を機に入社し、以降二十二年間、バスのハンドルを握っている。
たまに長距離や貸切バスを運転することもあるが、ほとんどは大分駅前から出る路線バスの運転を担当している。
本当は運転手になるつもりなどなかった。周囲が心配するほど、気ままに暮らしていた。それが自分らしい生き方だと思っていた。
しかし、結婚した頃にはもう、妻の腹の中に子供がいた。
親となる以上、子には責任を持たなければならない。奥村はそう思い、大型二種免許を取得し、就職を決めた。
長女は今年、大学を卒業する。次女も、高校へ進学した。
次女を大学へ行かせ、卒業させるまであと七年弱。それまで頑張れば、親の責任は果たせる。その後は妻とのんびり旅行でもするつもりだった。
バスの運転は、車体が大きいだけに気をつかう。しかし、基本的に回る道は変わらないので、慣れると案外、楽な仕事だった。
空になったバスを少し先にあるバスターミナルに納めれば、三十分ほどの休憩となる。
奥村はいったん左へ車の鼻先を向けたところで、バスを停めた。
曲がり角に短い横断歩道がある。人通りはまばらだが、駅へ向かう道沿いにあるので、たまに飛び出してくる人がいたり、猛スピードで横切る自転車が来たりする。
乗客を降ろして気が緩みがちなだけに、運転手たちは努めて注意を払う場所だった。
左右を丁寧に確認する。
バスは大きいが、ガラス面は広く縦に長いので、意外と視界は良好だ。
反対車線には駅前へ左折しようとしているグレーのワゴン車が停止線手前で停まっていた。
先に行ってほしいが、動き出す気配がない。
奥村はゆっくりとバスを進めた。車幅や人影を確認しながら慎重に動かす。車体がまっすぐになったところでアクセルを踏んだ。
その時、右前輪が何かに乗り上げた。