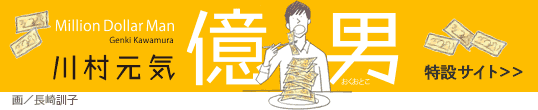西日が差し始めた石畳の道は、家族連れであふれ返っていた。休日の午後。走り回る男の子を父親が追いかけ、泣き出した赤ん坊を母親が抱きあげる。都心の高級住宅街に住んでいる家族たちの合間を抜け、小さく揺れる赤いリュックサック。うつむき黙ったままで歩く娘を後ろから見ていると、このまま一緒の家に帰るのだと錯覚する。
駅ビルに入ると、人波がふたりを置いてけぼりにするかのように、早回しで流れていく。別れの時間は近い。そのことを分かっていながら、言葉が出てこない。ショッピングフロアの入り口では福引きをやっていて、買い物袋を下げた客が列をなしていた。三千円相当の買い物をすれば、一回の抽選ができる。“豪華賞品”の写真が載った大きなボードが掲示されていた。一等は四泊五日のハワイへの旅。
まどかが、ボードを見て足を止めた。
「ハワイ、行きたい?」
一男が訊ねると、まどかは首を横に振る。彼女の視線の先を追ってみると、ハワイではなく三等の景品に向いていることに気付く。エメラルドグリーンの自転車だった。
「新しい自転車、欲しいのか?」
「……べつに」
「福引き、やろうか」
「いいよ。無駄なもの買わなくちゃいけないし」
最初の自転車を買い与えてから、もうすでに四年は経っているはずだ。窮屈そうに小さな自転車のペダルを漕ぐまどかの姿を想像すると、申し訳ない気持ちになった。
「もしよかったら、どうぞ」
突然、横から声がした。福引き会場の前で動かない一男たちを見かねてなのか、老婦人が福引き券を差し出してきた。
「いや、いいんです。すみません」一男は慌てて手を振った。「ただ、気になって見ていただけなんで」
「いえいえ。どうせ私が引いても当たらないから」老婦人はハズレの景品として山積みになっているポケットティッシュを見やりながら笑う。「八十年間生きてきて、今まで一度だって当たりゃしない」
彼女はこれまで、何回くじを引いてきたのだろうか。思い返すと、一男も福引きで大当たりをした記憶がなかった。この老婦人と同じように、ポケットティッシュを持ち帰るのが常で、当たったとしても百円分の買物券程度だった。