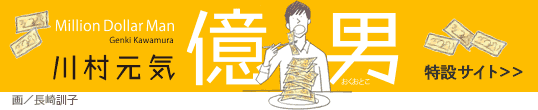「ごめんな……自転車当てられなくて」
一男が呟くと、ジングル音が駅のホームに響いた。アナウンスが、まもなく電車が駅に到着することを告げる。
「……いいよ別に」まどかは表情を変えない。「ていうか、本当に当てるつもりだったの?」
「いちおうね。本気で念じてみた。でも当たるはずがないよな……」
一男は苦笑しながら、深いため息をついた。息があっという間に白くなり、紫色の空に溶け込んでいく。
まどかがそっと一男の手を握った。柔らかくて、温かかった。驚いて見ると、まどかは恥ずかしそうにうつむいている。すっかり大人じみてしまったと思っていた娘の手はまだ小さくて、毎日手を繋いで歩いていた頃の記憶を呼び起こした。
この娘は赤ん坊の頃から、いつだってお見通しだった。一男が喜んでいること、悲しんでいること、悔しかったこと。そして落ち込んでいるときにだけ、とびきりの優しさをくれる。一男は、まどかより少しだけ強い力でその手を握り返した。
「今度まどかが気に入ったものがあれば、買ってあげるからな」
「そんなに頑張らなくていいよ。お父さん、そういうキャラと違うし」
まどかがうつむいたままで答えると、銀色の電車がホームに滑り込んできた。じゃあね。赤いリュックを揺らしながら、まどかが小走りに電車に駆け込んだ。ドアがぷしゅうと閉まるその間際、「誕生日おめでとう!」と一男は叫んだ。閉まったドアの向こうで「ありがとう」と口元を動かし、うっすらと微笑む娘がいた。