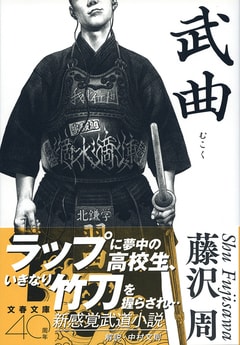私の心を攪乱するほど魅力的なシーンはそれだけではない。「化野(あだしの)」の中ではこんな場面に出くわすのである。
「そのうち、勢いを増して、芳烈とでもいいたいような女の放尿の音が聞こえてきた。店の中の静けさは若い女の放尿の音をいっそう轟(とどろ)かせるかのようで、こちらがかしこまってしまうような潔さや伸びやかさがあった。陶器の便器を液体が叩く鈴にも似た音や、ほとばしる尿の軋みすら聞こえるのである。聞こえないものと思っている女の心が、清々しい」。
主人公の作家と同じく、存在の根拠を根こぎにされた不安を抱え、ノマド的身体を海外の植民地に晒した詩人の金子光晴ならば、女の放尿の音を宇宙の音と融合させたかもしれない。もちろん、「京美人」の「化野」の女と、金子が描く「売春婦」とでは、その陰影に大きな開きがある。しかし、それでもそこに満ちる寂寞には何やら同じ空気が漂っている。
金子が帝国主義的な植民地という「化外(けがい)」の「界」を漂ったとすれば、『界』の主人公は、まるで因果の糸に操られるように、ふらふらと日本列島の「界」に足を踏み入れ、官能と死のあわいを彷徨うのである。
どうして主人公の作家は、「界」から「界」へと当てもない漂泊を重ねるのか。作家は何から逃れたいのか。
逃れようとして逃れられないもの、それは過去から、また過去の過去から「界」の中に染みついた人間の宿業ではないのか。明らかに『界』は、解脱を求め続ける中年男の魂の遍歴とも読める。キリスト教的に言えば、救いを求める罪深い男の懺悔とも言える。