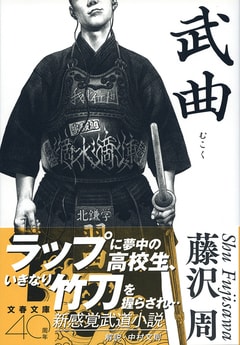だが、仏の教えであれ、キリストのそれであれ、解脱を、救いを求めるものは、近代という根無し草の境遇を生きざるをえず、だからこそ、生身の身体に宿る猥雑さ、そのエロスと死のあわいを徘徊せざるをえないのである。
それでも、そのあわいの中に後光がさすことがないわけではない。「比良(ひら)」の「界」にはその光が一瞬、垣間見られるのだ。
「百夜(ももよ)通いを強いて、やがて老いさらばえた女(筆者注・小野小町)と、百夜通いを強いられて湖底に沈んだ女(筆者注・若き修行僧を慕った女)が、手をつないで歩く影……。振り返ると、薄紫色にほころんだ雲の合間から、強烈なほどの銀色の日の光が斜めに零れて琵琶湖の面を差していた。神の階(きざはし)……」。
だが、その救いの光の粒子も、瞬く間に雲散霧消する。解脱など、救いなど、どこにもないのか。そうとわかっていても、「界」の放つ、歴史の宿業のような地霊の力に縋らざるをえないのか。だが、それは危うく、しかし危ういからこそ、死と隣り合わせのエロスに惹かれざるをえない。
それでも、主人公が最後にたどり着く「山王下(さんのうした)」という「界」には、冥府のような寂寥の世界にも仄かな救いの光がさしているのである。
「目を硬く閉じると、暗い季(とき)の底に朧(おぼろ)な月が震えた」。
絶望だけが残っているわけではないのだ。いや、寂寥と孤独の極地を踏破し、官能と死のあわいを知っている者だけが、人間の生成の真実に通じる仄かな光を見いだせるのかもしれない。
掛け値無しに名作だ。