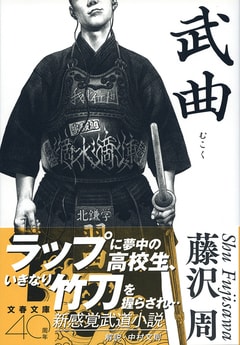艶めかしくも夢現の幽玄に満ち、そしてぞっとするほど美しい世界。『界』を読み進みながら、一瞬頭をよぎったのは、泉鏡花の名作『高野聖』であり、夏目漱石の『夢十夜』の世界である。
これはいったい、怪綺譚の幻想小説なのか、夢現の大人のメルヘンなのか。それとも、無意識の意識化とでも命名したくなるような、草臥(くたび)れた中年作家の告白小説なのか。色々な想念が交錯し、読み進むにつれて鏡花や漱石の名作にも匹敵する怪しげな磁力で「異界」の中へ引き摺り込まれていくような錯覚を覚える。
同時に頭の片隅で、「大丈夫か、気をつけろ、気をつけろ」と頻りに注意信号を送るもう一人の自分がいる。それほど、『界』にハマると、そこから無事生還できるか、心もとなくなるほど魂が抜き取られていくようで、危ないことこの上ない。古稀に近づく年齢にして、こんな危うい物語に出会うとは……。作家とは何と罪つくりで、この世ならぬものの化身であることか。
鏡花の『高野聖』や漱石の『夢十夜』がそうであるように、『界』は実に不思議な小説だ。読む者の魂を抜き取るように冥界に誘いながら、スルリと散文的な日常の世界に連れ戻し、やっと安心するのもつかの間、それがまた異界への窓口になっているのである。なぜそうした感覚に襲われるのか。