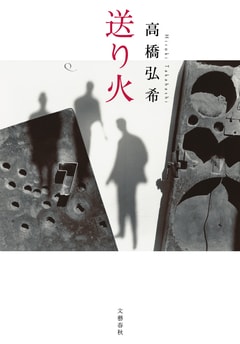苗字だけはころころ変わってはいるけど、たいした経験はしていないし、私はとりたてて優しいわけでもない。だけど、普段ほめることのない向井先生が言ってくれているのだ。私はひとまず「ありがとうございます」と礼を述べておいた。
「でも、どこか森宮さんには物足りなさを感じるのよね。腹を割っていないというか、一歩引いている部分があるというか」
「はあ……」
「何か思うところあるんだったら話してみたら? そのために教師がいるんだから」
「そう、ですよね」
なんでも話すようにと、昔から何度も私は先生たちに言われてきた。担任だけじゃない。保健の先生やスクールカウンセラーの先生までが、こまめに私に声をかけてくれた。先生たちは、いつだって私が悩みを打ち明けるのを待っているのだ。私に必要なのは、悩みだ、悩み。これだけ手を広げて受け止めようとしてくれているのに、何もないのでは申し訳ない。こういうときのために、悲惨な出来事の一つくらい持ち合わせておかないといけないな。とりあえず悩みをでっちあげてこの場を乗り切ろうかと思ったけど、鋭い向井先生には見透かされてしまうだろう。困っていることを挙げるとすれば、まさにこういうときだ。普通に毎日を過ごしているだけなのに、期待を裏切っているようで肩身が狭くなってしまう。無理した覚えなどないのに、元気なだけで気遣われてしまう。平凡に生活していることに引け目を感じなくてはいけないなんて、それこそ不幸だ。
「ま、教師に腹割るような生徒なんて、いるわけないか」
なかなか言葉を発しない私にあきらめたのか、先生はあっさりとした口調でそう言った。
向井先生が今までの先生と少し違うのは、私に向けているのが同情ではなく、疑問だというところだ。「かわいそうに」ではなく、「いったい何を考えているの」と私に投げかけてくる。同情されるのはくすぐったいけど、のんきに過ごしている私に、「本当はどう思っているのか」と問われても、参ってしまう。
「で、園田短大だっけ?」
先生は私の進路調査票に目をやった。
「あ、はい。そうです」
そうだ、ここは人生相談ではなく、進路相談の場だ。自分の中身を打ち明けることから解放された私は、大きくうなずいた。
「どうして短大へ? 森宮さんの実力なら、四年制の大学へも十分進学できると思うけど?」
「近くで栄養士の資格をとれる学校が、園田短大の生活科学科だったからです。私、食べ物関係の仕事ができたらいいなって考えてて……。園田短大ならフードスペシャリストの資格も取れるらしいし。近くて希望に沿った大学なんです」
「なるほど。進路については真剣に考えたのね。うん、いいと思う。合格圏内だし」
「ありがとうございます」
向井先生は五十過ぎのベテランの先生だ。化粧っけのない顔に一つにくくっただけの髪は、あまりにそっけなく、学問を教えるためだけに生きているように見える。おもしろおかしく自分のことを話してくれる先生もたくさんいるけど、向井先生は無駄なことは話さないから、誰もプライベートを知らない。
「じゃ、以上で」
先生はそう切り上げた。
進路については真剣に考えたのねと先生は言ったけど、どういうことだろう。他のことはいい加減だと言いたいのだろうか。そう聞きたかったけど、先生は次の生徒の名前を呼んだ。まあ、いいか。園田短期大学は合格圏内だと言ってもらえたのだから。私は軽く頭を下げると、教室を後にした。
【第2回へ】