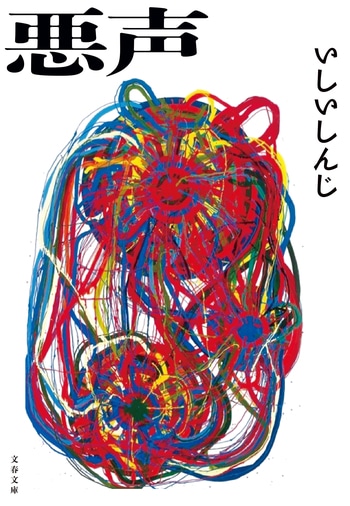「煙は居間から台所、窓をぬけ、田畑の上をかぼそく延びていった。小学校の教室にもその筋は流れてきたし、もちろん廃寺のコケの上にも、白糸をひくような煙の線がゆったりとたなびいた。なにかのほか、長々と流れつづけるその筋に気づいているものはいないようだった。正確にいえば、なにかは目で見たのでなく、たなびく煙を耳の奥で『きいた』のである。」
これは文学的な修辞だろうか。作者にはこのような表現をせざるを得ない、具体的体験があるのだろうか。風景が音に変わり、音が風景や光景を現出する。こうした視覚と聴覚の相互の移行は、あって不思議はないと私は思う。この作品全体を通じて、こうした感覚の相互変換は大切な部分の一つになっている。
直接に感覚が重複してしまう場合は、共感覚と言われる。アルファベットの文字に特定の色が付くような場合である。これは視覚の中で起こる重複だから、まあ許されるかもしれない。でも視覚と聴覚ではどうか。
なにか、と文字で書く。それを読んで、音にする。どちらでもいいじゃないですか。どちらも日本語で、意味は同じである。日本語遣いに共通だから、それが許される。でも個人の内部で、このような相互変換が生じたら、どうだろうか。
理屈っぽい話になるけれど、文学の面白さの一つはまさにここにある。私はそう思う。つい最近、フェルディナント・フォン・シーラッハの『禁忌』を読んだ。この主人公は共感覚者ということになっている。シーラッハの作品はふつうきわめてわかりやすい。しかしこの作品は違ったらしい。「わからない」という評が発表直後からあったという。
言語の世界に淫すると、わからないことはない、と暗黙に前提することになる。だから「わからない」のは欠点である。でもそれは作品の欠点か、読み手の欠点か。感覚経由で捉えた世界が個人によって異なることは、多くの人が気づいているはずである。言葉は世界を表現すると同時に、無限の詳細を取りこぼす。小説家はそれを、できるだけ掬(すく)いとり、救い出そうとする。読み手にとっても書き手にとっても、そこに文学の醍醐味がある。
この小説の面白さはまだある。第一章は「『ぶっしょうじ』縁起」と題されている。花咲さん、寺さん、いずれも固有名詞のようで、必ずしもそうではない。寺にいるから寺さん、桜を咲かせるのが上手だから、花咲さん。さらに養父母の家の代々の女性はキヌである。医者父子だけはまともな名前。そうした登場人物がそろったところで、「ぶっしょうじ縁起」が語られる。
廃寺には不釣り合いの大きさの木魚がある。その木魚の中というか、裏に寺の縁起が書き込まれている。そこでなぜ「悪声」であるか、はじめて説明がなされる。ここは見事な物語になっていて、私はここで初めて「物語」を読んでいる、と一種の興奮を覚えた。これ以降に続く章は、同じように物語を含みながら、感覚的な世界を横断する表現で続けられていく。第一章を読み終えたら、あとはきわめて読みやすくなった。よい文学はしばしばそうである。若い頃、バルザックの作品を続けて読みながら、最初の十ページは辛抱がいるなあ、としみじみ思った記憶がある。それは当然のことで、ある新しい世界に入っていくためには、それだけの準備がいる。現代人はその辛抱が足りない。私はそれを強く疑っている。いまでは辛抱は美徳ではない。辛抱するくらいなら、クレームを言う。それこそが現代人らしさであろう。べつに現代人を褒めているんじゃありませんよ。
現代の美徳は経済的、合理的、効率的であることである。それなら生まれた時に死ねばいい。憎まれ口をきくなら、いしいしんじの小説を読む程度の辛抱と時間がないなら、さっさとお墓に入ればいいのである。