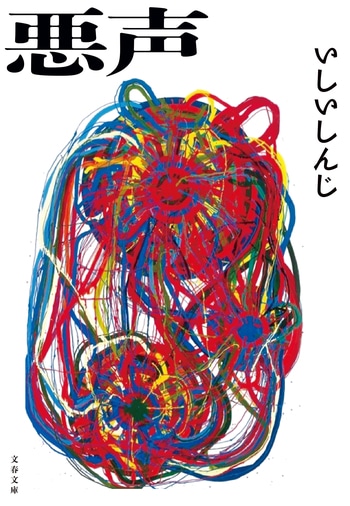軽率なことをした。読み始めてまずそう思った。上橋菜穂子、宮部みゆき推薦とあるから、そういうタイプの作品だと勝手に考えた。それならいくつか読んだ経験があるから、解説くらい、なんとか書けるだろう。
甘く見てはいけない。上橋、宮部ふうの作品であれば、筋を追うことで、ごまかすことができる。簡単にわかったつもり、読んだつもりになれる。この作品では、そうはいかない。久しぶりに、何日かかけて、一つの作品を文字通り読破した。一部分を持ち歩いて読んだから、本をバラバラに壊したのである。
冒頭は廃寺のコケの上に置かれた「なにか」だが、やがて赤ん坊だとわかる。赤ん坊だから、腹が空いた、と泣く。仕方がないから、コケは千年前に使ったきりの手を使う。すると本堂から若い女が現われ、スリッパを脱ぎ捨て、「なにか」に乳をのませる。「左乳房の上部に、北斗七星のひしゃくの形の刺青(いれずみ)が施(ほどこ)されてあった。」
コケになんでそんなことができるんだ。そういうことは訊かないでほしい。私は女が脱いだスリッパが何十も溜まるのが気になった。だって何度も乳を飲ませに来て、そのたびにスリッパを脱ぐから、スリッパが溜まる。私のなかでは、スリッパはまだ溜まったままである。解決はない。
村人も赤ん坊の声を聞いた。「あれはオニやろ。オニの声じゃ」。そこで村人たちはオニ退治にいくが、コケの上に居たのは赤ん坊。「なにか」は村の三十代の夫婦に引き取られる。
こういうことは、読めばわかる。解説もクソもない。じゃあなぜ書くのかというと、初めて読む人のために、びっくりしちゃあいけませんよ、と「解説」しているつもり、いわゆる老婆心である。導入部を読み飛ばすと、ただでさえわかりにくいかもしれない話が、まったくわからなくなる可能性がある。スリッパもひしゃくもオニも、いわば伏線になっている。あとからまた登場するから、読み飛ばさないほうがいい。読み方を指図するつもりはありませんけどね。
次の段になると、「わたし」が「なにか」と対話する形式になる。わたしがなにかの話を聞いている。「なにか」に括弧「 」を付けるか、付けないかで、時に文意が違ってしまう。でも途中から「なにか」には括弧が付かないことが多くなる。それが意図的かどうかは知らない。ともあれ読者としての私は、ある種の緊張を要求される。なにかという単語が出てくると、アレッ、と思う。ここでは固有名詞なのだが、これまでの癖がついてしまっているから、「 」が付かないと、瞬間的に固有名詞ではないと思ってしまう。しかも「なにか」というのは、ともあれ「あるもの」つまり存在者である。「なにもない」ではない。この作品の主人公の名として、上手に選んだなあと感じる。流石(さすが)ですね。
次の段では、廃寺でわたしがなにかと対談している。なにかと対話しているわたしは、どこの、だれだろう。当分わからないままである。とことん最後まで来ると、ふたたびこの「わたし」が登場する。ドイツ語には分離動詞がある。文章の終わりまで行かないと、イエスかノーかがわからない。肯定または否定の意味を持つ動詞の接頭語が分離して、文章の最後に置かれる。これは読者に緊張を要求するためだという意見がある。ともあれこの作品は、そうした伏線に満ちている。それがこの小説の面白さの一つである。謎解きの興奮とでもいうべきか。
さらに表現上の特徴として、感覚の共有というか、入れ替えというか、しばしばそれが起こる。初めのほうでは、養母の四十九日までの話があって、その部分に出てくる。線香の煙のことである。