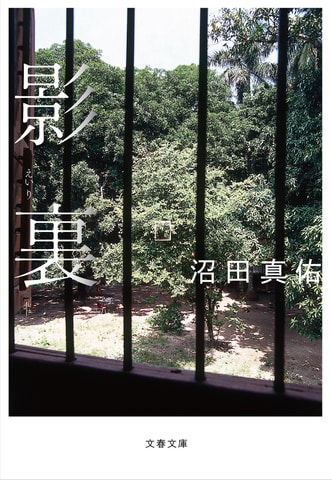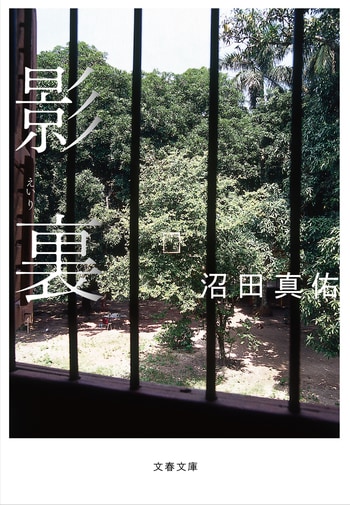震災当時は九州に暮らしていた著者だが、それまで趣味のように書いてきた文章が、3.11を境に書けなくなる。〈何かを表現しようとしたときに震災から離れられなくなってしまった〉(「文藝春秋」二〇一七年九月号受賞者インタビューより)という思いは、あのとき表現者を名のる者なら多かれ少なかれ、同じようにあったはずだ。その後、家族の住む盛岡に移った著者が、間接的に体験した震災を物語へと昇華するのには、あのような書き方しかなかったかもしれない。震災に対する著者の誠実な眼差しが、文体に、より重きをおいて表れたということなのだと思う。
その後の作品を読むと、「影裏」の文体から著者は、少しずつ放たれているように見える。精緻な文章はそのままに、著者の眼差しは、物語の大きなうねりのほうに見えかくれする。
芥川賞受賞直後に発表された「廃屋の眺め」の“廃屋”とは、物語の語り手が高熱を出したときに見る、定番の悪夢の景色である。廃屋の窓辺に立つ死者のイメージをはさんで、婚姻にまつわる二つの逸話が語られる。この物語において結婚とは、別種の生き物同士のかりそめの馴れあいである。恋情と死没の対比も含め、本来は相容(あいい)れないはずの二つの事物が隣りあったとき、否応なく滲みだす異形の空気が、奇談ともいえる短篇に凝縮されている。冒頭の銀鮒(ぎんぶな)と泥鰌(どじょう)の交わりについての挿話が、落語のまくらに似た役割を果たしており、この手法は「陶片」を含む、他の沼田作品にも見られる。これは歌舞伎や落語など、伝統芸能にも造詣のある著者が、受賞後に獲得した語りの型のひとつだと思う。