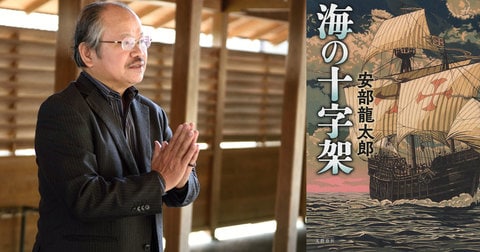「平安京はいつ生まれたのか?」と問われれば、日本人の大多数は、たちどころに「鳴くよ(七九四年)ウグイス平安京」と答えるだろう。では、「京都はいつ生まれたのか?」と問われたらどうか。日本人の大多数は戸惑うだろう。平安京が生まれた時が京都の生まれた時ではないのか、と。そんな問いがあり得るなど、想像の外にあったのではないか。
そこが本書の出発点だ。平安京と京都は違う。読者諸氏は不思議に思われるかもしれないが、次のようにいえば納得して頂けると思う。かなりの数の読者諸氏が、修学旅行や個人旅行で、京都に旅したことがあるだろう。では、京都で訪れた観光地の数々を思い出して頂きたい。神社仏閣なら、清水寺・金閣寺・銀閣寺・上賀茂神社・下鴨神社・知恩院・三十三間堂・北野天満宮・平等院鳳凰堂などがメジャーだ。風情のある繁華街なら、祇園の花街、先斗町の飲食店街、鴨川の河川敷、嵐山なども観光名所だろう。
実は、上記に挙げた“京都の”観光名所は、一つも“平安京の中にない”。最もメジャーな観光名所で平安京の中にあるのは、東寺くらいだ(京都御所さえ、平安京からはみ出している)。観光客は京都駅での乗り降り以外、一歩も平安京の土地を踏まないことさえある。
京都は、平安京の外に広がる、新しい開発地を含めた都市だ。それが今や主客転倒して、平安京の外の方が〈我々こそ伝統的な「都」です〉という顔をしている。平安京らしさといえば、誰もが歴史の授業で習った“碁盤の目”の土地区画(同じ大きさの正方形の集まり)だが、思い出して頂きたい。上記に挙げた観光地を歩いた時、道路や土地の区画がちっとも“碁盤の目”状でなかったことを。“京都らしい”観光地は、全く平安京らしくない。
神社仏閣は“京都らしさ”の最たるものだが、上記の通り、著名な神社仏閣の大部分は、平安京の中にない。なぜか。実は、〈平安京内に寺の類を造ってはならない〉というルールがあったからだ。近年、京都が世界遺産に選ばれた理由は神社仏閣の景観(構成要素一七件のうち、二条城以外はすべて寺社、うち一三件が寺)だったというのにまさか、と思うかもしれないが本当だ。いや、東寺は最初から平安京の中にあったはずだ、と感づいた読者もあろう。それに、今、平安京の領域内だった場所に、寺はいくつもあるではないか、と。しかし、東寺は特例で、最初から平安京の一部だった。ほかの寺はすべて江戸時代頃に入ってきた新参者か、「うちは寺ではない」といい張るトリックで京中にある。古代・中世には、東寺(と対の西寺)以外、平安京内に寺はない。
この〈寺が存在しない〉ことこそ“平安京らしさ”であって、〈京都観光≒寺の拝観〉といえるような“京都らしさ”とは完全に矛盾する。京都は、平安京という立地にも、平安京の設計思想にも囚われていない。平安京の名前だけが「京都」と変わったのでもないし、平安京が何となく拡大して「京都」になったのでもない。平安京の周りに、全く異質な都市域が開発されてゆき、不要な部分を切り捨てた古い平安京と接続されて、全体で新しい機能を果たすようになった。その全体が「京都」だ。平安京は、「京都」に求められた機能を果たせない。そうした平安京の機能不全に人々が見切りをつけた時こそ、「京都」を生み出そうという動機が高まった時だ。実は、“その時”は特定できる。では、いつから、なぜ、あの街を皆が「京都」と呼ぶようになったのか。それが本書のテーマである。
平安京は、全体を活用されたことがない(旧著『平安京はいらなかった』参照)。湿地帯の右京(西半分)や、低地で水害に弱い南部は宅地として好まれず、そもそも居住者が確保できないので、設計図通り開発されもしなかった。学校の教科書に載っている“平安京図”は歴史上実在せず、桓武天皇の妄想だった。頑張って入居した人々も右京や南部から次々と去り、左京の四条より北、つまり平安京の東半分の北半分に人口が集中した。
その左京に、外部の新興開発地が接合されてゆく。その代表格は、平安京の南の郊外の政権中枢「鳥羽」、鴨川の対岸(東側)の寺院街「白河」、白河の南の武士居住区「六波羅」だ。それらが継ぎ足されて造られてゆく「京都」という都市が、本書の主人公である。
都市は、それを造ろうという強い意志があって初めて生まれ、造った人の立場や理念を強く反映する。したがって、「京都」誕生のプロセスを追うことは、誰が、なぜ平安京を「京都」に転生させようとしたのかを、追究するに等しい。中でも重要なのが、鳥羽・白河地域を造りあげた白河法皇・鳥羽法皇と、六波羅をゼロから武士の一大居住区に造りあげた平家の三代(正盛・忠盛・清盛)である。
「京都」は、院政と平家なくして絶対に生まれなかった。特に、平家の台頭から清盛の強大な権力の完成までの過程は、「京都」の誕生から最初の完成までの過程と、完全に軌を一にしている。そして、平家は武士だ。すると、論理的必然として、重要な結論が出る。都に武士が登場し、都で権力の頂点を極めるまでのプロセスそのものが、「京都」の誕生から完成までのプロセスの一部であり、不可欠の要素である、と。
武士、特に関東にあった鎌倉幕府や江戸幕府が京都に果たした役割は、京都ではほぼ語られないし、極論すれば“京都を荒らしに来て去っただけの野蛮な外来者”くらいに思われている。観光地やマスコミが流す京都のイメージでは、京都に暮らしてきた天皇は常に善人で、武士はしばしば叩かれるか無視される。鎌倉幕府は承久の乱で天皇一家と戦争し、天皇を廃位して三人の上皇を島流しにした。江戸幕府も天皇を抑圧した。天皇なくして成り立たない京都で、そのような幕府が嫌われるのも無理はない。しかし、それは単なる郷土愛であり、コマーシャルにすぎないのであって、事実や真実とはあまり関係がない。
京都に武士がどう関わってきたか、というテーマを扱った本は山ほどある。しかし、武士こそが「京都」を造った主役の一人だ、と強調する点が、本書のオリジナリティである。そして、武士の誕生は、「京都」の誕生より早い。そこで本書はまず、武士が平安京をどう利用し、逆に平安京がどう武士を利用してきたか、という話から始めたい。そして、京都は、武士の時代の本格的到来、つまり源平合戦とその直前期の数年間で壊滅する。鎌倉時代の京都は、その壊滅からどう復興するか、という課題とともに始まるわけだが、その壊滅までにどこまで京都が発展したのか。本書は、それに至る道のりを追跡したい。
読者諸氏には、本書を手に執って、もう一度京都を訪れて頂きたい。京都駅に降り立った瞬間から、八〇〇~九〇〇年ほどの時間を超えて「京都」誕生の過程を追憶できるように、そして断片的に点在する観光名所を一つの面として、一つのストーリーとして体感できるように、私は本書を意識して書いてみた。同じ観光地が全く別の景色に見え、風情とは無縁のあの新幹線のプラットホームにさえ、感慨を抱いて頂けたら嬉しい。
(「はじめに」より)