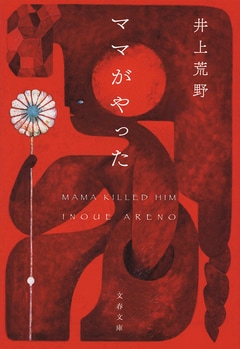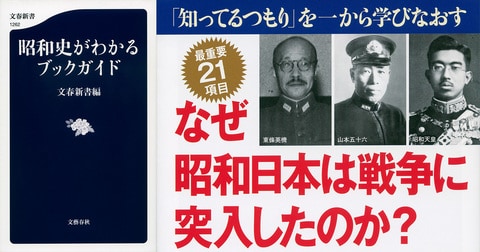巻頭に置かれたブルースに、まず驚く。一見いかにもありそうで、その実いやいや絶対あり得ない、あっけらかんと人を喰った歌詞。何度読んでも笑ってしまう。と同時にしみじみ味わってもしまう。だって、いいのだ、「八号棟の奥さまたち」やら「三号棟の奥さまたち」やら、「影ができない石畳」やら「移動カリー屋のおにいさん」やら、脱力感が絶妙で――。『あなたならどうする』という挑発的な書名に続いてこの“人妻ブルース”が現れる時点で、井上荒野という小説家のセンスやユーモア、技巧への自信のみならず、本人の人格というか性質(の一端)までほとばしっている。こんなにも尖った、才気溢れる一冊ができたのも道理だ。
ここには、ブルースを除くと九編の短編小説が収められており、九編とも、昭和の歌謡曲がタイトルになっている。私の世代にとっては懐かしい歌でありタイトルだが、もしこれらの歌を知らなくても(というより、知らなければなおさら)、一つずつが印象的で鮮烈で、なにより意味深長なタイトルだなと、改めて気づかされた。と書いて、そういえば、意味深長を縮めたイミシンという言葉を、最近あまり聞かなくなったな、ということにも気づかされた。イミシン――。おもしろい言葉だ。含みがあり、隠微で、つねに小声で語られる必要があり、おそらく正解はないのに、誤解だけはたくさんある。それに、白日のもとにさらすとたぶん変質してしまう。ということは、ここに収められた九編は、一編の例外もなく、どれも純正イミシン小説であると言えよう。
全編の土台にあるのは設定の妙だ。配偶者(たち)の病とか、地元という名の枷(かせ)とか、その閉塞感あるいは果てしのなさとか、しがらみとかなりゆきとか、謎の施設とか、お金とか、油断とか、断ることも可能な頼みごととか――。きわめてメロドラマティックでありながら、感傷からは限りなく遠く、荒涼とした方へ方へと突き進むことがなぜか自明で、容赦なく逃げ道のふさがれた、こんな設定をよく考えだすなと感心してしまう。登場人物たちはそもそもの最初から、かなりあやうい場所に立たされているのだ。
どの小説も、とてもかなしい。やたらにかなしい。そしてそれが、おもしろい。
たとえば「小指の想い出」の主人公である真悠(まゆ)のありように、私は胸をしめつけられる。常識というものを、「この世の自分以外のひとたちは、いったいいつの間に、どうやって身につけているのだろうと不思議で仕方がなかった」という彼女はまだ二十代前半だろうと思われる若さなのだが、「この世界の中に家以外にも自分の居場所はあるはずだという希望を、まだ捨てたくなかった」という理由で家の外に働きにでている。そして、家の外で出会った喬児という男に、いともあっさり(ほとんどやすやすと)籠絡(ろうらく)されてしまう。べつに、ものすごくひどいことをされるわけではないのだが、その、ものすごくひどいことをされるわけでもない、ということも含めて、もやもやとかなしい。
あるいは「うそ」の主人公である「俺」も、ほんとうに、痛いほどかなしい。タイトル通り噓つきの、ちゃらんぽらんな女たらし(こういう、中途半端に悪い男を書くのが井上荒野はめっぽう上手い)である「俺」に、私は自分がなぜこんなにかなしみを掻立てられてしまうのかわからない。彼の噓にだまされる(もしくはだまされたふりを選ぶ)女たちのことはちっともかなしく思わないのに。
無論、これは作者の思う壺であり、そこに身をゆだねてかなしみを貪(むさぼ)るのは読者の特権である。
また、この本に限ったことではないのだが、井上荒野はかなしみを誘発するディテールが抜群に上手い。この本でいえば「あなたならどうする」にでてくる口紅や、「古い日記」に登場するすきやきの肉、「うそ」のなかの、緑色の重厚なガラス製の灰皿――。本文を読まれたかたにはわかっていただけると思うが、それらの物体、何の変哲もない、べつな文脈に置かれていれば気にもとめないそれらの物体が、この本のなかではふいに、ぴたりと、得も言われぬ質と量でかなしみをあぶりだしてしまう。やめて、それはかなしいからやめて、と私は心のなかで悶絶しながら読むのだが、その悶絶は指圧師にツボを押されたときのそれに似ている。「やめて」と言いながら、内心「もっと」と言っているのだ。
私は夕暮れの空気が「もったりとし」ている(「サルビアの花」)だけでかなしく感じ、「鳩温泉」という温泉の名前(「ジョニィへの伝言」)のさびしさに虚をつかれる。温泉地に「すでに終わった催しのポスター」が貼られている(「時の過ぎゆくままに」)ことがかなしく、帰って行く若い男をマンションの窓から見送る若くない女の感慨――「あの子はどこへ行くのだろう」――(「東京砂漠」)を読んで胸をつまらせる。いくらなんでもかなしみすぎではないかと我ながら心配になるけれど、この場合、かなしみとはおもしろみであり、小説の醍醐味でもあるのだから喜ばしいことなのだ。
言うまでもなく、いま私が問題にしているかなしみというのは、登場人物の身に起きるかなしい出来事のことではないし、彼もしくは彼女の身になって(想像して、疑似的に)かなしむことでもまったくない。全然ちがう。むしろ誰の身にもならない素の自分のまま(いわば無駄に)感情が右往左往して、ああもう、ああもう、ああもう、と小説の外側で(完全に無駄に)気を揉む行為のことであり、ほとんど一人運動――たとえばある登場人物の気持ちを“わかる”と思い、ほんとうに、切実に“わかる”と思い、でも“そっちに行っちゃだめ。行ったら不幸になるわ”と、なぜだか確信を持って思い、“それでも行くのよね、行くしかないものね”ともまた、なぜだか別種の確信を持って思う――のことなのだ。一人運動だから心がさまざまに揺れる。“まさか”と“やっぱり”のあいだで、“行け”と“行くな”のあいだで、“いいやつじゃん”と“どうしようもないな”のあいだで、“ばかだなあ”と“ああ、わかる”のあいだで――。
誰はばかることなくそれらのあいだで思うさま揺れるこの快楽は、昭和歌謡の真髄かもしれない。