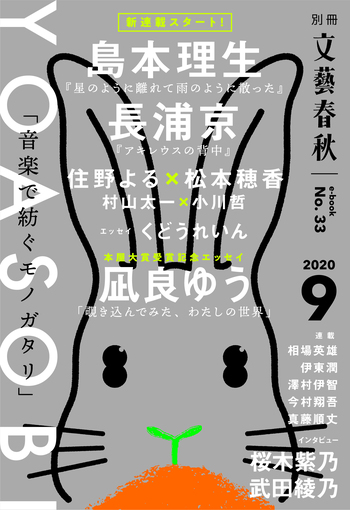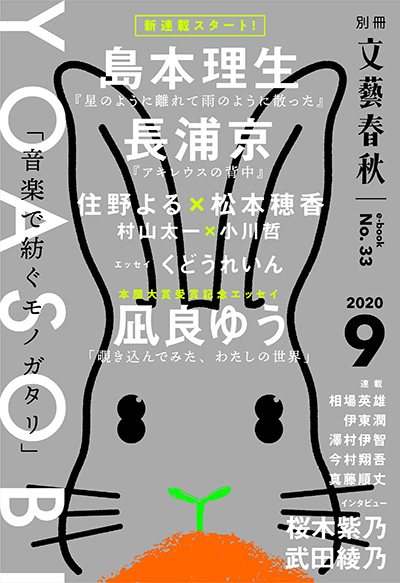
「もちろんです。大人ですから」
「俺の話で笑ったこともないし、愛想よくしてもらったこともないけどな」
「ちゃんと相手を選んでいるので。大人ですから」
「俺は優先順位の低い上司ってことか」
「あまり高くはないけど、それほど悪くもないですよ。評価すべきところはいくつかあるし」
「いい時代になったもんだ。二十年前にそんな口きいたら、女だって頭叩かれるだけじゃ済まなかったぞ」
「二十年前までそんなことしていたなんて、嫌な組織ですね」
「可愛げがないことばかりいってると、職権濫用してイビるからな」
「すぐに私が上になって、証拠の残らない陰湿なパワハラしますよ」
階級が上になるといっている。十歳以上の年齢差がある上司と部下の関係とはいえ、ふたりとも同じ警部補。役職は悠宇が主任。間明も係長とは呼ばれているものの、実際は係長待遇の主任だった。
「冗談と思えないから怖えんだよな」
間明が小さなミントのタブレットを出し、口に放り込む。
「馬鹿話はもういいですから、そろそろここに呼ばれた理由を教えてください」
「いや、ほんとに俺も知らない。ただ、メインはおまえで、俺は単なる付き添い役らしい」
「何をやらされるんですか? あの警視正、所属は警備局ですよね。本庁捜査三課とは完全にテリトリー違いじゃないですか」
「例のMIT推進の一環だろうな」
――あ、それか。
今進めているベトナム人窃盗団捜査に関するマスコミ対応について、何かいわれるのだろうと思っていたけれど、違うかもしれない。
「面倒ですね」
悠宇は独り言のようにいった。
「ああ、面倒だ」
間明もなぞるようにいった。
そしてふたりとも黙った。
ミッション・インテグレイテッド・チーム。
ネットを経由して集められた犯人による嘱託殺人や営利誘拐、海外にいる主犯格が国内にいる実行犯に指示を出して行われる強盗や窃盗、さらには直接面識のない相手からの教唆による殺人など、それまでの捜査一課、二課、警察庁、県警、外事課などの縦割りの枠組みでは対応が難しくなった新種の犯罪に対応するため、警察庁が考え出した新たな捜査手法だった。
事件の性質ごとに各部門が適任者を出し合い、有機的に機能するチームを作って、法令を遵守しつつも慣例に囚われない捜査を展開する。事件が解決すれば解散し、各自、通常の部署と職務に戻ってゆく。いわゆるタスクフォースだ。