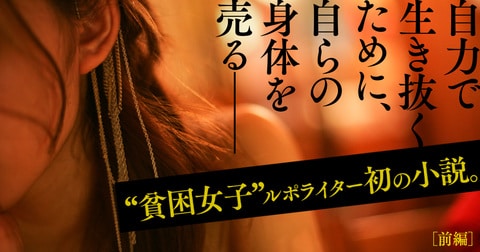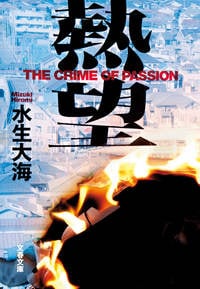
こんな人、絶対に好きになれない。こんな人生、絶対に送りたくない。そう思うのにページをめくる手が止まらないのはどうしてだろう。別に彼女に幸せになってほしいわけでもないし、「他人の不幸は蜜の味」というほど意地悪な気持ちもない。しかしいつしか、この人がこの先どこにたどり着くのか、見届けたくなっている。
一人の女性が人生の崖っぷちに立たされるところから始まる『熱望』。主人公の清原春菜の実家は兼業農家だが、田舎暮らしを嫌い大学進学を機に都会に出て、そのまま派遣社員となり、現在三十一歳だ。最近になって結婚相談所のパーティに出かけて知り合った男性と婚約したものの、乞われて金を用立てた直後から相手と連絡が取れなくなってしまう。さらに派遣先からは契約を打ち切られ、窮地に陥った彼女がとった行動とは――。
おそらく、清原春菜に共感をおぼえる読者は少ないだろう。たとえ似た境遇にあったとしても、「自分はこんなに性格悪くない」と思うはず。そう、このヒロイン、相当自己中心的な人間なのだ。だが人生の崖っぷちに立たされた時、人はこんなふうにエゴむき出しになるのかもしれない。これまでの作品でも利己的な人間を描いてきた著者だけに、その人物描写は的確だ。性格のねじ曲がった人間の心理を掘り下げ、そこから起きるさまざまな出来事をここまでテンポよく描ける筆力もさすがである。本作はミステリーやサスペンスに分類されるのだろうが、個人的には人間の滑稽さを浮き彫りにしたブラックコメディとしても楽しめた。
なんと言っても、清原春菜ってめちゃくちゃポジティブでないですか? たとえば、彼女はどうやらちょっと太めのようなのだが、そこにコンプレックスを抱くのではなく、「現代の理想体重が低すぎるだけ」ととらえるたくましさを持っている。実際、たとえば、これまでのファッションモデルの体型は細すぎたとして見直される動きがあるなど、彼女の主張はまったくもって正しく、世の外見で悩む人たちもこれくらいの自己肯定感を持っていいんじゃないかとは思う。だが彼女の場合、自分のためだったら他人を利用することをなんとも思っていない点、他者を尊重する気持ちがまったくない点が問題だ。次々困難にぶつかっても、それで落ち込んだり自己憐憫に浸ったりすることなく、すべて周囲のせいにする、あるいは周囲を見下すことでプライドを保っている、というタイプのポジティブさ。また、第一章の最後にある程度まとまった金を入手する春菜だが、決して生活に余裕ができたわけではないのに第二章の冒頭でプチ整形をしてご機嫌になっている様子などは、コミカルにさえ思える。
そして彼女、そこそこ要領がよいうえに、働き者なのだ。婚約者と連絡がつかなくなった際も彼の会社や結婚相談所に連絡し、結婚詐欺と気づいて警察に被害届を出すだけでなく自分でも聞き込みを実行し、さらには今後の経済的な状況を考慮して新しい派遣会社にも登録、ハローワークにも出向き……と、実に行動がテキパキしているではないか。また、その後いくつかの仕事に携わるのだが、犯罪行為も含めどれもそれなりにこなしている。読み進めながら思い出したのは、織田作之助の『夫婦善哉』だった。明るくしっかり者の芸者、蝶子が優柔不断な男に惚れて駆け落ちし、幾度も商売を替えながらなんとか二人で生きていこうとする、お仕事モノとしても読める夫婦小説だが、春菜も蝶子に負けないくらいへこたれずに行く先々で精力的に働いている。駄目な男に遭遇したばかりに苦労を背負うが、なんとか自力で人生を切り拓こうと奮闘する姿がなんだか痛快に感じられてくるのも同じ。また、どの状況でも最初はそれなりに順調にいく様子はある種のサクセスストーリーを読んでいる達成感を抱かせるし、窮地に陥ってもしぶとくまた次の場所を見つけていく姿は、ちょっとしたサバイバル小説を読んでいるようなスリルもある。
そんな春菜が関わる人たちもクセモノぞろい。兄嫁のもえや喫茶店の店主の小磯といった善人もいるが、まあ、大半は自己中心的だったり腹黒かったりで、春菜と身勝手さの度合いを競うバトルを繰り広げるようなものである。とんでもないことをして春菜が追われる身となってもその状態は続き、やがて、ついにラスボス(?)が登場して……(いや、彼女の人生においてあの人物がラスボスとは限らないのだけれども)。
春菜が“熱望”したのはなんだったのか。巨万の富が欲しかったわけでも、名声が欲しかったわけでもない。結婚詐欺に遭うまでは、市井の人間として、都市部で結婚して家庭を築くことを望んだだけだったのだ。だが窮地に陥ってからは愛よりも金が彼女の優先事項となる。のちに再び、愛する男と平穏な生活を望むようになるが、そこに至るまでの彼女は、その日その日を生きるのに精一杯だ。切羽詰まった人間は明日安全に過ごせるのかすら分からないのだから、五年後十年後を考えて計画を立てることなんてできない。つまり人生が暗転した時から、彼女にとっては明日生きることが、“熱望”するものだったのだ。
本書が痛快なのは、どんな窮地に陥っても、春菜が臨機応変に事態に対応し順応し、明日を生きる術を勝ち得ていくからではないだろうか。無反省で利己的というはた迷惑な性格だって、他人を不幸にしてでも自分は生き延びるサバイバル能力としては非常に優秀といえる。もはや日々の愉しみをどこに見出せばよいのか分からない状態にも陥るが、それでも、彼女は絶望せずに、「生きる」ことを熱望する。人生の意味や意義など関係なくシンプルにその欲求だけで、しぶとく、たくましく、ずる賢く生きていけるメンタルの強さは、時にまぶしいくらいだ。
読み手がどんな状況でこの物語を読むかによって、受け取り方も変わってくるだろう。自身も苦境に立たされているか、あるいは順風満帆に生きているかによって違いそうだ。ただ、経済、災害、感染症などさまざまな困難の要因がある現代において、春菜のような「生きるために生きる」姿には、なんだか励まされる人は多いのではないか。こんなふうに、人はもっとシンプルに生きたっていいのではないか、と思えてくる。もちろん、彼女のように身勝手に生きろとは言いたくないが。
春菜はもちろん、彼女を利用しようとする人たちも、現実世界で身近にはいてほしくない。ただ、そうした人間たちの末路を他人事として楽しんでしまえるのがフィクションの良さだ。人はきれいごとばかりを物語に求めるわけではないし、主人公に共感することだけが読書の愉しみではない。時に人は自分の身は安全なまま毒を味わってみたくもなるし、人間の醜さをのぞいてみたくもなるものだ。とはいってもただ悪趣味で下品なだけの小説を読みたいわけではない。そんな時に水生大海の小説はうってつけだ。読者を楽しませるエンターテインメント性を配慮している著者だからこそ、どの小説も安心して読むことができる。ただ、作品によって、ダークな方向に針が振り切っているのか、あるいは別の方向へ振れているのかが分かれるのは確か。あなたが次に手に取る水生作品がどのタイプなのかは、ページをめくるまでのお楽しみ。ただ、どれも、物語の面白さを堪能できるという点において、裏切ることは決してない。