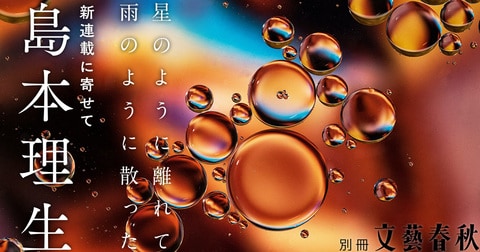明け方に目を覚ますときには、どうしてとなりの人も同じように起きるのだろう、と思うことがある。
横向きのまま目を開けると、どちらが先ともつかぬタイミングで彼の瞼が持ち上がり、視線が合ったら
「春」
と呼ばれた。頭のむこうの御簾に青い光が滲んでいる。
私は数秒黙って、喉を開き、ゆっくりと息を漏らした。
「昨日は、ごめん。亜紀君」
彼はほっとしたように、うん、と短く頷くと、昨晩の名前のことには触れぬまま夏用の薄い掛布団をまくり上げた。
浴衣がはだけてもだらしなくないのは、鍛えた肉体の輪郭がくっきりしているからだと思っていると
「だけどまだ俺、寂しい。春」
こんなにはっきりと、寂しい、と言う男の人に、私は出会ったことがない。
「うん」
ごめん、と私は言った。それから唐突に大雨が降った川の勢いに巻き込まれるように、彼の体が覆いかぶさってきた。
彼から流れ落ちる汗を目尻に受けると、互いが泣いているようになった。彼の汗はいつもべたつかない。さらさらと汗を流して正しく循環している体にしがみつく。プロポーズされたんだ、という事実がめまいのように感情を一回転させた。結婚というものがこの世にあることと、自分にその言葉が放たれることは、国境線を越えるような近くて異なる世界の出来事だった。
体が離れて、ひとりきりの布団で裸の両手足を伸ばすと、潔いほどの疲れが隅々まで行き渡っていた。
そのまま二度寝してしまいそうだったので、お風呂にでも入ろうと思い、起きて浴衣を羽織った。
「春、今日どうするか、一緒にもう少し寝ながら相談しようよ」
まだ上半身裸の彼が人懐こく話しかけてきた。私は帯を結びながら
「うん、でもあと一時間で朝ご飯の時間だから。お風呂入る」
と言った。えー、と子供みたいに不満げな声を受けて、振り返る。
「なんだか男女逆だな。行ってらっしゃい」
私は、汗かいたから、と笑ってタオルを取りに行った。