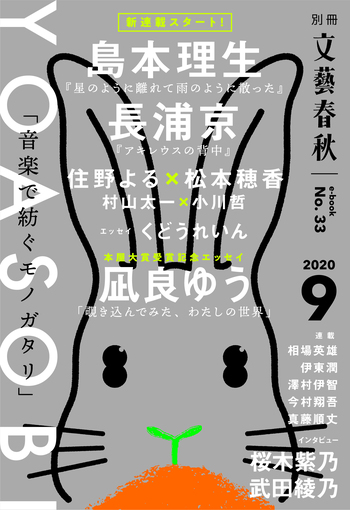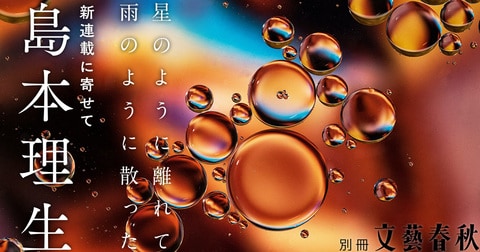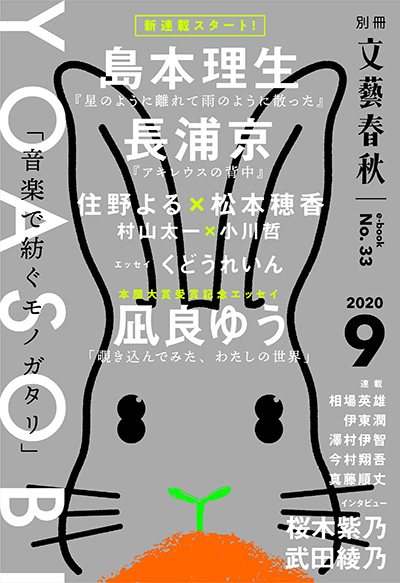
「茉里へ
僕はもう行かなければなりません。
僕の情熱はこのまま死ぬためだけに燃える星の終わりのようにどこまでも墜落していくのでしょうか。僕は焦っている。だけど焦りの言葉は、それが真摯であるほど、空転して滑稽なものになっていく。愛情と同じことです。一日に百回、愛シテイル、と繰り返す男を果たして誰がほんものだと受け入れるでしょうか。言葉は少ないほうがいいし、愛は語らないほうが何百倍も尤もらしい。でも、それは同時にただ一つの、ほんとう、を手放すやり方です。
僕がいなくなることを、イオンの旅を書くことを、とても遠い旅に向かうことを決定させたのは、ほかならぬ、あなたです。あなたはもうこれ以上、僕の思想、思考、本質を分断してはいけない。僕を、僕でないものでいいから愛してほしいと願ってはならない。そうじゃなければ、僕はいずれ、あの夜のように、あなたに手をあげてしまうでしょう。
どうして死んでもいいと思うほど他人を殴るのか、警察と両親は僕に何度も尋ねました。でも僕は警察と両親に暴力をふるったことはないので、彼らには答えられなかった。僕はただ、なんとなく、そうすることを望まれているような気がしたからです。僕は、あなたたちが望むなら、なんでもしてあげたいということを、ぽつん、と胸に思い浮かべるのです。
今年の冬の朝を覚えていますか。
初めて雪を見た春がインスタントカメラを持ち出し、ぱしゃ、ぱしゃ、と口ずさみながら雪を撮ろうとしてレンズを自分に向けたままシャッターを切っていたことを。僕はあのとき、なぜか春があまりにも無残に痛々しく感じられて、体が真っ二つになる想いがしました。
あれはきっと僕自身の姿でもあったのだと、今、思います。
だから僕は遠い旅について書かなくてはならない。
僕に本質はないのかもしれない。でも、愛はきっとあるのでしょう。そうだとしか思えないのです。そしてそれはいつだって死を内包しているものでなくてはならないのです。
さようなら、茉里。
僕のことは死んだと思ってください。
2000.8.9
」
第一章
広大な大学の敷地内では、素描のように緻密な自然の繁殖が起きて、校舎にたどり着くまでの学生たちの両目を、緑色に浸していた。蟬が途切れることなく鳴いていた。空が青いだけで、マスクの内側にこもる吐息の熱以外には、汗も吹っ切れたように清々しかった。
そもそも今年の夏は耐えがたいほどでは、まったくないのだ。二年前の夏はひどすぎて、卒論のために本校舎と図書館を往復しているだけで、二回ほど熱中症で倒れた。
図書館の入り口で、検温の器械を額に当てられた。無事に中に入ると、私は資料をかき集めて机に向かった。一時間ほどして、誰かが机の脇に立ったので、私は手を止めた。
「はかどってる?」
そこそこ、と返事をして、篠田君を仰ぎ見る。白いマスクをしているために、表情は、読みづらい。
彼は積み重ねた資料に目をやった。宮沢賢治の研究書と、法華経の解説書。それに聖書の解釈を扱ったものも数冊置いていた。