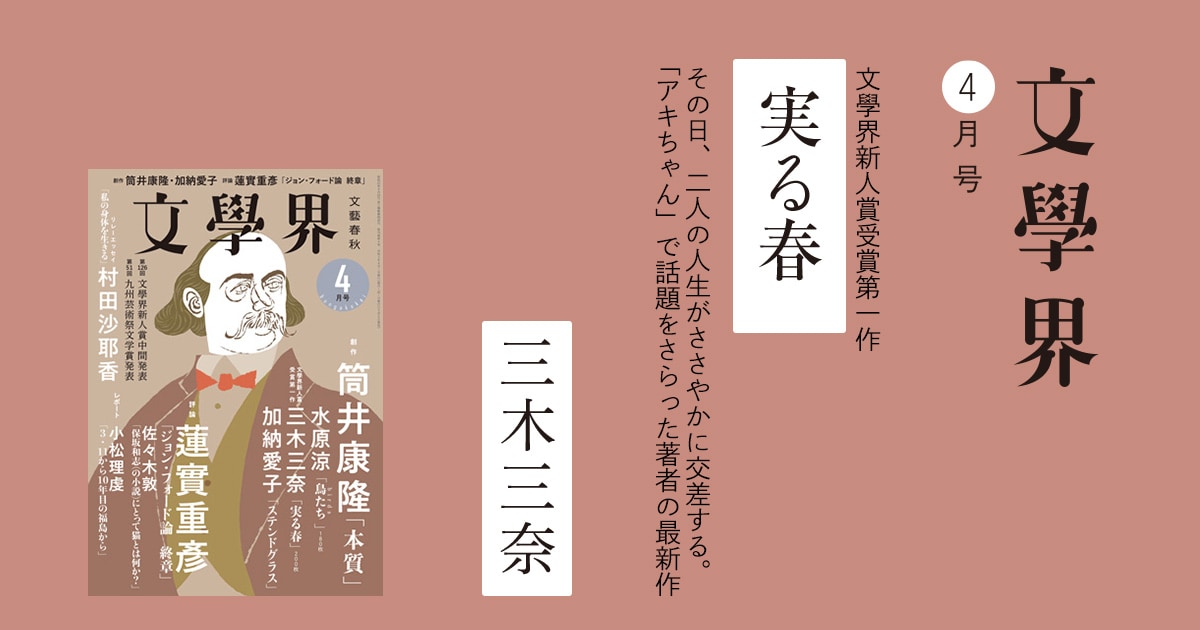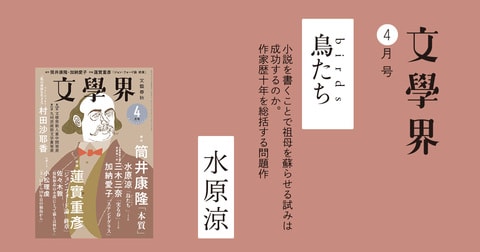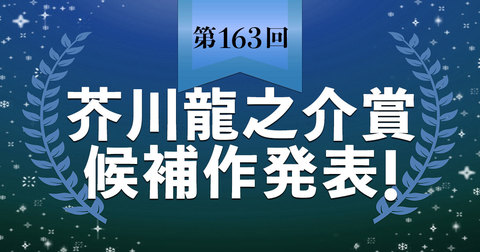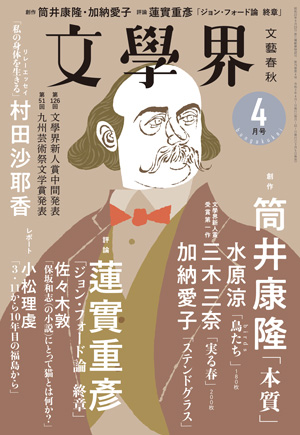
その日の昼さがり、脇実春(わきみはる)は、尻が乗ったりはなれたりするたびに、ぎぃっ、ぎぃっ、と音をたてるイスを、身をよじってけげんな顔で見おろしていた。
「そろそろ壊れちゃうんじゃないの、それ」
はす向かいに座る清水が声をかけると、
「ほんとうですよ。新しいの買ってくださいよ」
と実春はパソコンのディスプレイに向きなおって言う。
「いやいや、脇ちゃんがもう少し痩せたら、鳴らないでしょ」
清水が言うと、実春はディスプレイ横から顔をだして彼をねめつける。
「そういう問題じゃないんですよ」
「だって、おれのは鳴らないよ」
「じゃあ、交換してください」
「一緒だろ。脇ちゃんが座れば、鳴るんだよ」
そう言って清水はクック、と喉をならした。
「それ、どういう意味ですか」実春はとげとげしく言い、「じゃあ係長、一回このイスに座ってみてくださいよ。ぜったいに、係長が座っても鳴りますから」
キュウウウッ、とネズミの断末魔のような音とともに立ちあがった実春がイスを指さすと、
「やだ」
と清水は即答する。
「なんでですか」
「いま忙しいの。仕事してんの」
ディスプレイにかじりつくポーズを清水がとると、それを合図のように、背後で鳴っていたプリンターの作動音が止まる。実春はふり向くと、つかつかとプリンターに近づき、
「もう、また詰まった」
数分前にも言ったセリフを、より声をあらげて言った。
「なんか今日、プリンターすぐ詰まっちゃうんですけど。全然コピーがすすまないんですけど」
実春はプリンターの上部のカバーを上げ、詰まった紙を力任せに引っこ抜くと、はたくようにしてカバーをもどし、
「ねぇ、係長、聞いてます?」
とコピー用紙をぐしゃぐしゃに丸めて言う。
「なに、おれに言ってんの」
「そうですよ。ほかに誰もいないじゃないですか」
「また、脇ちゃんのひとりごとかと思った」
くつくつと笑う清水に実春は目をむき、席につくと、イスがぎゅぎゅっと鳴く。実春はため息をつくと、足元のごみ箱に紙の玉を投げつける。こうしたふるまいができるのは、建設会社のちいさな営業所であるこの一室にいるはずの所長や営業たちが、いまは皆出はらっているためである。いるのは三十すぎの清水と、ちょうど昼にでている、半年前に派遣されてきた、住吉という一つ下の女だけ。ここ最近は三人で昼を過ごすことも多い。
「わかったよ。江端をよべばいいんだろ」清水はそう言うと、受話器を耳と肩のあいだにはさんで背もたれによりかかった。
「……うん、また調子わるいんだよ。すぐ詰まっちゃう。こないだ、ちゃんと直してくれたの。なに、ほんとうかよ、ハッハッハ……」
実春からみて右手にある窓のブラインドは、日差しの強い夏をのぞき、大抵はあげたままにしてある。閑散とした住宅街にある営業所の、隣地はちいさな畑で、誰かがほそぼそと野菜づくりをしている。手前に並ぶ二本の梅は花を散らし、畑の黒い土に葉が見え隠れしている。その殺風景な景色を、実春はくすぐったいような気持でながめていた。電話で話す清水の口ぶりからして、江端がこちらに出向いてくることがわかったからだった。
「江端、すぐくるってよ」
電話を切った清水が言うと、実春は顔を髪で隠すようにうつむいて、そうですか、とつとめて冷淡な声で言う。
「すぐって、いつくらいですかね。お昼たべてからかな」
「さぁ、それは知らん」
実春は壁掛けの時計を仰ぎ見、とたんに気をもみ始めた。あれこれ考えめぐらしていると、休憩を終えた住吉が部屋に戻ってきた。
この続きは、「文學界」4月号に全文掲載されています。