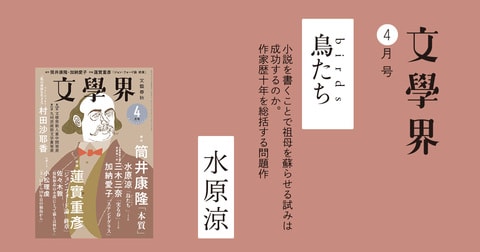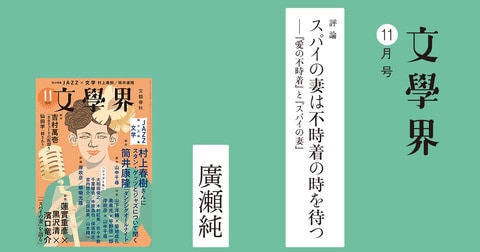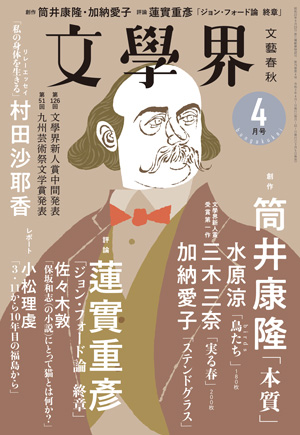
母親、または女たち
フォードにおける母親を論じるにあたって、雌馬の親子の愛情を描いた『香も高きケンタッキー』(Kentucky Pride, 1925)はともかくとしても、いずれも典型的な母親が主題となっている『マザー・マクリー』(Mother Machree, 1928)や『四人の息子』(Four Sons, 1928)、さらには『戦争と母性』(Pilgrimage, 1933)にさえ触れようとしていないのだから、ブライアン・スピトルズの『ジョン・フォード』(Brian Spittles, John Ford, Pearson Education Limited, 2002)という研究書は、とても精緻な論述による書物とはいえまい。もちろん、そこにはいくばくかの正しい論述も含まれてはおり、ときには重要な事態さえ指摘されている。例えば、その書物の終章にあたる「父権性か母権性か」(《Patriarchy or Matriarchy》)には、次のような一行が読めるのである。
「ハリウッドに生きる者としてはごく希なことだが、フォードは五〇年にもおよび、一度しか結婚していない」(p.114)。そういわれてみれば、フォードとほぼ同時代を生きていた映画作家たちは、アラン・ドワン Allan Dwan にしても、ラウール・ウォルシュ Raoul Walsh にしても、ハワード・ホークス Howard Hawks にしても、ウィリアム・A・ウェルマン William A. Wellman にしても、さらにはキング・ヴィダー King Vidor でさえ複数回の離婚歴を持っており、それにくらべてみれば、フォードの結婚生活は、たしかにハリウッドという特殊な社会においては、ごく希なケースだとさえ断言できる。
実際、1894年2月1日に合衆国東部のメイン州のケープ・エリザベスに、アイルランド移民の子ショーン・アロイシャス・オフィーニー Sean Aloysius O’Feeney として生まれたジョン・フォード――そのアメリカ名はジョン・マーチン・フィーニー John Martin Feeney というもので、生まれからしてカソリック教徒である――が、ユニヴァーサル Universal社の専属監督としてジャック・フォード Jack Ford と署名していた時期も終わろうとする頃、より正確にいうなら1920年7月3日――4日という説もある――に、二十四歳という年齢のメアリー・マクブライド・スミス Mary McBride Smith と結婚し、その死に至るまで彼女と離婚したことはなかったのである。ところが、そのときフォードの妻となったプロテスタントのメアリーには、二十四歳にしてすでに離婚歴があった。ロバート・C・マーチン Robert C. Martin という男と結婚していたことがあるからである。
フォード自身の孫のダン・フォードの『ジョン・フォード伝――親父と呼ばれた映画監督』(Dan Ford, Pappy : The Life of John Ford, 高橋千尋訳、文藝春秋、1987)には、ジョン・フォードが「監督レックス・イングラム主催のパーティの席上で、長い黒髪の見目うるわしい令嬢と出会ったのは一九二〇年の聖パトリック祭の日(三月十七日)のことだった」(48頁)と書かれているが、彼女はすでに離婚を経験しているのだから、「令嬢」という語彙はここにはふさわしくあるまい。「ジョンとメアリーは嵐のような恋におちた」(同前)とも書いている孫息子のダン・フォードは、折から禁酒法が施行されたばかりの合衆国の西海岸でフォード愛用のオープンカーを乗りまわしていた二人は、「もぐり酒場(スピーク・イージー)」にしばしば出かけては痛飲していたと書きそえている。さらに、メアリーの家庭は、英国、といってもスコットランドとアイルランド系の出自であり、アメリカでの家系をたどると17世紀までさかのぼることができるほどだという。しかも「サー・トマス・モアの直系の子孫」(49頁)だとも書き記している彼は、「家庭環境が不釣り合いであるという意識はフォードを悩ませる問題として後々まで残った」(同前)とさえ書いている。