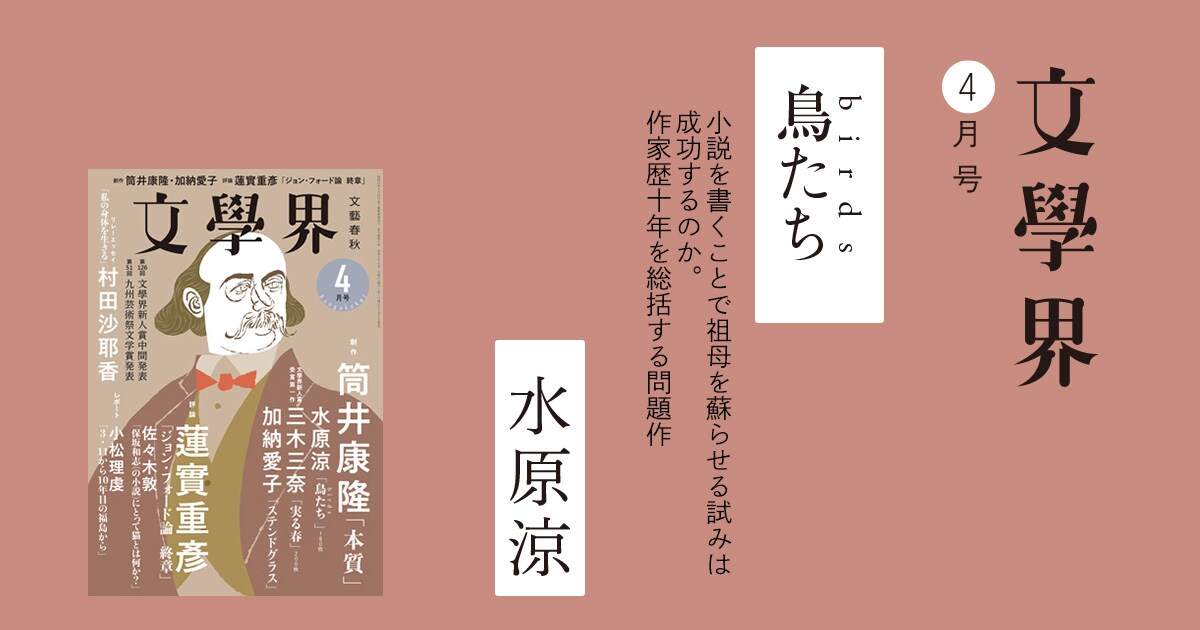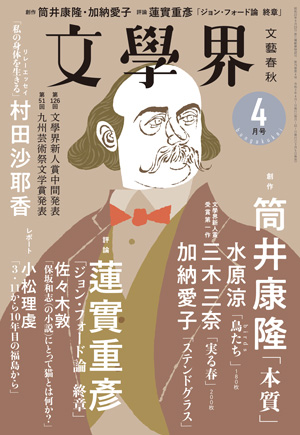
山陰本線の各駅停車は二両編成で、ほとんどの便がワンマン運転だった。乗員は車掌兼運転手のひとりきり、停車時に開くのは先頭車輛の前側のドアで、乗客はそこで切符を手渡したり定期券を見せたりして降りていく。二両目のドアは有人駅でしか開かなかった。最後尾には車掌室と運転室があり、運転室はいつも施錠されていたけれど車掌室は、マスターキーを抜いておけば不届きな乗客が計器類をいじっても反応せず、安全にさほど影響がないからか管理が甘く、三、四日に一度は鍵が外れていて自由に入れた。
とはいえ時には黒い油で汚れているそのドアを開けようという者なんて、通学中の中学生くらいのものだ。鳥取大学前駅、湖山(こやま)駅、鳥取駅。ほとんどの生徒はその三つの駅の間で乗り降りする。いずれも有人駅だから二つの車輛の四つのドアはすべて開く。彼らはドアの開閉ボタンを親指で突き、開ききる前にじれったそうに身体を差し込んで、汗の湿度と外のにおいをまとって駆け込んでくる。ドアを境界に空気の濃度が変わったように、最後尾を目指す彼らの足取りは不意に重くなり、気が急いていると知られるのを恥じるようにことさら慎重にリノリウムを踏みしめてしずしずと向かい、真っ黒な鋼のドアノブを指先でそっとつまむ。軽くひねって開くことを確認すると目配せをしあい、素封家(そほうか)の勝手口から侵入するように――じっさい、彼らはただ黙認、あるいは黙殺されていただけで、車掌室への立入はおもてむき禁止されていた――踏み込む。いくつかの計器類は無人でも動いていて、耳を澄ませば機関部の荒々しい駆動音の隙間からかちかちと、ブレーキの圧力計の短針の震える音が聞こえる。三、四人も入ればいっぱいの車掌室に、もちろんクッションの張られた客席などはなく――だからこそそこに入ろうとする客は彼ら以外にはいないのだが――、あるのはぐらぐらと揺れるスツールめいた椅子ひとつきりで、もちろんそこに座れるのは、最初に脂ぎったドアノブに手をかけた者だ。彼はふかみどりの固い樹脂性の座面に尻を叩きつけるように置き、ことさらにきいきい軋ませながら、後続の級友たちを見上げる。彼らが喋ることはいつも同じで、教員たちにまつわる生徒同士でしか通用しない符牒をつかった噂、部活の愚痴と夏の大会の展望、あるいは次の定期試験に向けて自分がいかに勉強を“していないか”ということばかりで、その間彼らの手は、サブザックの口を開け閉めしたり、油で汚れていないと解ったドアノブを撫でたり、反応しないスイッチやレバーを動かしたりしている。
室内に無数にある装置はほとんど電源を切られているし、〈米子運転所直通〉とテプラの貼られた受話器を取り上げても無音だ。唯一作動するのが、スツールの足下のレバーを踏み込むことで作動する汽笛だった。おそらくきわめて単純な構造をしているために、任意に機能を制限することができないのだろうし、線路に踏み込んだ動物や踏切に侵入した人間をおどかして逃げさせるためのものだから、勝手に鳴らされても運行に支障はないのだろう。それだって二度も三度も鳴らして楽しいようなものではない。ただ甲高い音が狭い室内に反響して耳を聾するだけだ。後ろの窓からはくねくねと曲がりながら伸びていく線路とそれを挟む工場の塀が流れていくのが見える。長く続く塀にはスプレーでなにかの落書きがほどこされているが、途中で飽いてしまったようにぷつりと途切れそこから先は、無表情に煤けたコンクリートブロックがのっぺりと積まれている。
車掌室が施錠されていても彼らのすることはそう変わらない。閉ざされたドアの前で床に尻つけて、衛生に気をつかう者はサブザックをクッション代わりに座り、変わらぬ四方山話で盛り上がる。ときおり視線を上げて窓外の景色を見やり、ついでのようにドアの向こうの、にぶい緑のペンキをまとわされた天井の光沢を見やるが、わざわざ鍵をかけて無害で悪意のない彼らから日常のちょっとした楽しみを奪った、顔も知らないJRの職員のことを考え、すこしだけ恨めしい気分になる程度だ。気の置けない級友たちと中身のない会話にふけることが大事なのであって、気に入りの場所が施錠されていたところで、何の問題があるわけでもない。
この続きは、「文學界」4月号に全文掲載されています。