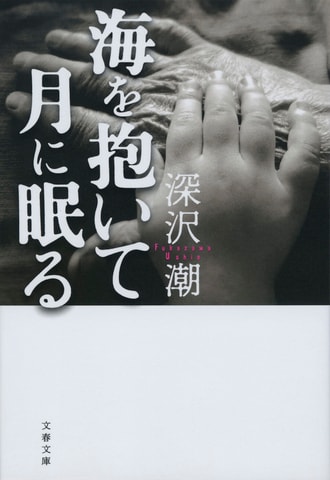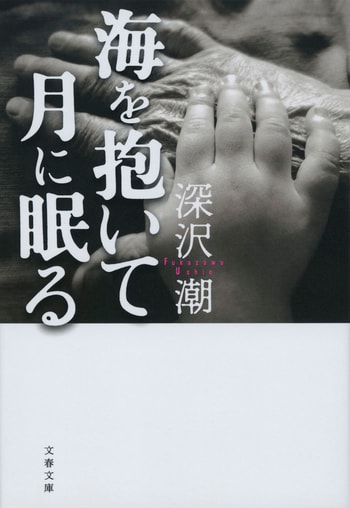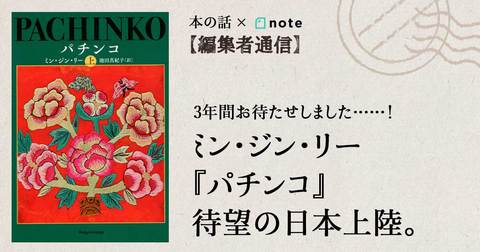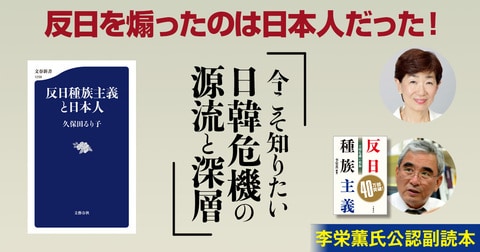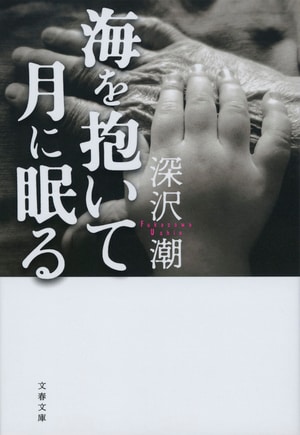
日本と韓国をめぐる状況は、今日、なかなか複雑です。
『冬のソナタ』がヒットした二〇〇〇年代から、日本でも韓流ドラマやK–POPにハマる人が激増し、何度かの波を経つつ、今日でもその人気は衰えを知りません。韓国発のファストフード店が軒をつらねるコリアンタウンは大人気。日本の飲食店やコンビニでは韓国から来た留学生がおおぜい働いていますし、日本の女の子たちは韓国のファッションやコスメに夢中です。
半面、公的な政治レベルでの日韓関係は必ずしも良好とはいえません。もちろんその背景には、かつて日本が韓国を植民地化していたという負の歴史があり、いまなお在日外国人の公民権を認めない日本政府の問題があるわけですが、二〇一〇年代には在日コリアンを標的にしたヘイトスピーチ(差別扇動表現)や、韓国への憎悪を煽る「嫌韓本」が横行し、社会問題にまで発展しました。
正と負の両面を含んだ、日韓をめぐるそんな今日の状況を、深沢潮ほどセンシティブ、かつ軽やかに小説化してきた作家はいないといっていいでしょう。深刻な歴史的背景や差別問題を内包しながらも、けっして重苦しくも告発調にもならない。彼女が描いてきたのは市井に生きるごく普通の人々です。
二〇一二年のデビュー作「金江のおばさん」(『縁を結うひと』所収)は、在日同士の縁談を二〇〇組もまとめてきた「お見合いおばさん」をユーモアとペーソスをまじえて描いた短編小説。『ひとかどの父へ』(二〇一五年)は、自分は日本人だと信じ、美人で裕福な在日の友人に複雑な感情を抱いてきた女性が、自身のルーツを知って内なる差別と向き合わざるを得なくなる物語。『緑と赤』(二〇一五年)はヘイトデモの嵐が吹き荒れる新大久保を背景に、在日であることを隠してきた女子大生、K–POPファンの友人、アニメなどの文化にひかれて日本の来た韓国人留学生、反ヘイトのカウンター活動に突き進む女性など、多様な人物が登場する群像劇でした。
さて、本書『海を抱いて月に眠る』は、そんな深沢潮がはじめて手がけた父の世代、すなわち在日一世の物語です。
〈父の人間関係について梨愛はまったく把握しておらず、通夜に来ている人たちをほとんど知らない〉。ところが、その見知らぬ弔問客の中に、声をあげて泣いている人がいた。〈父の死をここまで悼んでくれる人がいるなんて。/いったい何者なのか? 父とはどういう関係だったのだろう〉
このはじまり方からして、波乱のドラマを予感させます。
九〇歳(本当は八五歳)で死んだ在日一世の父・文徳允は大学ノートで二〇冊にも及ぶ手記を残していた! 物語はそんな文徳允の波瀾万丈な半生を軸に、父の過去を徐々に知る娘の梨愛の動揺を挟みながら進行します。
文徳允と名乗っていた父の本名は李相周。一九三一年、植民地時代の慶尚南道・三千浦に生まれ、四五年の解放後(日本側からいえば敗戦後)、旧制中学の同級生だった姜鎭河、韓東仁の二人とともに、日本に向かう密航船に乗った。だが船は対馬沖で遭難。九死に一生を得た三人は身分証に代わる米穀通帳を手に入れ、以後、相周は通帳にあった五歳上の「文徳允」として生きてきたのでした。
いつか必ず故国に帰ると決意しつつも、祖国は南北に分断され、やがて韓国には朴正熙の独裁政権が成立。徳允は韓青(在日韓国青年同盟)のメンバーとして、密航してきた仲間とともに民主化運動にのめり込んでいきます。
徳允と結婚した在日二世の南容淑はしかし、夫が理解できません。
〈あなたにとっての韓国人は、あくまで朝鮮半島に住む韓国人で、私たち在日韓国人ではないのね〉と容淑はいいます。〈在日韓国人は日本の社会で差別されてきて、ずっと苦しんできているのに、私たちが暮らしやすくなるようになんてあなたは考えてないでしょ。そりゃそうですよね。一緒に暮らしている妻のことですらどうでもいいんですものね。いつも目が向いているのは海のむこうばかり〉
祖国の民主化闘争に全身全霊をかける夫と、家庭をないがしろにする夫への不信をしだいに募らせていく妻。二人の溝は、息子の鐘明が誕生し、心臓に重い病気を抱えているとわかった頃から、さらに深まっていきます。
当時の徳允は、朴政権の下から亡命してきた金大中の支援闘争で駈け回っていましたが、それは韓国政府への反逆を意味します。金大中が滞在中のホテルから拉致された事件の後、徳允らは韓民統(韓国民主回復統一促進国民会議)を結成するも、その頃からKCIA(韓国中央情報部)の尾行の影がちらつきはじめ……。
容淑はついに夫の説得に乗り出します。〈お腹の子のためにも、もう韓民統での活動はやめてください。国にたてつかないでください。あなたになにかあったら心配です。私たち、路頭に迷ってしまいます〉
運動をとるか、家族をとるか。さあ、どうする徳允!
本書の最大の魅力はやはり、二つの名前を持った李相周/文徳允の波乱の半生が、現代史とともにドラマチックに描かれている点でしょう。
日本に密航し、偽名とはいえ新しい人生を手にした徳允は、日本で朝鮮人が生きていく厳しさに直面すると同時に、いやおうもなく祖国の動乱に巻きこまれていきます。南北の分断、朝鮮戦争、朴正熙の軍事クーデター、日韓国交正常化交渉の難航、ベトナム戦争参戦、金嬉老事件、金大中事件。あるいは二つの民族団体である韓国系の民団(在日本大韓民国民団)と朝鮮系の総連(在日本朝鮮人総連合会)の対立。
徳允ら密航三人組が民主化運動にのめり込んでいくのは、朴正熙独裁政権が誕生した一九六三年頃からですが、韓国ないし日韓をめぐる一九五〇年代~七〇年代の重要トピックはほぼ過不足なく盛り込まれ、在日の若者たちにとって祖国の動乱がどれほどの重く苦しい事態だったかがくっきりと浮かび上がります。
とりわけ三人組が亡命中の金大中と東京で面会し、胸を熱くするくだりは、本書の中でももっとも印象的なシーンのひとつといえましょう。
〈いまこそ、私が日本にいることに、意味が生まれる。/私は金大中氏の力になりたい。/独裁で苦しむ韓国の同胞のためになにかしたい。/キューバ革命を成し遂げたカストロとチェ・ゲバラのように、我々もなれるのではないか〉
そんなのは若さゆえのヒロイズムだ、と笑うのは簡単です。しかし実際、一九八七年に韓国が民主化されるまでの道のりは長く苦しいものでしたし、徳允ら三人組のような思いを抱く若者は、在日にも日本人にも多かった。若き日の徳允たちのパワフルな活躍ぶりは、ちょっと冒険小説のようでさえあります。
とはいえ本書の魅力はこのような「大文字」の歴史が語られているだけではありません。文徳允は家庭では自身の出自を一切語らず、活動家としての過去も隠していた。娘の梨愛から見た父は、日本名で暮らしながら韓国の食やしきたりにこだわり、些細なことで怒鳴りちらす不可解で疎ましい存在でしかありません。
最終的に徳允は、運動を捨てて家族を取ったわけですが、それは息子の病気と、祖国に残してきた母への思いからでした。人はそれを挫折、あるいは転向と呼ぶかもしれません。しかし、はたしてそうなのか。
〈もう二度と韓民統のような組織の活動はしないと約束して、一筆書いてください〉〈金輪際、仲間とも付き合わないでください。それと、これまでのことは誰にも口外しないことです。いいですね?〉。そう誓わされることでパスポートを手に入れた徳允の後半生は、一八〇度変わります。それは米穀通帳を手に入れて新しい人生を歩みはじめたときと同じくらい、大きな決断だったはずです。
表向きにはパチンコ店を営みながら二人の子どもを育て、陰では妻にも子にも内緒で、本国に送還されて獄死した韓東仁(金太竜)の妻と娘を支える。それは徹底して家族と仲間のためだけに生きる「小文字」の人生でした。
横暴な父親に見えながら、彼は妻の要求を受け入れ、子どもたちには好きな道を選ばせた。前半生が国家の民主化を目指す人生だったとしたら、後半生は自身が支配者の座を降り、家族の民主化に努める人生だったといえないでしょうか。
興味深いのは、一〇代で出奔した密航三人組が、それぞれのやり方で、最後には再び故郷に帰還していることです。志を貫いた韓東仁(金太竜)は韓国に送還されて獄死。姜鎭河(朴永玉)は引退後、ひとりで故郷に移住します。そして晩年の李相周(文徳允)は三千浦を頻繁に訪れて、家族のための家まで建てた。
割り切れない人がいるとしたら、夫の出自や名前が偽りであることを最後まで知らずに死んだ、妻である容淑や慶貴でしょう。が、その無念さは彼女らの娘である梨愛と美栄によって回収され、大きな和解に至ります。
深沢潮の小説では、誰も溺愛されないかわりに、誰も断罪されません。すべての登場人物と適度な距離が保たれ、すべての人物の選択が尊重されます。同じ船で密航したアン・チョルスが敵側に回り、コ・グヨンが大金持ちになっていた、なんていうのも物語に奥行きを与える挿話として機能しています。
日本には「在日文学」と呼ばれるジャンルがあり、戦後第一世代にあたる金鶴泳、李恢成、金石範らを嚆矢として多くの作品が書かれてきました。しかし現在、日本には多様なルーツ、多様な国籍の人々が住んでおり、在日コリアンのありかたも多様。文学の世界にも日本語を母語としない作家が多数参入しています。
友達のいない鐘明のために、手紙をそえて千羽鶴を贈った美栄。〈げんきになったら、あおうね。みよんとおともだちになろうね〉。作中でもっとも心温まるこのエピソードに、この作品のトーンが凝縮されています。そのときはすれ違っても、いつか和解は訪れる。『海を抱いて月に眠る』は世代も国境も超えた希望の書なのです。