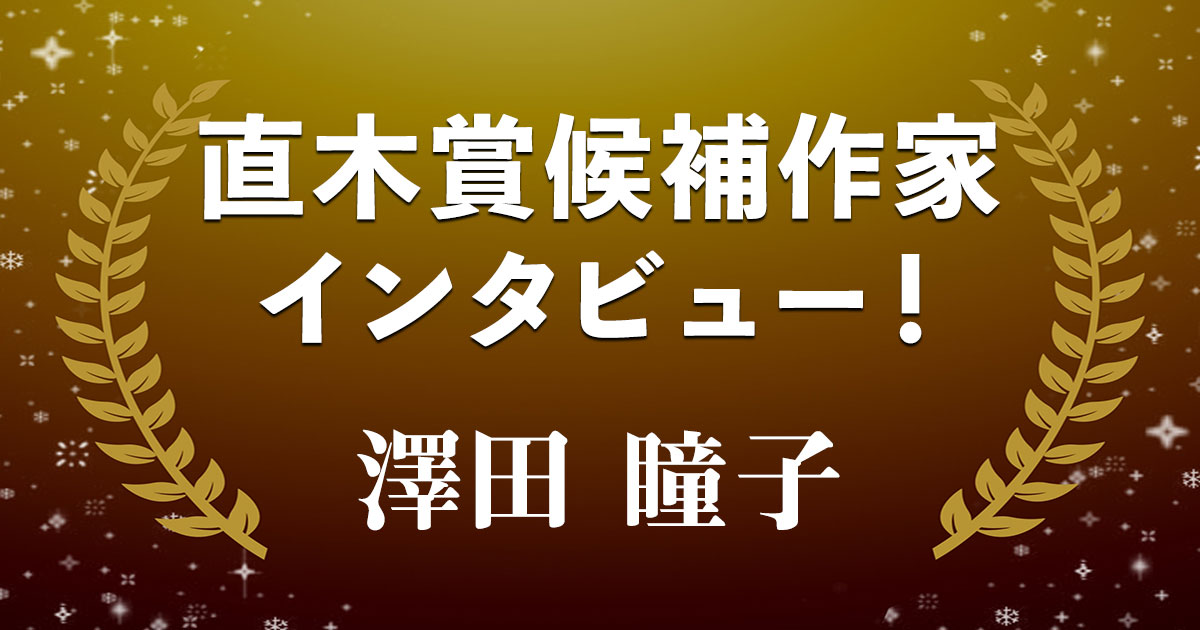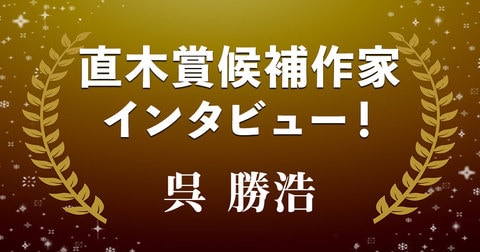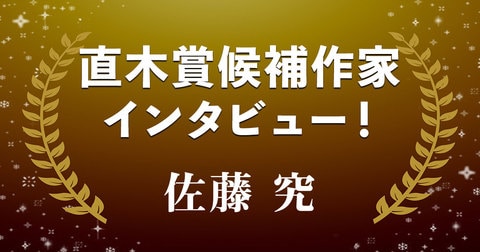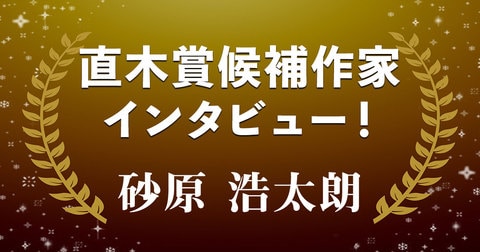澤田瞳子さんの最新作『星落ちて、なお』は、狩野派の流れを汲みつつも自在な画風で幅広い作品を描いて画鬼と呼ばれた絵師・河鍋暁斎(かわなべきょうさい)の娘であり、自らも絵を描いた河鍋暁翠(きょうすい)の数奇な人生を浮かび上がらせる。
「もともと河鍋暁斎が大好きで、日本の絵師の中でいちばんうまい画家だと思っているんですけれど、絵師そのものについては『若冲』で描ききったと考えているんです。それで担当編集の方とお話しして、『若冲』を書いたからこそ書けるものがあるのではないかと盛り上がりました」
物語は、明治二十二年の河鍋暁斎の死から始まる。父であり師であった暁斎を失った娘のとよ(暁翠)は、悲しみに浸る暇もなく、河鍋家の行く末を背負うことになる。腹違いの兄・周三郎も絵師であったが、ことあるごとにとよに難癖をつけ、河鍋家を継ぐ気もない。放蕩気味の弟・記六は頼りにならず、妹のきくは病弱であった。
幼い頃から暁斎に絵の手ほどきを受けたとよは、父の死後も、絵の道を進んでいくのだが――。
「天才的な人物を家族に持った人にはかねて関心がありました。その上で絵や家族に振り回される人物を書いて、絵師を描くことの向こう側へ行きたいと思いました。絵に限らず、親子だから、家業だから、ということで逃れられないことは誰にも大なり小なりあって、とよの生きた人生は一面、我々全員が共有できる人生でもあります」
明治初期を舞台にした『名残の花』につづく近代を描いた今作。自身が得意としてきた古代史と異なる部分に苦しんだところもあったという。
「史料が多いですね。掘り出したら、とても時間が足りないし、史料自体も、書いてあることがそれぞれに違って、どれが正しいのか迷うこともありました。でもそのおかげで、日本の近代の濃密さを改めて感じましたし、数年単位で、価値観が次々転換していく時代の目まぐるしさもよく分かりました。書いている途中は二度と嫌だとさえ思いましたが、書き終えた今はこの面白い時代をもっと知りたいと考えています」
父の影に翻弄されながらも、ふたつの時代を生き抜いたとよ。その眼には何が映っていたのか。
「人生って結構嫌なことが多いですよね。でも八、九割方嫌なことがあっても、一、二割のいいことがあったら我慢できる。とよの人生には、確実にそういう幸せな時間があったと思うんです。河鍋暁翠という絵師ではなく、河鍋とよという一人の女性を書けたと思います」

澤田瞳子(さわだ・とうこ)
1977年京都府生まれ。2010年に『孤鷹の天』でデビューし、11年同作で第17回中山義秀文学賞を最年少受賞。15年『若冲』が第153回直木三十五賞候補となり、同作は16年に歴史時代作家クラブ賞作品賞、第9回親鸞賞を受賞。17年『火定』、19年『落花』、20年『能楽ものがたり 稚児桜』が直木三十五賞候補となる。20年、『駆け入りの寺』で第14回舟橋聖一文学賞を受賞。
直木賞選考会は2021年7月14日に行われ、当日発表されます