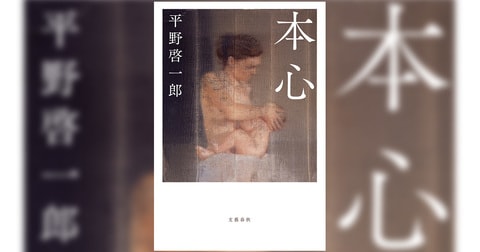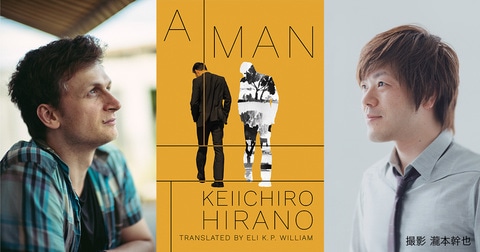『マチネの終わりに』(2016年)は、現代の世界史的な出来事を背景にした、美しい恋愛物語だったが、私は、「未来は過去を変える」というその主題に、改めて、まったく別のアプローチで取り組むことを考えていた。
人は、様々な条件で生まれてくるもので、自らの生い立ちに誇りを持って生きている人もいれば、そのために著しい人生の困難を抱え込んでいる人もいる。
今とは違った人生だったなら、というのは、所詮は平凡な想像かもしれないが、後者の人たちにとっては、切実な願望である。
もし、自分の過去を誰か他の人の過去とすっかり取り替えることが出来るならば?
『ある男』の着想は、そんな思索からだったが、私はこのことを、やはり愛を通じて考えたかった。
一体、愛に過去は必要なのだろうか?
人にはそれぞれ、言いたくないことがあり、すべてを曝け出してこそ、嘘偽りのない本当の人間関係だ、という考え方が、私は好きではない。愛し合う者同士にも、隠しごとはあるはずだし、それは当人が、ある時ふと、相手に話したくなった時に話せばよいことである。一生、言わずに済ませることも、少なからずあるだろう。
しかし、黙っているだけでなく、その過去がすべて嘘だったとしたならば、やはり穏やかではあるまい。
私が、過去を偽ろうとする動機として考えたのは、一つには犯罪との関わりであり、もう一つには差別される経験だった。
物語は、事故で亡くなった夫が、実は、自分が信じていたのとはまったく違った人物だった、という残された妻の衝撃を以て始まる。では、一体、誰だったのか? それを探ってゆくのが、主人公の弁護士・城戸である。
私は、城戸が、その謎の男の本当の素性を調査することにのめり込んでゆく姿を通じて、私たちにとって、他者とは一体、どんな存在なのか、そして、小説体験とは何なのかを考えたかった。
私たちはそもそも、何故、小説を読むのか? それは、登場人物たちへの共感の故だろうが、しかし、何故自分の心の内を、わざわざ、他人の人生に仮託しながら感じ取るのだろうか? 自分の心の最も深い傷に、他人の傷を経由することでしか触れられないというのは、どういうことなのか?
『マチネの終わりに』は、私の本としてはよく売れ、デビュー作『日蝕』以来のイメージも更新されたが、だからこそ、『ある男』がどのように受け止められるかはわからなかった。しかし、結果として、多くの読者に恵まれ、二作とも英訳が決まった時、アメリカの出版社は『ある男』の方をこそ、私の英語圏でのデビュー作に相応しいと判断したのだった。
文庫化によって、更に多くの読者の手に届くことを願っている。