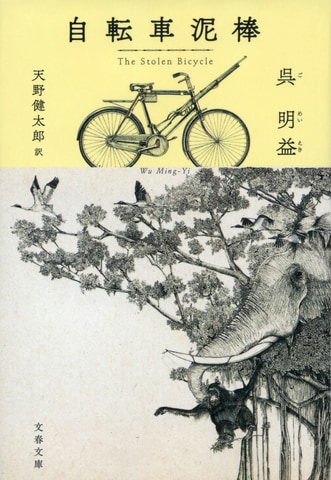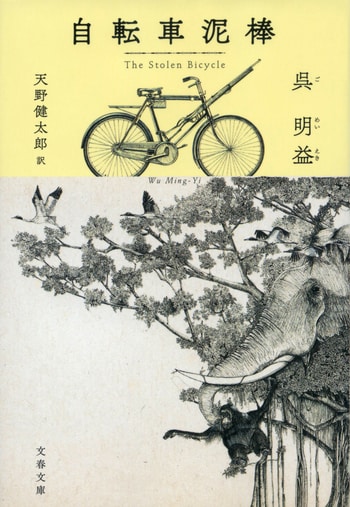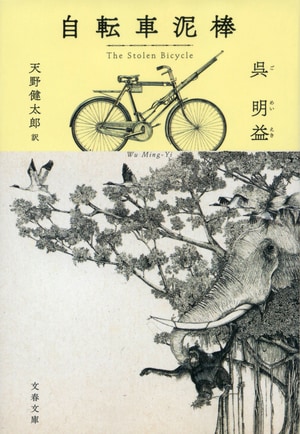
わたしは幸運なことに、呉明益さんと直接会って話したことがある。ある文芸誌の企画で、呉さんの短編集『歩道橋の魔術師』をめぐり、台湾出身の作家・温又柔さんと三人で鼎談を行ったのだった。
鼎談の最後に、呉さんが「記念に」と差しだしてくれたのは、白地の表紙に美しい――そしてどこかシュールな――花木が描かれた大判のソフトカバーの本で、ページをひらけば、自転車の細密画も収載されていた。そう、この『自転車泥棒』の原著『單車失竊記』だった。作中の凝った挿画もすべて呉さんが描いたものだと知って、わたしはその多才さに仰天した。
とはいえ、悲しいかな、ページの上に書かれた言葉が読めない。それでも、わたしはこの原著を居間の窓辺に、古いSFの洋書ペーパーバックと隣り合わせに並べて置き、いまも折々に眺めている。
ちなみに、その鼎談の場で、台湾語も中国語も解せないのはわたしだけだったから、呉さんの言葉はすべて、彼を日本に紹介した翻訳者である天野健太郎さんに通訳してもらった。天野さんがそれから数年のうちに鬼籍に入られるとは夢にも思わなかった。もちろん、世界がコロナ禍に見舞われることなど予想もしていなかった。皆でひとつ部屋につどって、大いに論じ、声を出して笑ったあの鼎談の場を思いだすと、まさに僥倖のひと時であったことを痛感するのである。
■
『自転車泥棒』は自転車が主人公の大河小説だ。語り手は小説家にして自転車マニアの「ぼく」。「ぼく」が生まれ育ったのは、『歩道橋の魔術師』の舞台にもなった中華商場である。日本でも高い評価と人気を得たこの短編集は、歩道橋で連繫した巨大な商業施設と団地周辺の暮らしを、八人の語り手が回顧する形で展開する。中華商場界隈の子どもたちは、歩道橋に現れるマジシャンとそれぞれ人生の微妙な時期に出会い、この体験がのちのち大なり小なり人生の転機につながるという見事な構成だった。
個々人の人生を短編に結晶させた『歩道橋の魔術師』の精緻さはそのままに、『自転車泥棒』は長編小説の大河を悠々とくだる。まず、「ぼく」の家族の歴史は「盗まれた自転車」に始まると言い、時を一九〇五年にまで遡行する。旅順でロシア軍が日本軍に投降した年だ。その年に生まれた「ぼく」の祖父は子どもの頃から、自分の自転車をもつという夢があり、妻がお産のときには、その自転車に乗せて運んでやりたいとも思っていた。
この祖父の夢の起点には、自分が生まれた日の「台湾日日新報」の記事がある。字の読めなかった曽祖父が、自分の息子は識字力を身につけるようにとの思いから、彼の誕生日の新聞を保管していたが、ここに自転車の盗難事件が報じられていたのだ。自転車を盗られるのは、いまの価値で言えば、高級車一台、いや、戸建ての家一軒に匹敵する経済的打撃だったという。
祖父は自分の自転車をもつに至らなかったが、父は何台か所有した。そして三台目の「幸福印」の自転車とともに失踪したのだった。
■
後年、小説家になった「ぼく」のもとに読者から、彼の先行作の小説のなかで、商場が解体されたあと中山堂で行方不明になったあの自転車はどうなったのか? という質問のメールが届く。
ここで作者がイタリアの大作家ウンベルト・エーコの論を引きながら、創作論を少し展開しているのがおもしろい。エーコの「小説を読む際の基本原則」は、要約するとこうだ―読者はそれが虚構のものだと暗黙の裡に了解し、それでいて作中のできごとを作者の「噓」とは考えず、本当に起きたことと思い込むこと。これはおそらく、エーコの「経験的読者とモデル読者論」(『開かれた作品』)から引いているのだろう。
メールを送ってきた読者はこの原則どおりに「ぼく」の本を読み、読了後もその世界を漂っているらしい。虚構と現実の境を教える返事を書けば済むことだが、「ぼく」はそうはしなかった。読者が指さしてみせたのは、彼がフィクションのなかに混ぜ込んだ実在の自転車だったからだ。それは「ぼくの実生活の心に突き刺さっていた針」だった。
彼は父不在の過去と、その痛みに向きあうことになり、「幸福印」の自転車探しの旅が始まる。それから数年後に、父のものと似た自転車に行き会うのだが、本当の「旅」はその先にあるのである。
「ぼく」はその道程で個性的な人たちに次々と出会う。戦場カメラマン志望の原住民青年アッバス、その父で日本軍に従軍したバスア、四川で中国軍インド遠征軍に拾われたムー元隊長、動物と動物園を愛する人たち……。日本統治時の戦火や、日本軍に使役された象の一生、マレー半島で日本軍によって組織された「銀輪部隊」のことも明らかにされる。
■
父親と失われた自転車というモチーフは、作者の実体験から来ているという。メタフィクショナルな半自伝小説と言えるが、作中には「ぼく」の語り以外にも、多彩なフォームの文章が盛りこまれてくる。前述の「銀輪部隊」や、ビルマ方面軍のことは、原住民族のツォウ語と日本語が混ざりあい、「山肌と風のように、あるいは樹木と寄生植物のように寄り添い、もはや分かつことができない」という混合言語(からの翻訳文)で語られる。それから、アッバスのミャンマーでのサバイバル記や、美しい蝶と蝶の貼り絵にまつわる小説の断片、はたまたある動物園飼育員の娘から送られた日本語の手紙なども挿入される。
技法として非常に興味深いのが、章と章の間に「ノート」と題してはさまれる自転車の博物誌だ。台湾の自転車史の黎明には、資生堂の創始者福原家が関わっている。この「ノート」に、自転車産業の発展、販路拡大、人気デザインやブランドの移り変わりなどが記され、その自転車小史だけで、台湾の戦争をふくむ歴史や社会状況が如実に語られることになるのだ。
幕間に自転車史をはさみ世界観を語らせるというこの手法は、ウクライナ系イギリス人作家マリーナ・レヴィツカの『おっぱいとトラクター』なども想起させられた。こちらの小説では、若い妻を迎えたウクライナ人の父が調子づいて「ウクライナ語版トラクター小史」と題する大真面目な論文を書き、これが章間にはさまれていく。一台の農業トラクターの発明がソ連にコルホーズを誕生させ、英国で自動車に革命を起こし、武器を生み、米国における株価大暴落と世界恐慌まで引き起こした(⁉)のがわかる仕組みだ。
■
呉明益の文学には、外国のさまざまな作家作品の影響が見られるが、『自転車泥棒』というタイトルからも察せられるように、イタリアのヴィットリオ・デ・シーカ監督の名画「自転車泥棒」には、ずいぶん傾倒したようだ。あるいは、ダミアン・ハーストなどの西洋現代美術についてもさりげなく考察されている。
呉さん本人から聞いた話では、一九七〇年代前半生まれの彼ら世代がいちばん触れている文学は欧米のものだという。その影響は考え方のみならず、言葉自体にもおよび、呉さんたちの書く中国語は欧米の語彙や文法の影響を強く受けている。上の世代の作家からは「中国語らしくない」と言われることもあるとか。わたしはそれを聞いて、アメリカ文学を読みこんできた村上春樹の書く文章が「翻訳調で日本語らしくない」と、言われつづけてきたことを思いだした。
実際、台湾語ではなく中国語で書く時点で、「翻訳」している感覚があると、呉さんは言った。それでも中国語で書かざるを得ない事情がある。そのことに対する思いを彼は声高に語らなかったが、自らの小説言語について話す言葉のなかには繊細な考察と感慨が鏤められていた。その小説世界と言語には、当然ながら、台湾と中国と日本の歴史と文化が複雑に入り混じり、その混交が刻印されているのだ。それは本作の序盤のこんなくだりにも表れているだろう。
いつごろからか忘れたが、異言語を操る人に出会ったら必ず、「自転車」をなんと言うか訊くようにしていた〈中略〉
自分が育った環境においても、自転車という単語から地域的属性を見出すことができる。台湾で今「脚踏車」という単語が指すものを、もし「自転車」と言ったなら、それは戦前台湾の日本語教育を受けた人だろう。「鐵馬」や「孔明車」と言うなら、その人の母語は台湾語ということになる。「単車」や「自行車」という単語を口にすれば、おそらく中国南部からやってきた人たちだろう。もっとも今は、それぞれ交じり合って、明確な区別はなくなってきている。
原住民族の作家が中国語で書いた文章には、失われゆく民族の言語のスタイルがいまも残っているという。たとえば、と呉さんは言って、拓拔斯・塔瑪匹瑪(Topas・Tamapima)という布農(ブヌン)族の作家が書いた作品では、「少し待った」という場合、「牛がおしっこする時間ほど待った」と表現するということを笑いながら教えてくれた。
そうして各々の民族の言語がもつ響きの独特の美しさと優雅さについてひとしきり語ると、彼はほうっと息をついた。それは、悲嘆のため息ではなく、あくまで言葉そのものを愛おしむ吐息であった。