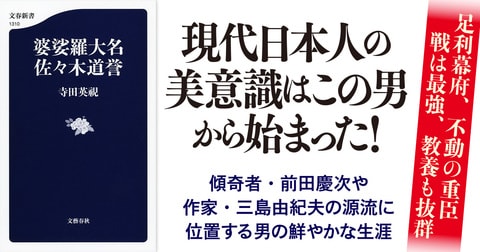最初の長編『炎環』の第一部を書き始めたのが一九六二年、はじめての新聞小説『北条政子』を書いてからもすでに十年の歳月が流れている。その間鎌倉時代を扱った作品をさほど多く書いたとはいえないのだが、この時代のことはいつも頭から離れなかった。書きながら考え、書き終っても考えていた、といっていい。こうして、とりわけ材料を漁るためでもなく、何度か『吾妻鏡』を読みかえしているうちに、いつか表紙もとれ、ボロボロになってしまった。こうなったとき、この時代の語りかけてくるものが、はっきりと私の胸の中に位置をしめるようになった。
大きな変革の時代だ、ということは前から感じていた。私が小説にとりあげたのも、そこに興味を持ったからなのだが、その実態が『吾妻鏡』の中から浮かび上って来るに及んで、変革の大きさ、深さを改めて痛感させられた。もし日本に真の変革の時代とよべるものがあったとしたら、この時代を措(お)いてないのではないか、という思いが、今は確信に近いものとなっている。
それは外からの力に突き動かされての変革ではない。内部の盛上りが必然的に一つの道を選ばせたのだ。その盛り上りの中核は何者か? このとき歴史の中に姿を現わして来る東国武士団である。一一八〇(治承四)年にはじまる一連の行動は、これまで頼朝の挙兵とよばれて来たが、これが頼朝個人の行動としてではなく、東国武士団の行動として捉えられたとき、はじめてこの時期の歴史的な意義が明確になるのではないか。
そのことを書くとしたら、小説という形式ではあり得ないだろうと思った。それではどういう形にすべきかを考えはじめてから四、五年は経つ。いまこうして書きあげたものは小説ではない。しかし歴史書のつもりはさらにない。しいて祖形を求めるならば、明治以降の数人の文筆家が歴史上の個人について書いた史伝、評伝がそれにあたるかもしれない。これら専門の歴史家以外の立場から書かれた作品が、一人の人間について述べているのに対し、私は歴史そのものを対象としているということになろうか。
いわばこれは私の鎌倉時代を扱った一連の小説の原点であり帰結である。もの書きとして、歴史へのアプローチにはさまざまの形が考えられるし、一つの時代に取組む以上、納得ゆくまでつきつめるべきだと思うが、さきに書いた『相模のもののふたち』を東国武士団の列伝とすれば、これはその総論編にあたる。
どうやらここで私は、大小いくつかの作品で扱って来た鎌倉時代に対する一つの決算書を書いたことになるのかもしれない。『吾妻鏡』を本格的に読みはじめてから二十年近く、そのときの私は旗揚げのころの頼朝と同じくらいの年齢だった。が、現在の私の年まで彼は生きていない。そうなのだ、一年前にすでに彼は死んでいる。書きあげたよろこびよりも、そんなことをしきりに考えるこのごろである。
終りに──。執筆にあたって用いた史料は、『吾妻鏡』はじめ、文中にできるだけ出典をしめしたが、その一部には『大日本史料・第四編』を利用したものもある。なお直接間接に下記の文献からさまざまの示教、示唆を得た。付記して謝意を表したい。
挿入した系図は主として『尊卑分脈』『続群書類従』などに拠ったが、東国武士団の系図には異同があり、別の説もあることをお断りしておく。配置の都合上、必ずしも配列は年齢順によらず、史上有名な人物でも、本文に関係の薄いものは省略した場合もあることを付加えておく。
(1978年記)