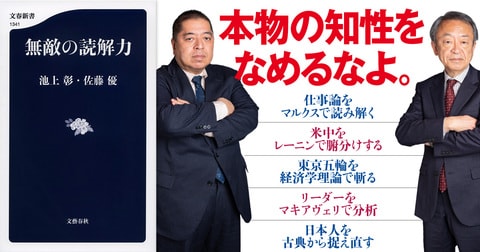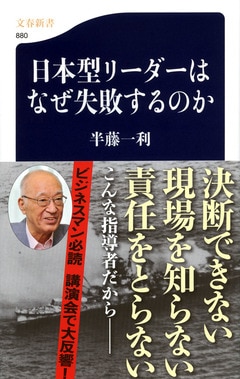改ざんなし黒塗りなし!
時事ネタを得意とするお笑い芸人が、忘れちゃいけないあの出来事を徹底記録。
3月9日に発売されたプチ鹿島政治コラム集『お笑い公文書2022 こんな日本に誰がした!』から「第五章 新聞はコロナ・五輪の2021年をどう伝えたのか?」より「おじさん新聞とアップデート」の一部をご紹介します。

おじさん新聞とアップデート
私は新聞を14紙購読しています。一般紙、スポーツ紙、夕刊紙・タブロイド紙。ずっと個人で読み比べを楽しんでいたのですが、ネタにしたら反響があったので現在はテレビ・ラジオやコラムでも新聞ネタをやっています。そんな私にとって、新聞はどう五輪を伝えたのか? これは大きな興味でした。
まず、開催前に感じたのは新聞の揺れる思いです。テレビ局はどうせお祭りになるのは見え見えですが、新聞は立ち位置が苦しそうでした。
だって、これだけツッコミどころが多い「興行(五輪)」は本来ならマスコミとしては格好の取材対象でしょう。しかしあろうことに新聞は東京五輪の神輿を担ぐ側にまわってしまった。大ボケの東京五輪師匠を担ぐ側になっていたのです。これ、痛恨のミスです。メディアとして「伝える」という意味をはき違えた。ウオッチャーとして外側から淡々と出来事を伝え、深掘りするのが新聞だろうに、中の人になっておいしい「絵」や「ネタ」を発信したいという欲望に負けてしまった。何度も言いますがこの判断はミスだったと思います。後述しますが、大手紙がそんなことだから本来はゲリラ的立場であるはずの媒体が五輪ではよく活躍していた。ゲリラが王道を制すという逆転現象を生みました。
今年に入ってもコロナは感染拡大、五輪運営はずさんという状況が続き、新聞(全国紙)には次第に葛藤が見えてきました。「お前は開催についてどう思うのだ」という当たり前の「論」を新聞は求められるようになったのです。
たとえば朝日新聞。5月26日に五輪中止を求める社説を掲載しましたが、そこへの道のりのほうが野次馬としては面白かった。この状況での開催について支持なのか不支持なのか。いつ言うの? という興味があったのだ。
そんななか、朝日で注目したのは5月14日のオピニオン欄でした。慶応義塾大学の山腰修三教授(ジャーナリズム論、政治社会学)の「メディア私評」。タイトルは『ジャーナリズムの不作為 五輪開催の是非、社説は立場示せ』(5月14日)。
《5月13日現在、朝日は社説で「開催すべし」とも「中止(返上)すべし」とも明言していない。(略)社説から朝日の立場が明確に見えてこない。内部で議論があるとは思うが、まずは自らの立場を示さなければ社会的な議論の活性化は促せないだろう。》
これには興奮しました。大学教授の寄稿ですからこれは朝日の意見ではありません。でもこれを朝日の社説を書くエライ人たちも当然読んでいるわけで、掲載後の社内の様子を想像したら興奮したのです(野次馬ですいません)。しばらく社説に注目しましたが、無反応の日々が続きました。
すると地方紙が一気に注目を集めたのです。5月23日の信濃毎日新聞である。
『東京五輪・パラ大会 政府は中止を決断せよ』(社説)
この社説はSNSでも話題を呼んだ。2日後に西日本新聞も続いた。
『東京五輪・パラ 理解得られぬなら中止を』(社説・5月25日)
そして朝日は5月26日に社説で『夏の東京五輪 中止の決断を首相に求める』を発表。大きな話題になりましたが、信毎より3日遅れでした。
もちろん、社説はネタによっては論説委員が何日も何カ月も議論をして準備をしているのだろう。だから地方紙に刺激されて掲載したわけではないはず。しかし信毎の「3日後」という掲載タイミングは絶妙に遅れた感があった。
社説は自分のことを「社説」と呼ぶ
さて、その点を頭に入れると今度は朝日「社説」の読み方が面白くなるのです。独特の文体というか表現に気づいてしまいました。
先ほど紹介した開催中止を求めた5月26日の社説には人々が活動を制限され困難を強いられるなか、それでも五輪を開く意義はどこにあるのかと説いたあと、こんな一節が続く。
《社説は、政府、都、組織委に説明するよう重ねて訴えてきたが、腑に落ちる答えはなかった。》
ここで注目したいのは「社説は」という言葉づかいです。社説は自分のことを「社説」と呼ぶのです。なんかアイドルみたい。私はこの発見にワクワクしました。
説明しましょう。私は昔、言葉づかいが難しいので社説が苦手でした。しかし芸人になって新しい読み方を発見しました。それは“社説の擬人化”です。社説を「大御所の師匠が小言を言っている」と想像して読んでみることにしてみたのです。すると社説のちょっと難しくてエラそうな言い方も面白くなってきた。
そんな「擬人化」を一人で実践していたのですが、社説による「社説は」という自分語りはまさに擬人化を楽しめるではありませんか。なんならちょっと可愛く見えてきてしまった。
ただ、この「社説は」表現は可愛さだけではありません。大事な点がもう一つあります。
「社説は」と区別化することで、朝日のほかの部署の論調はともかく「私(社説)はずっと五輪に小言を言ってきたのだからね」とアリバイを言っているようにも読めるのです。そして今こうして中止を求める社説を出したけど「別に遅くはないんだからね」という行間を感じるのです。
実はこの「社説は」という言葉づかいは五輪関連社説の節目節目に登場していました。いくつか例をあげます。
開会式当日(7月23日)は、
《社説はパンデミック下で五輪を強行する意義を繰り返し問うてきた。だが主催する側から返ってくるのは中身のない美辞麗句ばかりで、人々の間に理解と共感はついに広がらなかった。》
ほら、開会式という大一番の社説で「社説は」(私は)今まで何度も言ってきたからねという確認とアピールをしています。そして「それなのに主催側から返ってきた言葉はなんだ」とご立腹。大一番の日にふさわしい「社説は」の使い方です。
『五輪閉幕へ』(8月7日)では、
《社説は4年前、法律や条例の対象外である組織委にも、文書管理を徹底して国民への説明責任を果たすよう求めた。改めて念を押しておきたい。》
この日はわざわざ4年前という具体的なアリバイまで披露していました。
いかがでしょうか。こうしてみると朝日社説は五輪のスポンサーやってるけどどうなんだよ、という世間の視線に対して「いやずっと前から私(社説)は小言を言ってますから」というアピールに懸命だったように見える。こんな読み方は意地悪でしょうか?
「社説は」という言葉づかいが出てくるときはすなわち「感情」があふれ出ているとき。五輪関連の社説の節目節目に登場したということはそれだけ「世間はいろいろ言うけどちょっと待ってくれ」という主張があったということです。
このつづきは本書にてお読みください。