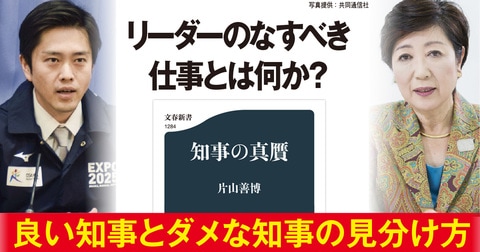二〇一七年一〇月二日に、一人で立憲民主党の設立を宣言してから三年。二〇二〇年九月一五日、国民民主党や無所属の仲間と合流し、衆参両院で一五〇人の議員からなる新たな立憲民主党を結成した。ようやく、次期衆院選に向けて「政権の選択肢」となるためのスタートラインに立てた。
衆議院が解散された二〇一七年九月二八日、当時所属していた民進党が、小池百合子東京都知事率いる「希望の党」への、事実上の合流を決めた。翌日、私は、小池百合子氏の掲げていた理念には同意できないと考え、「希望の党」へは加わらない決断をして、地元埼玉五区の自治体議員の仲間に伝えて了解を得た。
その後、立憲民主党を結党することになるが、多くの仲間が、「希望の党」から「排除」される見通しとなった事態を受けての、急な結党だった。だが、選挙戦では私自身が驚くほどの大きなご支援をいただき、結党からわずか二〇日で五五議席を獲得して、野党第一党になることができた。
その後も紆余曲折はあったが、私たちの旗のもとに入党してくれる仲間も少しずつ増え、二〇一九年夏の参院選では、野党間の選挙区調整や選挙協力もあり、議席をほぼ倍増させることができた。
同年秋の臨時国会からは、国民民主党などの仲間と国会内の会派をともにすることになり、質量ともにトータルとしての国会での論戦力が増した。野党議員の追及によって「桜を見る会」問題をはじめとする安倍政権への疑惑がより明確になるとともに、新型コロナウイルス感染症への対応では、政府に一定の協力を行いつつ、野党側から積極的に多くの対策を提案し実現させてきた。
これらに加え、大学入学共通テストの民間委託や検察庁法改悪を阻止するなど、与野党の議席差を感じさせない「成果」を国会内で上げていることにも、ぜひ目を向けていただきたいと思う。
この間、私は、立憲民主党や私自身が訴えてきた「自民党政権にかわる新しい社会のかたち」が、有権者の皆さんになかなかうまく伝わらないもどかしさを感じてきた。
二〇一七年の衆院選で、私は「右でも左でもなく、前へ!」と訴えた。それ以前からも一貫して、自身の立場について「『保守』であり『リベラル』」だと説明してきた。これらの言葉は、有権者の皆さんから強い共感の声をいただく一方で、「何を言っているか分からない」との批判も少なからず受けた。
日本では、五五年体制当時から、与野党の対立を「右」「左」で表現してきた。自民党を中心とする与党側が「右」、社会党を中心とする野党側が「左」。五五年体制が崩壊した現在では、これがそのまま「保守」と「リベラル」という言葉に置き換えられている。つまり、日本の政治に関する言論環境の中では、「保守」と「リベラル」は対立概念とされてきた。
私は、その「常識」に異を唱えるべく、あえてこうした言葉遣いをしているのだが、そうした私の立場に違和感を覚える人が、少なからずいることも理解できる。
そんな中で、二〇二〇年の年明けから、新型コロナウイルス感染症の脅威が世界に襲いかかった。このウイルスの猛威と、対応に追われる安倍・菅政権の迷走は、結果として現代日本が抱える多くの問題点や課題をあぶり出した。
新型コロナウイルスの感染拡大は、なお予断を許さないが、このことによって私は、これまで訴えてきた「私たちが目指す社会」の方向性は間違っていないことを確信した。「多様性を認め合い、困ったときに寄り添い、お互いさまに支え合う」社会。上から画一的に社会を導くのではなく、社会を「下から支えて押し上げる」政策。こうした方向性が、今こそ求められている。
この機会に改めて、私の考える「ポストコロナの社会像」を明らかにしたいと考え、二〇二〇年五月二九日の定例記者会見で、「支え合う社会へ─ポストコロナ社会と政治のあり方(命と暮らしを守る政権構想)」を発表した。
これは、党で議論して決定したものではなく、私個人としての「たたき台」に過ぎない。しかし、安倍政権に不安や不満を抱く皆さんや、自公政権に代わる新しい政権を目指す皆さんの間では、その趣旨や本質について、おおむねご理解いただけたと確信している。
そして、国民民主党などとの合併で新たにスタートするにあたってつくられた新しい「綱領」において、新たな知恵やアイデアも取り込みながら、その方向性を多くの仲間と共有することができた。
本書は、会見で発表した政権構想や、新しい立憲民主党綱領のベースになっている考え方、特に官房長官として対峙した二〇一一年の東日本大震災以降、折に触れ考えてきたことを執筆した。私の政治理念や政治哲学、ビジョンと呼んでいただいて良いと思っている。私が誤解を恐れず訴えてきた「『保守』であり『リベラル』である」という言葉の意味についても、詳細に説明している。
念のため付け加えれば、立憲民主党の個別政策や総選挙に向けた選挙政策を記したものではない。考え方を説明するのに必要な範囲で各論の記述もあるが、網羅的な個別政策は、幅広い国民の皆さんにご意見やご提案をいただきながら、党全体として、深化させた政権構想へと練り上げていくことになる。
第2章で述べているが、自民党に対抗しうるもう一つの選択肢として認められる上で、本質的に重要なのは、その時々の社会状況に応じて短期的な目標として示される各論よりも、理念とか哲学とも呼ぶべき「目指す社会像」を明確にすることだと確信している。
さて、私には、一九九八年に新民主党(新進党解党を受け、旧民主党を含む四党が合併してできた民主党)が結成されてそう間もない時期に聞いた、忘れられない言葉がある。
今となっては若気の至りと言うしかないが、当時二期生だった私は、若手の同僚議員とともに、当時三期生の岡田克也さんに、党の代表選挙に立候補することを要請した。岡田さんは、その要請をにべもなく一蹴したのだが、その理由は、「総理になる準備ができていない」というものだった(その後、岡田さんは、総理になる十分な準備を整えて、民主党の代表となった)。
野党第一党の党首は総理候補であり、その準備もないのに手を挙げることは、国民の皆さんに対して無責任極まりない。ある意味で当然のことだが、そのことを明確に認識していた岡田さんの真面目さと真剣さに、私はたじろいだ。
二〇一一年三月、私は、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故に対応する菅直人総理(当時)を、官房長官としてすぐそばで支えていた。その対応に至らない点があったことは、私も含めて重く受け止めていかなければならない。
この深刻な危機への対応を通じて、私は、「総理の責任の重み」を、なお一層、痛感させられた。
三月一二日の早朝、菅総理は、原子力発電所を含む被害状況を直接に把握する必要があるとして、ヘリコプターで総理官邸から飛び立った。その直後、万一の場合が頭をよぎり、私は背筋が寒くなった。私は、総理大臣臨時代理順位の第一位、総理に万一のことがあれば、この空前の危機に、トップリーダーとして対応しなければならない。発災直後から、官房長官として、すべての責任を背負ってこの危機に対応するのだと、腹を据えていたつもりだったし、その時点では、専門家から原子力発電所が爆発する可能性はないと言われていたが、官房長官等の一閣僚とは質的にも量的にも比べものにならない、総理が背負っているものの重さを、はじめて、みずからのこととして垣間見た瞬間だった。
そして、三月一二日に水素爆発が起きるなど、事態がさらに深刻化する中、三月一五日未明、東京電力が、福島第一原子力発電所からの撤退を打診してきた。事態が深刻化し、現場で作業を続ける方々には、命に直接かかわる危機が高まっていた。現場での作業を止めれば日本全体が大変なことになるから、撤退はありえないと思いつつも、平時に一般論として「命を懸けて欲しい」と言うのと、現に存在する危機にあってお願いすることは、決定的に意味が違う。
私は、関係する政府首脳や専門家と情報や認識を共有した上で、総理に判断を仰いだ。当時の菅総理は、いつも以上に毅然とした態度で、そしてためらうことなく、撤退は認めないと決断した。当然の決断と思いながら、同時に、このように重い判断を決然と下したことに、総理の責任の過酷さを改めて痛感した。
民主党が下野した後、何度か行われた野党第一党の党首選挙の都度、立候補を促す声をかけてくれる仲間がいた。それぞれの時点で、そもそも立候補に必要な推薦人が集まってくれるのかわからなかったが、それ以前に、私は、総理になる準備も覚悟もできていなかったために、そのありがたいお誘いをお断りしてきた。
本書は、二〇一四年ごろから執筆を始めたものである。下野した民主党の一員として、そしてリーダーシップを発揮することを勧めてくれる仲間もいる中で、総理になる準備と覚悟を、執筆を通じて確認していきたい、という思いだった。
慌ただしく展開する政治の流れの中で、本書を書き上げることができないまま二〇一七年九月の民進党代表選に立候補した。本書の出版は間に合わなかったが、総理になる準備が整い、その覚悟ができたと確信したからに他ならない。
その後は、私が想像もしなかった展開で野党第一党の代表となり、政権の選択肢となるために、そして、政権奪取を目指すために、さらに慌ただしい日々が続いた。そんな中でも、何年にもわたって、何度となく書き直しや書き加えを重ねながら、政権選択選挙=衆議院総選挙までに世の中に示したいと思ってきた。
本書を書き上げ、そんな準備と覚悟の一端を示すことができたと思っている。
まずは、先入観にとらわれず本書をお読みいただき、日本の未来を考えていただければありがたい。
二〇二一年四月
(「はじめに」より)