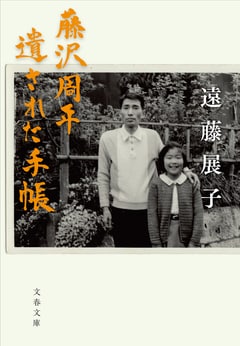藤沢周平の傑作長篇を原作としたオリジナル時代劇『三屋清左衛門残日録』、シリーズ第6作『三屋清左衛門残日録 あの日の声』の製作が発表された。2016年の第1作より三屋清左衛門役を演じる北大路欣也さんに、話をうかがった。

久しぶりにこの場所(三屋家隠居部屋)に帰ってくると、ほっこりする、というか、とても和みますね。
シリーズ6作目になりますが、毎回、作品のテーマは変わるので、とても新鮮な思いでやらせていただいています。鏡の前で、これから清左衛門になるんだなと思うとき、気持ちがいいですよね。こういう人物になれたらいいな、という主人公に対する思いがあり、その世界に入っていく喜び、やりがいがある。
なかなかお目にかかれないくらいの人物像ですし、これは藤沢先生の魂だと思うんです。そういうエネルギーが、ぼくを支えてくれています。
道場で子供達に稽古をつけ、孫の小太郎もすくすくと育ち、と平穏な日々を送る三屋清左衛門。ほのぼのした場面で物語は始まるが、ある時、額を斬り割られた普請奉行・志田弥右衛門、背中から袈裟斬りにされた奉行助役の大関泉之助——斬り合ったと思われる二人の血まみれの遺体が見つかる。
駆けつけた弥右衛門の息子たちは、泉之助の父・大関助太夫に、「泉之助から仕掛けた斬り合いに相違ない」と言い放つ。
今回の脚本を読ませていただいたとき、現代とオーバーラップする感覚がありました。世界のあらゆる情勢にゆらぐ人間の心…そんなものを、感じましたね。珍しく、「怒り」も感じました。
一番大切なのは“出会い”であり、お互いを支え合う思いである。それはこれまでの作品にも出てくる大きなテーマなんですけれども、今作でも、登場する皆さんがそれを感じたのではないでしょうか。
親子の宿命、それをどう受け止めるか
――助太夫は泉之助の養父であり、実の親は、20年程前に起こした騒ぎによって自ら禄を返上、武士を捨て、今は百姓をする赤松東兵衛。東兵衛は泉之助の葬列の場に突然現われ、この裏には企みが隠されている、ただでは済まさぬ、と面前で訴えます。
今回のテーマの一つには“父と息子の葛藤”というものもありますね。
皆さん全員、“親子”を経験しているでしょう。みんな、親がいる。でも一人一人違う。
その、ある意味「宿命」を、どう受け止めていくのか――。
この物語でも、父の思い、息子の思いが一致するかといえば、そうではない。息子は父の背中を追う。お父さんの正義が息子にとって憧れだった、というのはわかります。一方で育ての親である養父は、それ以上に想いが深まる。もっと大事にしたい、もっとこうしたい――。
そういう二人の父親が出てきます。その運命の行く末が、あまりにも違う、皮肉なものになっていくというところに、愛もあるけれど悲劇もある。清左衛門にとっては、赤松が20年前なぜ武士を捨てたのか、当時、何か見逃していたことがあったのではという思いに駆られ、事件に身を投じていきます。
――清左衛門はいまは隠居していて、何の肩書も地位もない立場です。そういう人だからこそ表現できる世界が、あるのでしょうか。
清左衛門自身は意識していないのだけれども、もって生まれた才能、というか、今いる場所・出会う人に対して一番素直に、真正面から向き合いながら、どう対応していくかを考える――。しっかりと地に足をつけ、何か目標をもってそこにたどりつこうとして生きている人、そういう人じゃないでしょうか。
たまたま先代の殿のお側付き、という立場だったけれども、前面に出ずに、あらゆることが常にいい方向にいくよう、いつも考えている。自分自身のことだけを考えて、生きて来た人ではない。やっぱり憧れますね、清左衛門には。
ぼくは「三屋」を、現代劇より現代劇だ、と思っているんです。こんな想念の人がいたら、いい会社ができるだろうし、いい村ができるだろうな、と。時代劇・現代劇の境目がない作品ですよ。

――町奉行・佐伯熊太役の伊東四朗さん、嫁の里江役である優香さん……シリーズでおなじみの共演者の方たちとは別に、駿河太郎さん、小野寺昭さんなど、今回新たに共演される方もいますね。
初めてご一緒する方の場合、役のイメージでまず対面します。やっているうちに、あっ、この人はこういう感覚をもっているんだな、とお互いにわかってくる。役のもっている魅力を十分に感じ取り、現場に来てぶつかる。そういう新鮮な喜びがありますね。
最初のうちはそれなりに遠慮もあるんですが、役を通じて知り合うようになってきて、楽屋裏でぼくの経験したことのない話を聞いたりすると、へーーっと思える。
13歳の時から役者をやっていますが、いまでも新しい出会いがあるというのはありがたい、幸せなことです。
東映京都撮影所からはじまった俳優人生
――1956年、この東映京都撮影所で撮られた映画『父子鷹(おやこだか)』で、デビューをされました。先ほど“父と息子”の話が出ましたが、北大路さんとお父様である市川右太衛門さんは、どのような親子だったのでしょうか。
ぼくは2歳で終戦を迎えましたが、戦後まもなくは映画を撮れなかったので、みんな舞台で地方巡業に出かけていく。一旦出かけたら、しばらく帰ってきません。めんこになった父の姿とはよく顔をあわせていました(笑)。
あるとき皆が帰ってきて、食事をしているところへ迎えに行きました。あそこにお父さんがいるよ、と言われ、父親に「こっちへこいこい」と呼ばれたけれど、飛びついてはいけなくて、どうしよどうしよと隠れてしまった。やはり特別な存在でした。
父は釣りが好きで、朝3~4時から鴨川上流で鮎釣りをするんです。ぼくは小学校に行く前に、自転車でおにぎりを届けにいったりしました。若い頃の勇ましい、大きな親父さんを覚えています。
ある時たまたま、『父子鷹』の子役を探していた。今みたいにプロダクションはありませんし、麟太郎というその役と偶然同じ年齢だったことから、この世界に入れていただきました。そのレールはぼく自身が敷いたものではない、“運命”ですよね。
この東映京都撮影所は、俳優・スタッフ含めて、宝の島ですよ。先人の方々の、ものすごい努力のあとが、今も残っている。自分も先輩に教わりながら、追いつこう追いつこうと思ってやってきましたが、若い後輩の方たちが時代劇を受けついで、盛り上げていってくれたら、本当に嬉しいですね。
――『三屋清左衛門残日録』シリーズ、北大路さんにとって、改めてどういう作品でしょうか。
現代もの・時代劇、これまでいろいろな役をやらせていただきましたけど、これは若くては絶対にできない役。それが70代前半で出会えたことは、非常にラッキーでした。自然に役を受け入れることができました。
自分自身の人生と、清左衛門の人生。並ぶというわけではないけれど、追いかけることができます。ぼくにはぼくの残日録がある――理想の老後を、清左衛門を通して表現できる。清左衛門は、奥さんを先に亡くした寂しさはあるだろうけど、そこは嫁がちゃんとフォローしてくれている。なんて幸せな老後だろう、と思いますね(笑)。