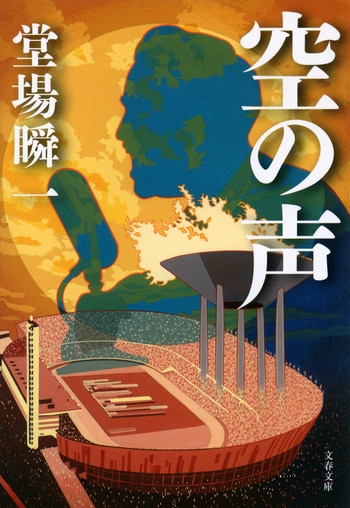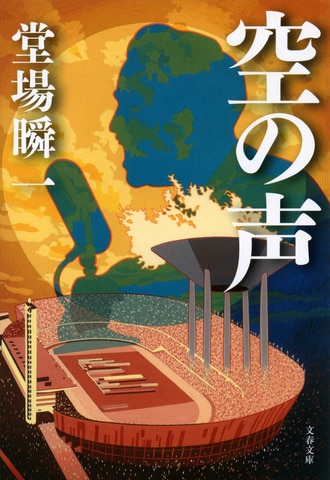
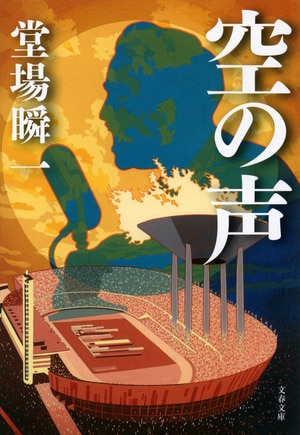
駆け出しの頃、ベテラン編集者から「作家は評伝を書いてこそ一人前」と言われた。そのことがずっと頭に引っかかっていて、実際にターゲットにしている人もいる。例えば、1930年代から1950年代に活躍した喜劇役者の古川ロッパ。何とか書きたいと長年資料を集めながらも、未だ実現できていないが、逆に一瞬で引きこまれて書き上げてしまった人もいる。私にとってそれが、和田信賢だった。ただしこれは評伝ではない。あくまで小説だ。
2020年の東京五輪を前に、五輪関係の小説を何冊か一気に刊行しよう、という企画を2017年から進めていた。地元で五輪が行われるのは、私の人生でこれが最後だろう、という思いがあったからだ。その時には、まさかコロナ禍で開催が1年先延ばしになるとは考えてもいなかったのだが。
得意のマラソン、日本が金メダル獲得の可能性がある野球、大谷翔平ではないが複数競技の「二刀流」という3本は比較的早く決まったのだが、もう1本で悩んだ。一つぐらい、オリンピックの歴史を振り返る作品があってもいいな、ぐらいの考えでいたのだが、具体的に何を取り上げるかがなかなか決まらない。
どうしたものかと、当時の文藝春秋の担当者と本格的に打ち合わせを始めたのが、2017年の秋である。オリンピックの歴史と言っても、日本人が最初に参加したストックホルム五輪は、別の作品で書いている。どうしたものか……。
担当者とあれやこれや案を出し合い、日本が戦後、国際社会に復帰して最初に参加した夏季五輪、ヘルシンキ大会を舞台に取り上げることは決まった。この時は、レスリングフリースタイルの石井庄八が、金メダルを獲得している。戦後初の日本人金メダリストか――と一瞬心が動きかけたが、レスリングというのは、描写が非常に難しいスポーツだ。試合シーンの描写に命を賭けている私としては、これは大変な難題になる。
さらに調べていって行き当たったのが、和田信賢という存在だった。体調が悪い中、現地からの中継に参加して、その後パリで客死――こういう劇的な人生は、作家の琴線に触れる。しかも、日本放送史の黎明期に一際輝く存在だったことも分かった。こういう情報が積み重なった末、担当者と顔を見合わせて「勝ったな」とニヤリとした。
元々「報じる側」にいた私にとって、五輪を「伝えた」人を主人公に取り上げることには意義がある。私はペン、和田さんはラジオというメディアの違いはあるものの、大先輩の足跡をたどってみたくなったのだ。
わずか1時間かそこら調べただけで、私はまったく偶然に知った和田信賢という人物の虜になっていた。これだけの人を書かないわけにはいかない。
本書内でも和田さんのキャリアについては触れているが、ここで改めてまとめておく。
1912年、東京に生まれた和田さんは、1934年、日本放送協会に第一期のアナウンサーとして入局する。和田さんが一躍その名声を輝かしいものにしたのは、戦前の相撲中継である。双葉山の連勝記録が69で止まった時の中継を担当していたのがまさに和田さんで、その情緒あふれる実況は、当時の相撲ファンの想像力をどれだけかきたてただろう。本人は、自分の中継を「瞬間芸術」と呼んでいたという。
和田さんはその後、1945年8月15日の終戦放送の進行役を担当、終戦の詔勅を朗読した。アナウンサーとしては「硬軟」両方をこなせる人だったことが、ここからも分かる。戦後は山形放送局に異動になったが、直後に退職、講演などの活動をすることになる。しかしアナウンサーとしての技術と人気をNHKが放っておくわけもなく(当時は民放がなかった)、間もなくラジオクイズ番組「話の泉」の司会者になった。バラエティ番組の走りのようなものだが、徳川夢声(作家、俳優)やサトウ・ハチロー(詩人、作詞家)山本嘉次郎(映画監督)ら癖のある出演者を向こうに回して番組を盛り上げ、司会者としての人気は戦後の絶頂期を迎える。最近はアナウンサーもタレント化しているが、その走りとも言える存在であったようだ。
そして念願のヘルシンキオリンピックの取材団に加わったのだが、出発前から体調を崩しており、満足のいく中継はできなかったようだ。帰国前に立ち寄ったパリで体調はさらに悪化し、異国の地で客死したのは先に書いた通りである。あまりにも生き急いだ感じがしないではない。
アナウンサーになってから戦前の相撲中継、終戦、そして戦後の人気番組の司会と、和田さんの人生は波乱に富み、どこを切り取っても興味を惹かれる。しかし今回のテーマはあくまで「五輪」。それ故、和田さんの劇的な人生全てを書き切ることは、早々に諦めた。彼の最後の「仕事」であるヘルシンキ五輪中継に的を絞り、「伝える」覚悟、そして意義を描くことに挑んだつもりである。だから一生を描き切る評伝ではなく、小説になった。
単行本が刊行された時には「そんなに体調が悪いなら行かなければよかったのに」「仕事を果たせなければ行った意味がない」という感想をよく聞いた。しかし現在とは状況が違い、当時は海外渡航も不自由な時代である。このチャンスを逃したら次はない――と和田さんが必死になったことは想像に難くない。
私は「行かなければよかった」とはまったく思わない。一人のプロが覚悟を固めて仕事に挑んだ姿に、ただただ圧倒されていた。そのせいか、日々悪化していく体調を描くのは非常に苦しい作業になったのだが、和田さんの行動が間違っていたとは一度も考えなかった。命と引き換えにやらねばならないこともある――敗戦のショックから立ち直りかけていた日本には、和田さん以外にもそういう覚悟を持った人が少なくなかったはずである。
文庫化にあたって改めて読み直してみたが、やはり和田さんの行動には感情移入してしまう。そして、自分がこれまで楽な仕事しかしてこなかったのでは、という後悔に苛まれるのだ。命を賭けて小説を書くというのがどういう感じになるかは分からないが、自分は果たしてそこまでの気持ちをこめて、全身全霊で普段の仕事に取り組んでいるだろうか。
和田さんと私では仕事の内容が全く違うので「先生」とは呼べないのだが、これからも折に触れ、和田さんの生き方を思い出し、自分の仕事、そして人生のあり方を反省することになるだろう。せめて「師匠」ぐらいは呼ばせてもらいたい。
和田さんのことを調べて、その「時代」にも強く興味を引かれるようになった。戦前、戦中、戦後――日本が一度壊れ、そこから立ち直っていくダイナミックな時代。私はこれからも歴史小説を書くことはないだろうが、これぐらいの「近過去」には非常に引きつけられる。現代日本の基礎ができたのがこの時代であり、混乱期を描くことで、現代の諸問題のルーツを探ることができるのではないかと思っている。
既にこの時代を舞台にして『動乱の刑事』(講談社文庫)『幻の旗の下に』(集英社)を書いたが、まだまだ書くべきこと、書くべき人はたくさん存在すると感じている。おそらく今後も、この時代を舞台に書く機会を探っていくだろう。
とはいえ、終戦前後のこの時代も、既に70年以上前になる。「一世代30年」という考えに基づけば、既に二世代以上前の時代になり、立派に「歴史小説」になってしまうのかもしれないが。
(「文庫版あとがき」より)
-

<堂場瞬一インタビュー>五輪に命をかけた伝説のアナウンサーがいた
-

<堂場瞬一インタビュー>自由を奪われた時代だからこそ、仕事とは何かを考えさせられる物語。
-

「何かを決めることができる会議体ではない」汚職が次々と明るみに…東京オリンピック大会組織委の“実態”とは
2022.11.03インタビュー・対談 -

文春文庫秋のミステリーフェア
2022.11.07特集 -

「文春文庫 秋100ベストセレクション」プレゼントキャンペーン
2022.09.01特集 -

「IOCは『汚職事件があった国では開催できない』と言うべき」東京オリンピックで露呈したスポーツ界の“悪しき体質”
2022.11.03インタビュー・対談
-
『圧勝の創業経営』
ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
応募締切 2025/07/26 00:00 終了 賞品 『圧勝の創業経営』5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。