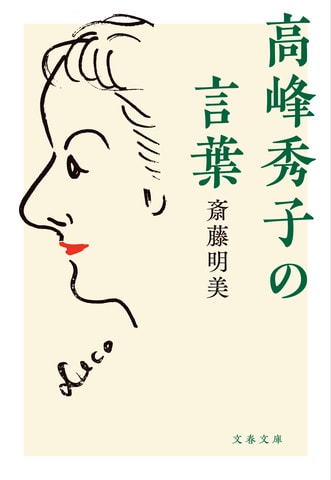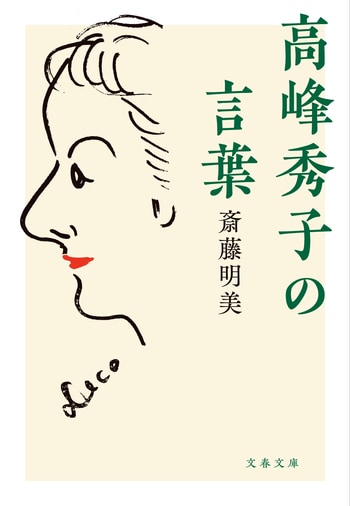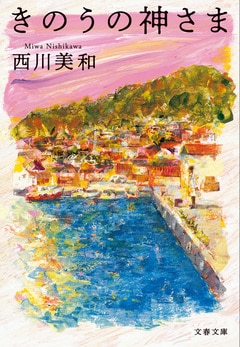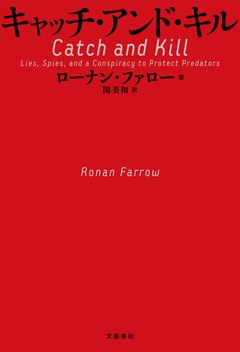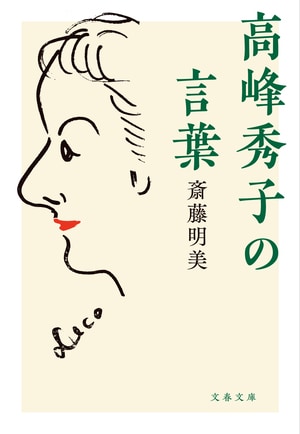
本書には“惹句”になるような高峰の言葉を集めたが、それだけでなく、日常でふと返ってくる彼女の言葉もまた絶妙だった。
ある深夜、八十歳を過ぎた高峰が骨折して、救急車で運ばれ手術した。松山と私は術後の無事を見届けてその夜は帰宅することにした。病院の暗い駐車場で、少し離れた所にいるタクシーに乗り込もうと、松山の手をとって急ぎ足に向かった時、グギッというイヤな音がした。私は左足首を骨折した。
翌日、二人で病室を訪れると、私が松葉杖をついているのを見て、ベッドの高峰は目を丸くした。
「大好きなかあちゃんが右脚を骨折したから、私は左を骨折したの」
照れ隠しに言うと、高峰から返ってきたひと言が、
「余計なことしちゃったね」
これ以上妥当な言葉があるだろうか?
その後、松山の世話をしながら病院の高峰のもとに通った三か月の間、私はイヤというほど、その言葉が身に染みた。
松山家で夕食をご馳走になった後、高峰が私を見送ってくれた時だった。玄関外のガレージには金属の横格子がはまっている。その脇のドアを閉めた後、私は名残を惜しんで、中にいる高峰に向かって格子の間から手を延ばして叫んだ、「かあちゃ~ん」。
高峰がひと言、
「ギャビーッ」
わからない人にはわからない。
ある日、松山家の食卓で料理を待っていた私は、台所の高峰に向かってカウンター越しに言った、「あんまりお腹が空いたから、かあちゃんのことが大きなニワトリに見えてきた」
台所から高峰が、
「黄金狂時代」
これも、わからない人にはわからない。
ある晩、私の知らない食材がテーブルに出た。
「何? これ」
私が訊くと、高峰が煙草をくゆらせながら、
「ま、やってみな」
いなせである。
七十も半ばになった、もと大女優が言う言葉か。カッケーッ。
だから話が面白いのは当然だった。
「あんた、『覇王別姫』って映画、観たことある?」
ハワイの松山家で二人で話していた時だった。
「ううん、ない」
と、高峰はおもむろに語り始めた、
「昔、中国でね、一人の男の子が親に売られるんだよ。すると人買いが『この子の指は六本あるじゃないか』って値切ろうとした。するとその親は子供の手を台の上に置いたかと思うと、やおら傍にあったナタをつかんで、パーンっと子供の指を一本切り落とすんだよ」
キャー。私は心の中で叫んだ。
「やがてその子は年上の少年と知り合って、おニイちゃんとも慕って成長していくんだけど、そのおニイちゃんのことが好きになる(中略)でもおニイちゃんはある女の人を好きになってね。それを知った主人公の青年は、最後、剣を持って踊りながら、クッ、と自分の喉をかっ切る。いい映画だから観てごらん」
み、観てごらんって……。私は身体が固まっていた。
それを語っている時の高峰の眼。喉をかっ切ると言った時の、龍のようなその眼! 仕草、声音……。私は一瞬も高峰の顔から目が離せず、物語を“観て”いた。
帰国後、ビデオを借りてきて「覇王別姫」を観たが、ハッキリ言って、高峰の語りのほうが面白かった。
ちなみに、その後、千葉の幕張で映画祭があり、高峰が功労賞を受けたのだが、壇上にいると、以下、高峰の話。
「背の低い、冴えない男が舞台に上ってきて、いきなり私の手を両手でつかむと、何か中国語でまくしたてるんだよ。なんだろう、この人って思ってたら、傍にいた女の人が、その人通訳だったんだね、『私は昔からあなたの大ファンで、あなたの映画は全部観ています。おめにかかれて本当に光栄です、と言っています』って。それ、レスリー・チャンだったの」
「えーーーッ」
私は思わず声を上げた。
「映画観てるのに、わからなかったの?」
すると高峰は、
「だって映画の中と全然違うんだもん。髪はボサボサで背が小さいし、ほんとに冴えない男だったから、わからなかった」
その数年後、名優レスリー・チャンは、自殺する。
人が発する言葉は、どこから出てくるのか? もちろん脳が指令を出すのだが、当然、端から無いものは出てこない。しかし所有している語彙が多ければよいというものではない。難解な言葉を知っていればよいというものでもない。学歴も関係ない。今、どの言葉を発するか。一体、その言葉の選択は思考回路のどこをどう動いて、最終的に口の外に出るのだろう?
そして選んだ言葉の出し方。つまり話し方。
高峰も好きだった「十二人の怒れる男」という名作映画がある。
父親殺しの容疑で逮捕された十八歳の少年を十二人の陪審員が裁く話だ。状況証拠から見てすぐに全員一致で有罪評決に達すると思えたが、ヘンリー・フォンダ扮する建築家だけが最初から無罪に投票する。「へそ曲がりっていうヤツはいるものだ」と他の陪審員に揶揄されながらも、彼は一つ一つの証拠を粘り強く検証していき、やがて一人、また一人と無罪に意見を変えていく。その時、たまりかねたように一人の老人が自論をがなりたてるように喋り始める。それは人種への偏見、スラム街に住む人間への蔑みなど、あらゆる偏見に満ちた意見だった。すると陪審員たちは壁際の椅子へ、窓辺へと、次々に席を立ち、その老人に背を向ける。「聞いてくれ、あのガキは嘘つきだ、悪党だ、おい、わしの話を聞けよ……」、目の前の席にいた紳士に「やめたまえ。金輪際、あなたの話は聞きたくない」と言われ、老人は力なく席を離れ、隅の小さな机に向かう。席に戻った建築家が「どんな場合も個人的偏見抜きにものを考えるのは容易じゃありません」と語り始めると、皆が席に戻っていき、建築家の言葉に耳を傾けていくのだ。
テレビドラマだったこの作品を名匠シドニー・ルメットが映画化したのだが、このシーンは圧巻であり、言葉というものに内在する人間の根源的な問題を観る者に突きつける。
耳を傾けずにはいられない、目を離すことができない語り口と言葉。講釈師や俳優などが決められた台詞を語る時も当然だが、それが己独自の言葉となった時、その違いが極めて明確に表れるのだ。男であれ女であれ、何歳であれ、どんな職業の人であれ。
声高に多くを語っても人の心を動かさない人、静かなひと言が心を鷲掴みにする人、その違いはどこにあるのだろう?
私は高峰に出逢ってから、高峰が死んだ今でも、そのことを考える。
あの高峰秀子という人の言葉は、どこから来るのか――。
感性か?
「合ってる?」、死んで高峰に再会したら、訊いてみるつもりだ。
まもなく生誕百年を迎える母・高峰秀子に捧ぐ
令和五年 正月
(「あとがき 文庫化によせて」より)