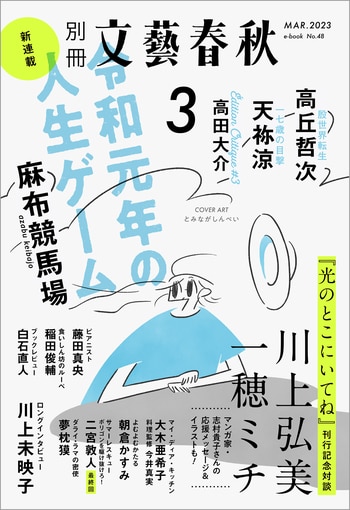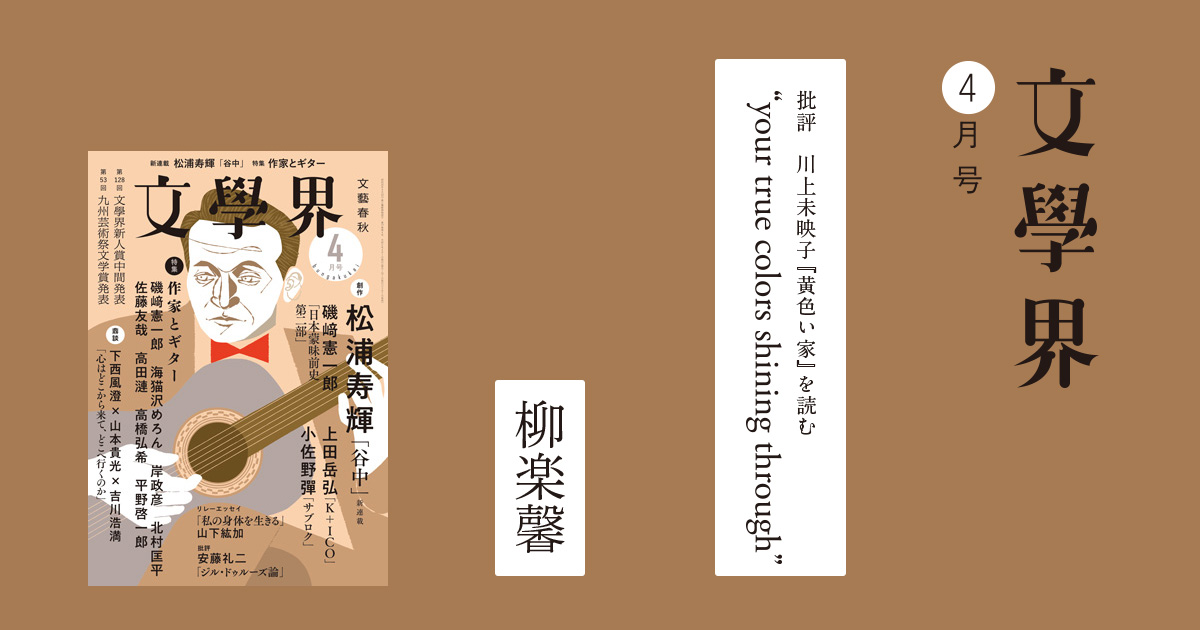「カネ」「家」「犯罪」、そして「カーニヴァル」
——新作の『黄色い家』、夢中になって読み、胸が熱くなりました。これは新聞に連載された長篇ですね。
川上 ありがとうございます。そう言って頂けて、ほっとしました。新聞連載を始めるにあたって、最初になんとなく、女の人たちが疑似家族みたいに暮らしているイメージが浮かんだんです。そのコミュニティがどうやって成り立ち、どう変容していくのかを書きたいと思いました。
——第一章の「再会」は、二〇二〇年が舞台です。主人公の四十歳の伊藤花は、小さなネット記事を見つけて動揺する。それは吉川黄美子という六十歳の女性が捕まり、裁判が行われたという記事。どうやら花は少女の頃に黄美子や、蘭や桃子という少女と一緒に暮らしていたらしい。さらに当時、彼女たちは何か犯罪に手を染めていたらしい。一体何があったのか……と思わせて、第二章からは九〇年代に遡り、花と黄美子の出会いからが語られていく。着想の段階では犯罪が絡んでくる話になるとは思っていなかったのですか。
川上 誰かが何かをやって、その疑似コミュニティの中の関係が変わっていくのかな、というくらいの感じでした。
まず、新聞連載だということを考えたんですよね。新聞って限られた行数で「こんな事件がありました」という事実を伝えるけれど、その事実の後ろには見えないものがある。事実の後ろにある個別性を書くのも小説の大事な仕事だと思うので、新聞連載をやるなら何かの記事から始めて、それを読んで受ける印象が、必ずしも現実や、経験した本人の記憶と重なるわけではないし、本人でさえ真実がどこにあるのかわからない、そういう感触をつかみたいと、書きながらプロットを作っていきました。
——え、こんなに一級のミステリーになっているのに、事前にプロットは作らなかったのですか。
川上 私もわからなかったんです。最初の、花の中学生時代を書いているうちに、だんだん花や黄美子さんの性格がわかってきて、じゃあこういうことかな、って。
——東京の東村山でスナックで働く母親と暮らす花は、十五歳の夏、帰ってこない母の代わりに黄美子と過ごす。二年後、十七歳で黄美子と再会した花は、家を出て彼女と一緒に三軒茶屋でスナックを開きます。わたしは読んでいて、この先、黄美子が主犯格となって犯罪に手を染めていくんだろうと思ったんですよね。
川上 そう、最初はそういう印象を持ちますよね。でも、誰だって生きていると加害してしまうこともあれば被害を受けることもある。常々そのバランスは非対称ではないかと思っていたので、敢えて「主犯」を作らないようにしました。
あと、これは勝手に感じている傾向なんですけど、長篇を書くと暗い小説にならないんですよね。大阪人だからなのか、どこかに明るさと面白さを求めてしまう。だからということもないのですが、とにかく今回は、「カネ」「家」「犯罪」、そして「カーニヴァル」でいこうと思いました(笑)。どんな仕事にも必死さがあって、その必死さは笑いや滑稽さに通じるんですよね。みんなで家の壁に黄色のペンキを塗る場面があるんですけど、ああいうカタルシスのあるシーンを作りたかったんですよね。
一九九〇年代の「青春」を描くなら?
——一九九〇年代という時代はどのように意識されていましたか。
川上 私は七六年生まれなので、九〇年代に青春を過ごしました。今、Z世代と呼ばれる若い子たちの間で九〇年代がブームですよね。あの頃の音楽が流行ったり、映画の『ラン・ローラ・ラン』みたいな格好をしている子たちを見かけたりする。同じように、九〇年代には、その二十年前、つまり七〇年代の作品や音楽がリバイバルしていた。この周期問題というのはずっと頭にありました。
それと、たとえば村上春樹さんの『ノルウェイの森』は、村上さんが青春時代の学生運動のことを振り返って書かれていますが、村上さん世代の人なら、そういったみんなが共有している若さと直結した物語がある。一方で、私たち世代が青春時代を振り返る時、何が書けるんだろうという問いはずっと持っていました。もちろん、地下鉄サリン事件や阪神淡路大震災といった、大きな出来事がありました。あるんだけれど、青春との重なり、という意味合いでは何が書けるのかな、って。

——当時の三軒茶屋の雰囲気、世の中の空気がリアルでした。
川上 当時は渋谷系の音楽が流行ったりもしたけれど、別のところでしのぎを削っていた子たちの話にしたくて、東村山や三軒茶屋を舞台にしました。
私が大阪から東京に出てきて三軒茶屋に住み始めたのがちょうど二〇〇〇年、二十四歳の時なんです。だから九〇年代の東京については肌で知ってるわけじゃなくて、ちょっと距離があるんですよね。
さらに花は私の四歳くらい年下で、彼女の世代とは流行が数年分ずれるんです。私の中学生時代のヤンキーを書こうとすると、着ているのがミキハウスになっちゃうわけです。このズレがけっこう切実で。瀧井さん、わかってくださる?(笑)
——すごくわかります(笑)。
川上 それだと花の世代にとっては古いんですよね。二、三年の差でファッションも全然違う。もう109の時代になっていたから、ルーズソックスだな、話題になるのはX JAPANとかディカプリオだろう、などと一つずつアジャストしていきました。
——花が未成年ながら黄美子さんのスナック「れもん」を手伝ってちゃきちゃき働いていく様子は痛快でした。花って、金額を非常に細かく把握していますよね。一日の売り上げとか、生活費とか、貯金額とか。
川上 金額は詳細に書きました。なんといっても、カネの小説なので(笑)。当時のスナックのこともちゃんと書いておきたかったんです。スナックって、地元のみんなが集まるあたたかい場所、みたいな幻想がありますよね。気心の知れたママがいて「おかえり」みたいな……。でも、素敵なスナックもあるけれど、ハードな側面もありますよね。夜の世界にもいろんなレイヤーがあることは書いておきたいな、と思っていました。
——花がすごくしっかり者で、応援したくなります。
川上 連載中も、SNSなどで「花ちゃんがんばれ」みたいな感想をいただくことが多くて、私まで嬉しかったです。
花は一生懸命なんですよね。地頭もいいし、真面目だし、ちょっとスタミナ系というか。同世代には受験勉強にエネルギーを注ぐ子もいればスタートアップにエネルギーを注ぐ子もいるだろうけれど、花にとっては、身ひとつで生き抜いていくぞという、夜の世界だったんでしょうね。
——彼女の視点から語られていきますが、本人が自覚していない幼さと、そこからの成長と変化がすごく伝わってきます。
川上 『黄色い家』も『夏物語』もどちらも一人称ですが、『夏物語』の夏子は作家だから言葉を持っている。でも、花は使える語彙が限られている。そんなところも新鮮で書いていて面白かったです。

——そのなかで、花から見た黄美子さんの印象が変わっていきますね。最初は優しい大人の女性という印象でしたが、花がしっかりするほどに、少しずつ黄美子さんの頼りない一面が見えてくる。
川上 そうそう、十五歳の頃に出会う大人って、その人にどんな事情があるかもわからないし、なんか違う世界の人だなって思えたり、ちょっと見上げる感じがありますよね。でも十五歳が得られる他人への洞察力と二十歳のそれとは違うから、花もだんだん黄美子さんへの印象が変わっていき、事情を知ることになる。
二人と繫がりのあるアウトローの映水が言うように、黄美子さんは利用される人なんですよね。弱い者がさらに弱い者を叩くような、搾取の構造の中にいる人。もちろん昼の世界もそうなんですが、夜の世界はさらに外からは見えない作りになっているのだと思います。