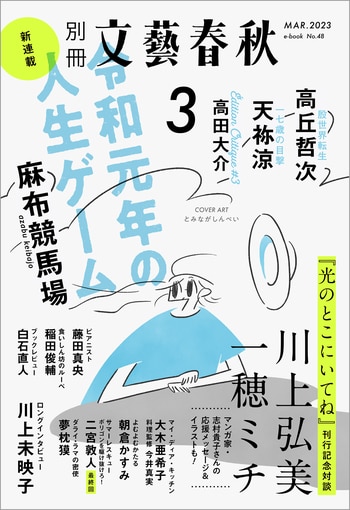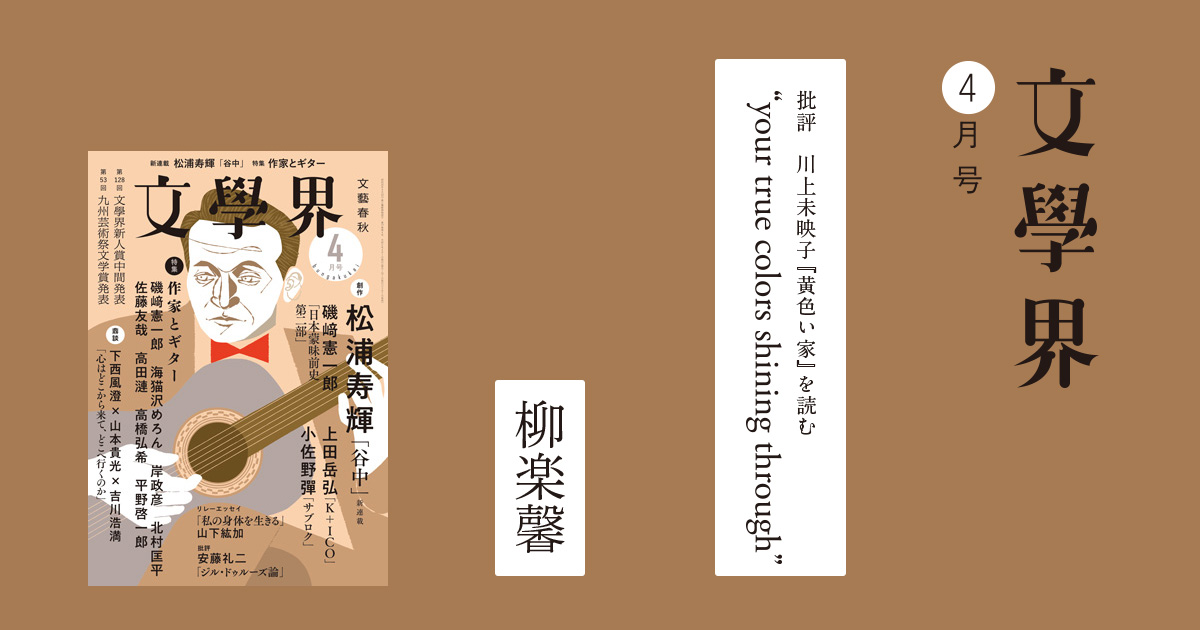連載中に届いたメッセージ
——ところで、黄色という色が非常に象徴的に使われていますが、これも自然と出てきたものですか。
川上 黄色というモチーフは構想段階から決めていました。それで店の名前が「れもん」になって、風水に凝った花が「黄色は金運の色」とか言い出すようになって。九〇年代はスピリチュアルの時代でもありましたね。最後の章のタイトル「黄落」も、かなり早い時点で決めていました。
——執筆する前に章タイトルを決めたのですか。
川上 そうなんです。第一章の「再会」を書いた後に、残りすべての章タイトルを決めました。お金の話だから「千客万来」とか「一攫千金」がいいなとか、家の話だから「一家団欒」だな、とか。熟語がいいなと思って、あとは流れに沿って選んでいきました。そこから各章の内容を積み上げていったという感じ。
——その書き方で、こんなリーダビリティのある構成を作りあげたとはびっくりです。読者を楽しませるためのエンタメ的な要素は意識されましたか。
川上 それが、そこはあまり考えなかったんです。新聞連載を始める時に、編集者から「暗い時代だから読んだ人がちょっと明るくなるようなものであれば嬉しい」というリクエストをいただきましたが、でも人って、楽しい話を読めば明るくなるわけでもないでしょう?
実際、連載中に、花と同じような状況にある女の子からメッセージが届いて、それは嬉しかったですね。「川上未映子さんの『黄色い家』が読みたくて、家賃13200円の家に住む私が毎月4000円する新聞買ってる。続きが読みたくて夜中2時まで起きて新聞やさんが届けてくれるのを待ったりもする(原文ママ)」って。私はこういう読者に支えられているんだなということを絶対に忘れないでおこうって、いつも感じていることだけれど、今回、特に強く思いました。
——新聞連載は楽しかったですか。
川上 そうですね。自分は本当に長篇を書くのが好きなんだと実感しましたね。今回、前作の『夏物語』同様、原稿用紙で一〇〇〇枚くらいの長さになったのですが、執筆時の体感としては前作の半分くらいのボリュームなんです。知らず知らずのうちに創作の体力がついていたのかもしれません。あとは加齢で、単に話が長くなってる可能性も(笑)。
——川上さんは、言葉による創作は詩から始められているじゃないですか。詩を書いて、エッセイを書いて、そこから小説の依頼があって。短篇が話題になり、中篇や長篇も書くようになり。
川上 そうそう、私は詩人なんですよ!(笑) だから書き始めた頃は、自分に一〇〇〇枚の小説が書けるとも、ちゃんと構成のある話を作れるようになるとも、とても思えなかった。でもその時々で自分には難しいなと思うことに少しずつ挑戦してきたことが、今に繫がっているのかもしれません。いずれにしても、有難いことです。

「日本文学」を超えて、自分の物語として読んでほしい
——前作『夏物語』は翻訳もされて海外でも評価されていますよね。
川上 アメリカでは普通にあることですが、『夏物語』は、執筆前から英語の版権が売れていたんです。『黄色い家』も嬉しいことにオークションでたくさんのオファーを頂いて、もう翻訳が進んでいます。編集者と話し合って、英語のタイトルは『Sisters In Yellow』になりました。
——作品が翻訳されることについて、思うことはありますか。
川上 一人でも多くの人に小説を読んでもらえることはすごく嬉しい。でも、各国語でいろんな人たちに読まれていけばいくほど、自分が日本語というマイノリティ言語で書いていることは意識せざるを得ないというところもあります。英語の「強さ」については、考えさせられます。また仕事の進め方については、海外の版元はやりかたが全然違うので、コミュニケーションも含めて、いろいろ勉強になっています。
——海外の読者からの感想は。
川上 『夏物語』に対しての海外のあるジャーナリストの言葉が記憶に残っていて。作中に出てくる精子バンクについて、その方に「日本の人はこんなに悩まないといけないの? 私たち普通にやってるけど」と言われたんです。でも、日本の人でも、そのジャーナリストの国の人でも、精子バンクについて個々人でそれぞれの考えがあるはず。私の書いたものが日本全体の空気を表しているわけではありませんよね。
私はたしかに日本を舞台に書いているけれど、本来は、「日本」とかそういうカテゴリーから零れ落ちるものを掬い上げることが文学だよなと思う気持ちもある。それでも、日本語で書くと、どうしても「日本文学」としてカテゴライズされてしまう。
とはいえ、私も、他国の文学をそうやって読んできたんです。たとえば、オルハン・パムクを読んでトルコを少し知ったような気持ちになるし。それも読書の楽しみの一つではある。それでも、本に感動する瞬間って、どこの国の作品かを超越して共有できるものを見付けられたときにも、訪れると思うんです。
『夏物語』は、海外でも自分のこととして読んでくれる人が多くて、それが何より嬉しかったですね。
——次はどんな作品を考えていますか。
川上 ずっと言ってるんですが、もう長いこと宗教について書くことを考えています。社会現象としての宗教問題ではなくて……うーん、構想はあるんですが、自分に書けるか、まだわからないかな。昨年から「ピーターラビット」シリーズの翻訳も始まったので、そこで見えてくるものもあるでしょうし、新作はじっくり準備を進めたいと思っています。
川上氏撮影:当山礼子(見出し画像、本文2点目)
塚田亮平(本文6点目)
かわかみ・みえこ 大阪府生まれ。2007年、デビュー小説『わたくし率 イン 歯ー、または世界』が第137回芥川龍之介賞候補に。同年、第1回早稲田大学坪内逍遙大賞奨励賞受賞。08年、『乳と卵』で第138回芥川賞を受賞。09年、詩集『先端で、さすわ さされるわ そらええわ』で第14回中原中也賞受賞。10年『ヘヴン』で平成21年度芸術選奨文部科学大臣新人賞、第20回紫式部文学賞受賞。13年、詩集『水瓶』で第43回高見順賞受賞、短篇集『愛の夢とか』で第49回谷崎潤一郎賞受賞。16年、『あこがれ』で渡辺淳一文学賞受賞。「マリーの愛の証明」にてGranta Best of Young Japanese Novelists 2016に選出。19年、『夏物語』で第73回毎日出版文化賞文学・芸術部門受賞。本作の英訳は2020年米TIME誌が選ぶ今年の10冊、米New York Timesが選ぶ今年の100冊、米国図書館協会が選ぶ2021年ベストフィクションの11冊などにも選ばれ、世界40か国以上で刊行が進む。また、『ヘヴン』の英訳は、22年、ブッカー国際賞の最終候補に残った。『すべて真夜中の恋人たち』の他、村上春樹との共著『みみずくは黄昏に飛びたつ』など著書多数。「ピーターラビット」シリーズの翻訳も手掛けている。
人気作家の作品&インタビューがもりだくさん♪ 「WEB別冊文藝春秋」はこちら