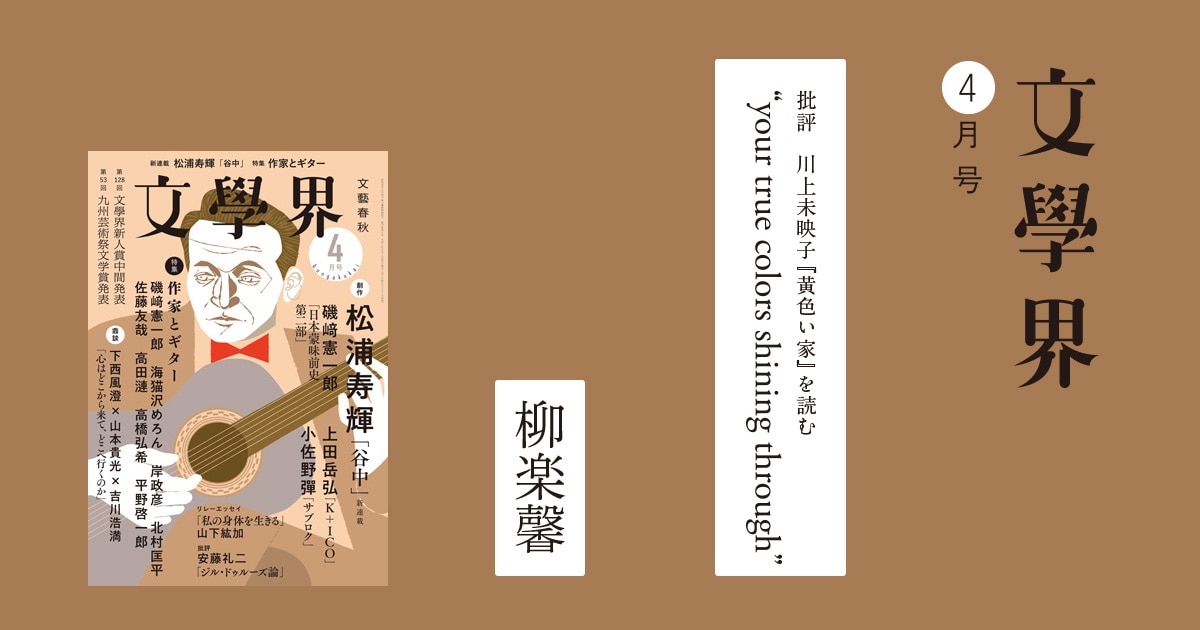不遇のまま死んだゴッホへの思いを書き綴ったことのある川上未映子のことだから、彼女の新作を手に取って、巨匠による同じタイトルの絵を思い浮かべるひともいるだろう。『黄色い家』ではたしかに、主人公たちの家が黄色くなる。しかし、これからこの作品を読むひとには、シンディ・ローパーの名曲“Girls Just Want To Have Fun”をミュージックビデオとともに視聴することを勧める。「朝の光のなか、家に帰ると母さんが……」という歌詞のとおり、早朝の街路をシンディがひとりで、けれどのっけから弾むように踊りながら帰宅する。眉をひそめる両親をよそに、やがてシンディばかりか、肌の色も髪型もばらばらの何人もの「ガールズ」が楽しげに誇らしげに街にくりだし、デモ行進ともパレードともつかない彼女たちのムーヴメントが、それを当惑しつつ見ていた男たちですら仲間に引きいれていく。私(たち)の生きる喜びと幸せを歌うシンディは、みなを引き連れてまた自宅に戻り、全員を自分の部屋へと招き入れる。
この歌を小説にしたのが川上の『黄色い家』だなどと、安直なことが言いたいわけではない。主人公・伊藤花が、一九九〇年代の後半に他の女性たちと共同生活を送った家は、多様性のユートピアでも弱者のためのシェルターでもなかった。しかし、高校卒業を待たずに家を出た花が、母親と姉の中間くらいの存在だった吉川黄美子とともにスナック「れもん」をはじめたときに思い描いていたのは、おそらくはシンディの部屋のような、雑多なものを受けいれる、ゆるやかであたたかな空間だっただろう。花と黄美子、さらに専門学校にもキャバクラにもなじめなかった加藤蘭、そして容姿に恵まれないが誰もが認める美声をもつ玉森桃子を加えた四人は、同じ家で暮らしはじめる。やがて不運に見舞われ犯罪に手を染めた末に、黄美子をのぞく三人はその家から逃げ出す。月日は流れ、新型コロナウィルスによってかき乱される現在を生きている伊藤花は、「第一章 再会」で黄美子が逮捕されたことを偶然に知り、『黄色い家』はここから過去へとさかのぼる。
このように、ひとつの家族的共同体の成立から崩壊までの流れが『黄色い家』の主軸なのだが、少しずつ追い詰められる彼女たちの物語の重要な展開を伏せたままでは、これ以上『黄色い家』について語ることはできない。余計な情報を遠ざけて川上未映子の新作に触れたい読者には、読了まで以下の記述を読まないことを勧めておく。
『黄色い家』の第一章だけを読んだ者は、黄美子のことを、庇護者を装い未熟な女性たちを支配して、その狭く息苦しい世界に君臨する危険人物として思い描くだろう。風水で金運を呼びこむ色とされ、黄美子の名前にも入っている「黄色」にちなんだ店「れもん」では、きっと早晩、黄美子を中心とした凄惨な流血沙汰かなにかが起こり、純朴な花の目の前で黄美子の本性がさらけ出され、閉鎖的コミュニティは内側から崩壊する――そんな予想が的外れだったことは、作品を読めばすぐにわかる。
というのも、吉川黄美子は悪行の加害者というにはあまりにも受動的すぎるのである。花が(ついで蘭と桃子が)犯罪に加担していくあたりでは、黄美子の存在感がかなり希薄になる。いわゆるその筋の男である安映水によると、最低限の自衛・保身をする頭も回らない黄美子は「悪い人間からしたら、そのまんま、金の成る木」である。「ある意味、物みたいになってんだよ。いろんな遣い道のある物な」。ゆえに、花や映水の配慮で彼らの悪事からすら半ば閉め出されている黄美子は、およそ遣い道のない「物」ということになる。
さらに言うと、黄美子は、それ自体に用途は無いが象徴的な意味を担うお守りに近い。金運上昇を願う花が部屋の西側の「黄色コーナー」に集める「すべて黄色の物たち」や、桃子が花に買ってきた黄色のミサンガのような「物」に、黄美子は似ているのだ。「つけるときに願いごとをして、切れたときにそれが叶う」ミサンガは特にそうだが、こうしたお守りは、壊れることで願いを叶えたり、持ち主が危ない目にあう直前に予兆として壊れたり、あるいは身代わりとして壊れて結果的に持ち主を救ったりする機能がある(と信じられている)。だから、黄美子を捨てて逃げた花が自分の罪を「心のなかで黄美子さんに押しつけた」のも当然だ。お守りに似た黄美子には実質的な力などないが、願いが叶わなければそのお守りのせいにされるように、黄美子は責任を押しつけるには最適で、だからこそ「悪い人間」の格好の標的なのである。いよいよ悪事が露見する不安と恐怖に駆られた花は、そうすれば事態が魔法のように好転するとでもいうかのように部屋の壁に黄色のペンキを塗りたくるが、結局はまさにその黄色そのものに全部お前のせいだと責められる声が聞こえて、花はカッターナイフで黄色を削り落とそうとする。一方的に持ち上げられ、やはり一方的に排除されるという点で、黄美子は確かに「黄色」と同じ運命をたどる。
この点で、川上の筆致は実に周到だ。作品終盤、黄色いペンキを落とそうとする花にとって、カッターナイフは汚れを落とすための道具、つまり雑巾やふきんの等価物である。他方で、なにかにつけて無頓着な黄美子が部屋の掃除にはこだわり、「たいして汚れてもいないのにいろんなところをせっせと拭いて」いることは早い段階から語られていた。あるとき、花が見た悪夢のなかで、黄美子がいつものようにふきんを手にする。「いつのまにか黄美子さんの手のなかのふきんは包丁なのかナイフなのか、銀色の刃物に変わっていて、それに気がついた瞬間、黄美子さんはそれを私のお腹にぐさりと刺したのだ」。ふきんが刃物に変わる悪夢が、やがて花自身の手で、花自身も気づかぬうちに現実となり、彼女はふきんと同じ目的を果たすための刃物を握りしめる。花にも黄美子にも思い通りにできないものによってすべてがずっと前から決められていたかのようだ。公開されたばかりの映画『タイタニック』を観た花の夢のなかで、レオ様ことディカプリオも言っている。「自分で決めた人生を生きる人間なんか、この世にいないってことだよ」。万人に科せられるこの受動性をひときわ濃く深く刻みこまれているのが、つまり吉川黄美子なのだ。
もちろん川上は、黄美子を単なる「物」みたいな存在のまま終わらせない。花や蘭の実家は、まだ二〇歳になるかならないかという彼女たちの金をあてにするほど貧しく、裕福な家に生まれた桃子は特に母親との折り合いが悪すぎて、とにかく三人には居場所らしい居場所がない。だからこそ寄り集まっていたはずの花たちのあいだにも亀裂が走り、桃子と花が揉みあいになったそのとき、黄美子の怒号が響く。
黄美子さんはいつのまにか壁に立てかけてあったクリスチャン・ラッセンの絵を両手でつかんで頭のうえにふりかざしており、つぎの瞬間、押入れのふすまにそれを思いきりぶっ刺した。(…)わたしたちは微動だにせずに、鈍い金色の額縁に入ったラッセンの青光りする海が何度もふすまに突きたてられるのを見ていた。
ラッセンの、しかも直筆サイン入りの本物だというこの絵は、桃子の母親の俗物根性の証として言及され、高値で売るために桃子たちが勝手に持ち出したものだった。それが気に入られて花たちの手元に残され、そんなものがあることを読者もすっかり忘れたころ、こうしてラッセンが巨大な刃物のように暴れ狂う。
このラッセンを振り回す黄美子の場面で、私は不明を恥じた。というのも、私は「ラッセン」を舞台装置のようなものとしか思っていなかったのだ。『黄色い家』の現在時は二〇二〇年で、花が黄美子たちと暮らした九〇年代末はすでに遠い過去である。そんな別の時空として「九〇年代末」を演出するために「たまごっち」等々が言及され、ラッセンもそのひとつであるかに見えた。しかし考えてみれば、(一応は)芸術作品であるラッセンの絵画こそ、悪人にとって黄美子がそうであるように「金の成る木」ではないか。それ自体に用途が無いという点でも似たもの同士である黄美子とラッセンがここでひとつになり、しかも例外的に、なすがままの「物」であることを止めて凶暴な存在感を発揮する。
そして改めて強調すると、黄美子が振り回すのは「鈍い金色の額縁に入ったラッセンの青光りする海」である。『黄色い家』の黄色(およびそれに類する金色)と、それと対になる青に注目を促して、この文章の締めくくりとしたい。「さっきまで金色の西日に満ちていた部屋は知らないあいだに薄青になっていて」とあるように、花は黄色い光と青い影の交錯のなかを生きていく。そして、とつぜん花の前から姿を消した黄美子が、花を思って食べ物をありったけ詰めこんだ冷蔵庫を開くと漏れてくる「薄い黄色の光」こそ、花を黄美子という女性に強く結びつけている。
では「青」はどうか。「暗黒の海」で死ぬ「レオ様の澄んだブルーの瞳」や、右と左を間違えるというだけの理由で子どものころに黄美子が右手に入れられた「青っぽいあざのような」入れ墨、そして悲痛な死をとげる女性・琴美の「青黒い痕」など、小説家・川上未映子は死と暴力の影あるいは夜そのものを「青」で描く。この点で『黄色い家』は、光/闇のそれぞれをおおむね白/黒に対応させていた『すべて真夜中の恋人たち』とは異なる。ただし、この二つの作品の結末は瓜二つである。これら二つの場面は、読者である私がそれを見ているのではなく、その光景の方が輝く二つの瞳となって私を見つめ返しているのかと錯覚させるほど、忘れ難く美しい。
『黄色い家』に先立つ短編集『春のこわいもの』でも、夜の闇はすでに「青」で描かれていた。『すべて真夜中の恋人たち』の川上未映子は光と闇の、いわば「明暗」の作家だったが、彼女はとっくに闇そのものの青さに気づき、そこに輝かしい黄色を重ね塗りする準備を整えていた。川上の描く「青」と温かい「黄色」の組みあわせに、私たちは目を見はるべきだ。青く澄んだ夜の闇と黄色い光だなんて、まるでゴッホの『夜のカフェテラス』や『星月夜』のようだ。川上未映子の新作は、『黄色い家』と題された黄色と青の装丁の本で、その頁からは、この小説家が獲得した彼女の真の色彩が輝きあふれだしている。
(初出「文學界」2023年4月号)
■ プロフィール
柳楽馨(やぎら・かおる)
文学研究者。84年生まれ。
文學界(2023年4月号)目次
【創作】
松浦寿輝「谷中」(新連載)
長いパリ暮らしを経て、台東区谷中に住むことになった画家の香坂。入り組んだ路地で彼は何と出会うのか
上田岳弘「K+ICO」
SNSで収益を上げるICOは、かつて自分を救ってくれたウーバー配達員Kを探していた。二人は再会できるのか。ついに連作完結
小佐野彈「サブロク」
巨大な雪壁に向かって突き進む彼は、誰よりもかっこよかったーー著者の新境地”フリースキー”小説
磯﨑憲一郎「日本蒙昧前史 第二部」
美男子のテレビ俳優は、付き合っていた舞台女優から映画女優を紹介され、交際することに。縦横無尽に描かれる魅惑と迷妄の昭和史
【特集】作家とギター
「6本の狂ったハガネの振動」はなぜ私たちの心を震わせるのか。作家6人が楽器との関係を語り、小説家と音楽家がギターをめぐるエッセイを綴る
〈インタビュー〉平野啓一郎「「上手い」のはスゴイこと」/岸政彦「ギターは個人に寄り添ってくれる、どこか寂しいもの」/高橋弘希「音楽は趣味ではできない」/佐藤友哉「恥ずかしいからこそ、やれること」/北村匡平「演奏と執筆は繋がっている」/磯﨑憲一郎「ウィルスが甦ったデトロイトの夜」
〈エッセイ〉海猫沢めろん「ギター・バンド・小説」/高田漣「アンドロイドはみ空の夢を見た〜32/42/52/62/72/82」
【批評】
安藤礼二「哲学の始源――ジル・ドゥルーズ論(前編)」
▼ 本稿はこちら
柳楽馨「“your true colors shining through”――川上未映子『黄色い家』を読む」
【鼎談】下西風澄×山本貴光×吉川浩満「心はどこから来て、どこへ行くのか」
【リレーエッセイ「私の身体を生きる」】山下紘加「肉体の尊厳」
第128回文學界新人賞中間発表
第53回九州芸術祭文学賞発表【発表と選評】五木寛之・村田喜代子・小野正嗣
【文學界図書室】松浦寿輝『香港陥落』(池田雄一)/グレゴリー・ケズナジャット『開墾地』(いしいしんじ)
【強力連載陣】砂川文次/円城塔/金原ひとみ/綿矢りさ/西村紗知/奈倉有里/王谷晶/辻田真佐憲/藤原麻里菜/平民金子/高橋弘希/松浦寿輝/犬山紙子/柴田聡子/河野真太郎/住本麻子
表紙画=柳智之「深沢七郎」