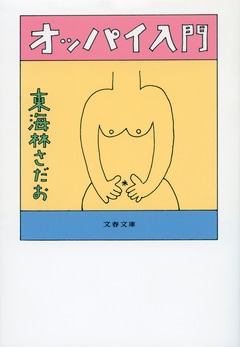飄然と暮らすことが難しい時代になった。人間の抱える矛盾を受容した上で面白がったり、生活のあれこれを少し意地悪く観察したり、何事にも例外がある大前提を省略して語ることを善しとしないムードは、年々高まっている。
ゆらぎのない明確な意思を表明しろと、世間に凄まれているとすら感じることも増えてきた。持つ者と持たざる者の境界線はくっきりと引かれ、ものごとの善悪はモザイク状で、簡単には白黒をつけられないという当たり前も共有しづらくなった。そして、こういうことを言ったあとに「あくまで、個人の感想ですが」と添えないと怒られる。
誰に怒られるか。顔の見えない世間に、だ。功罪を列挙したら、罪のほうがやや多くなってしまったSNSのせいだ。もちろん個人の感想ですが。
飄然と暮らすことが最も難しくなったのが、二〇二〇年初頭から始まったコロナ禍だろう。未知のウイルスのせいで世界中が同質の不安に苛まれ、経済は逼迫し、心に余裕がなくなりユーモアは禁忌になった。もう少し詳しく書くなら、ユーモアが「心温まるもの」か、「悪ふざけ」かを、他者が断罪するようになった。
連帯より対立や排除が際立ち、家に留まり続けて誰もがヘトヘトになった。見通しのきかない未来に眉間に皺を寄せているか、声高に主張しているか、小さなしあわせを寿(ことほ)いでいるか、くらいしか許されなくなった。壮大な社会実験に強制参加させられているようでもあり、余裕がなくなると集団はこう変わる傾向にあると知った。
だから、『マスクは踊る』を読んで心底驚いたのだ。これは「オール讀物」平成三十一年三・四月号から令和二年十一月号に掲載された連載をまとめたものなので、タイトルからもわかる通り、プレ・コロナからパンデミックど真ん中に書かれたエッセイ集だ。しかし、どこからパンデミックに突入したのか気づけなかった。東海林先生が、飄然と暮らし続けているからだ。娯楽小説誌という掲載誌の特性をさっぴいて考えても、驚きは変わらない。
コロナに関しての記述がないわけではない。話題としては、当然扱われている。掲載号と照らし合わせてみると、二〇二〇年五月二十二日発売の六月号が「散歩道入門 コロナで大躍進を遂げた運動」でコロナの初出。「コロナ禍」という言葉がメディアで使われ始めたのが二〇二〇年二月から三月あたりらしいので、辻褄はあっている。
エッセイ界(というものが存在するのであればの話ですが)の末席を率先して汚すタイプの欲深い私なら、災いの足音が聞こえていたであろう四月二十二日発売の五月号で、我先にとコロナに触れていたと思う。一方、東海林先生のエッセイは「令和の“チン”疑惑 電子レンジと安倍内閣」である。もはや超然としている。いや、こっちも大事なことなので、世間に背を向けスカしているわけではないのだろうけれども。
コロナについての記述があるにもかかわらず、私がプレ・コロナとポスト・コロナの境目に気づけなかったのは、先述の通り、東海林先生が飄然と暮らし続けていたから。つまり、東海林先生の生活を描く態度がブレなかったからだ。どれほどのことが起こっても、一定の距離を保ち世間を眺める筆致には美学がある。社会の諸問題から目を離さずに、しかし一定の距離を保ち続けるには胆力が必要で、簡単なことではない。私なんか、時代のムードに合わせてコロッと文体を変えた。
戦争経験者は強いな、と思う。東海林先生は昭和十二年生まれで、私の父親は昭和十三年生まれ。どちらも戦中派の最後と言えよう。すえたご飯を食べた経験を持つ世代。
世代で十把一絡げに語ることが忌諱されがちな昨今だが、日本が過去に経験した最悪の禍を生き抜いてきた人のへこたれなさは、良くも悪くもすさまじい。良い例が東海林先生。悪い例を知りたかったら、昭和十二年生まれの内閣総理大臣経験者を検索してみることをおすすめする。いや、三人いるな。私が言いたいのはオリンピックのほうです。
第二次世界大戦を幼少期に経験した諸先輩のユーモアに助けられたことは、一度や二度ではない。困難が迫ってきたときほど、それを面白がる。やせ我慢の冷笑とは一線を画すものだ。その余裕はどこからくるのか、戦中派の末席を汚す我が父親に尋ねたら、価値観が一夜にしてひっくり返ったからかもしれないと言っていた。
納得のいく説明もないまま昨日までの悪が今日から善となり、教科書に黙々と墨を塗った、もしくは親に塗られた子どもたちが、令和のOVER八十五歳だ。世間が掲げる規範に対する疑念や距離感は、我々のそれとは大きく異なる。結果、変化への耐性が高い。
耐性が順応性や客観性として現れる場合と、不屈なまでの不変(学ばなさとも言う)に現れる場合があり、年功序列に従って権力を行使される側=戦後生まれにとっては危険なガチャでもある。
「ガチャ」とは最近のインターネットスラングで、お金を入れてレバーを回すとカプセルに入ったおもちゃがランダムに出てくる小型販売機を由来に持つ、スマホゲームのランダム型課金システムを指す。課金しても欲しいアイテムが手に入るとは限らず、それが射幸心を煽るのだが、インターネットスラングでは「子どもは親を選べない」など、選択の余地がない境遇を強いられる場面で使われる。半世紀ほど生きた私のような世代にとっては、親の老化が新たな親ガチャであり、ガチャは自分の行く末でもある。
しかし、大人は自身の性質をガチャに任せる必要はない。成熟した大人なら、ある程度は自分で選び取れる。順応性や客観性を尊びユーモアのある人生を選ぶか、時代の変化に鈍感なまま恐竜のように絶滅していくかを運に任せずにいられる。
東海林先生がなにを選んだかは、この一冊を読めば理解できる。軽妙な文体とは裏腹に、幼少期から世間をつぶさに観察していることがよくわかる。観察力は、人を恐竜に退化させない抑止力だ。
東海林先生の生きる指針が窺える「コロナ下『月刊住職』を読む 仏教界より葬儀界が……」を始めすべての稿に、おちょくりに擬態した批評がちりばめられており、やわらかだが強い意思表明がある。人間のディグニティについての深い考察を見逃してはもったいない。こういうことを書くのは本来不遜で無粋なので避けたいところだが、これは文庫の解説なのでご容赦ください。
話変わりまして。本作には、医師の長谷川和夫さんとジャーナリストの田原総一朗さんとの対談が収録されており、東海林先生が最も恐れているのは認知症であることがわかる。好奇心を失い、自分の頭で世の中を見渡すことができなくなるのを恐れていると言い換えても、誤解はないだろう。
邪推の域を出ない話ではあるが、よく聞く「自分のことがわからなくなるのが嫌だ」とか「周りの人に迷惑を掛けたくない」などの理由とは異なる印象を受けた。ご自身を、世の中に対峙する視座と定義していらっしゃるように思えた。己の五感で世間を味わい尽くすことこそが、生きる醍醐味だとも。
キーボードを打ち始めて十年しか経っていない若輩者の暫定的な見解を記すのは気後れするが、勢いに任せて書くと、エッセイは「朝起きてご飯を食べて出かけて夜帰ってきて寝ました」を、どれだけ読むに堪えうる文章にできるかにかかっている。堪えうるか否かを決めるのは、書き手の視点だ。視座を固定するのは、欲望だ。生活の起伏が激しければよいというものではない。誰にでも複製可能な正解や結論が書かれていることでも、当然ない。
なんでもない日常の、ちょっとした引っかかりにこっそり虫眼鏡をあて、「なるほどね」とか「言われてみればそうだ」といった読後感を与えられたらしめたものと思いながら私は書いているが、目指す頂は東海林先生の立つ場所だと、本作を読んで確信した。飄然と暮らし、己の欲望から目を背けず、日常を素通りせずに書いていくということ。
最後に、私のようなすれっからしに解説執筆の機会を与えていただいたことに感謝する。平成二十七年度の講談社エッセイ賞を受賞した際、東海林先生は審査員のひとりだった。あまりに不慣れなことで、授賞式できちんとご挨拶もできなかった記憶がある。選んでいただき、ありがとうございました。あのとき助けていただいた鶴です。
いつか恩返しができればと祈るような気持ちでいたが、これがその十分の一くらいにあたるといいなと、鶴は祈るような気持ちでいっぱいだ。