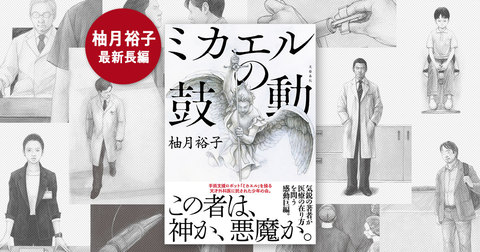このたび刊行となったエッセイ集は、デビューしてから十五年のあいだに書いたものだ。
改めて見ると、思っていた以上にあり、なかには書いていることを忘れているものもあった。覚えていてもすでに原稿がないものもあり、集めてくださった担当編集者Tさんはかなり大変だったと思う。このエッセイ集は、Tさんの努力なくしては出なかったものだ。まずはTさんに、この場を借りて御礼申し上げたい。
私はデビュー当時から「原稿離れ」が悪く、ぎりぎりまで直しを入れる。しかし、今回は直すつもりはなかった。書いた当時の自分の気持ちや考えを、そのまま残したかったからだ。とはいえ、書いた時期も内容もばらばらのものを一冊にまとめるとなると、時系列を整えたり、いまになって気づく誤字脱字を直す必要がある。内容は直さなくとも、目は通さなければならず、原稿を読んだ。そして、愕然とした。
私は日々、人としても作家としても成長したい、と思っている。その気持ちは、デビュー当時から変わらず、いまも精進している。
十五年という時間は短いようで振り返れば長い。多少はその努力が実っているのではないか、と思ったが、原稿を読んでみてこれがまったく変わっていない、とわかった。嘘ではない。さらに言うならば、頭の中は子供のころと同じなのだ。
ここで私の生い立ちを書かせていただく。おおまかなことは、この本をお読みいただければおわかりになると思うが、改めて記しておく。
私は岩手県釜石市の出身で、家族は両親と兄がひとりいた。
父は仕事で転勤が多く、私も引っ越しを繰り返していた。だから、幼馴染みといったつきあいの長い友人はいない。
子供の頃から本が好きで、学校の図書館や地域の公民館から借りてきて読んでいた。私が本好きだった理由は、両親の影響があると思う。ふたりとも本が好きで、父は歴史や時代小説、母は小説に限らず絵本や漫画も読んでいた。
母は本を読んだあと、私と一緒に感想を語り合った。
「お母さんはあのキャラクターが好き。あなたは?」
「私は別な人がいい」
「このお話は、このあとどうなっていくと思う?」
「きっと、ピンチの主人公を誰かが助けに来るんだよ」
「あのシーン、とってもよかったね」
「うん、感動した」
そんな母との会話は、とても楽しかった。その体験が、私の物語における想像力を育んでくれたのだと思う。
子供の頃の私は、あまり活発ではなかったように思う。転校が多く、やっとその土地になじんだと思うと引っ越さなければならない。新しい学校ではそこにはすでに子供同士のコミュニティが出来上がっていて、仲がいい友達はなかなかできなかった。一緒に遊ぶ子がいなかったため、いつもひとりで本を読んでいた。
ひとりでいる私を周りは「可哀そうな子」と思っていたかもしれない。でも、私自身はそれほど思いつめてはいなかった。
もともとひとりでいることが苦ではなかったし、友達がいない淋しさは本が埋めてくれていた。ページを開けば魅力的な登場人物たちがいて、さまざまな世界で活躍している。その世界に没頭しているあいだは、淋しさを忘れることができた。
いまも、誰かといるより、ひとりの時間のほうが多い。誘えば食事やゴルフに付き合ってくれる編集者はいるが、ふと思い立った時に気軽に声を掛けられる友人はいない。
昔と同じく、たまに淋しいと感じるときもあるが、そんなときはやはり本を開く。そこには自分が知らない出来事や人の価値観、ドラマがある。その世界にどっぷり浸かっていると、いつしか心が穏やかになっている。
好きな物語のテイストも、昔と変わっていない。
子供の頃に好きで観ていたテレビは古谷一行さんが金田一耕助を演じた「横溝正史シリーズ」や「必殺仕事人シリーズ」。映画なら「ゴッドファーザー」「仁義なき戦い」「マッドマックス」。愛読していたマンガは「ブラック・ジャック」「北斗の拳」「漂流教室」といったバイオレンス要素が強いものだ。ちなみに初恋は渡瀬恒彦さんとブルース・リーである。
この話をすると多くの方から「少女漫画とか恋愛ドラマとかは苦手なんですか」と訊かれるが、そうではない。私の世代だとマンガなら「キャンディ・キャンディ」や「はいからさんが通る」「エースをねらえ!」も読んでいるし、ドラマなら「コメットさん」といったファンタジーものや、恋愛ドラマの金字塔のひとつ「101回目のプロポーズ」も観ている。どれも面白かったが、胸に深く刻まれているのが、バイオレンス要素が強めのものなのだ。
どうしてなのか、自分なりに考えたことがある。出た答えは、きっと私は個が好きなのだ、だった。世の中の不条理や理不尽な出来事に、なににも属さず、己の信念に基づき立ち向かっていく。泥にまみれ傷だらけの見た目はかっこいいとは言えないが、その闘う姿がとても尊いのだ。もがき、あがき、泣きながら、懸命に前に進もうとする登場人物の生き方に感動する。そのような作品は、いまでも好きだ。
子供のころからいまに至るまで、なにか変わったことがあるならば、読み手から書き手になったことだろう。
作家になってから「子供の頃から作家を目指していたんですか」と訊かれることがある。実は、そうではない。小説は好きだったが作家になろうと思ったことは、一度もない。
私は二〇〇八年に「このミステリーがすごい!大賞」で大賞をいただき作家としてデビューした。そのときの投稿作品がデビュー作『臨床真理』(角川文庫)だが、投稿したときも作家になるつもりはなかった。投稿した理由は、自分がどこまで小説というものを書けているのか、を知りたかったからだ。自分が書く文章が果たして小説と呼べるものになっているのかすらわからないままの投稿だった。
投稿先を「このミステリーがすごい!大賞」にした理由は、運よく一次予選を通過すればサイト上で短い選評がもらえたからだ。いまは、一次や二次を通過すればコメントがもらえる新人賞が増えているようだが、当時は最終選考まで残らなければなんのコメントももらえない賞が多かった。自分の作品のどこが悪くてどう直せばもっとよくなるかがわからなかったのだ。「作家になりたい」ではなく「小説が上手くなりたい」と思っていた私は、ほんの数行のアドバイスが欲しくて、「このミステリーがすごい!大賞」に応募した。
結果、その作品がデビュー作となったのだが、その話をすると「嬉しかったでしょう」と言われる。だが、私の場合はそのまったく逆だった。受賞の連絡をうけたときにまっさきに思ったことは「どうしよう」だった。助走期間がまったくない状態でのスタートで「私に二作目が書けるのだろうか」という不安しかなかった。
二作目がどれだけ大切かは、当時、通っていた小説家講座で知っていた。
私はデビュー前に、山形市で行われていた小説家講座に通っていた。月に一度、第一線で活躍している作家や編集者が訪れ、受講生のテキストを講評してくれるのだ。それを知った私は、時間を見つけて通っていた。作家になりたいという思いはなく、ただ作家に会いたくて顔を出していた。
講座には足掛け四年通ったが、顔を出せたのは半分くらいだった。そのなかでお会いした作家や編集者の方々は、それぞれの文学論をお持ちで、テキストの読み方も違っていた。ただ、誰もがひとつだけ共通することを言っていた。「作家はデビューしてからが大変だ」ということだ。少々乱暴な言い方になるが「書き続けていればいつかデビューはできる。しかし、そこから生き残るのが大変だ」とのことだった。
加えて編集者は「特に二作目は大切です」と言っていた。デビュー作は「××新人賞受賞作」という看板がつき注目されるが、二作目はそれがない。看板がないところでどれだけ読者を掴めるかが作家として生き残れるかどうかの大きな分かれ目になる、というのだ。考えているネタもない。専門知識もない。文章にも自信がない私が、どれほど不安だったかお察しいただきたい。
さきほど、作家を目指していたわけではない、と書いたが受賞の知らせを受けたあと「作家になれたからには生き残りたい」と強く思った。それはいまでも同じだ。
デビューしてから十五年になるが、次の作品が書けるだろうか、という不安と、作家として生き残りたい、という思いは変わらない。日々、常になにかに怯え、自分を奮い立たせながら書いている。
デビューしてから、いろいろなことがあった。思いがけない喜びがある一方で、辛い哀しみもあった。どちらが多かったか、と訊かれてもどう答えていいかわからないが、ひとつ言えるのは、私は人に恵まれている、ということだ。
編集者のみなさんは、飴と鞭を上手に使い、筆が進まない私を引っ張ってくれた。なにかしらで落ち込んでいると、励まして元気をつけてくれた。
取材でお会いした方々もそうだ。なにも知らない私に親切に教えてくださり、つまらない質問にも丁寧に答えてくれた。原稿のチェックを引き受けてくださった方もいる。その方々なくして、私の作品は成り立たない。
それは、装丁に関しても言える。私は、カバーのイラストやデザインは、すべて担当編集者にお任せしている。
今回、カバーにGLAYのTERUさんの絵を勧めてくれたのは、あとがきの冒頭に出てくる担当編集者Tさんだ。Tさんは私がデビューした当初からのお付き合いで、いままでにも何冊か一緒に作っている。いつもその作品に合いそうなタッチのイラストを何点かあげて「柚月さんはどれがいいですか」と訊ねるのだが、今回は違った。他の候補はなく「TERUさんの絵をカバーにしたい」ときっぱりと言ってきた。
Tさんが見せてくれたTERUさんの絵は、青が印象的なものだった。透明で、儚げで、淋し気で、でも力強い。私は観た瞬間、強く引きつけられて「TERUさんにお願いしましょう」と即答した。
TERUさんに連絡をとったあと、私もTさんも気が気ではなかった。お願いしても、使用許可が出るかわからなかったからだ。祈るような思いで返事を待っていたが、TERUさんからの回答は「OK」だった。
ふたりで喜んでいると、さらに嬉しいご連絡があった。原稿を読んだTERUさんが、絵を描きおろしてくださったのだ。私が目を奪われた青で、優しくも凜とした花は、私の拙いエッセイに美しい彩りを与えてくれた。多忙ななか、絵を描きおろしてくださったTERUさんに、この場を借りて深く御礼申し上げたい。
インタビューで「これから書きたいものはなんですか」と質問されることがある。そのたびに自分自身に「なんだろう」と問うが、その答えもいつも同じだ。
人が心に抱えているものだ。世の中の不条理に対する怒り、愛しい人を失う哀しみ、貧しさからくる飢え、病の苦しさ、死への恐怖といったものだが、それは翻せば生への喜び、愛しい人がいる幸せ、豊かさからくる満足、誰にでも平等に訪れる死へと繋がる。
これは時代や国が違っても、誰もが抱く感情であり、普遍的なテーマだと思っている。それらと向き合ったときに悩み、考え、決断し、前に進む姿を描いていきたい。
私はきっとこれからも、新しいなにかに出逢い、影響を受けながらも、なにも変わらず書き続けていくのだと思う。たくさんの人に支えられながら、なにも変わらずに小説を書いていくのだと思う。
結びに、この本や私の作品を手に取ってくださった読者のみなさまに、心から感謝の気持ちをお伝えしたい。書店やインターネットには、古典と呼ばれる古いものから、昨日発売になった新刊まで、数えきれないくらいの作品がある。その数多の物語の中から、自分が書いた一冊を手に取ってもらうことがいかに大変なのか、わかっているつもりだ。だからこそ、読者の方が最後のページを閉じたとき「面白かった」と言ってもらえるような作品を書こうと思ってきたし、これからもそう思いながら書いていく。
がんばります。
「あとがき」より