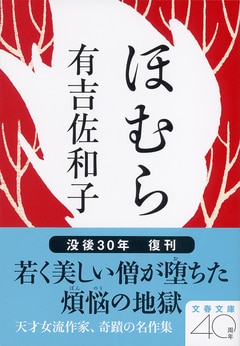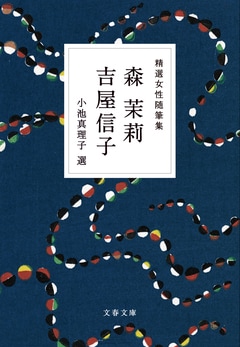有吉佐和子は、日本の近代文学の主流だった私小説とは距離を置いた作家で、さまざまな題材を用い、ストーリーで引きつける小説を書いた。『三婆』(昭和三十六年)、『香華』(昭和三十七年)、『華岡青洲の妻』(昭和四十二年)、『真砂屋お峰』(昭和四十九年)などは、小説で読まれただけでなく、舞台になって、今も繰り返し上演されている。
また、人種差別や〈戦争花嫁〉の問題を取り上げた『非色』(昭和三十九年)、離島に起きた射爆場移転問題を通して日米安全保障条約を考える『海暗』(昭和四十三年)、認知症の高齢者の介護問題を扱った『恍惚の人』(昭和四十七年)、権力闘争のために存在を踏みにじられた女性が主人公の『和宮様御留』(昭和五十三年)など、社会性の高いものも書いている。しかし、声高にメッセージを突き付けるのではなく、話の展開に引き込まれて読み進むうちに問題のありどころに気付く、といった作りになっている。
有吉はこうして多くの読者を得、それに応える旺盛な創作活動を見せたが、残された小説の数に比して随筆はあまり多くない。これには理由があった。
「地唄」が昭和三十一年一月号の「文學界」に新人賞候補として掲載されたとき、有吉は二十四歳であった。ときはちょうど日本の高度経済成長期の始まりで、週刊誌の創刊が続き、テレビも普及しつつあった。当時は若い女性作家が少なかったこともあり、有吉はすぐマスコミの寵児となった。本書の「有吉佐和子Ⅰ 二十代の随筆」にある随筆は、この時期に求められて雑誌に掲載されたものである。中には、華やかなデビューをした有吉に対する、必ずしも好意的なものばかりではない周囲の反応を苦い思いで書きとめた随筆もある。有吉は、大正デモクラシーの中で育った開明的な両親のもと、のびのびと育てられた。その真っ直ぐな言動は、旧来の価値観に馴染んだ人々から誤解されるもととなっていたようだ。なぜこうなのか? と彼女は考え始める。少数派の視点から世界を捉え直す小説を書く、という姿勢は、この体験から育まれた。
生前唯一の随筆集である『ずいひつ』(新制社、昭和三十三年)が刊行された翌年、有吉はニューヨークのサラ・ローレンス・カレッジに留学した。留学を決めた理由のひとつに、売れっ子作家生活に疲れての日本脱出願望があった。のちにこの時期のことを、「当時の有吉佐和子という名前には、なんの実体もなかったのである。空洞のマネキン人形に世間が着せているけばけばしいドレスを認めたとき、私はようやく慄然として、ああ私は何者だろうと激しく自分に問い訊した」(「ああ十年!」、『われらの文学15』講談社、昭和四十一年)と振り返っている。そして、「一年間の外国留学を終えて日本に帰ってきたとき、私はかたくかたく決意をしていた。それは小説を書くということであった。言葉を換えて言えば、小説以外のことはするまいという決意であった」(「不要能力の退化」、「新潮」昭和四十三年一月)とあるように、長編小説の執筆に専念するため、それ以外の仕事は極力避けようとした。避けたい仕事の中に、随筆の執筆も含まれていたのである。
しかし、演劇関係の仕事には積極的に取り組んでいた。小説執筆と違い、総合芸術としての演劇の場合、共同作業が求められる。有吉は、社会経験を積まないうちに若くして作家となったことを意識し、人との関わりが求められる演劇の仕事を大切に思っていた。そうした意味では、ルポルタージュも同じであった。一九七〇年代以後は、有吉の中でルポルタージュの占める割合が増えてくる。
*
「有吉佐和子II ルポルタージュ」は、『女二人のニューギニア』(朝日新聞社、昭和四十四年)と、『日本の島々、昔と今。』(集英社、昭和五十六年)の抄録である。
昭和四十三年の二月から、有吉はカンボジア、インドネシア、ニューギニアを旅し、四月に帰国した。行く前に書いた「日記」(「風景」昭和四十三年三月)には、「畑中幸子さんから『本当に来る気か』という三度目の念押しである。『凄いところよ!』などと書いてある。凄くたってなんだって私は出かけることにきめているのだ」とある。続けて、その意気込みの理由を、「どこでも行きたいんだ、私は。足腰の立つうちに、地球はどこの隅でも見残しておいてはならないという気がする」としている。この旺盛な好奇心は、いつか見聞したものを小説に役立てよう、という作家魂の表れでもあった。また、父親が横浜正金銀行に勤務していた関係で少女時代をジャワ(現、インドネシア)のバタビア(現、ジャカルタ)、スラバヤで過ごした有吉には、ときに日本を出て海外で息継ぎをする必要があったようだ。
畑中幸子は文化人類学者で、このときすでに、東京大学大学院社会学研究科博士課程在籍中にポリネシアで行なったフィールドワークを基にした『南太平洋の環礁にて』(岩波新書、昭和四十二年)という著書があった。こうしたフィールドワークのプロが「凄いところよ!」と警告していたのだから、現地の状況は有吉の想像をはるかに超えていた。その顚末は、ユーモアをまじえて『女二人のニューギニア』に描かれている。四月に帰国した有吉はマラリアを発症し、六月まで入院した。
『日本の島々、昔と今。』では、(1)焼尻島・天売島、(2)種子島、(3)屋久島、(4)福江島、(5)対馬、(6)波照間島、(7)与那国島、(8)隠岐、(9)竹島、(10)父島、(11)択捉・国後・色丹・歯舞、(12)尖閣列島、と回って、島の人々と交流し話し合ったことを軽妙な会話で綴りつつ、綿密な調査で背景を埋めている。有吉の離島への関心は、ルポ「『姥捨(おばすて)島』を訪ねて」(「婦人公論」昭和三十三年九月)以来のものである。本書には、この中から父島のルポ「遥か太平洋上に」が収められている。
『日本の島々、昔と今。』が刊行されるにあたって、「すばる」(昭和五十六年七月)に、有吉佐和子と深田祐介の対談「ノンフィクションのおもしろさ」が掲載された。ここで有吉は、「離島というと何となくうらさびしいイメージがありますから、時代の現実から切り離されたところだというアプローチになるだろうと思ってたら、意外にもオイル・ショックを直接受けているというのでね、これはもう現代そのものが書けるなと思った」と発言している。これは連載一回目の焼尻島・天売島の現地取材をした後の手ごたえである。有吉が取材を始めた昭和五十四年八月は、第二次石油ショックから半年ほどしか経っていない時期だった。
また、焼尻島・天売島の章には、「日本は島国で、大陸の国々の国境紛争について理解することが出来ない日本人が多かったのだが、二百カイリや大陸棚などの主張が出てくると、海は国境になったと言っていいのだろう。日本にとって、今や海は国境だ」と書かれている。昭和五十二年(一九七七)に施行された領海法と漁業水域に関する暫定措置法により、排他的経済水域(経済的な主権がおよぶ水域)、いわゆる二百海里問題が浮上した。世界各地で、領海の線引をめぐる紛争が起きた。現在も未解決のところが多く、日本でも領海をめぐる政治問題が、近年ますます緊迫している。
一方、ルポは、離れた陸と陸とを結んできた海の歴史も追っていて、近代国民国家の単位でものごとを考える癖のある我々からすると、ひどく意外な交流の諸相を示してくれる。それは、父島の歴史にも、如実に現れていた。
有吉佐和子の小説は読みやすいので物語の型に沿った小説と思われがちだが、娯楽性は備えつつも、実は意外な着眼点から小説を展開させている。少数派であるがゆえに見落とされてきたものを取り上げよう、としてきた作家なのであり、この姿勢は離島を取材する眼にもつながっていた。農業国だった日本において、漁業が取り上げられる機会は農業より少なかった。大切な問題があるのに書きもらされてきた、と彼女は訴える。
先にあげた深田祐介との対談で、有吉は「小説書きじゃないとできなかったルポだと自負するところはありますね」と述べているが、それはこれまでの作家としての歩みを背景にした発言だった。