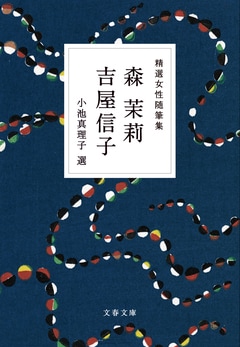このアンソロジーには、向田邦子(一九二九―一九八一)のエッセイが厳選されている。この一冊で多様な向田ワールドを味わい尽くすことができる。あらゆるものに関心を懐いた作者が自由奔放な連想を駆使し、とびっきり上質で、なつかしくて美味しい世界を私たちに提供してくれる。しかも本書では、ほぼ発表された順に並べられているので、向田がエッセイストとして新たな世界を切り開いていった様子をつぶさに見ることができる。
最初の三作品「テレビドラマの茶の間」、「寺内貫太郎の母」、「名附け親」は、向田邦子が「ホームドラマの女王」として活躍していた時期の作品である。多忙なシナリオ作家が、出版社の求めに応じて、ドラマの楽屋裏を少しばかり明かした内容になっている。『寺内貫太郎一家』ファンにとっては、願ってもない耳寄りな話が聞ける。
売れっ子脚本家だった向田邦子を突然病魔が襲った。昭和五十年十月、向田は東京女子医大病院で乳がんの手術を受け、その後も手術時の輸血が原因で血清肝炎にかかり、右手が利かなくなってしまった。この苦境の最中に、「銀座百点」からエッセイを隔月執筆してほしいという依頼が舞い込む。テレビの仕事はすべてキャンセルにしていたが、この仕事だけは左手でも書いてみたかった。
再発におびえ、向田邦子は自分の寿命がそれほど長くないように思えた。また病に臥すと、テレビ作家の虚しさをつくづく感じた。いくら心血を注いでも、台本は当時、放映のあとゴミ箱へ捨てられていたのである。その点、エッセイは視聴者の動向など気にせず、自分の気持ちを素直に述べることが可能で、しかも活字として後世へ遺すことができた。仕事を引き受けた心境を、向田は「のんきな遺言状」をしたためると表現している。
「銀座百点」に掲載されたエッセイは好評で、後に『父の詫び状』のタイトルで刊行された。内容は作者の自伝に近く、そこには家族への情愛や戦前の昭和への郷愁が色濃く表れている。特に父親は、暴君のように振る舞いながらも、その心底には家族を愛おしむ気持ちを隠し持ち、魅力的な人物に描かれている。このエッセイへの高い評価で自信を得、向田はシナリオにおいても、シリアスドラマという新しい領域へ踏み出すことになる。
最初のエッセイ集『父の詫び状』により、向田邦子はエッセイ作家としての地位を早くも不動のものにした。本書にはそのなかの代表作「魚の目は泪」、「ごはん」、「子供たちの夜」、「父の詫び状」、「隣りの神様」が収録されている。しかしその筆力は一朝一夕に生み出されたわけではない。シナリオを創作するなかで十分に培われていたのである。むしろシナリオ作家であったからこそ、ユニークなエッセイストが誕生したともいえる。
向田邦子のエッセイにはおおむね心理描写がない。人物の行動が淡々と記述されているだけである。またごてごてした形容も一切ない。このように簡潔な文章でありながら、向田の作品は読むそばから情景がありありと浮かび上がってくる。これは彼女が脚本家であったことと大いに関係がある。シナリオには場所を指定する「柱」、簡単な「ト書」、それに「台詞」しかない。人物の心理や細かな状況描写は、すべて演出家に委ねられている。だがエッセイでは、この「ト書」にあたる部分を大幅に増やせる。シナリオ特有の簡にして要を得た文章で、人物の表情や身振りを的確に表現することができ、しかも行間において、読者が様々なイメージをめぐらすことを可能にした。
向田邦子独特の脚本作りも、エッセイに大きな影響を与えている。シナリオ作家は執筆の際、通常「ハコ書き」を用いる。最初に各シークエンスの要点をまとめ、ドラマ全体の構成をあらかじめ決めるやり方である。しかし彼女は「ハコ書き」を好まなかった。構成にこだわると、ドラマの流れが滞ってしまうだけでなく、頭の中でひねり出された筋は徐々にやせ細り、筋を推し進める力を失ってしまうからである。
向田流のシナリオ作りは、ストーリーを転がしながら、ドラマを太らせていく方法である。作者は先のことなど考えず、今書いている場面に全精力を注ぐ。そして浮かび出た出来事を掬い取り、次の場面へとつないでいった。先の成果を得るために事件を起こすのではなく、事件が生じてからその対処を考える。このようにして新しい物語を紡いでいったのである。
エッセイにおいても、この「転がし」の手法が用いられる。何か無性になつかしい出来事を思い出すと、向田は急いで原稿用紙に書きつける。そして書き終える頃になると、その話のなかの一節や言葉に刺激されて、時間や場所も全く異なる別の思い出が不意に飛び出し、彼女の持つ筆を突き動かすのである。
奔放な連想の楽しさを、向田邦子は「ねずみ花火」(『父の詫び状』所収)において、「思い出というのはねずみ花火のようなもので、いったん火をつけると、不意に足許で小さく火を吹き上げ、思いもかけないところへ飛んでいって爆ぜ、人をびっくりさせる」と書き記している。この手法で書かれたエッセイには、少し長めのものが多く、例えば「ごはん」、「女を斬るな狐を斬れ」、「父の詫び状」、「隣りの神様」、「夜中の薔薇」などがある。
一方で、思い出が主題に則して並べられた、味わい深いエッセイも数多くある。「お弁当」は心にしみる壺漬の挿話を取り込んで、弁当にまつわる話が語られる。「反芻旅行」などは、「反芻」という言葉から作品を思いついたのであろう。楽しい事柄はそれを思い返したとき、実際に体験した以上の喜びがよみがえってくると説く。そして結びに、草を反芻する牛の一文で話を終えている。「傷だらけの茄子」は、台風が来る前から通り過ぎるまでの向田家の様子が生き生きと描かれている。タイトルもまた秀逸である。「桃太郎の責任」では女性の長電話が延々と綴られる。それは「桃太郎」に要因があると断定し、責任を昔話の主人公に負わせるところが愉快である。
「ヒコーキ」は、何度読んでも悲しくなる。全体を通して、飛行機と荷物受け取りの話が面白可笑しく語られている。ただその一節に、向田は飛行機に「まだ気を許してはいない」と告白し、旅行に出る際、「縁起をかついで」部屋や抽斗の中も散らかったままにしておくと書いている。しかし台湾の取材旅行のとき、彼女は珍しく部屋を片づけて出かけた。
ところで、向田邦子にとって大きな問題が持ち上がる。『父の詫び状』に対し、刊行ほどなくして向田家から苦情が出た。家族の秘すべき事柄を彼女が明かしてしまったからである。向田は「あだ桜」(『父の詫び状』所収)で、「祖母は、今の言葉でいえば、未婚の母であった。父親の違う二人の男の子を生み、その長男が私の父である」と記述した。彼女とすれば、父親敏雄の性格や行動を読者に納得させるためには、彼の出生にかかわる事実に触れないわけにはいかなかったのである。
家族の言い分はもっともであった。だが作者にとって、父親を中心とした向田家の出来事は大きな鉱脈なのである。それを題材に幾つものエッセイがまだ書けそうな気がした。そこで向田は父親ではなく、自分を主人公に据えて、子供の頃の思い出を描くことにする。これでいくらか家族に気兼ねせず書けるようになった。この種の作品としては、前述の「お弁当」や「傷だらけの茄子」、それに「ポロリ」や「職員室」を挙げることができる。特に後の二作品は、自分を茶化し、失敗談を軽妙に語っている。
本書のエッセイのなかで、読者はあまり馴染みのない言葉を目にする。例えば「ひとかたけ(一片食)」(「お弁当」、「食らわんか」)、「耳ざとく」(「傷だらけの茄子」)、「時分どき」(「隣りの神様」、「ポロリ」、「お弁当」)、さらに探せば「火取って」、「冥利の(が)悪い」、「持ち重り」などがある。これらの語は残念ながら、今では死語となってしまった。向田が戦後のぞんざいな言葉づかいに反撥し、昔聞いた美しい言葉を残そうと、意識的に採り入れたものである。彼女の歯切れのよい文章に挿入されると、半ば廃語となった言葉が、あたかも宝石のようにキラリと輝きを放つ。
家族の思い出以外の素材も、向田邦子は新たに見つけた。そのレパートリーには、当然のことながら、旅行や食べ物にまつわる話も入る。特に嬉しいのは、向田が「食らわんか」のなかで、自分の得意料理を伝授していることである。また一歩踏み込んだ試みとして、彼女はエッセイに性の問題を持ち込もうとした節がある。女学生だった作者が、スカートの奥に隠した性への複雑な思いや体の変化を、「襞」のなかでさりげなく告白している。さらに「夜中の薔薇」では、「子供が見てはならぬ妖しいもの」へ読者をいざなう。
そして向田邦子が最も好きだった題材は、小さきものや弱きものが見せる愛すべき姿である。「草津の犬」ではスジ肉を必死にねだる犬が描かれ、向田の飼う「マハシャイ・マミオ殿」は「まことに男の中の男であります」と称賛される。「キャベツ猫」や「お手本」においては、様々な特技を持つ犬猫が登場し、後者では文鳥、マムシまで紹介される。
作家の優しい眼差しは、動物だけでなく人間にも向けられる。「ゆでたまご」では、遠足の日、体の不自由な娘の母親が「これみんなで」と大量のゆで卵を持ってくる。またその女の子が運動会のとき、徒競走でビリを走っていると、生徒に評判の悪かった先生が彼女と一緒にゴールまで走ってくれた。「お弁当」の女の子は、貧しいおかずを恥じていたが、邦子が壺漬を美味しいと言ったので家に連れてくる。帰宅した母親が瓶を勝手に開けたことを叱責すると、泣きながら訳を話す。娘の心情を察した母親は、邦子に丼いっぱいの壺漬をふるまった。
この二作品において、向田邦子は市井の人々が垣間見せる厚情に焦点を当てている。大きな善意が施されるわけではないが、彼らの労りあう姿が読者に温かいものをいつまでも残す。両作品は素晴らしいエッセイであると同時に、少し手を加えれば第一級の短編小説になったであろう。筋の展開や人物造型がしっかりなされているため、乾いた文章にもかかわらず、人物の心情がきちんと伝わってくる。もっとも「お弁当」は、向田が直木賞を受賞した年の作品であり、エッセイと小説がすでに近似したものになっていた。
向田邦子は早すぎる晩年、シナリオ、エッセイ、小説の三足草鞋(?)をはくことになる。しかし向田はどの領域においても手抜きをしなかった。エッセイは忙しい彼女が一息ついたとき、ほどよい枚数で自由に書くことのできるとても好きな分野であった。頭に浮かんだ情景をスケッチ風にすばやく切り取る。そして彼女の感性が見慣れた風景に別の色合いを与える。向田が長年培ってきた文章技法は、このジャンルでも存分に発揮することができたのである。
末筆になるが、向田文学の特質をなす四つの要素を彼女の来歴から紹介し「解説」を終えたい。
一.長女の頑張り 向田邦子は家族や他人の難儀を見過ごせず、無理を承知で多くの事柄を背負い込む。これは文筆活動においてもいえることで、彼女は執筆依頼をなかなか断われず、常に超人的な量の仕事をこなさなければならなかった。
二.転居の利点 父親の職業の関係で、向田邦子は小学生の頃から何度も転校した。そのつど新しい学校や土地の言葉、習慣に馴染まなければならなかった。このような体験は幼い子供に大きな負担を強いた。しかし作家向田にとって、これは素晴らしい財産となる。小さな余所者は周囲を冷静に観察する能力を養うことができた。また四辺とのぶつかり合いのなかから、新たな視点を獲得することも可能となった。向田作品の斬新な発想は、この子供時代の異邦人的体験が重要な要因になっているように思われる。
三.雑誌「映画ストーリー」の効用 向田邦子は映画誌の編集者として映画を浴びるほど観た。しかもこの雑誌は映画批評ではなく、公開前の作品紹介と、そのあらすじを詳しく述べることを編集方針にしていた。向田は試写や編集作業で、必然的に様々な映画の筋を知ることになる。これが後年、彼女のバラエティーに富んだ物語を生み出す有力な源泉となった。
四.森繁久彌の知遇 向田邦子は森繁久彌から大きなチャンスと多くの知識を得た。森繁は名伯楽である。彼女の文才をいち早く見抜き、執筆の機会を与えた。そして向田の能力を確信すると、自分が担当するラジオ番組「森繁の重役読本」のシナリオを彼女一人に任せてしまう。さらにテレビ界へ進出したときには、向田をさっそく脚本スタッフの一員に加える。このように森繁の強力な後押しで、彼女は大きな可能性を秘めた新しいメディア世界へ飛び立つことができたのである。