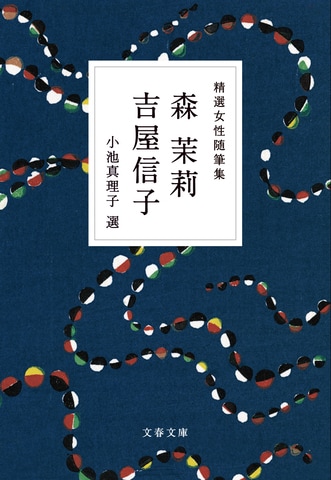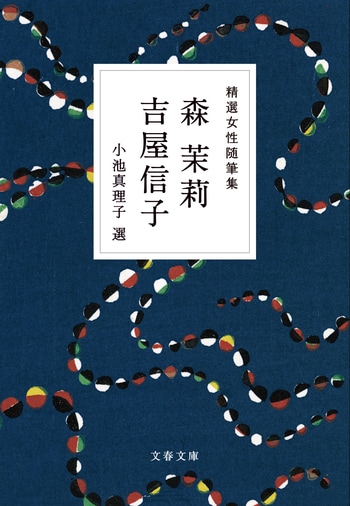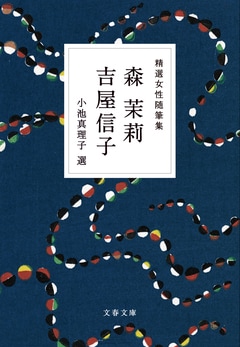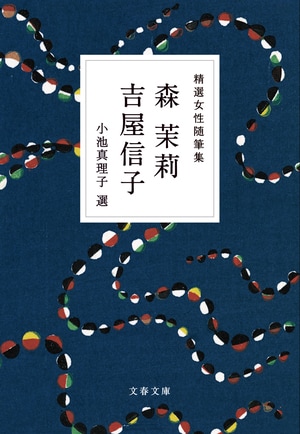
森茉莉の文学世界は、自由奔放ともいえる変幻自在な感性が、豪奢な語彙と縒り合わされて、独特の魅力を放っている。その茉莉の文学形成と生涯を辿ってみたい。
今回の森茉莉セレクションの巻頭に置かれた「幼い日々」は、幼年時代を過ごした千駄木の家での日々を描く長編エッセイである。十七編中、発表時期は最も早い昭和二十九年だが、この一作によって、文学者・森茉莉が誕生したと言える見事さである。陰翳に富む精妙な文章を、流れるように綴って間断がない。これ程に完成度の高い作品が可能だった秘密は、茉莉の人生そのものの中にある。
森茉莉は、明治三十六年(一九〇三)一月七日、東京市本郷区駒込千駄木町に、森林太郎(鷗外)と志け(しげ)の長女として生まれた。母は大審院判事荒木博臣の長女。茉莉に続いて、不律(夭折)・杏奴・類が生まれたのも千駄木の家だった。最初の妻・赤松登志子との間に儲けた長男・於菟を含めて、子供たちは皆、ヨーロッパの響きを纏う名前である。長生した四人の子供たちは、於菟の『父親としての森鷗外』(昭和三十年刊)、茉莉の『父の帽子』(昭和三十二年刊)、杏奴の『晩年の父』(昭和十一年刊)、類の『鷗外の子供たち』(昭和三十一年刊)というように、全員が父のことを書いた。汲めども尽きぬ人間鷗外の魅力がなさしめた四冊である。
茉莉が生まれ、十六歳で嫁ぐ日までを過ごした東京・千駄木の家で、鷗外はこの時期に、陸軍軍医総監や帝室博物館総長などを歴任し、『青年』『雁』『澀江抽斎』などの代表作を書き、『ファウスト』『マクベス』を翻訳刊行した。鷗外はまた、観潮楼歌会を主宰して、上田敏や斎藤茂吉や石川啄木たちを招き、幼い茉莉も賑やかな文学サロンの談笑の輪の中にいた。茉莉が生まれ育ったのは、鷗外が公私ともに最も充実した時期だった。
茉莉の幼年時代は、明るく楽しさに満ち、遠いヨーロッパから、美しい洋服や帽子が届き、時にふと不安の影がよぎることがあっても、その不安は父が追い払ってくれる。鷗外の美学も文学も、すべてが茉莉の周囲にあった。世界は父と地続きで、父のいる千駄木の家は、居ながらにして世界と繫がっていた。
永遠に続くかとさえ思える、静謐で満ち足りた千駄木時代を経て、フランス文学者・山田珠樹との結婚、そしてパリ滞在、滞欧中の鷗外の死という、大きな変化の時代がやって来る。「蛇と卵」「巴里の想い出」には、大家族の中での新婚生活や、パリ滞在中に体験したヨーロッパの文化と人々の暮らしが描かれ、無垢で柔らかな茉莉の心に、外部の世界との接触が、次第に深く刻印されていったことを垣間見せる。
帰国後数年して珠樹と離婚し、短期間に終わった仙台での再婚時代を経て、母の死と、妹・杏奴の文壇デビュー、千駄木の家の焼失……。人生の荒波が次々と押し寄せ、茉莉が現実に曝される。取り残されたような寂寥感が、茉莉の身辺を包み込む。
その中にあって、珠樹との離婚後、二十代半ば頃から翻訳や劇評を雑誌に発表し始めたことは、茉莉の自立を促し支える、大きな拠り所となったろう。対象を正確に自分の言葉に置き換えてゆくこれらの執筆を助走期として、三十代から四十代には、『鷗外全集』(岩波書店)の月報などに、父の思い出を書く機会も増えていった。
弟・類の結婚が契機となって、三十八歳で一人暮らしを始めた茉莉は、八十四歳で亡くなるまで、疎開中を除いて、一貫して一人暮らしだった。茉莉は何よりも、文学に生きることを選び取った。誰にも気兼ねせず、自由に自分の感性を解き放つことができる文学の世界こそ、茉莉の生きる場所であり、アパート一間の空間を、茉莉はみずからの審美眼によって荘厳し、そこでの生活スタイルは、世間の人々の型に嵌った価値観への辛辣な批判となった。
「好きなもの」「三つの嗜好品」「エロティシズムと魔と薔薇」「最後の晩餐」のように、美しいと思うもの、美味しいと感じる食べ物や飲み物など、茉莉が自分のお気に入りを書いたエッセイ。そして、「道徳の栄え」「ほんものの贅沢」のように、世俗の価値観を激しく撃つエッセイ。これらは、茉莉の優雅と辛辣を体現している。
森茉莉は見る人であり、眼で考えるタイプの批評家であるから、独自の用字法こそが、茉莉の美学を支える基盤となっている。歌語・詩語とも言える独特の重力を持つ表現は、明確で力感に満ちた言語感覚と相俟って、強靱な散文の構築を可能とした。現代屈指の散文家としての茉莉の達成である。
文学者にとっては、言葉こそがすべてであるが、言葉というものは、発声されるやいなや飛び去り、消え去る。時刻が飛び去るように……。それなら言葉を封じ込め、一瞬で心に刻み込むにはどうしたらよいか。茉莉の独特の用字法は、その問いかけに対する一つの回答である。難解な漢字は、しかしよく見れば限りなく美しく、オリーヴは橄欖と書いてこそ、緑なす樹木の立ち姿が顕れ、葉もそよぐ。パンは麵麭と書いてこそ、焼きたてのよい匂いが漂い、ビロードは天鵞絨と書いてこそ、その質感が目に浮かぶ。
平安時代の希代のアンソロジスト・藤原公任が『和漢朗詠集』を編纂し、殿上人も女房たちも、漢詩文の教養を身につけたのは、それが単なる知識ではなく、彼らの社交や恋愛に欠かせぬものだったからだ。江戸時代には漢詩の読み仮名(ルビ)を、洒脱な江戸言葉で振るまでに、外来文化が浸透した。近代になって、欧米体験を有する鷗外も漱石も荷風も、漢字・漢語の美学を摂取して、和・漢・洋の言葉を活かし切った。茉莉もまさしく、その文学伝統を受け継ぐ文学者である。
茉莉が翳り、茉莉が微笑う。またある時は、猛烈に怒る。「椿」はごく短いエッセイで、執筆時期は未詳ながら初期の作品とされる。停電の夜、洋燈と蠟燭の光が瞬くほの暗い室内で、内裏雛を描いた古い水彩画やガラス壺に挿した乙女椿の枝が、幼年時代の記憶を呼び覚ます。このような、ふとした思いがけない体験が、長編エッセイ「幼い日々」を執筆する契機となったのではないか、とさえ思わせる佳品である。「怒りの蟲」「続・怒りの蟲」も、「蟲」という字を見ただけで、「虫」の三倍も強烈な印象だが、自分の姿を戯画化するユーモアがある。
室生犀星・三島由紀夫・川端康成について書かれた三編のエッセイは、三者三様に文学の深淵を茉莉に指し示した彼らへの、献辞(オマージュ)である。茉莉は恐ろしい文学の魔界に、たじろぐことなく向き合った。余談になるが、犀星と三島にはすぐれた森茉莉論があり、『文藝別冊・森茉莉』(河出書房新社)で読むことができる。
茉莉はアパート一間での生活を、繰り返しさまざまなエッセイで軽妙に描くので、「森の中の木葉梟」も、猛スピードで繰り出される言葉の氾濫が、そのまま混乱を極める自室の描写となり、饒舌体の極致と思って読み進めるうちに、三島由紀夫への稀に見る痛切な鎮魂歌であったことに気づく。三島の死によって、茉莉の世界が崩壊の危機に瀕している。その悲痛な思いを振り払おうとして、言葉を撒き散らしているのだ。悲しみの淵にあってなお、生涯の大長編小説『甘い蜜の部屋』を書き続ける茉莉に、胸を衝かれる。
今回の森茉莉セレクションの最後に置かれた、「恋愛」。もし漢字に漢字でルビを振ることが可能なら、この二文字へのルビは「鷗外」以外にありえない。茉莉の人生を貫く主題である。「森の中の木葉梟」の修羅を静かに謡い納めて、夢幻の彼方に茉莉は静かに退場する。けれども読者が再びこの本を開く時、茉莉は何時如何なる時も、わたしたちの傍らに立ち戻って、微笑い、翳り、黄金色の言葉を降り注ぐ。