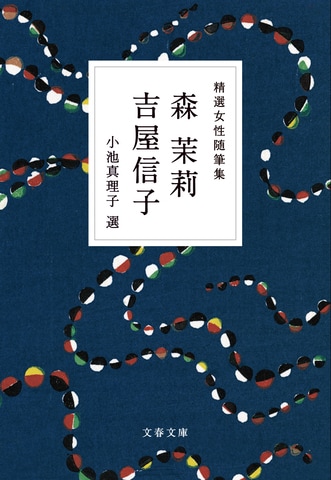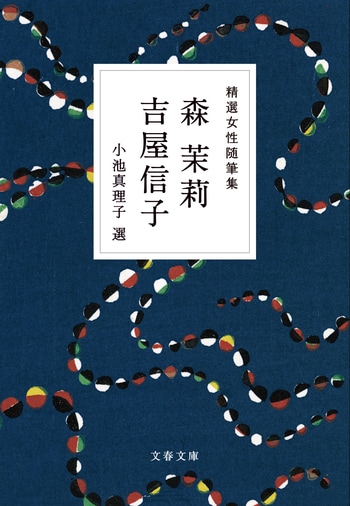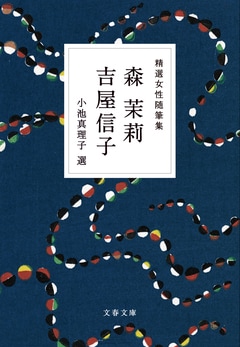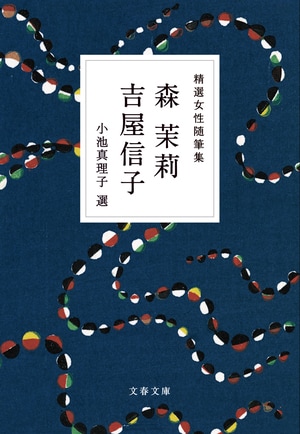
逞しき童女〈岡本かの子と私〉
純徳院芙蓉清美大姉〈林芙美子と私〉
この二篇は『自伝的女流文壇史』(中央公論社、昭和三十七年刊)より。
「小説中央公論」(季刊)に昭和三十六年から連載されていたもので、前者は昭和三十六年夏季号(七月)、後者は同じ年の秋季号(十月)に載った(連載ではほかに田村俊子・三宅やす子・山田順子などが取り上げられ、さらに宮本百合子や矢田津世子などの思い出が書き下ろされて単行本となった)。
吉屋信子は明治二十九年(一八九六)一月十二日生れ。昭和四十八年(一九七三)七月十一日に死去。両親とも山口県出身だが、地方官吏の父親は転勤が多かった。吉屋信子が生れるころは新潟県庁勤務だったが、小学校に上がるころは栃木県の役人である。
「逞しき童女」では岡本かの子との出会いを綴る前にみずからの投書家時代を回顧していた。すでに小学生のころから少女雑誌に投書が採用されており、栃木高等女学校の四年生のころからは「新潮」や「文章世界」に投書するようになっていた(女学校四年生は現在の高校一年生にあたる)。やがて投書をやめる決心をした……というのは大正三年、満十八歳のときのこと。上京し、中村武羅夫に会いに行った……というのは大正四年。このとき岡本かの子と会ったわけだ。そして大正九年、「地の果まで」を「大阪朝日新聞」創刊四十年記念の懸賞募集に応募した結果、幸いにも一等当選したのをきっかけに……と回想が続いていたけれども(厳密には応募したのは大正八年、新聞に連載されたのが大正九年)、その前に「花物語」があることは書いていない。大正五年から八年ほど「少女画報」に連載した「花物語」は女学生の千姿万態を描く連作短篇である。「鈴蘭」「月見草」「フリージア」……など題はすべて花の名前だった。新しい少女小説として好評を博したようだが、吉屋信子はそのような地位に甘んぜず、さらなる飛躍を求めて懸賞に挑んだのであろう。応募原稿は筆者の名を伏せて審査されたという。実力で勝ち取った勝利だった。
「逞しき童女」の末尾近くに、岡本かの子の遺影の前での《一平氏とわたくしの言葉など》が和木氏の追悼文にちょっと挿入してあった……と書いてある。これは「三田文学」昭和十四年四月号の和木清三郎「岡本かの子の死を悼む」のことで、吉屋信子は「花が、白木蓮とか、牡丹のような、大らかな花がお好きだったわねエ」などと言い、岡本一平は「君なんかいいね。一人死んじまやア、それで終りなんだ!」と言ったという。
與謝野晶子
昭和三十八年の二月から七月にかけて「朝日新聞」朝刊に連載された「私の見た人」の一篇(「與謝野晶子」は三月三十日・三十一日に掲載)。『私の見た人』(朝日新聞社、昭和三十八年刊)にまとめられた。
與謝野晶子に初めて会ったのは徳富蘇峰の学士院恩賜賞の祝賀会場だった……というが、この賞は蘇峰の『近世日本国民史』の既刊分(十冊)に対して授けられたもの(その三十九年後、全百巻で完結する)。授賞式は大正十二年五月二十七日にあり、祝賀会は六月十二日にあった。場所は帝国ホテル、出席者は千余名。
『私の見た人』では蘇峰の思い出も綴られている。大正十一年、大森駅でたまたま声をかけられたのが出会った初めだという。
底のぬけた柄杓〈尾崎放哉〉
昭和三十八年から翌年にかけて吉屋信子は俳人の伝記をあちこちに書いたが、これは「文藝春秋」昭和三十八年十月号に載ったもの。『底のぬけた柄杓――憂愁の俳人たち――』としてまとめられた(新潮社、昭和三十九年刊)。ほかに杉田久女・富田木歩・村上鬼城・岡崎えん女などを扱う。
本郷森川町
エッセイ集『白いハンケチ』(ダヴィッド社、昭和三十二年刊)に収められている。
「大阪朝日新聞」に応募した「地の果まで」の一等当選の知らせは大正八年十二月にもたらされた。翌年の紙面には三人の選者(幸田露伴・徳田秋聲・内田魯庵)の選評も載り、「地の果まで」の連載も始まった。
選評のうち、「地の果まで」に最も好意的なのは徳田秋聲だった。吉屋信子は三人の選者に礼状を書き送ったが、返事を寄越したのは秋聲だけだった。だからこそ秋聲の家に行こうと思ったのであろう。初めて訪れたのは大正九年四月のことである。この年、秋聲は数えで五十歳。同い年の田山花袋とともに「生誕五十年祝賀会」が催されたのは(吉屋信子の記憶とはすこし違って)同じ大正九年の十一月のことだった。
この文章は「東京だより」昭和二十八年九月号に「先生」の題で載っていた。本に入れるときかなり書き足し、書き直し、題も改めている。もとは《よくなにかの時に(どなたに師事なさいましたか)と、いわれることがあるけれど、私は文学の師というものをはっきり持ったことはなかった》……で始まっていたが、書き直されて、いささか唐突な書き出しとなった。
宇野千代言行録
「別册文藝春秋」第八十八号(昭和三十九年六月)に載ったもの(目次では「特集 文壇人物読本」の一篇)。朝日新聞社版『吉屋信子全集』では第十二巻のうち「随筆(未刊)」の部にはいっていたが、《だからなおさら八十嫗まで九十嫗まで生きる覚悟も、もっともである。》というところで断ち切られていた。初出誌ではこの一文が誌面左側ページの最後に来ている。もう一ページ分続くことを見逃したまま『吉屋信子全集』が作られたのであろう。今回は完全な形で収録した。
吉屋信子が宇野千代と初めて出会ったのは大正十三年ごろと推定され、とすると(満年齢では)信子二十八歳、千代二十七歳のころか(宇野千代は吉屋信子より一歳下)。
吉屋信子がフランスに行ったのは昭和三年のことで、宇野千代が浴衣で出席した送別会(壮行会)が開かれたのは、八月二十日のこと。
ヨーロッパ各地を回り、アメリカにも寄って日本に戻って来たのは昭和四年九月だが、その年、宇野千代は尾崎士郎と別れ、やがて昭和五年から十年まで東郷青児と暮している。
昭和十四年には北原武夫と結婚することになる。宇野千代にとって尾崎士郎は一歳下、東郷青児は同い年だが、北原武夫は十歳下であった。北原武夫が前妻を結核で亡くしてすぐのころから親しくなり、昭和十四年四月に(ここに書いてあるように吉屋信子と藤田嗣治が媒酌人となって)結婚式を挙げた。宇野四十一歳(誕生日の前なので)・北原三十二歳であった。かくて北原宇野夫妻は今に至るまで添いとげて……と書いてあるが、「宇野千代言行録」が発表されたすぐあと、二人は離婚している。
「スタイル」は昭和十一年の創刊。昭和十九年に休刊したが、昭和二十一年に復刊し、一時好調だったがやがて経営不振に陥った。『おはん』は昭和三十二年刊で、女流文学者賞と野間文芸賞を受賞している。スタイル社が倒産したのは昭和三十四年。
わたしは八十までも九十までも生きたいなァ……と語ったという宇野千代は、吉屋信子より二十年以上長く、満九十八歳まで生きぬいた。
馬と私
「文藝春秋」秋の増刊「秋燈読本」(昭和二十六年十月)に「私は女馬主」の題で載ったもの。『白いハンケチ』に収める際、改題したのであろう。
先日、アンナ・カレニナの映画を見て……とあったが、『アンナ・カレニナ』(一九四八年のイギリス映画)が日本で封切られたのはちょうど昭和二十六年九月のことである。ジュリアン・デュヴィヴィエ監督、ヴィヴィアン・リー主演。
廿一年前
もともと「中央公論」昭和十年十二月号に書いた文章を昭和三十二年五月刊の『白いハンケチ』に収めるにあたり、短い前書きを付し、題も変えたもの。「中央公論」のこの号では「女とひとり」という通し題のもと、宇野千代「私の独身生活」、細川ちか子「あへてノロケる」、吉屋信子「一つの例外」の三篇が並ぶ(宇野千代はこのとき短い独身期間にあたっていた)。
最後に『広辞林』と『大言海』を引いたところがあるが、じつは「中央公論」では《次に、大槻文彦翁の大言海を開いて、(れ)の部をきよろ/\探せど、ついに(例外)の文字は無かつた》と書いてあった。これは間違いで、『大言海』にも「例外」は載っている。しかし「れいぐヮい」という表記だったので(しかも「れいか……」の次のページなので)、気づかなかったのだろう。そこを書き直して単行本に入れたわけである。