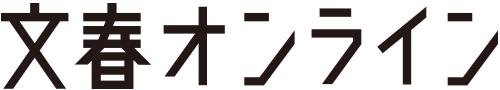〈「アフリカに行かなんだら、借金返済まで75年」心臓病の幼い娘のために…借金を抱えた父親が見つけた“まさかの儲け話”〉から続く
町工場を営む筒井宣政の二女・佳美は、心臓の疾患を持って生まれ、出生後すぐに「長くは生きられない」と宣告される。9歳になるまでは精密検査を行うことすら難しく、宣政と妻の陽子は難病の娘の成長を待つしか術がなかった――。
『アトムの心臓 「ディア・ファミリー」23年間の記録』は、そんな実話をもとにしたノンフィクションだ。ここでは本書より一部を抜粋して紹介する。
9歳になり、ついに精密検査を受けられるようになった佳美を病院に連れていった筒井夫婦が突き付けられた“厳しい結論”とは……。(全2回の2回目/最初から読む)

◆◆◆
手術ができない
筒井夫婦の共通点は、向日性ということである。
特に、キリスト教精神を拠り所にする陽子は、辛くても人のせいにしないで、力を尽くすことを心がけている。神様だけでなく、人様もよく見ているもので、助けてくれる人が必ず現れるものだ、と信じていた。だから、会社の手伝いに始まって、主婦、佳美の介護者という1人3役を、髪を振り乱しながらこなしてきた。乳母日傘で育ったのに、奈美の目には、まるで竹を割ったような性格に映っている。
そうして待ちに待った日がやってきた。
1977年、夫婦は9歳になった佳美を連れて、名古屋大学医学部附属病院にいた。佳美の心臓に治療機器を入れる本格的な検査である。それだけの体力がついたと判断されたのだ。
長い検査が終わり、夫婦はドキドキしながら、担当医が口を開くのを待った。
「佳美さんは三尖弁閉鎖症という難病です。心臓の三尖弁という弁が先天的に閉じているうえ、心臓に穴が開いています」
陽子の声にならない溜息が漏れた。
――9年も待った結論がこれなのか!
心臓の役目は、全身に血液を送ることである。全身を巡った血液は、心臓の右心房へ戻り、右心室を通って肺へと送り出され、酸素を取り込む。この右心房と右心室の間にあるのが三尖弁である。
ところが、佳美の心臓は、ポンプである右心房と右心室の間にある三尖弁が閉鎖しているので、右心房と右心室に血液の交流がなく、血液が正常に流れない。肺動脈も欠損して、肺高血圧症や肺動脈閉鎖症なども引き起こしていた。欠陥箇所は7カ所もあるという。
「手術はできないのでしょうか」
陽子が声を絞り出した。医師の顔は曇っている。
「とても残念ですが、現代の医学では手術はできません。このまま温存すれば10年ほどは生きられるかもしれません」
他の医療機関も次々に回ったが…
――そんなわけがあるものか。
陽子の心は医師の言葉をはねつけていた。外に遊びには行けないが、佳美は私のそばで洗濯物をきちんと畳んだり、キッチンで洗い物を手伝ったり、しっかりと生きているではないか。
夫婦は佳美を連れ、大阪にある国立循環器病研究センターや東京の最先端の医療機関などを次々に回った。そのたびに、声もなく首をうなだれて戻って来た。
やはり、国内で手術できるところはない、というのだ。佳美が幼過ぎてメスが入れられず、きょうまで身体の成長を待った。その間に心臓が悪いなりに血液を送り出し、異常は血管など心臓以外の箇所にも及んでしまっているという。
「国内でできなければ、海外はどうでしょうか」
病院で陽子は食い下がった。
この10年前に、南アフリカ共和国で世界初の心臓移植手術が行われている。これをきっかけに、世界中で年間百件ほどの移植手術が報告され、日本でも1968年に札幌医科大学教授の和田寿郎が実施していたが、臓器提供者の脳死判定を巡って医療界と世論の強い批判を浴び、日本での脳死臓器移植はストップしたままだった。
借金を返しつつ、手術のために蓄えた貯金は2000万円を超えていた。保険は適用されない。海外であれば、血液の調達などにも現金が必要となり、2000数百万円が必要だと聞いていた。
「日本でだめならアメリカで、それがだめならイギリスでできませんか。お金は用意します」
「カルテをアメリカまで送ってみましょう」
医師はそう言って、米国の病院にもカルテを送り、治療の方法を模索してくれた。だが、返ってきた答えはやはり、「手術は不可能です」という非情なものだった。
佳美のために手を尽くしたあれもこれも、何もかも否定されてしまった。「何とかしなければならない」という思いだけが頭の中をぐるぐると巡る。二人は打ちのめされ、涙も出なかった。それから数カ月を、二人はぼんやりと気が抜けたように過ごした。
「お金だけど、寄付しませんか」
しばらくして、陽子が「お父さん」と声をかけてきた。思い詰めているのが宣政にはよく分かった。
「せっかくたくさんのお金を貯めてくれたけど、佳美ちゃんに全然使えなかったね」
「うん」
「そのお金だけど、寄付しませんか。佳美ちゃんのような子供の治療を研究する施設なんかに」
突然の提案に宣政は絶句した。父親としては、「そうか、そうしよう」と言いたかったのだ。だがもう一人の実業家の顔が「うーん」と生返事をさせた。
――この人は寄付なんか嫌なんだろうなあ。
陽子はそう思った。
一方の宣政の脳裏にはアフリカでの熱い日々がよぎっている。
「汗水をたらし、親父の借金を7年で返した。カネの亡者のように生きてきたんだ。そう急に寄付と言われてもなあ」
2、3カ月間、ずっと考え、佳美の蒼ざめた顔を見ていた。そのうちに、「会社は順調にいってるし、遊興三昧に使うカネでもない。手術費として貯めた金だから、やっぱりこの金は寄付しよう」と思い直して、陽子に「やっぱりお前の言うようにするよ」と告げた。
そう決めると、夫婦は名古屋大学病院に寄付の申し出に行った。
「うちの子は手術できないとおっしゃったでしょう。それなら、この手術費用を寄付しますから、これから生まれる子供がこういう病気を持たないように、病気で生まれてきても治るような研究を、先生、ぜひやって下さい」
ところが、担当医は実直な人で、寄付は受け取れない、と言った。
「そんな大金、うちの病院にもらったって、いまは誰もそんな研究をしていません。どうしても寄付したいっておっしゃるんだったら、女子医大がいいですよ」
女子医大とは、東京都新宿区河田町にある東京女子医科大学病院を指している。東京女医学校を母体に1908年に開設された名門病院で、心臓、脳、消化器、腎臓病治療などで国内でもトップクラスの手術件数を誇っていた。
特に心臓外科の分野には、動脈管開存の手術をわが国で初めて成功させ、日本の心臓外科の扉を開いた教授・榊原仟がおり、全国から心臓病患者が押し寄せていた。榊原はそのころ、東京の代々木に心臓病専門の榊原記念病院を開設して女子医大にはいなかったため、助教授の小柳仁を名大病院の担当医に紹介してもらい、佳美を連れ、夫婦で新幹線で東京に向かった。
女子医大の「一匹狼」男性医師への期待
寄付の話をするためだけではない。小柳は佳美が患う三尖弁閉鎖症に関する論文を雑誌「心臓」に二度寄稿していた。
小柳は母子家庭で育ち、苦労して新潟大学医学部を卒業した後、榊原主任教授の女子医大第一外科に入局しているという。女子医大の卒業生は全員が女性だが、医局には全国から彼のような一匹狼的な男性医師が集まっていた。
その小柳に、宣政は賭けるものがあった。苦労人で自信家でもあるという。もしかすると、新しい治療法を提案してくれるかもしれない、と期待していたのである。
夫婦は外来で小柳に佳美を診察してもらったうえで、これまでの経緯を説明し、懇願した。
「この子に手術を施して、助けてもらうことはできませんか」
だが、小柳ははっきりと「できません」と言った。
宣政より5歳年上で41歳になっていたはずだが、眼鏡をかけたその顔は厳格そうで落ち着いて見えた。手術方法はまだ世界中どこにもなく、世界中の医師が模索しているところだ、と説明を加えた。
「必死で一緒に考えましょう。この子を看病しながら、新しい手術法ができるのを待ちましょう」
小柳から聞いた希望の言葉はこれだけだった。がっかりしたが、気を取り直して宣政は寄付の話をして帰った。
「このお金で人工心臓を作りませんか」
1カ月以上が過ぎ、夫婦は小柳から女子医大に呼び出された。そこで思いがけない提案を受ける。
「このお金で一緒に人工心臓を作りませんか。この分野のために投資したらどうでしょう」
「ええっ、人工心臓ですか!」
青天の霹靂だった。人工心臓は、全身に血を送る心臓を機械で代行させる装置だ。
宣政はへどもどしながら答えた。
「先生、それは僕には難しいですよ……」
人工心臓には、全置換型人工心臓と補助型人工心臓の二種類があって、全置換型は、血液を送るポンプとそれを動かす駆動装置を作り、欠陥のある心臓とそっくり入れ替えるものだ。補助型は一定期間だけ心臓の役目を代行させ、問題のある心臓を休ませたり、手術を加えたりして、本来の心臓に戻すという一時的な装置である。
佳美の場合、そもそも先天的な欠陥をかかえているから、小柳の提案は全置換型人工心臓を作ることを意味した。
それは神の領域に踏み込むことであった。
困惑して顔を見合わせる夫妻に、医師は熱っぽく説いた。
「10年も一生懸命に研究しているうちに、素晴らしい心臓ができるかもしれません。懸命にやりましょうよ」
人工心臓の開発は約20年前に、米国クリーブランド・クリニック人工臓器部で始まっていた。開発の主役は名古屋大学大学院出身の心臓外科医・阿久津哲造である。
1958年1月、阿久津は塩化ビニールを素材とする全置換型人工心臓を作り上げた。研究所の上司であるウィレム・コルフ博士とともに、犬に埋め込んで実験して1時間半、犬の生命を維持した。それは「アクツ・ハート」と呼ばれ、「世界初の人工心臓が完成した」と米国発の大きなニュースとなっていた。
――そのときよりもはるかに研究は進んでいる。しかし、自分たちがうまく作れるものだろうか。
宣政は考え込んだ。
アフリカでの商売が円高の影響を受け、会社の売上利益は圧迫されつつあった。宣政がアフリカの地を踏んだ時は固定相場制で、1ドル360円であった。しかし、変動相場制に移行してからは円が毎年高騰し、1978年10月には152円を記録している。1ドル360円の頃に比べると、利益は半分以下だ。
打開の道の一つとして、医療分野に進出できればいいな、という思いはあった。ビニール加工技術のノウハウを生かし、点滴チューブのようなものを作れないだろうか。計算してみると、医療用点滴チューブは1キロあたり10万円になり、利益を見込めそうだった。
だが、点滴チューブのようなシンプルな構造の製品を作るのと、人工心臓を作るのでは、天と地ほどの違いがある。果たして自分が挑んで良い領域なのかさえ分からない。
無謀な賭けに打って出る決意
宣政が返答できずにいると、小柳はこうも言った。

「できなくても、業界の発展のためになりますよ。業界のためにならなくても、こういうことにお金を使いきったということであれば、皆さんも満足いくんじゃないですか」
その言葉に夫婦は胸を打たれ、無謀な賭けに打って出ようと決意した。
佳美のために何かをしたくて、もがいてきたのである。まだ何かしてあげられることがある。そして、それは他の病気の子供たちを救うことにもつながる。そこに、ほんのかすかな光を感じたのだ。
後で知ったことだが、阿久津も「人工心臓を作ってみようじゃないか」とコルフに言われて、成功の確信のない漠然とした思いで出発したのだ。後藤正治の『人工心臓に挑む』(中公新書)によると、阿久津は「自然心臓に似た人工物をともかくもつくり上げて、動物実験にまで持ち込むしかない」と文献も何一つないところから始めたという。
当時、日本の人工心臓は東京大学と大阪大学が競って研究をしていた。東大の研究所は当時の文部省、阪大は厚生省のバックアップをそれぞれ受け、国の資金で研究をすることができた。
東大の研究を担っていたのは、医学部教授であった渥美和彦である。人工臓器の権威となる渥美は、漫画『鉄腕アトム』の作者・手塚治虫の旧制中学の同級生であり、お茶の水博士のモデルの一人とされている。
たとえて言えば、「アトムの心臓」を作ろうとしている研究者であった。
一方の東京女子医大は、心臓病治療においては群を抜いていたが、莫大な資金を必要とする人工心臓を研究する体制ではなかった。
後になって、宣政はこう考えた。
「東京女子医大なりに、人工心臓の分野にも進出したいという思いがあったのではないか。自分はそのための試金石のようなものだったかもしれない」
学会のそうした事情を知ることなく、ど素人の夫婦は人工心臓の勉強にのめり込んでいった。このとき、宣政は37歳、陽子は35歳である。
INFORMATION
映画『ディア・ファミリー』6月14日(金)より公開中
主演:大泉洋/監督:月川 翔/配給:東宝
映画公式サイト:https://dear-family.toho.co.jp/