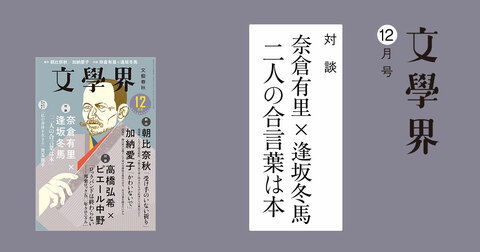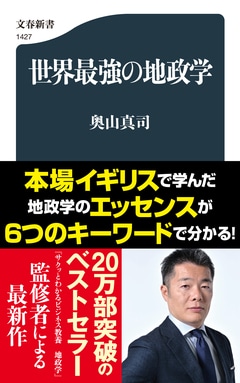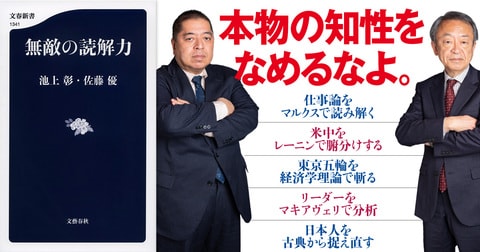ここは午前の光が差し込む明るい教室です。二〇二二年の春、都内の大学で文学を専攻する学生たちが、ロシア文学の授業に集まりました。学生たちの雰囲気が例年よりやや不安げに見えるのは、二月末からはじまった戦争のせいでしょうか。シラバスによれば授業は演習形式で、ゴーゴリ、プーシキン、ドストエフスキー、ゲルツェン、チェーホフ、トルストイといったおなじみの作家たちの作品を一コマにひとつずつ扱っていくという、ごくスタンダードな内容……の、はずでした。ところが、授業を担当する枚下先生は、どうやらいっぷう変わった人のようです。
シラバスをよく見ると、こんなメッセージが書いてあります──
自分がふだん暮らしている世界とはまったく違う、はるか遠くに感じられるものごとにじかに触れるためには、いったいどうしたらいいのでしょう。この授業では、あなたという読者を主体とし、ロシア文学を素材として体験することによって、社会とは、愛とはなにかを考えます。
ロシア文学らしいというか、いきなり「社会」や「愛」だなんて少し大仰な気もしますが、さて、いったいどんな授業なのでしょうか。まずは教室に入ってみます。すると、おや? 教室の真んなかあたりの席に座っている真面目そうな男子学生が、なにか語りたそうにしています。それではこの先は、彼に案内してもらいましょうか──
初回ガイダンス
枚下先生の第一印象は、山だった。それも、雪をかぶった巨大な山。授業開始の時間ちょうどに、身長二メートルはあるんじゃないかというどっしりとした初老の教授がドアを開けて、のしのしと教室に入ってくる。真っ赤なシャツはまるで夕陽に染まった山肌だ。教壇に立った先生は、頭にきれいな白髪の髪を輝かせて見下ろすように教室全体をみまわすと、僕たちを見て「ふふーん」と一瞬だけ唐突に無邪気な笑みを浮かべてまた真顔に戻り、
「ロシア文学の授業ですね。枚下です。どうぞよろしく」
と挨拶してから、
「まだ履修登録が終わっていなくてみなさんの名前がわからないので、いまから回す紙に名前と学年を書いてください、あ、ふりがなもふってくださいね」
となめらかなテナーの声で言い、A4サイズの白いコピー用紙を最前列の学生に渡した。
ごく普通の初回ガイダンスの風景。朝十時四十分に始まる二限の授業で、履修者は十数人か。まだ寝ぼけた顔をした学生も多い。前から回ってきた紙に「新名翠」の整然とした字が浮かんでいるのを一秒ほど見つめてから、なるべく丁寧に「湯浦葵」と書き、となりの入谷に渡す。そして横目で、蛇がのたうったような個性的な字で「入谷陸」と書き入れられるのを見届ける。
この三人の名前の並びを見るたびに僕は、去年、一年生のときの最初のロシア語の授業を思いだす。ネイティブ教員のタマーラ先生はソ連時代に日本人のロシア文学研究者と結婚してからずっと東京に住んでいるおばあさん先生で、ふっくらしているのにひょいひょいと身軽に教室じゅうを歩き回りながら元気にロシア語をしゃべりまくる。自己紹介のとき、まず新名翠の苗字を聞くと「ニーナ! ロシア語にするとお名前みたいな苗字ね、かわいらしくてあなたにぴったり」と微笑み、続いて僕の苗字を知って「まあ、このクラスにはユーラもいるの!」と仰天した。最後に入谷の苗字を聞いたときにはもはや微笑みどころではなくなって、「イリヤ! どうしちゃったのかしら今年は、みんな私が子供のころ仲の良かった友達の名前よ……」と笑いながら涙ぐんでしまい、教室がどことなく温かな祝福に包まれたのだった。それ以来タマーラ先生は、ほかの学生のことは基本的に下の名前で呼ぶのに、僕たちのことだけは「ニーナ、ユーラ、イリヤ」と苗字で……とはいえ完全にロシア語の名前と化した発音で呼ぶ。おかげで僕ら自身も自然にお互いを「新名」「湯浦」「入谷」と敬称略の苗字で呼び合うようになったってわけだ。
と、僕が得意の回想にふけっていると、まだ手書き名簿を回し続けている教室に枚下先生のうたうような声が響いた──
「この授業では基本的に一回の授業でひとつの作品を扱います。みなさんの課題は、授業までにその作品を読んでおくこと。そして授業ではその作品を体験すること。この授業は体験型でおこないます」
僕は思わず先生の顔を見た。おもしろいことをいう先生だ。「体験型」って、なんだ? 作品の世界に入り込むっていうことだろうか。だとしたら得意だぞ。僕は新名みたいにとびぬけて洞察力があるわけでも、入谷みたいに器用になんでもこなせるわけでもないけど、小説を読みだすと周りが見えなくなることにかけては負けない。なんたって、長所なのか短所なのか自分でもわからないくらいだからな。
初めて自分がちょっとおかしいんじゃないかって思ったのは、小学校三年生のころ、読書の時間にクラスのみんなと図書室で本を読んでいたときだった。そのとき、めちゃくちゃ面白い本をみつけたんだ。僕みたいなちょっとひ弱な男子が、夏休みの終わりに何人かの友達と不思議な世界に迷い込んで恐竜に会う──っていう冒険小説なんだけど、読んでいるうちに図書室もみんなも視界から消えて、僕は主人公の体験を追うみたいに、本のなかの世界にいた。気がついたときにはほんとうに図書室に誰もいなくなってて、給食の時間も終わりかけてた。つまり僕はそのとき授業の時間が終わったチャイムにもみんなが教室に戻っていくのにも(たぶんそのとき誰か友達が僕に話しかけていたことにも)給食のいい匂いが漂ってくるのにも気がつかずに本のなかから帰ってこれなかったってことになるわけだけど、でもはっと気づいたときに感じたのは不安や戸惑いじゃなく、「すごい本をみつけたぞ!」ってことで、有頂天になってその本を借りて帰ったっけ。
それからは、またそういう体験がしたくて学校のある日は図書室に入り浸って、休みの日は自転車で市立図書館に通って、本を読んだ。
中学に入ったころ、読書好きの友達ができた。名前は渉。好きな本は僕とはぜんぜん違って、大人が読むような日本の小説ばかりをたくさん読んでいて、村上龍(※1)の熱狂的なファンだった。そのころの僕はヘッセ(※2)にはまっていて、文庫で読めるやつを片っ端から読んでいた。渉の勧めてくれた本を読もうとしたけど、数ページで心臓がひっくり返りそうになったからやめた。本人に言ったら大笑いされたけど、それでも僕たちはそれぞれ好き勝手に自分の読んだ本の話をし続けた。あいつは村上龍で、僕がヘッセ。会話が成り立ってたのかっていったら微妙だけど、学校の話でも塾の話でもなく、本の話ができる友達ができたのが嬉しかった。でも渉は中学卒業の直前に親の転勤でロンドンに行ってしまったきり、向こうで暮らしている。渉とはメールやショートメッセージでやりとりを続けているけど、もうずっと会っていない。
僕は大学の文学部に入り、なかでもいちばん本の虫みたいな人がたくさんいそうな気がしたロシア文学科に進んだ。そしていま、ロシア文学の授業に出ているわけだ。
枚下先生がホワイトボードに大きくいくつかの単語を書いている。僕を含め学生たちはその文字を目で追う──「戦争」「国家」「恋」「喜劇」「愛」「悲劇」「死」「時間」。そして、踊りだしそうなステップでくるりとこちらを振り返り、
「さて問題です」
と言ってまた一瞬だけにっこりと笑顔になり、ふたたびおおげさなくらい真面目な顔に戻って、
「みなさんは、ここに書かれた言葉がわかりますか?」
と続ける。どういう意味だろう。ななめ前に座った新名がひとつひとつの単語を確かめるように見つめ、なにかがわかったようにちいさく頷く。となりの入谷は首をかしげる。そうだ。ある意味ではわかるし、ある意味ではわからない、と僕は二人を見て思う。枚下先生は戻ってきたできたての手書きの名簿にちらりと目を落とすと、どういうわけか僕をまっすぐに見て、
「湯浦君、どうですか」
と、訊いた。僕は目を丸くする。だって、この先生の授業に出るのはこれが初めてだし、先生は僕を知らないはずだ。さっきの紙に名前を書いた順番で僕の座っている場所がわかったのか? いくらさほど人数が多くないとはいえ、正確にわかるものだろうか。不気味に思いながらも、僕は慎重に答えようとする──
「わかることと、わからないことがあります。たとえば戦争とはなんなのか、辞書的な意味でも、時事的な意味でも、よくわかるように思えます。二月からはじまったウクライナ侵攻のニュースを見て、衝撃を受けているところでもあるし……。愛っていうのはそれに比べると曖昧模糊としているしよくわからないけど……少なくともこれまで読んだ本から、たくさんの人がその言葉にいろんな意味を込めてきたことは知っていると思います。喜劇や悲劇については、一般的なイメージと文学用語としての定義がずれているって話を、別の授業で聞いたことがあります。えっと……それで、そういうのをぜんぶまとめて『わかる』かどうかといえば、わからない気がします」
言い終えて、横で入谷が笑いをこらえているのに気づく。「あいまいもこ」と小声で言われる。いつものやつだ。僕はどうもふつうの人は口頭で言わないような言葉をしゃべる癖があって、それが入谷には面白くて仕方ないらしい。ま、いいけど。
肝心の発言内容にはあんまり自信がなかったが、
「なかなかいい答えですね」
と、先生がゆっくりひとつ頷くのをみて、ちょっとほっとする。
「ほかになにか発言したい人はいますか?」
ななめ前の席の新名翠が細い腕をまっすぐに挙げる。少し緊張気味に指先に力を入れているその姿に、僕はいつものように見惚れてしまう。先生はこんどは名簿も見ずに新名だけを見て、
「はい、新名翠さん」
と指名する。やっぱりだ。先生はもう誰が誰だか完全にわかっているらしい。あの手書きの名簿と僕たちの顔を一瞬で覚えたのか? いや、名前はともかくどうやって顔と一致させたんだ。でも新名はとくに気にするふうもなく口をひらき、
「これらはかけ離れた言葉のようでありながら、それぞれ『何々とはなにか』という問題が長らく問われ続けている点で共通していると思います。戦争とはなにか、国家とは、愛とは、時間とはなにか。そしてそれらはいずれも学問の分野を横断するような、広がりのある多様な議論になっています。悲劇と喜劇については、一見すると文学ジャンルの問題に限られるようにも思えますが、ひょっとしたらそこにまだ私たちの知らないなにかがあるということなのかな、と考えました」
とまとめる。いいことを言ったような気はするのだけれど、僕はついその声に気をとられてしまう。新名の声には風鈴が鳴るような不安定な心地よさがある。風に揺らぐ音をいつまでも聴いていたいような感じだ。枚下先生は大きく頷いて、続ける──
「いいところをつきますね。まず世のなかには、意味がわからなくなりやすいのに、わかっていると思われてしまいがちな言葉というものがあります。新名さんが言っているように、本来なら古今東西その定義についてたくさんの議論がなされてきたにもかかわらず、それとはまた別に無限の多様な解釈が自己主張をしている。湯浦君が『愛』について言ってくれたように、たくさんの人が異なる意味を込めて、しかも日常的にかなりの頻度で使っている言葉というものがある。みなさんは、たとえば『すべては愛』だとか、それに類した表現を聞いたことがあるでしょう。でもほんとうに『すべて』が愛だったとしたら、なにかを名指すという言葉の本来の意義が失われてしまうことになります。テリー・イーグルトン(※3)の言葉を借りるなら、『どんな語でも、もしそれがありとあらゆるものを意味するようになると、その語の明晰な輪郭は失われ、最後にはただのうつろな音となってしまう』でしょう」
かつん、と頭に小石が当たったような感じがして、僕はまばたきする。僕が「曖昧模糊」としか表現できなかったもどかしいものに、先生がすごいヒントをくれた気がする。なにかを名指すという、言葉の本来の意義が……失われてしまう……。
入谷が手を挙げて、
「じゃあ、『すべては愛』ってのは正しくない表現だってことですか?」
と訊く。入谷はいつも発言に躊躇がなくてなんにつけても見切り発車なところがあるけど、いい質問をすることも多い。先生は予期していたかのように「ふふーん」と鼻を鳴らし、
「確かに、『すべては愛』という表現そのものが無意味でばかげているように思えることもあるでしょう。辞書をひいたとき、『愛』の語義に『すべて』と書かれていても困りますね。しかし、それを『正しくない』表現と決めつけるのはまだ早い。だってそう表現をした人は、きっとなにかその人にとって大切なことを言おうとして、その結果として意味のインフレとそれゆえの大暴落が起きてしまったのではないでしょうか。そうだとしたら、そんな発話者の意図を無視して『正しい』『正しくない』を決めつけるのは、ちょっと残酷です。そう思いませんか?」
入谷が唇をとがらせて、小刻みに二度うなずく。考えながら聞いているときの癖だ。先生は続ける。
「たとえば、もし人生のなかであなたが発する言葉について、『辞書的に正しいかどうか』だけを常に問題にされ続けるとしたら、どんな感じがするでしょう。なにか話をするたびに、正確な表現かどうかのみに焦点をあてられるとしたら? もちろん、討論をするときや論文を書く場合であれば、綿密にひとつひとつの言葉の語義を確認し、なるべく正確に読み手に伝わるように言葉を使う必要があります。でも、友達とおしゃべりをしているとき、恋人とかけがえのない時間を共有しているときなんかには、その人が言葉に込めている独特のニュアンスを一所懸命に読みとろうとしたりとか、その人がどうしてその言葉を使うのかを考えてみたりだとか、逆にその人が使いたがらない言葉があればそれがなぜなのか、 相手がこれまでどういう言葉に傷ついてきたのかを考えたりとか、そういった『語義ではないもの』にも気を配ることによって、より親密な対話が成り立つものでしょう。いいかえるなら『ほんとうに正確な語義』は、コミュニケーションの文脈を読みとるという視点においては、人の数だけあるといってもいい。文学作品を読むときは、辞書的に正確な語義を知ることだけでなく、まるで友人や恋人に対するように、本に対してそうした『辞書的な語義ではないもの』に配慮することも大切になってきます。これは、小説を『体験』するうえでとても大切なことです」
そこまで話すと、枚下先生は教卓の上に置いてあったプリントを列ごとに配りはじめた。
「課題図書の一覧です。それぞれの授業までに読んできてください」
※1 村上龍(1952─)小説家。代表作に『コインロッカー・ベイビーズ』『イン ザ・ミソスープ』など。
※2 ヘルマン・ヘッセ(1877─1962)詩人、小説家。代表作に『車輪の下』『デミアン』『ガラス玉演戯』など。
※3 テリー・イーグルトン(1943─)文芸批評家。代表作に『文学とは何か──現代批評理論への招待』『アフター・セオリー──ポスト・モダニズムを超えて』など。ここでの枚下先生の引用は『イデオロギーとは何か』(大橋洋一訳、平凡社ライブラリー、33 頁)より。
「シラバス・初回ガイダンス」より