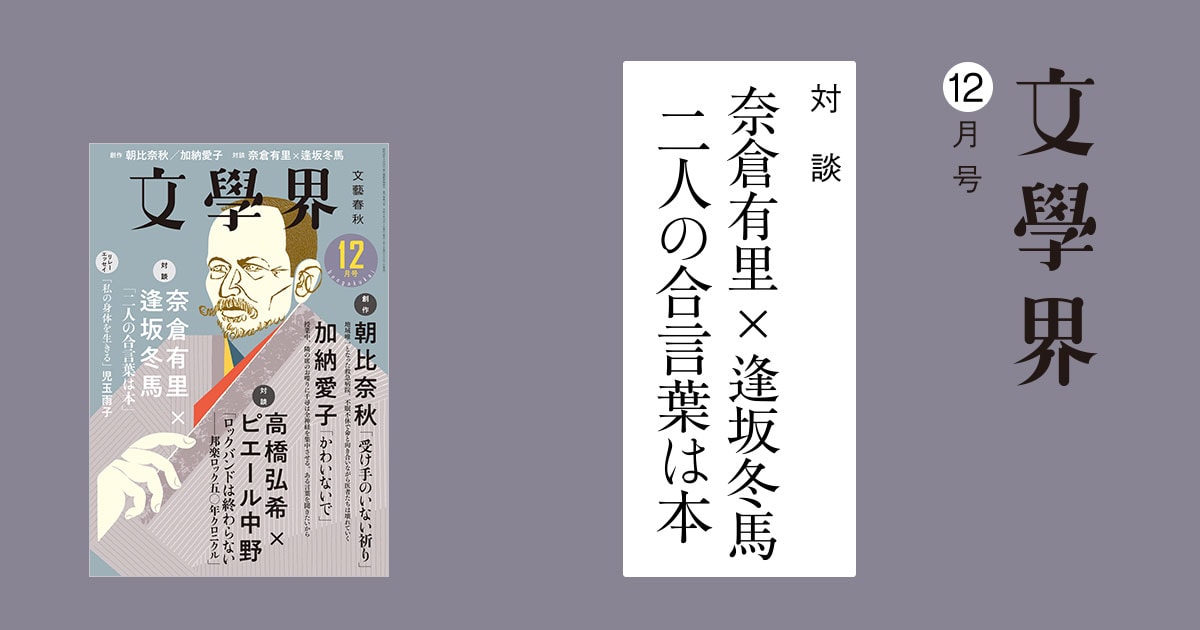実の姉弟であり、同時期に初めての単著を上梓した、ロシア文学者・奈倉有里氏と、小説家・逢坂冬馬氏。対談集『文学キョーダイ!!』の刊行を記念して、「異性を書く」をとりまく問題、ロシア情勢、そして危機下の「文学の力」について語り合う。
◆プロフィール
奈倉有里(なぐら・ゆり)●1982年、東京生まれ。ロシア国立ゴーリキー文学大学卒、東京大学大学院博士課程満期退学。博士(文学)。著書『夕暮れに夜明けの歌を』で紫式部文学賞、『アレクサンドル・ブローク 詩学と生涯』でサントリー学芸賞(芸術・文学部門)を受賞。近著に『ことばの白地図を歩く――翻訳と魔法のあいだ』『ロシア・東欧の抵抗精神――抑圧・弾圧の中での言葉と文化』(共著)。
逢坂冬馬(あいさか・とうま)●1985年、埼玉生まれ。明治学院大学国際学部国際学科卒。『同志少女よ、敵を撃て』でアガサ・クリスティー賞を受賞し、デビュー。同書は2022年本屋大賞を受賞し、第166回直木賞の候補にもなった。近著に『歌われなかった海賊へ』。
■往復書簡と対談の間で
奈倉 今日は、私と逢坂さんの対談本『文学キョーダイ!!』についてのお話ということで、まずはこの本の成り立ちについて確認してみましょう。
私と逢坂さんについて「姉弟って、ほんとの姉弟ですか」って言われることがあるんですが、ほんとの姉弟です(笑)。初めての単著が出たのがちょうど同時期で、二〇二一年の十月に私の『夕暮れに夜明けの歌を――文学を探しにロシアに行く』という本が出て、同じ年の十一月に、逢坂さんの『同志少女よ、敵を撃て』が出ました。
その流れで、往復書簡をして書籍にしませんか、というお話をいただいたんです。でも、逢坂さんからトークの方が良いのではないかと提案があって。
逢坂 そうなんです。依頼をいただいたのが、『歌われなかった海賊へ』(早川書房、十月十八日刊)のプロットを練っている時期だったんですが、ちょうどすごく苦戦しているタイミングで。ですから、書き仕事は全部新作の小説に注力しなければならないと思っていたんです。
そこで押井守監督が、姉の最上和子さんという舞踏家の方と対談本を作っていたことを思い出したんです。対談なら書き仕事を増やさないで済むし大丈夫かなと提案しました。でもやってみたら、対談は対談で結構大変だった(笑)。
奈倉 大変でしたね。私は、ふだんインタビューを受ける際も事前に原稿を用意して、ゲラにもそうとう手を入れるんです。だから最近はインタビューの依頼でも、文章で書かせてくださいと返しているくらい。対談にしても最終的にはかなり手を入れるはずだから、往復書簡の何倍もの時間がかかるんじゃないかと思った覚えがあります。
逢坂 結局二人して、原稿でかなり手を入れることになりましたね。
ちょっとご説明すると、この本ができるまでの流れって普通じゃないんですよ。普通、対談というのは、まず録音データをそのまま書き起こしてデータにした、文字起こし、というのが作成されるんですね。そのうえで、言葉や話の流れを整理した原稿が出来上がるんです。普通、作家がチェックするのは原稿から。でも今回は、文字起こしの段階から僕らでチェックをしました。
それも、原稿になる前に二回チェックをしているんですよ。まず、「えーっ」とか「あーっ」とか、意味のない相槌も残っている、発言通りのテキストデータを受け取って、二人で言い間違いや事実関係にまつわる修正をしました。そのうえで、構成や小見出しはまだついていないけれど、言葉が整えられたデータが届く。その段階から、さらにガンガン加筆しました。
まず奈倉さんが先に赤字を入れるんですが、現場で話していなかった発言が突然出現しているんですよ。となると、それに僕が応答しないと会話が成立しませんから、さもその場で話しているように相槌を追加したりして。同時に、僕の方でも話していなかったことを思いついて追加しました。たとえば、高橋源一郎先生が姉弟だと知らずに、僕らに同時にラジオのオファーをくださった、というくだりは加筆で生まれた部分ですね。
奈倉 その加筆に対して、私がまたリアクションを書き足して。
逢坂 そうやって出来上がった原稿を、最後に石井千湖さんが整えてくれました。
奈倉 石井さんが整理してくださった原稿を受け取ったときは本当に驚きましたね。「これで本に近づいたな」という感動がありました。本当に感謝しています。
逢坂 そうそう。
奈倉 そこにさらに手を入れて、この本が出来上がりました。だから結果的には、話したことと、書いたことのちょうど中間くらいの本になったように思います。
逢坂 結果的に往復書簡に接近してしまいましたね。対談も、意外と楽ではないなと思った(笑)。
でも、この書籍のおかげで『歌われなかった海賊へ』の執筆がはかどりました。『文学キョーダイ!!』が忙しさのピークを越えたところで、『歌われなかった海賊へ』の執筆が進みだし、小説が一段落すると『文学キョーダイ!!』のゲラが届く、といったスケジュールで。別に示し合わせたわけでもないのに、締め切りが交互にやってきました。
■異なる航路、同じ母港
奈倉 編集部からは今日の対談にあたり、「書籍では触れなかったお二人の思い出があればぜひ」とトピックのリクエストがありました。逢坂さん、いかがですか。
逢坂 ……今日、そんなにちゃんとした流れでしゃべるの?
奈倉 私、基本的に書いてあるものを話すことしかできないので。
逢坂 私、脱線させるのが大好きなので。
奈倉 脱線すると、わけがわからなくなるから。話を戻して、思い出話をしますと、私はよく友達に「弟がかわいい」と言っていたんです。私が中学生、逢坂さんが小学生のころかな。友達が家に来ると、「おー、これが自慢の弟か!」と言われた記憶があります。
逢坂 二十余年も経って、もう当時の面影なんてなくなっていますけれどね。ちょうど本日で三十八歳になりました。
奈倉 おめでとう。あまり変わってない気もします。
逢坂 本当に?(笑)
奈倉 でもたぶんいまは、ふだんは目の前の仕事で頭がいっぱいで、お互いを意識する機会がないですね。
それからこの本の「おわりに」にも少し書いたんですが、私は家族というものを特権化したくないんです。ある一定期間同じ家に住んでいたからといって、相手のことを理解しているとは限らない。むしろ、わかったつもりになりがちだからこそ、見えていないこともあって。
逢坂 そうそう。
奈倉 だからこそ、相手の書いているものを読むといろんな驚きがある。
逢坂 自慢じゃないんですが、『文学キョーダイ!!』の「はじめに」で書いた、「本書は世界という巨大な島を両岸から航行して観測し、文学岬ロシア港で再会した二隻の船の航海日誌であり、船乗り同士の語り合いでもあります」というたとえは、我ながらよく思いついたなと思っていて。
奈倉 間宮林蔵の話も印象的でした。間宮は上司である松田伝十郎と、樺太が島なのか半島なのか、手分けして確かめに行った。「わたしは西、そなたは東を行くのだ。もし、カラフトが島ならば、どこかで会えるはずだ」と言って、二人は樺太の南端で別れたんです。
逢坂 僕らも同じように、母港は一つなんです。でも、そこから出発した後は全く違う航路を辿っていて、相手がどこにいるかはわからない。ですから、二〇二一年の十一月ごろに、偶然二人の単著が世の中に出て、内容がどちらもロシアに関連していたのは偶然だったんですよね。最近は、お仕事でよく会うんですが、互いの生活圏も違いますし、基本的には、お互いの船の場所はわからないんです。
奈倉 本が出たときに別々の船の上から「おーい」って場所を確認するみたいな。
逢坂 結局書いたものを通じてしか、なかなか相手を理解できないですよね。
■「異性をうまく書ける」とは
奈倉 ですから、この書籍を作る作業を通じて不思議だったのは、意外と二人に共通点があったことでした。
逢坂 たとえば性別の話ですね。文章だけを通じて作者像を理解する人にとっては、僕は女性だと思われることが多いんです。一方で、奈倉さんは男性だと思われることが多い。これは本当に驚きましたね。
奈倉 そうそう。でも『文学キョーダイ!!』の中でも話しましたが、私は男性が主人公であっても、「異性の視点」だと思って書いてはいないんです。「文學界」で連載している「ロシア文学の教室」もそうです。かといって、同性だと思って書いているのかといわれたら、そういうことでもなくて。
そもそも性別とは、基本的には必要なときにだけその特性を発揮するものであり、必要なときというのは非常に限られているんです。それはいわば公私の両極で、ひとつはごく親密な、当人が「この人となら性にまつわる話ができる、そういう関係になれる」と感じ、相手に対して心を許した場合。もうひとつは逆に極端に公の場で必要性のある場合、医療の場などで識別が必要な場合です。そうでない場合――たとえば学校とか会社とか、日常的な交流の場で性差を重視するのは、社会に刷り込まれた一種の強迫観念のようなものですし、それは容易に、強い立場の側から弱い立場の側への圧力を温存する構造につながります。小説のなかの登場人物の性別は、場合に応じて異なる相応の必要性を担っているからその性別になるのであって、著者の生物学的な性とはなんの関係もありません。
逢坂 「異性をうまく書ける」という評価は、その評価を下す側の無意識の前提を示していますよね。そういう人たちは性別を内面に転化していて、その内面化された性別が明確な特性を持っていると考えている。人種や国籍など、他のカテゴリーで考えてみればわかりやすいんですが、それは非常に危険な考え方なんです。
僕らが共通していたのは、難しいことに挑戦するつもりで異性を書いたのではないということです。あくまで、普遍的な人間を書こうとした結果なんですよね。
僕は『同志少女よ、敵を撃て』において、女性が直面したジェンダーギャップは確実に意識していましたが、「女性特有」の内面を書いたつもりは全くありません。むしろ内面が同じだからこそ、差別的な待遇を受けた時の反応を類推して、理解することができる。
奈倉 この本のテーマの一つは「本を読むとはどういうことか」なんですが、そもそも読者が自分の性別を、本を読む時点で問題にする必要はまったくないわけですよね。本は人間が抱えてしまう世俗的な属性からその人の内面を解放してどこか別世界に連れていってくれるもの。書き手の意識としていうなら、読者がどんな目の色をしているのかを問いただすような本を書くべきではないということと同じで。
逢坂 そんなことがあっちゃいけない。
奈倉 目のたとえでいうなら、私が書こうとしているのは、目の色や、大きさや、形ではないんです。描写をしてはいけないということではありませんが、どこに焦点をあてるかの問題として――その奥にどんな感情が宿っていて、なにを訴えようとしていて、というところに核心があるんです。
逢坂 「異性」をことさらに難しいものだと捉えようとするから、逆に変な描写をするひとがたくさんいるわけですよね。異性を特徴としてとらえようとすると、変な決めつけが生じてしまうんです。小説でも、それ以外のジャンルでも、「女性らしく」「男性らしく」書こうとした結果、きわめて珍妙な人物ができあがってしまったりする。それ、ちょっとやめない? と思うんです。
性別によって、社会に差が生じていることは事実です。賃金の格差や社会進出における格差などがまさに問題になっているわけですが、それは内面に差があるのではなくて、置かれている社会構造の問題なんです。
すごく異性がうまく書けている、と僕の作品を読んだ人がいるとしたら、どうしてそう思うのか、一度自分に問いかけてみると、面白いことが起きるんじゃないかな。
奈倉 「異性を書く難しさ」については、『同志少女』のインタビューでよく聞かれたことみたいだけど、今回の対談で、お互いに何度も「人に聞かれなかったら考えなかった問題だよね」と言いあいましたね。
逢坂 本当に考えなかった。びっくりしました。
奈倉 なぜそういう質問をされるのか、ということについて考える機会にはなったんですけどね。
逢坂 『同志少女よ、敵を撃て』の作者は実は女なんじゃないか、と結構な人に間違われましたが、まさに『アンナ・カレーニナ』みたいですよね。
奈倉 本のなかでもお話ししましたが、トルストイの『アンナ・カレーニナ』は、アンナの内面が非常に巧みに描かれていますよね。作家のリュドミラ・ウリツカヤも言っていましたが、女性の内面は女性しか書けない、と考えている人が、誰が書いたかを知らずにあの作品を読んだとしたら、きっと「作者は女性だ」と信じ込んで、「さすが女性だな」と感心すると思う、と。
逢坂 トルストイと自分を同列に並べているというわけではないんですが、トルストイも、「女性なるもの」を研究対象のように他者として観察して書いたわけではないと思います。人間を観察して、人間性の表出する瞬間をとらえようとした結果が、女性だったり男性だったりしただけ。本当は読者も、そのリアリティが性別によるものではないということは、感じているはずです。
奈倉 そうですね。トルストイ本人も、他の人の作品について批評するときに同じようなことを言っていました。人間の外側しか知らないと、どうしても噓やごまかしのある造形になる。その人物が、実体のない存在になってしまう。問題はどちらの側から書くか、というところにあって、外的な要素――性別や身分や人種にこだわるのではなく、「内面の理解」という点に立つことが大事だ、その意識がないといけない、という。
逢坂 もちろん、現在の社会のギャップを考えれば、自分が男性の立場から、戦争とジェンダーというテーマを書いてもよいのか、ということは結構考えたんです。女性をうまく書けないから、という話ではなく、ある種のフェミニズム的テーマを、男性である私が書くのは倫理的に危ういかもしれない、とは思った。でも、全く予期していなかった「女性をうまく書けている」という驚きの声を前にして、もし自分が女性だったらまず間違いなく「女性ならではの戦争小説」と言われてしまっただろうなと思いました。
■戦争と小説の関係
逢坂 『同志少女よ、敵を撃て』でもう一つ難しい問題だったのが、エンターテインメント性についてです。大前提として、小説として面白くなければならないわけですが、戦争小説を面白く書くことには危険性がありますよね。
ウクライナ侵略が始まってから、読者の方の感想に一つ変化が生まれました。それまで、僕の小説を誉めてくれる人というのはありがたいことに「本当に面白かったです」「素晴らしかったです」というふうに感想を伝えてくれたんです。でも、戦争が始まった瞬間から、感想の頭になにか一言つくようになった。「こういっていいのか分からないんですけれど、すごく面白かったです」のように。作者としては少し悲しい気持ちもあるんですが、頭になにかつけてしまう発想を責めるつもりはまったくなくて。自分が読者だったとしても、必ずそう言ったと思います。それだけ読者が、目の前の戦争という事実に、真剣に向き合ってくれているということだと思うんです。自分自身が、執筆中に「戦争小説を面白く書く危険性」をかなり強く意識していたことも、読者の方からの感想が変化したときに気がつきました。
奈倉 『文学キョーダイ!!』のための最後の対談が今年の四月で、その後も刻々情勢は変化してきました。
逢坂 情勢の話は本当に地獄ですよね。戦争が起きたときにはもちろん強い衝撃を受けましたが、こういう形で戦争が継続するとは思っていなかった。今はそのことに衝撃を受けています。さらに恐ろしいことに、続いていく戦争に対して、あらゆる意味で慣れが生じてしまっている。
奈倉 なすべき議論が置いてけぼりのまま、都合のいい解釈が進む面は確かにありました。国によっては武器の輸出が日常になってしまう。
逢坂 今、アメリカの連邦議会では予算審議が佳境を迎えていますが、ウクライナ支援のための予算が大きな問題の一つです。アメリカが巨額の費用を投じてウクライナに支援を行っていることについて、共和党が反対しているわけですね。これを、「支援疲れ」という一言で完結させている人がいますが、そうではなくて、慣れの問題なんですよ。
コロナ禍以後のリセッションが来るかもしれないといわれているアメリカにとって、税金の使われ方として、海外に膨大な戦費が使われているということに、むしろリアリティができてしまった。開戦当初は支持されていた武器支援が、他の予算と同じようにその多寡を論じられる存在になってしまった。どんどん武器を送った方がいい、という立場から発言しているわけではないんですが、慣れているとき特有の反応が起きていますよね。
奈倉 各国が独自の判断で「正しい」と思う国に武器を支援したら、行き着く先は世界大戦しかありません。そもそも武器を輸出すべきではないですし、もっといえば武器を製造すべきではないという根本的なところに立ち返るべきです。慣れるのではなく、時間の経過とともに考えなければいけないことは多々あります。いまだに「核が抑止力になる」と主張する人がいるとしたら「ロシアの核保有がいったいなんの抑止力になったのか」を考えなきゃいけない。核を脅しに使って侵略に至った事例の重大さを顧みるべきです。それでも「抑止力」と言いたがる人や、軍縮を「非現実的」と揶揄する人々こそが陥りやすい「非現実性」は、「自分たちの国は侵略などしないのだ」という最も安直な思い込みです。ロシア国内のプロパガンダも「我が国は善良である」という前提と、「全世界がロシアを攻撃しようとしているから軍備を拡大しなくてはいけない」という危機感を、徹底的に国民に叩き込もうとしました。
ロシアの内部については、いろいろなところに執筆してきましたが、お金の話に関していえば、ロシア政府による兵力集めも結局は金銭的に追い詰める方法に頼るようになっています。
まず、比較的一般的な方法として義勇兵の家族に一定額の支払いをする身売りのような制度があったり、ほかには、刑務所で服役している人に対して、服役期間を兵役と交換できるようにする仕組みを考案したり。若い青年を招集するための施策としては、志願して兵士になった人に、国立大学の返還不要の奨学金や、家族への年金を約束しようとする。
無償で大学に行けるかもしれないという幻想と、その子自身の命が天秤にかけられてしまうような、酷い困窮にあえいでいる人がいる。服役の例では思想犯が多くいることも重要です。政府はまず逮捕や貧困で国民を苦しめ、あたかもそこからの救いの手立てのように軍への志願を提示している。
最も重要なのは戦争を生んだ社会構造に目を凝らし、そうした社会を作らないようにすることですが、いまの報道はそこに目を向けられていない。たとえばウクライナについて、とりわけ日本のテレビの報道は、戦局の変化に特化したものが極端に多いですね。うちはテレビはありませんが、たまに見る機会があると恐ろしくなります。ロシアでもテレビはまっさきに言論規制の対象となり、最終的には政府見解の反復で見る人の思考をゾンビ化させる「ゾンビ箱」と呼ばれましたが、注意すべきなのはまさにそういうところにある。報道をゾンビ箱にしてはいけない。
逢坂 くり返し報道される戦況地図がまさに象徴なんだけど、地図と数値に換算して物事を見るようになってしまうんですよね。
今、奈倉さんが言ってくれた、ロシア内部で起きていることは、実は二〇〇三年頃にアメリカで行われていたことと全く同じです。当時、イラクへの派兵が想定よりも長引いたこともあって、アメリカでは兵士の数が足りなくなっていました。国民皆兵の国ではないから、どうするかというと、リクルーターが若者をスカウトするんですね。その時のうたい文句が、「返還不要の奨学金が受けられる」とか「軍隊のなかでも勉強はできる」、「前線に行くわけではない、後方支援だから」みたいな感じなんです。そうやって、人間をリソースとして見て、若者を兵力に変えるために、あらゆる手段を取った。その時に標的になるのはもちろん、経済的、社会的に弱い立場の人達ばかりです。
当時、恐ろしい記事を読んだことがあります。リクルーターから「前線には送らない、イラクには行かない」と言われて入隊した青年がいたんですね。しかし約束を破られ、イラクに派兵されることになってしまった。そこで彼の母親が軍隊に抗議したそうなんです。でも、「本人が拒否するというなら、軍法会議にかける」と返された。そして続けて言うには、「規則上、軍法会議の被告人は裁判中、銃を持つことができない。つまり派遣に抗命するとあなたの息子は銃を持たずにイラクに行くしかなくなるが、それでもいいですか?」と。そんなの、血の通った人間のすることじゃないじゃないですか。同じことを、今はロシアがやっているんです。
■自分の足元を見つめなおす
奈倉 そういった「共通点」こそが、私たちになにができるかにおいてポイントになってきます。『文学キョーダイ!!』の中でも、国家権力が膨れ上がっていく段階には非常に多くの共通点がある、という話をしました。たとえばロシアでも、報道が規制されたり、人権団体が弾圧されたり、といった兆候がありました。ですから、「共通点」を知ることで、気づくことができるようになる。
逢坂 全体主義国家であれ、戦争であれ、それを捉えなおしていくことで、自分自身が今属する社会の、足元を見つめなおしていかないといけないですよね。「あんな恐ろしい国になったらおしまいだ」と他人事としてとらえることは可能かもしれないけれど、足元では起こっていることは実は似ているかもしれない。そのことに気づかなくては。
少し前に、回転寿司店で醤油差しを舐めた少年がいましたね。彼の行いは確かに許されないかもしれませんが、それを血眼になって国中で総叩きにする反応は、ロシアで起こっていることと同じなんです。本の中でも触れましたが、奈倉さんが「ロシアの言論はいかに弾圧されたか」(『新潮』二〇二三年四月号)で書いていた、ポケモンGOに関してのニュースがあって。
奈倉 二〇一六年に、教会でポケモンGOをプレイする様子をYouTubeにアップロードした若者が逮捕された、という事件ですね。ただしポケモンGOの若者の場合は「言論の自由を規制する刑法はあってはならない」という確固とした信念を訴えるためにやったことなので、その点では醤油差しの件とは事情がかなり異なりますが、これに対してメディアは、「ありえない行動」「若者だからと見逃してはならない」などと、世論を煽るような報道をしました。
逢坂 このことが、本当に日本とは無縁だと思いますか? と問いたい。
奈倉 日本の場合はさらに、そうした騒動が企業側のブラックな雇用制度をごまかすことに利用されている点も重要ですが、ロシアの例をみていくと、言論や信教の自由を規制する法律がどういう風に成立するか、その成立を目くらましするためにはどんな手法がとられるかがよくわかります。
ある極端な事例が起こったときに、「許せないですよね」と一般市民に訴えかけて、「規制をしなくてはならない」という合意を取る。でもその結果成立する法律は、市民の首をも絞めるようなものになっている。そうやって、「許せない」と多くの人に思わせるような事例が、多数を操るためのロジックに使われていくんです。
逢坂 しかも、みんなと一緒に怒っていない人は、倫理的に正しくない、という印象付けがなされていくから恐ろしい。
世の中が、権力以外のものに対して、一斉に一生懸命怒っているときって、実はとても利用されやすいんですよね。それは怒りだけでなく、無関心さも同じだと思います。なにかに注目していない、という状況は、とても都合よく利用されやすい。
奈倉 本当にそうですね。でも、そういう状況の中で抵抗をしてきた人たちがいて、その人たちのことを知ることで、一種の協力ができると思います。
逢坂 協力、というと?
奈倉 最近、医療系の雑誌に、ロシアで医学部を短縮する法案が出ている、ということを書きました。ロシアの医学部は六年制なんですが、その課程を短縮して、付け焼刃でもいいから早く戦力になる、軍医を作りたいという動きがあるんです。
逢坂 ものすごく無理がありますね。
奈倉 国家が国民の人権を徹底的におろそかにすると、最終的に医者までもが人を殺す軍隊のためにあるんだという考えに行きついてしまう、ということを書きました。
その原稿について、奈良県でずっと医師をされている方からお手紙をいただきました。「自分もずっと同じことを心配していた。自衛隊のために軍医が必要だ、といつか言われるのではないかと危惧して、ちょうど先日、その危険を訴える講演をしてきた」と。つまり悪い例というのは、見る人が見れば役に立つんですよ。言論規制にしてもそうですが、「ロシアにこんな例があって、その行きつく先は侵略戦争なんだ」と示すことができる。それは「人権弾圧をする権力者を警戒する」という連帯であり、そうした知識を分かちあうことは、世界で人権や人命を擁護している人々との協力の一環なんです。
逢坂 若者は将来の兵士として、あらゆる欺瞞によって兵士にさせられ、それ以外の職業の人達も軍隊に協力させられる。これは、反復されてきた総力戦の理論ですよね。独ソ戦の最中も、戦時下の日本も、まったく同じことをしてきた。あらゆる存在は、戦争にいかに寄与するか、ということで存在意義を示すことを強いられる。
それは小説家も無関係ではありません。歴史を振り返れば嫌と言うほど見えてきますが、文学は戦争を抑止するためだけにあったのではなく、助長することもあった。ありとあらゆる人にとって、戦争は無縁であるはずがないんです。
僕も、常に戦争のことを意識して日常生活を送っているわけではありませんが、こういう事例を知ることが、自分と社会、戦争と自分の関係性を問い直すきっかけになります。総力戦理論というのは悲しい事例ではありますが、そうやって、自分の足元を問い直す作業が、今必要なのではないかと思います。
奈倉 知ることと考えることができれば、たとえば人権を制限するまずい法案が出てきたときに、気づくことができる。「これはおかしい」と判断できるのは、その人の大切な能力なんです。それだけで充分、無力ではないんです。
逢坂 本当にその通りです。近代ファシズムは、ある日、突然成立することは決してない。常にファシズムに向かう危険性が、必ずどの国にも存在します。その萌芽に気づけるかが大事なんですよね。抗議の声すらあげられなくなってから気づいても遅いんです。ロシアだって、ソ連崩壊からプーチン政権が成立する前くらいまでは、「民主的ロシア」というものに対しての期待感があったんですから。
奈倉 多様な時代・場所・言語で書かれた本を読んでいくうちに、そういうことに気づけるようになります。どうすれば人権を大切にできるのかについては、古今東西さまざまな作家が書き続けてきたのですから。
■文学教育の意義
奈倉 そういえば『文学キョーダイ!!』の中で、逢坂さんが人文系の大学教育についていいことを言っていましたよね。
逢坂 そもそも人文教育の根本は、国家から独立した、知的に自立した人間を作るという発想から始まった、という話ですね。西欧で国家による一元管理から逃れていくため、近代国家を問い直すための自主学習に大学の起源がある。各国の目指す教育の目的を見ると、その国の置かれている現状がよくわかります。
日本の歴史を辿ってみるとわかりやすいですよね。明治期に近代的な教育機関というものが成立してから終戦まで、教育の目的は「臣民の育成と国力の増大」だった。戦後にそれが終焉を迎え、学問の自由が憲法により保障され、本来の人文教育の模索がはじまったはずなのに、それが成熟する前に実学主義にとってかわられてしまったのが現在です。実学主義と同時に、そもそも知的に独立した人間を形成するのを憎むかのような、「人文主義憎し」の風潮が着々と進行していますね。
奈倉 この件については、田島正樹先生の『文学部という冒険――文脈の自由を求めて』という本をぜひ読んでいただきたいですね。この中で田島先生は、ヨーロッパの大学の始まりまで遡って、文学部は大学の心臓である、と書かれています。
逢坂 大学における文学教育、というと、奈倉さんは「文學界」で「ロシア文学の教室」という連載をしていますよね。
奈倉 主人公が大学生で、ロシア文学について授業を受けている、というタイトルそのままの小説です。もうすぐ連載が終わって、一冊の本にまとまる予定です。
逢坂 楽しみです。あの連載は、高校生のお子さんがいるご家庭に、特に強くおすすめしたいですね。大学で文学を学ぶ、ということにすごく憧れが持てる一冊になると思う。読書体験をテキストを通じて再体験するという、なかなかないことができる、本当に珍しい小説です。
奈倉 そんなに褒められると困っちゃいますね。
逢坂 公の場でもないと、互いの作品を褒めあうのって気持ち悪いじゃん(笑)。でも、本心ですからね。本当にめちゃくちゃ面白いです。
奈倉 ありがとう。公の場でなくても、普段から褒めてくれているような気がしますけれど。
逢坂 こういう本の依頼がなければ、これだけ姉と弟で話すことはなかったと思います。お互いに母港が同じ、でも異なる船という関係性はきっとこれからも続いていくでしょう。だから、ひょっとしたら、あと十年後くらいに『文学キョーダイ!! 2』が出るかもしれない。
奈倉 十年後まで生きていなくちゃいけないですね。
逢坂 それぞれ見ていくもの、聞いていくもの、出力していく言葉は、これからも全然違うと思います。でも、どこかの地点で会ったら、またお話をしましょう、と。今はそういう気持ちになっています。
奈倉 まさにそんな気持ちです。あ、うまい感じに終わりましたね。
〔本稿は二〇二三年十月八日に、芳林堂書店高田馬場店にて開催されたトークイベントを再構成したものです〕
(初出 「文學界」2023年12月号)