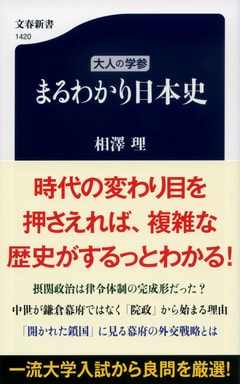Ⅰ 歴史とリーダーシップの教訓――歴史家リウィウスとポリュビオスの警告
ウクライナ戦争は、虚構の活劇ではない。日々繰り返される戦闘の真実、複雑にからみあった外交の駆け引き。これらは、現代に生きる人間たちに多くを反省させる歴史の教訓を与えてくれるのではないか。古代ローマの歴史家リウィウスが書いた『ローマ建国以来の歴史』の一節を引くのは、現代人にとっても意味深いことだ。「輝かしい歴史の記念碑に刻まれたあらゆる種類の事績を教訓として見つめることは、歴史を学ぶ上できわめて有意義かつ有益なことである。歴史をたどり、諸君と諸君の国家にとって見習うべきものがあれば、それを選ぶがよい。そして、おぞましく始まり、おぞましく終わったものがあれば、それを避けるがよい」(邦訳1、序言一〇、岩谷智訳)。
確かに、ウクライナ戦争はおぞましく始まった。それがおぞましく終わるのを避けられるかどうかは、先人たちの行為のなかに、手本となる良き先例があれば、それを学ぶ現代人の知恵にかかっている。反面教師となる悪しき例もありながら、斥けなければ現代未曾有の戦争はおぞましく終わることだろう。人びとは、今後どう振る舞うべきか、より適切に判断するには、リウィウスのように道徳的な意味での歴史の有用性を信じるのも一策であろう(リウィウス邦訳6、安井萠解説参照)。実際に、現代に生きる者たちはリウィウスの描いた人物たちの振る舞いのなかに、ウクライナ戦争の登場人物とその行動が試行錯誤を繰り返すのと同じ人間の迷いを見出せるかもしれない。
かつてローマの歴史家ポリュビオスは、「現実的歴史」を書く者なら、第一にさまざまな歴史書を読みこなし、その内容を比較対照すること、第二に出来事の現場を訪れて実見し、川や港など陸上と海上におよぶ特定の場所と距離を調べること、第三に自ら政治や軍事など国家活動に携わり、その実情を知るべきだと考えた(『歴史』3、一二巻25e、城江良和訳)。こうして、古代では、ペロポンネソス戦争でトラキア方面艦隊を指揮したトゥキジデス(ペリクレスの崇拝者)や、ローマのガリア遠征を成功させたカエサルが世界史屈指の歴史書を自ら叙述したのである。
ポリュビオスの指摘は、理屈だけなら、現代の政治や戦争にもあてはまる。やがて、忌まわしいウクライナ戦争が終わり歴史叙述の季節が訪れるなら、その最適な執筆者は、何と言ってもプーチンとゼレンスキーに違いない。この二人なら、一級の機密文書に接することができただけでなく、自らが最終的に決意を固めた戦争と抗戦の責任者として、軍と戦場の配置状況をいちばん詳しく知っているからだ。もちろん彼らの史家としての文才は、カエサルはもとより後醍醐天皇の重臣で『神皇正統記』を著した北畠親房にもはるかに及ばないであろう。しかし彼らに共通するのは、歴史の材料を探し出す歴史家というよりも、歴史の材料そのものを創り出したリーダーだという点にある。この意味では、ポリュビオスがいう「歴史を書く者」というよりも、歴史を作る者こそプーチンとゼレンスキーにあてはまる表現というべきだろう。
ロシアとウクライナの歴史家なら、この二人が書く歴史と多少なりとも共通する視角と人物描写にしばらくしばられるかもしれない。ロシア以外の歴史家であれば、プーチンを侵略と暴行の限りを尽くした悪徳の体現者と見なし、祖国侵略の悪逆に敢然と立ちあがった高邁な美徳にあふれる政治家こそゼレンスキーという図式を好む者もいるはずだ。もちろん、歴史は特定の時間と空間において一回的にしか発生せず、時空を超えてまったく同じ事件が発生することはない。まったく同じ性格と能力を持つ人物も時空を超えて生まれない。しかし、別々の歴史の局面に現れたリーダーの個性とリーダーシップの役割には似たところもある。ウクライナ戦争におけるプーチンとゼレンスキーの特性と問題点を考える上で、第二次ポエニ戦争のカンナエの会戦(前二一六)でローマ共和国軍を圧倒したカルタゴのハンニバルと、カルタゴ本国に長駆して起死回生の反撃をしかけ、ザマの戦い(前二〇二)でハンニバルを破ったローマの大スキピオがかりそめの手がかりになるのもそのためなのだ。
リウィウスによると、ハンニバルの「残虐さはおよそ非人間的で、その欺瞞ぶりはカルタゴ人的不実の水準すら超えていた。彼は真実や神聖さを軽んじ、神を恐れず、誓約をいっさい顧みず、宗教的畏怖心など持ち合わせていなかった」。そして、住民虐殺や都市略奪など「貪欲と残虐に突き進む気質」の持ち主なのであった。ローマ人史家によれば、ハンニバルのリーダーシップは常に邪悪と結びついていた。
他方、リウィウスの描く大スキピオは、ほとんど完璧なローマ市民であり、祖国救済の英雄として描写される。豪胆・武勇・規律に照らして申し分のない英雄であり、親孝行・敬神・親切・寛容にあふれた模範的な市民にほかならない。もちろん、リウィウスは大スキピオのリーダーシップをすべて模範的に評価したわけでもない。彼もハンニバル流の狡猾な作戦を辞さず、アフリカでは和平に応じるふりをして作戦に必要な情報収集を怠らなかった。要するに、当時のローマ人の許容範囲内だったとはいえ、大スキピオのアフリカ遠征への動機にはゆきすぎた野心も含まれていたというのである(安井萠解説)。
リウィウスも認めるように、ハンニバルは悪徳、大スキピオは美徳の体現者という単純な区分で歴史を解釈できるわけでもない。そして、いまのプーチンとゼレンスキーを比較しても、古代のリーダー以上に、現代の二人を悪徳と美徳という点で截然と分けるのはむずかしい。ここに文学と異なる歴史学のむずかしさがある。さしあたり言えるのは、現代のウクライナ戦争を考えるうえで、歴史とリーダーシップの教訓がいかなる対比と類推を可能にするのかということだ。
Ⅱ 「盾を構えたとき以外は無敵の男」――プーチンとクラッスス
戦争は始めるよりも終わらせる方がむずかしい。プーチン・ロシア大統領は、ウクライナ戦争を、四日で終わった二〇一四年のクリミア占領や一九六七年の六日戦争(第三次中東戦争)くらいの短期で終わると確信していたはずだ。ましてや自分が戦争犯罪の容疑で国際刑事裁判所から逮捕状を出されるとは思わなかったに違いない。実際には、戦争はすでに一年半以上も続いている。ウクライナのほぼ二〇%はロシアに占領されたままであり、八〇〇~九六五キロメートルの前線に沿ってロシア軍の塹壕がはりめぐらされている。
一九八〇年に始まったイラン・イラク戦争は、八年に及ぶ消耗戦になった。他方、一九九一年の湾岸戦争は約一カ月で終わる。二〇〇三年のイラク戦争も、ブッシュ大統領の戦争終結宣言でいえば二カ月ほどで終結した。しかしウクライナ戦争は消耗戦と長期戦の様相を示している。プーチンの基本戦略は、もはやキーウやハルキウの占領やゼレンスキー政権転覆にあるのではなく、ウクライナの国家的アイデンティティの消滅を図るほどの大胆さにこだわっているわけでもない。ウクライナの方も、二〇二三年六月に始まった反転攻勢は狙ったほどのスピードで進んでいない。
言い換えると、戦局は、二〇二三年七月下旬現在、やや静かな膠着と均衡の様相を呈しているかに思える。現状はどちらにとっても、ウィンストン・チャーチルの言葉をもじるなら、悲観主義者ならあらゆる機会の中に問題を見いだし、楽観主義者ならあらゆる問題の中に機会を見いだせる局面とでも言えようか。
消耗戦の長期化で利益を得るのはプーチンの方であろう。一年間に夥しい兵器と兵員を失ったとはいえ、ロシアにはボリシェヴィキ革命と第二次世界大戦を通して培われた人権と法の支配を無視する悪しき伝統がある。正規兵から民間軍事会社ワグネルに徴募した受刑者に至るまで、無謀な軍事作戦に人員をいくらでも犠牲をためらわず投入するプーチンの手法は、スターリンと同じである。二人は、戦争が失敗や敗戦に終わるなら、自分の政権と権力基盤が崩壊することを知っていた。二人が戦争の長期化で米国のルーズベルト大統領や中国の習近平主席に助けを求めたのは「戦争が続くこと」にとりあえず自分たちの生命がかかっていることを痛感していたからだ。まだしもスターリンの時代なら、ナチス・ドイツと「戦い続けること」でドイツを非ナチ化し非軍事化することが、ロシアだけでなく欧米にも必要だと説明することもできた。しかし、プーチンのいうウクライナの非ナチ化や非軍事化を戦争目的として受け入れる人びとは、もはやロシア人の間でも多数とはいえない。
必要なら国民や兵士の膨大な犠牲もいとわぬ覚悟は、第二次世界大戦(大祖国戦争)中に赤軍のジューコフ元帥も得意としたが、プーチンが指揮すれば人命を失うばかりで戦略的成果もまず収められない。六月のドニプロ川にあるカホフカ水力発電所のダム決壊と洪水は、その意図がウクライナ軍の東岸渡河の阻止にあったにせよ、これまでのキーウやハルキウなど大都会への無差別ミサイル攻撃、バフムト攻防戦などのように、ジュネーヴ条約違反をものともせぬ野蛮な作戦である。
これらは、スターリンやジューコフの時代であればいざしらず、現代では欧米や日本など民主主義社会から厳しく批判され、ロシアの文化性や芸術性への尊敬心や信頼度まで損なう暴挙にほかならない。「兵は凶器であり、やむをえない時にのみ用いるものだ」と自戒したのは、唐の太宗・李世民である。後漢の光武帝は「兵を一度動員するごとに頭髪が真っ白になる」と述懐したことがある。プーチンの同盟者・習近平なら、古来いたずらに兵をもてあそんだ者は全滅したという太宗の戒めを知っているはずだ。プーチンは、さながら前秦の苻堅のように、東晋を併合しようと兵を挙げたのに、水の戦いで大敗し逆に滅んでしまった先例を知らないだろう。隋の煬帝も高句麗侵略を何度も企てながら、徴兵を受けた人民の恨みを買い、匹夫に殺されてしまった。プーチンは、「あにたやすくすなわち兵を発するを得んや」という太宗の警句を聞いたこともないのだろうか(『貞観政要』守屋洋訳)。軽々しく兵を動員するなど、もってのほかである、と。
プーチンを見ると、古代イランにあった大国パルティアの征服を朝飯前と見くびって不名誉の死を遂げたローマのクラッスス(カエサルら三頭政治家の一人)を想い出す。「盾を構えたとき以外は無敵の男」の権力欲と名誉欲に引きずられたローマ人は何の利益も得られず、祖国も不運な目に遭った(プルタルコス『英雄伝』4、柳沼重剛訳)。この姿はプーチンとそのまま重なるかのようだ。蓄財術にたけた二人は、驚くほど戦下手な点でも共通している。クラッススに輪をかけて戦下手のプーチンは、“凍結された戦闘”と誰かが名付けた持久戦をひたすら維持できればよいと肚をくくった形跡がある。欧米がウクライナに武器と援助物資を送り続ける忍耐力も萎え、政治的意志力を弱まらせた結果、ロシアの戦は負けでないと国民を納得させられたなら上々吉ということなのだろう。
プーチンの戦下手は、「プリゴジンの乱」(二〇二三年六月)への対処でも露呈した。かつてのヒトラーのエス・エス(親衛隊)やイランのハメネイ最高指導者の革命防衛隊のように、正規の国防軍機構から自立した独裁者の権力維持装置こそワグネルだったはずだ。軍作戦の攻勢から防御、積極性から受動性への変化に伴い、エリート間の対立が表に露出し、大統領独裁体制の隙間にあった楔がきしみを立てて毀れる結果をもたらした。プリゴジンの乱は、長期的に見ればプーチン独裁体制を弱体化から解体へ向かわせるモメントとなり、ウクライナのゼレンスキー政権の耐久力を増す事変となった。ベラルーシの首都ミンスクに逃れたプリゴジンも、もはやプーチンとの相互依存によって権力の蜜を吸い続ける旨味を失った。民間軍事会社のワグネルと創設者のプリゴジンは、メディアやケータリング・サービスだけでなく、リビアを拠点としてサハラ以南のアフリカに傭兵網を広げていた。プリゴジンの部隊がはじめウクライナに入ったとき、ウクライナ当局はハリーファ・ハフタル大将の率いるリビア国民軍(LNA)の兵士たちがプーチンによって派遣されたと非難したものだ。実は、これは、二〇一九年以来LNAを訓練しその傭兵にもなったワグネルの投入を誤解したものであった(Biancamaria Vallortigara, “Mercenary Fighters in Libya and Ukraine,” Beehive, X-5, 2022)。
権力の眩しさと金の輝きに目のくらんだプーチンとプリゴジンとの仲たがいは、「主となりて貪れば、必ずその国を喪ぼし、臣となりて貪れば、必ずその身を亡ぼす」という『貞観政要』にある唐の太宗の言葉を連想させないだろうか。プリゴジンの乱は、プーチンの戦争を何とかしてロシア国民の戦争もしくは祖国防衛戦争の装いにして化かそうとしたプーチンの思惑をだいなしにすることになった。そのうえプリゴジンは、ウクライナ諜報機関筋に接触して、ロシア軍本隊の配置と移動を教えるかわりに、ワグネル部隊への攻撃を一時停止するように頼んだと囁かれている。米国諜報筋から漏れた情報が本当だとすれば、プリゴジンは、二三年八月二三日に死亡したが、六月以前からプーチンを裏切っていたことになる(Washington Post, 6-6-2023、電子版、以下同じ)。
Ⅲ ピュロスの勝利――ゼレンスキーはファビウスか、大スキピオか
さて、欧米の識者は、ウクライナのゼレンスキー大統領を古代アテナイ(アテネ)の民主主義守護者のペリクレスとよく比較しがちである。ロシアの専制独裁から自由欧州を守る盾になっているというのだ。しかし、ペリクレス時代のアテナイは繁栄の絶頂期にあったのに、ウクライナのGDPはロシアの約一〇分の一にすぎない。ゼレンスキーは、クリミア喪失後の国力弱体期にウクライナの衰退する国政を引き受けた。むしろ彼は、古代ローマで粘り強くカルタゴ侵略軍に抵抗したファビウスと比較すべきかもしれない。あえて比較すれば、ゼレンスキーの方がファビウスよりも戦上手に見えてくる。ハンニバル将軍との決戦を避けたファビウスと違い、ゼレンスキーは国民の士気を高め東部ドネツク州の要地バフムトの攻防戦からも逃げなかった。
ゼレンスキーは、戦争を膠着化させ無限に引き延ばすかに見える“恐露病”のバイデン大統領ら欧米首脳に不満を隠さなかった。彼によれば、戦争が長引くほど復興費も高くつき、難民の戻るべき職場・産業も少なくなる。ウクライナへの有償援助の支払額は、時間が経つにしたがい巨額の債務となるはずだが、欧米政府はもとより、メディアもこの件について議論しようとしない。ゼレンスキーは、プーチンに休戦と講和を受容させるには、大スキピオがザマの戦い(前二〇二年)でハンニバルを破ってカルタゴ国家を降伏させたような短期で目を瞠る戦果が必要だと信じているようだ。むしろ膠着した戦況下で、攻める側のプーチンは逆にファビウスの「負けない」という戦略に近づいている。ゼレンスキーと彼の将軍たちは、ウクライナが「勝てる」ことを示すザマの戦いの現代版が必要なのだ。大スキピオのザマ作戦とその戦捷こそゼレンスキーの戦略目標になるだろう。
しかし、ザマ型の勝利を得るには彼の本来嫌う戦争の長期化も覚悟せねばならず、欧米の支援疲れを増すに違いない。ここで双方の戦争目的が改めて問われる。ゼレンスキーにとり祖国防衛戦争での敵撃退はナショナリズムの神話となるが、NATOとEU加盟をロシアに認めさせる以外の政治的成果を得る可能性は低い。ゼレンスキーが本当に二〇二二年以前にロシアに取られたクリミア・東部二州(新たに占領中の州を含めれば四州)もすべて奪還する気なら、イラン・イラク戦争くらいの時間でも足りないかもしれない。とくにクリミア奪還には、時に永久築城をほどこしたロシアの堅固な防禦線を突破するだけでなく、ロシアのウクライナ占領軍全体の殲滅まで必要とする。少なくともクリミア奪還には、ロシアからドンバス(東部二州)を経てクリミアに通じるランドブリッジ(陸橋)をまず遮断する必要があり、次いで半島とロシアを結ぶケルチ海峡大橋を破壊するのが不可欠である。しかし、それはロシアが認められないレッドラインに近づくことを意味する。最悪の場合は、核兵器使用の可能性が高まるのである。
こうなると、プーチンは反核の国際世論などを意に介さず、自らの条件に固執して徹底抗戦する覚悟を決めるか、かりにも旧ソ連の時代のような核兵器の相互確証破壊の記憶をよみがえらせ妥協を図るかもしれない。しかし、ウクライナは非核保有国であり、ロシアの核使用を抑制する手立てに乏しい。もっとも、過去にもクリミア戦争や日露戦争のように戦争終結をはかったり、第一次世界大戦のブレスト・リトーフスク条約のようなドイツなどとの単独講和やアフガニスタン侵攻の不名誉な撤退などを認めたりした例もなくはない。継戦か講和か、いずれかを選ぶのは決して簡単ではない。戦争を継続しても、講和を図っても、プーチンの政治生命は弱まるだけでなく、風前のともしびとなるのは必至であり、最悪の場合は生命そのものの喪失に直面するかもしれない。
ひるがえってウクライナには、ロシア以上に徹底抗戦を継続する基礎体力はあるだろうか。ロシア国民にとっては嘘と非義で固めた戦争から得るものは何もない。ロシアはこの戦争が招く国力の衰退と国威の凋落を名誉のとばりで覆い隠す必要がある。プーチンが譲れないのは、最低でもクリミア・東部二州の維持であろう。二二年二月の侵攻以前の境界線での休戦ということだ。ウクライナがこの線を越えてロシアから全占領地を取り返そうとするなら、ロシアには妥協はありえない。ロシアはウクライナによるクリミアの奪還と再統合をレッドラインの本筋として設定するはずだ。ここで初めて戦術核の使用可能性を現実的な作戦の俎上にのせるかもしれない。しかしプーチンといえども「歴史への畏れ」を否定するのは容易ではないだろう。ゼレンスキーもプーチンも、クリミアはともかく東部二州も含めた相当に広い領域を相手に委ねて講和するのは、“悪魔のシナリオ”あるいは“呪いのシナリオ”の受け入れにほかならず、妥協しがたい政治選択であろう。
侵略されたウクライナにとって遺憾ながら、戦争が長くなれば個々の軍事状況では勝利を収めても、政軍的には「ピュロスの勝利」となるおそれがある。これは戦場での損害があまりにも大きいために、実際に貸借勘定で得るものがあまりにも少ない勝利のことだ。前三世紀のエペイロス王ピュロスは、各大国相手に勝利を収めたが、「もう一度ローマ軍と戦って、仮にこっちが勝ったとしても、そのときわれわれは全滅するだろう」と悲観論を隠さなかった(『英雄伝』3)。ハンニバルは、最高の将軍として、第一にピュロス、第二に大スキピオ、第三に自分を挙げたほどである。もっともこれには異説もあり、第一にアレクサンドロス大王、第二にピュロス、第三に自分を挙げたともいう(ゴールズワーシー『古代ローマ名将列伝』、阪本浩訳)。
結局のところ、戦争も政治の延長である限り、どこかで妥協を図らなくてはならない。最近、プリゴジンの乱が起きる前に、米国CIAのウィリアム・バーンズ長官がキーウを訪れた時、ウクライナ政府は秋までに占領地の大部分を奪還し、各種大砲とミサイル防衛システムをクリミアとの境界付近まで進出させ、東部でも領土を奪還して休戦交渉に持ち込むという野心的な政治プランを示したという(Washington Post, 30-6-2023)。しかし問題は、歴史をひもとけば、こうした反転攻勢がただちに政治的に効を奏するか否かについて、誰も楽観的に語れないところにあるのではないか。
Ⅳ 台湾とウクライナは二者択一か――安全保障関連三文書の意味
江戸時代によく読まれた『太平記秘伝理尽鈔』は、日本と外国の事件の是非を議論して、後世のいましめとすべきと主張した書物である。こうした先人の知恵に忠実に、プーチンの愚挙とウクライナの善戦から思い切った教訓を得た国の一つは日本であろう。ことに二〇二二年一二月に安全保障関連三文書(「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」)が閣議決定されたのは、日本の安全保障環境の急速な歴史的変動を無視しては考えられない。また、二〇二三年三月に戦時徴用工問題や対韓貿易制限措置による緊張を低減する努力がなされたことをはじめとして日韓首脳会談の実現、その後の日韓外交関係の好転は、ユーラシアの西部ではウクライナ戦争が起き、東部では北朝鮮の核脅威や中国による台湾有事の危険性が高まる現在、民主的価値観を基本的に共有する日米韓三カ国が安全保障の領域で共同歩調をとるべきユーラシア戦略に不可欠の条件であった。
米国の共和党議員のなかには、台湾防衛を優先するために、ウクライナ支援を削るべきだと考える政治家もいる。しかし、これは間違っているのではないか。台湾の指導者も言うように、台湾の安全は米国の強固なウクライナ支援の意志持続にかかっているからだ。米国やEUがウクライナを見捨てるなら、それは米欧が台湾の放棄もやむなしと考えているというメッセージをロシアや中国に送ることにもなりかねない。それは、とくに中国の術策にはまることを意味する。誤解すべきでないのは、米欧や日本が台湾に関心を抱くのは、「台湾の独立を守る」ためでなく、「台湾の民主主義を守る」ためである。これまで世界は、中国が香港市民の民主主義的反対派、新疆ウイグルやチベットの自治区民族の自決権の自由な意志を踏みにじるのを見て見ぬふりをしてきた。しかし台湾は、現実に中国の内政に組み込まれている地域ではない。むしろ、現実的に自由と民主主義を享受し世界の市場や気候温暖化やコロナ問題でも独自の取り組みをしてきた。この独特な「地域」が守ってきた民主主義的価値観の意義を尊重すべきである。台湾は、民主主義の堡塁でもあり、米国が事実上の同盟の継続となる「台湾関係法」を制定し、日本が日本台湾交流協会を設置して適切かつ特別な関係を維持しているのも故ないことではない。
そもそも中国が台湾侵攻に際して重視する要因は、ウクライナの未来ではなくアジアの軍事バランスなのである。台湾を優先するあまりウクライナを無視するのは、或る米国シンクタンク所長の表現を借りるなら、「燃えている家の鎮火に努めるよりも、燃えていない家の前に消防車を停めて将来の火災に備えるべきだ」と主張するようなものだ(Washington Post, 10-5-2023)。
台湾は長いこと法の支配による自由と民主主義の模範的な実践者であり、普通選挙による政権交代が平和裡に行われてきた。そして、自由と民主主義を基本的価値観として共有する「地域」として、その中国への統合は、台湾人の理解と同意による営みであるべきなのである。民主化された台湾は、半導体技術などで世界をリードしており、各種部品のグローバルサプライチェーンの重要な環である。中国も同じ利益を共有するはずだ。台湾有事が発生すれば、中国の市場価値と部品調達網も大きな損害を受ける危険性は、ロシアの教訓が示す通りである。その際、日本は最重要の地域当事国として、ウクライナ問題における欧米のように、東アジアの安全保障と人権と法の支配をめぐる行動原理と規範について世界に発信せねばならない。
二〇二三年五月のG7広島サミット首脳宣言は、ウクライナ支援の継続・強化と並んで、中国についても、東シナ海や南シナ海の状況に深刻な懸念を表明し、力や威圧によるいかなる一方的な現状変更の試みにも強く反対すると、日本の立場を明確に取り入れた。台湾海峡の平和と安定の重要性を改めて確認し、問題の平和的な解決を促した。これも、あくまでもウクライナ問題との優劣をつけていない。
中国は台湾相手の作戦を四日から六日あたりで決着がつく小戦争と見ているらしいが、台湾の政治と軍事が見せている断固とした決意、日米という信頼できる民主主義国家の柔軟な姿勢と対応性、台湾自らの軍民両面における半導体技術の独創的な創意工夫を無視できない。ウクライナの教訓を踏まえた米国の台湾への有償軍事援助二〇〇億ドル(未処理)の実施意欲なども無視すべきでない。また、中国の呉江浩新駐日大使は、最初の記者会見で、日中関係が「重大な岐路に立っている」と主張したのはともかく、「台湾有事は日本有事」との認識を「中国の内政問題を日本の安全保障と結びつけることだ」と、日本を批判したのは問題ではないか。大使は「日本の民衆が火の中に連れ込まれることになる」と牽制したが、日本の世論から強い反発を受けたのは当然であろう(『読売新聞』四月二九日付朝刊)。
日本政府は、「国家安全保障戦略」の核はあくまでも外交であると説明している。台湾有事は中国の内政だけにとどまらず、ウクライナ戦争のように周辺にも大きな衝撃を与える戦争となる。これこそ中国の成長と繁栄を逆戻りさせるピュロスの勝利にしかならないことを歴史が証明することになろう。
(ウクライナ戦争:読売新聞「地球を読む」二〇二三年三月二六日付を基に書き下ろし)
「序章 ウクライナ戦争と台湾有事――歴史に学ぶリーダーシップと国家の運命」より