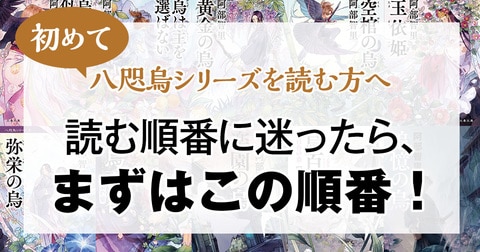NHKアニメ『烏は主を選ばない』の深層に迫る、八咫烏外伝「すみのさくら」を全文期間限定無料公開!(7/1~7/31まで)
ジャンル : #エンタメ・ミステリ

現在毎週土曜日23:45~NHK総合で放送中のアニメ『烏は主を選ばない』は、第13話で原作『烏に単は似合わない』と『烏は主を選ばない』のクライマックスを迎えました。そこで明かされた浜木綿の過去を描いた作品が、阿部智里さんの原作「八咫烏シリーズ」の外伝「すみのさくら」(『烏百花 蛍の章』所収)です。
「八咫烏シリーズ」外伝には、本編に登場する多彩な八咫烏たちひとりひとりを照射した、魅力的な短編がずらりと並んでいます。作品をさらに奥深く味わっていただくために、本外伝「すみのさくら」の全文を特別公開! 7月1日から7月31日までに期限限定になりますので、ぜひこの機会にどうぞお愉しみください。
八咫烏シリーズ 外伝
「すみのさくら」
阿部智里
「参りましたよ」
女房の言葉に撫子が顔を上げると、さっと御簾が巻き上げられた。
その向こうには、ゆっくりと透廊をゆく、女の一団がある。
行列の中心を歩むのは、撫子の義理の姉である。
一歩一歩を歩むごとに、宝冠から垂れる翡翠が、玲瓏な音を奏でている。
彼女の肌はただやたらに白いのではなく、外界渡来の象牙のような、しっとりと濡れた質感をしていた。鮮やかな黒髪が垂れている下にあるのは、これ以上ないほどに見事な女房装束だ。
菖蒲を中心に四季の花が縫い取られた深い瑠璃色の唐衣の下は、きっぱりと潔い裏山吹である。純白から先へゆくにしたがって濃い藍色に変化する裳、その引腰の紅はなまめかしく、腕には、やわらかに透けた領巾をかけている。
彼女は今日、日嗣の御子――若宮殿下の后候補として、桜花宮へと登殿する。
姉は登殿に際し、浜木綿の君の仮名を与えられた。血筋では撫子の従姉にあたる女であり、実父は、この南家の先代の当主であった。だが、金烏宗家に対し看過し得ない過ちを犯したとかで、ついには妻もろとも秘密裏に処刑されたと聞く。
その、唯一の忘れ形見が浜木綿だ。
十年ほど前、南家出身の皇后が産み落とした宗家長子の長束は、日嗣の御子の座を弟の若宮へと譲り渡している。だが南家としては、何らかの手段で、若宮が即位する前に、その座を兄宮へとお返し願おうと考えているのだ。
撫子の父達は、出家した兄宮を還俗させ、実の娘である撫子を后にする心積もりなのである。
当然、いずれ失脚する若宮の妻の候補に撫子を出すつもりなど毛頭なく、だが、誰も出さないわけにはいかないので、一時しのぎの人身御供として選ばれたのが浜木綿であった。
父母をなくしてから、彼女は南家を放逐されている。それから、身分が回復するまでの数年間を、下賤の者――山烏に混じって、暮らしていたのだ。
聞くところによると、山烏というものは、平気で鳥形に転身するのだという。
生まれてこの方、撫子が目にしたことのある鳥形の八咫烏など、飛車を牽く大烏だけだ。馬にさせられるなんて、よほどの重罪人か、八咫烏としての尊厳を自ら放棄した者であると決まっている。それなのに、人前でも平然と転身して見せる山烏の神経は、高貴な中央貴族である宮烏からすれば、厚顔無恥もいいところであった。
もし自分が浜木綿であったら到底耐えられないだろうと思ったが、彼女は耐えがたきを耐え、身分が回復される時まで生き抜いたのだ。
とてもすごいことだと思うし、撫子はある意味で、彼女のことを尊敬している。
だからこそ、いつも所在なげで、父や女房に言われるがまま、唯々諾々と従っているその姿には、どうにも哀れを催すものがあった。
今も、渡り廊下を行く立ち姿はすらりとしてまるで撓んだところがないのに、面はしっかりと伏せられている。
彼女は愚鈍ではなかったから、親の仕出かしたことを恥ずかしく思っているのだろうし、もう二度と、山烏に戻るまいと必死なのだ。だというのに、これから切り捨てられるばかりの若宮のもとへ送られる心中は、察するに余りあるものがあった。
「浜木綿」
思わず、声を掛けていた。
しずしずと行く一団は足を止め、浜木綿が小さくこちらに顔を向ける。
「撫子さま」
わたくしに何用でございましょう、と丁寧に問う。
姫様、とうろたえる女房を押し留めて透廊へと出れば、さっと女達が道を空け、浜木綿と真正面から相対することになった。
こんなに近付いても、浜木綿は頑なに、目を合わせようとはしなかった。
「この度の登殿、まことにめでたきこと。わたくしからもお祝い申し上げます」
半ば、励ますような気持ちで声を掛けると、浜木綿はハッと顔を上げた。
「卑屈にならず、つよい心持ちでお行きになってください。いかなることがあっても、南家の宮烏としての誇りをお忘れなきよう」
どうかつつがなくお過ごしあれと、そう言った撫子と浜木綿の視線が、しっかりと交わった。
まじまじと見つめあう。
姉の黒い瞳が、青い光を帯びるほどに澄んだ色をしていることを、撫子はこの時、初めて知った。
そしてふと――浜木綿の目がぐにゃりと、三日月を描いた。
それは、間違ってもにこりなどという健全な笑みではなかった。
彼女は、まるで悪い遊びを覚えた子どものように、にやり、と笑ったのだ。
「――お心遣い、痛み入る」
そう返した声は、それまでにはない張りと若々しさに満ち溢れ、どう聞いても『不敵』としか言いようのない、強烈なえぐみを含んでいた。
「んじゃ、お前も達者でな」
ひらりと片手を上げると、宮烏とは思えない気軽さで、浜木綿は撫子の脇を通り過ぎようとする。
撫子だけでなく、このやり取りを聞いていた女達は、いずれもあっけに取られていた。
「お待ち!」
一番に我に返ったのは、浜木綿付きの女房、苧麻だ。
「撫子さまに向かい、何という口の利きようだ。さんざん教え込んだというに、貴族の礼をもう忘れたか」
それとも何か、と問う苧麻の口調はひどく苦々しい。
「まさか、若宮の妻になりさえすれば、撫子さまより上の立場になれるとでも思っているのではあるまいな……?」
嬲るような言いように、浜木綿はあからさまに眉をひそめた。
「とんでもない。最初から、撫子とアタシの関係に、上下があるなどとは思っちゃいないよ」
ならば、と言いかけた苧麻を、しかし浜木綿は鋭い眼光で睨み据える。
「だが、お前とアタシの間には、上下の礼が必要だ」
一体、誰のおかげで南家の登殿が叶ったと思っている。これからは、自分の立場をわきまえることだね、と。
嘲笑うように言われ、苧麻は絶句した。
それを鼻で笑うと、浜木綿は立ち竦む一行に背を向け、颯爽と歩み始めた。
――あの豹変のしようは、何だ。
撫子は呆然としていた。
せめて、自分は優しくしてあげようと思っただけなのに、まさか、あんな態度を取られるとは思わなかった。登殿することで調子に乗ったのだとしても、この突然の変化は明らかに異様である。
こちらを一顧だにせずに、ぴんと姿勢を伸ばして歩む、美しい女の背中。
浜木綿は一体、何を考えているのだろう?
* * *
墨子の一番古い記憶には、琵琶の音がしている。
にこにこと笑いながら、楽器を奏でる母の姿。そして、母と同じように笑いながら、墨子を抱っこして琵琶の音を聞く、父の姿。
涼しい四阿の外には光があふれ、花々がまぶしく輝いていた。
父も母もとても嬉しそうで、墨子自身、とてもとても楽しかった。だからこそ、最も幸せな記憶として、いつまでもその光景だけは心に焼き付いているのだ。
そこは、父が母のために造らせた庭園だった。
当主の奥方が美しい花を好むと知った商人たちが、競って珍しい花を届けてくれたので、華音亭と名付けられたそこには、いつも何かしらの季節の花が咲き乱れていた。
枝がしなるほどにたくさんの花を付けた、薄紅の桃。
夜明けの空のような薄紫をした、八重咲きの朝顔。
墨子の顔より大きく、まん丸な金色の菊。
とろりと濃厚な、黒く見えるほどに濃い赤の椿。
墨子は、言葉を覚えるのと並行して、花の名前を覚えて育ったのだ。
暗い部屋に閉じこもり、雛遊びをするよりも、母に手を引かれながら、ひとつひとつの花の名前を教えてもらうほうが、はるかに楽しかった。
幼かった娘の目から見ても、父は母にほれ込んでいたように思う。
自慢げに墨子に語って聞かせることには、父には決まった許婚がいたのに、それを蹴って母を正室に迎えたのだという。挙句、山内を代表する四大貴族の当主ともあろう人が、男児がないまま、一人娘の墨子を溺愛していたのだった。
跡継ぎがいないことで、他から何も言われなかったはずはないのだが、父は、母のほかに側室を持とうとはしなかった。
墨子にも弟が必要だわ、ときつい調子で言った母に対し、父が鷹揚に応えた言葉を覚えている。
「なあに。焦らなくても、そのうち出来るさ」
側室は持たないからお前が焦る必要はない。私が百歳まで当主として頑張ればいいだけのことだ、と笑う。
「それに、我々にはこの子がいる」
間違いなく、お前に似て美人になるぞ、と墨子の頭を撫でる父は満足そうだった。
「墨子はこんなに可愛いのだから、長束彦殿下だって大切にしてくださるに違いない。いずれ、私の娘が金烏の妻となり、母となるのだ!」
そう言って墨子を抱き上げ、くるくると回した。
墨子はきゃあきゃあと声を上げながら大喜びで、それに困ったような顔をしつつも、母だってまんざらではない様子であった。
墨子は、自分は日嗣の御子長束彦の妻になるのだと思っていた。
当時から、弟宮に譲位の可能性は囁かれていたはずなのだが、父はそれを全く気にしていなかった。いずれ長束彦は山内の頂点に立つし、お前は彼の正室として次代の金烏を産むのだ、と言い続けていたのだ。
「心配するな。父が、すぐになんとかしてあげるさ」
弟宮なんか、その気になればどうとでもなる、と。
満ち足りた幸せな日々の中で、唯一、不穏な影を持って語られたのが、弟宮の存在だった。墨子自身、幼心に「はやくいなくなってしまえばいいのに」と思っていたくらいだ。
大人達の難しい事情を、理解していたわけではない。
だが、父も母も、父母に侍る周囲の者達も、弟宮が邪魔な存在であることは誰に憚るでもなく口にしていたから、ただ弟宮は『悪いもの』なのだと、信じて疑っていなかったのだ。
忘れもしない。
その女が華音亭にやって来たのは、新緑のみずみずしい、とある晴れた朝のことだった。
梔子の花の香りが漂い、滑らかな泥の上に横たわる澄んだ水面に、玉のようなしずくを乗せた蓮の葉が青々と広がっていた。
ちょうどその時、墨子の周囲には人がいなかった。
侍女が、水差しを取りに戻ったのだったか。残された墨子はひとり、四阿で蓮池を泳ぐ青蛙を眺めていたのだった。
「あんたが、夕虹の娘だね」
静かな声と共に、蚊遣りの香の煙にまぎれるようにして、ひとりの尼が現れた。
頭に頭巾を巻き、暗い色をした衣を纏った女だ。
当時五つだった墨子は、その尼を老婆だと思った。
墨子の身の回りの世話をする女達は、みんな若くて優しかったが、そいつは眉間に深い皺を刻み、何やら厳しい面差しをしていて、なんとも気味が悪かったのだ。
「あなた、だあれ」
「アタシは青嵐だ。昔、あんたの母さんを育てた女のうちの一人だよ」
「お母さまの羽母なの?」
それにしては、随分とぶっきらぼうで、礼儀のなっていない女だと思った。
「あんたの母さんが呼んでいる。おいで」
言うが早いか、拒否する間もなく、女は墨子の手を取って歩き始めた。
履物を履く時間すら惜しむような性急さに、墨子は面食らった。
しかも、だんだんと早足となり、女は邸から離れる方向に向かっていくのだ。
「ねえ、どこへ行くの。母屋はあちらよ」
青嵐は無言だった。
墨子はどんどん恐ろしくなっていった。
何かおかしい。もしやこの女は、ひとさらいではないだろうか。
「だれか」
助けを呼ぼうとした瞬間、女は墨子の口を手で覆った。
「大人しくおし! もう、時間がないんだから」
いよいよ恐慌状態になりかけた墨子の耳に、突如、甲高い悲鳴が届いた。
庭の向こう――母のいる、邸の方からだ。
「こいつを早く!」
青嵐が怒鳴った時、綺麗に整えられた躑躅の垣から、見慣れない男達が飛び出してきた。
墨子は竦みあがった。
お母さま、お父さま! 誰か助けて!
口を布でふさがれ、麻の袋へと放り込まれる。
暑くて苦しくて、そして何より恐ろしくて、それきり何も分からなくなってしまった。
次に気が付いた時、墨子は今までに見たことのないような、粗末な小屋に閉じ込められていた。
格子戸からは金色の光が漏れ、すでに黄昏時となっていることを知った。
床には藁が敷かれ、農具と思しき壊れた道具が壁に立てかけられている。
絹の細長は、気を失っているうちに、信じられないくらいごわごわした粗末な着物に替えられてしまっていた。藁の上で恐る恐る立ち上がった墨子は、そこで、長く整えられていた髪が、ばっさり切られていることに気付いて仰天した。
母親ゆずりの、くせひとつない、自慢の黒髪だったのに!
「目が覚めたかい」
にぶく軋む引き戸を開けて、青嵐が小屋に入ってきた。
墨子は反射的に叫んでいた。
「近付くな、この、ぶれいもの!」
咄嗟に手に触れていたものを投げつけたが、軽い藁は、女に遠く届かないまま、ひらひらと舞い落ちていった。
「わたしを誰だと思っているの。こんなことをして、お父さまが知ったらすぐに――」
「黙りな!」
その瞬間、頬に鋭い衝撃が走った。
地面に倒れ、口の中に血の味がして、ようやく、顔を叩かれたのだと知った。
「お前はもう、南家のお姫様じゃないんだ。これから先、いっぺんだって家のことを口にしてみな。こんなもんじゃ済まさないよ」
こんなに怖い顔を向けられたことも、ぶたれたことも、大きな声で怒鳴られたことも、生まれて初めての経験だった。
――こいつは、その気になれば、わたしをどうにでも出来るのだ。
それに気付いて、ようやく、背筋に恐れが這い登ってきた。
震えながら黙りこくった墨子に安心したのか、女は声をわずかにやわらげた。
「ちゃんと言うことを聞くならば、叩いたりなんかしない。いいね?」
無言のまま、必死で頷く。
もう、痛いのは嫌だった。
それからしばらくの間、墨子は山烏の男児の格好をさせられたまま、あちこちを転々と移動した。
大体は、最初に閉じ込められたような小屋で寝泊りし、移動は夜に行われた。
粗末な衣も、不味い食事も、汗の匂いのする男に抱えられての移動も、全てが嫌で嫌で仕方なかったが、誰も、墨子のことを気遣ってはくれなかった。
青嵐は、墨子を叩いた日から姿を見せず、男達は、必要最低限しか話そうとしない。何が起こっているのかも、これからどうなるのかも全く分からなかった。
心細くて、毎晩のように泣きながら、それでも、きっと父が助けに来てくれるという、それだけを希望に墨子は耐えた。
再び青嵐が姿を現したのは、南家から攫われて、十日ほど経った後のことだった。
「お前が住むところが決まったよ」
開口一番に言われた言葉に、墨子は耳を疑った。
「わたしの、住むところ……?」
「ああ、そうだ」
わけのわからないまま連れて行かれたのは、墨子も見覚えのある寺院であった。
忘れるわけがない。そこは、南本家の菩提寺である、慶勝院であった。
拐かされて連れて来られるにしては、あまりに意外な場所だった。青嵐と墨子を出迎えた神官達も見知った顔で、しかし、今はみんな一様に、緊張した面持ちをしていた。
もしや、寺院の中に父母がいるのではないかと期待したが、柱の陰からこちらを覗いているのは、粗末な身なりをした子どもばかりである。
「今日からお前は、ここで世話になるんだ」
ちゃんと挨拶しな、と促されて、困惑した。
「……どうして?」
堪らなくなって、青嵐を見上げる。
「どうして、ここに住まなきゃいけないの。わたし、おうちに帰りたい」
また叩かれるかと思ったが、青嵐はじっとこちらを見つめるだけで、何も言わなかった。
以前、父母と墨子をにこやかに出迎えてくれた神官達も、視線をやると、無言のまま顔を逸らしてしまう。
沈黙に耐え切れず、墨子は言い募った。
「か、帰ったら駄目って言うのなら、いいよ。わたし、我慢できる。きっといい子にできるから、だからお願い。せめて、お父さまとお母さまに会わせて……」
小さく呟くと同時に、とうとう涙がこぼれる。
墨子を険しい顔で見下ろしていた青嵐の頬が、ひくりと震えた。
「……そんなに言うのなら、会わせてやろう」
おいで、と言った青嵐は、墨子の手をしっかりと握りしめたまま、歩きだした。
迷いの無い足取りで、墓所の中を進んでいく。
周囲には夏草が生い茂っていたが、先祖の墓は綺麗に掃き清められ、きちんと花が供えられていた。立派な百合の花に囲まれた墓所は、一見しただけでよく人の手が入っていると分かる。
だが、青嵐に手を引かれてたどり着いた所は、他と明らかに様子が異なっていた。
墓石があるのは同じだ。
それなのに、何の花も供えられていない。
土の匂いが濃くしていて、まだ、出来たばかりの墓であると分かった。
灰色の墓石と、その周囲の土盛だけが黒々としていて、草さえも生えることを避けているかのような、濃厚な死の気配が取り巻いている。
――まるで、そこだけ色を失ったかのような墓が二基。
その前で、青嵐は足を止めた。
「さあ、挨拶するんだ」
「え?」
青嵐の声に、墨子は弾かれたように顔を上げた。
「お前の、お父さんとお母さんだ」
そんな、と耐え切れずに悲鳴を上げた。
「死んだんだよ――流行り病で」
「ごびょうき? そんなの嘘よ!」
「嘘じゃない」
最後に会った時、母は元気に笑っていた。昼に、葛餅を一緒に食べようと約束していたのだ。いつも通りの朝で、何も不穏なことなんてなかった。
「嘘、嘘。青嵐は、嘘ばっかり言う!」
青嵐の嘘つき、と叫ばずにはいられなかった。
「アタシが嘘つきだったとしても、お前の両親が死んだのは、紛れも無い事実だ」
青嵐は墨子の癇癪に取り合わず、「現実を受け入れるんだね」と静かに言い切った。
「お前には、諦めるほかに選択肢はないんだ。分かったのなら、寺に戻るよ」
再び引っ張ろうとする手を強く振り払う。墨子が睨み上げると、青嵐は嘆息した。
「ああ、もう、分かった。気が済むまで、勝手にしな」
そう言い捨てて、伽藍の方へと歩いていく。
青嵐の背中から目を外し、墨子はひとり、二基の墓に向かい合った。
よろよろと墓石に歩み寄り、そこに、父母の名前があることに気付いてしまえば、もう、我慢は出来なかった。
悲鳴を上げ、泣きじゃくる墨子に、誰も声をかけてくれることはなかった。
何もかも、おかしいことが多過ぎた。
父母が突然病死したことも、自分が屋敷から連れ出されたことも、納得出来るはずがない。まだ、南家の屋敷で両親が生きているように思えてならず、何度か寺を抜け出そうとしたが、その度に青嵐に連れ戻され、厳しく折檻された。
結局、墨子は青嵐の言いなりになるしかなく、あの女は何かを隠している、という疑念だけが、ひたすら大きくなっていった。
しぶしぶ生活を共にすることになった子ども達は、皆、孤児であった。
身寄りのない少年少女は、毎日、神官達にまじって勤行し、墓の手入れをすることによって、この寺で最低限の衣食住を得ているのだと教えられた。
墨子はそんな孤児の中のひとりとして、墨丸という名を与えられたのだった。
戸籍上の性は、男とされた。
周囲には当然女だと気付かれていただろうが、神官達に何か言い含められでもしていたのか、子ども達が必要以上に墨子に関わってくることはなかった。
それが、墨子にはありがたかった。山烏の子ども達はみな一様に日焼けしていて、目はらんらんと輝き、それだけで別の生き物のようで、どうしても慣れなかったのだ。
毎朝、彼らに混じって講堂で山神にむかって手を合わせ、一通りの祝詞を聞いてから、寺中の掃除を行う。道具一式を持って墓石を磨く者、供える花を山に採りに行く者、食事の支度をする者、やることはさまざまだ。
ある時、墨子は花摘みに参加させられた。
ひときわ大きな山百合を見つけ、それを両親の墓に持って行こうとした時、一緒に花を摘んでいた子達から止められてしまった。
「墨丸。あそこに花を置いては駄目だよ」
声をかけて来たのは、子ども達の中でも年長の少女だった。
「どうして?」
「あのお墓は、前の南家当主さまのお墓だもん」
「……前の当主さまのお墓だったら、どうしてお花を供えてはいけないの」
あんた知らないの、と知ったかぶった少女達が次々に嘴を挟んできた。
「教えてあげようか」
「本当はね、前の当主さまが、病気だったなんて嘘なんだ」
おおげさに周囲を見回して、少女の一人が墨子に耳打ちする。
「殺されちゃったの」
墨子は息を吞んだ。
「――誰に?」
「それは言えない」
「怒られちゃうもんね」
さんざめく少女達に、墨子は両手を合わせた。
「お願い。誰にも言わないから」
「ほんとう?」
「ないしょだよ」
とおるさま、と風のような囁きが耳をくすぐる。
とおる?
「それって――」
「今の、当主さまだよ」
少女達が、顔を見合わせる。
「前の当主さまの弟だったのに、お兄ちゃんを殺しちゃったんだって」
「おっかないよねえ」
「とおるさまにばれたら、この寺もハンイを持っていると思われるから」
だから、あのお墓にお花は供えちゃいけないの、と。
その後も少女達は何かを言っていたようだったが、もう、墨子の耳には何一つ届かなかった。
とおる――融。
その名前は、知っている。何度も会ったことがある。
墨子の、叔父だ。
胸が、早鐘を打っている。
ぱちぱちと音を立てて、分からなかったことが一気に見えていくような気がした。
南家の当主は、立派な立場だ。
融は、父のことがうらやましかったに違いない。
だから、殺してしまったのだ。自分が南家当主になるために。
「おのれ……」
そうと分かってしまえば、煮えたぎるような怒りが湧いてきた。
両親を殺した者が、今ものうのうとこの世に生きて、しかも、南家当主の座についているなんて、絶対に許されない。
――わたしが、仇をとってやる。
墨子が、叔父のいる南本家へと向かったのは、湿気に、月のにじむ夜だった。
皆が寝静まるのを待って、厨から包丁と食料を盗み出し、寺を抜け出したのだ。
飛車を使えばすぐの道行きだったが、今の墨子には望むべくもない。南家本邸まで徒歩で行くことを考えると、どれだけ時間がかかるかは分からない。だが、宮烏の誇りにかけて、鳥形に転身するなどという選択肢はなかった。
幸いにして、この寺から町までは参道が伸びている。町に出て一番大きい道を辿りさえすれば、迷うことなく南本家まで行けるはずだった。
虫除けにと教わった、香りの強い草を肌にこすりつけたが、何匹もの蚊や蚋がぷぅん、と耳障りな羽音を立てて、墨子の体にまとわりつく。
羽音だけでも心底不快だったのに、すぐにあちこちが痒くなり始めた。
空が白む頃には町へと着き、井戸を借りて手足を洗ったが、虫に食われた部分はぷつりと血が出ており、真っ赤に腫れ上がっていた。それだけでなく、こっそりくすねた草鞋がこすれて、踵や足の指の間の皮も擦り切れて血が出ていた。
水場を見つける度に休憩をとろうとしても、宿や店先などでは、みすぼらしい墨子が来るのを嫌って追い払われてしまう。少し前であれば、声をかけただけで恐縮しきっていたような連中に邪険にされたかと思えば屈辱だったが、いつ青嵐が追いかけて来るか分からない今、そんなことを気にしている余裕はない。
ちょうど同じ方向へ向かう商人の馬車の荷台に乗せてもらえ、そこでようやく少し眠ることが出来た。しかしふと目を覚ますと、「役所に届けた方がいいんじゃないか」と相談している声に気が付き、慌てて馬車から飛び出す羽目になった。
歩いて歩いて、ようやく南家本邸の付近に着いたのは、日が暮れてからのことであった。
意外にも、やっとのことで邸が見えても、喜びは湧いてこなかった。ただ、懐にしまった包丁の重みを感じ、頭の中を血が駆け巡る音が聞こえるのみである。
築地塀の周囲には、見張りの兵がいる。
兵に気付かれないように、そっと裏手へと回ると、塀に面した道の一角が、白くなっていた。
くすんだところのない、上品な白い花が、黒い道の上に無数に散らばっている。
沙羅の花が落ちているのだ。
母が好んでいた花だ。華音亭に植えられていたことを思い出し、急いで近くに向かう。
邸の外れである。
父が新たに造らせた華音亭の周りは、他と塀のつくりが違う。竹を交差させて編んだそこならば、うまいことよじ登れそうだ。
どきどきしながら、兵が通り過ぎる瞬間を待ち、音を立てないように飛び出した。
築垣を登る際に手を少し切ったが、構ってはいられない。沙羅の木の枝に乗り移り、なめらかな樹皮を伝って地面に下りて、ほっと息をつくことが出来た。
勝手知ったる我が家である。一度中に入りさえすれば、こちらのものだ。
当主のいる寝殿に向かおうと周囲を見回し、そこで、墨子は息を吞んだ。
淡い月明かりの中で浮かび上がったのは、濃く生い茂った夏草だ。
――たった二月ばかりの間に、いつだって手入れが行き届いて美しかった母の庭園は、見る影もなく荒れ果ててしまっていた。
愕然とする墨子のことを嘲笑うように、あまりに多すぎてうるさいような虫の声が、湿った夜の中に響いている。
おそるおそる歩けば、ちくちくとした雑草が体にまとわりつき、ねばるような細い毛が衣にべったりとつく。花の香りよりも、踏み潰した草の青い匂いが鼻を刺激した。
ひどい、と思った。
更地にするでもなく、あえて荒れたままにされていることが、まるで見せしめのようだった。
草を泳ぐように掻き分け、母と墨子のために新築された棟へとたどり着くと、そこは閉め切られていた。中には入れそうもなかったので、諦めて高欄の下に入る。
この上の廊下は、毎日行き来したのだ。迷うはずもなく、寝殿に面した中庭へと向かった。
急く心を抑えるように、台盤所の下をじわじわと進み、長い時間をかけて、やっと寝殿へとたどり着いた。
はあ、と息を吐き、懐にしまっていた包丁を取り出す。
これでいい。ここで様子をうかがい、叔父の姿を確認したら、一気に刺してやるのだ。
高欄の下からわずかに顔を出し、中を覗こうとした、その時だった。
「それで、私を殺すつもりなのか?」
飛び上がった。
慌てて見上げれば、庇を隔てた向こう、蔀の上からこちらを覗き込むようにして、一人の男がそこに立っていた。
何十回、何百回も思い描いていたその顔が、薄闇の中に浮かび上がっている。
――憎き叔父、その人だった。
「お父さまと、お母さまのかたき!」
叫び、包丁を振りかざしてから、しまったと思った。
思いのほか、高欄が高かったのだ。
渾身の力をこめて飛び上がるも、全く届かない。
慌てて左右を見たが、近くに階はない。仕方なく、包丁を庇に置いてから、高欄に手をかけてよじ登ろうとしていると、叔父は悠々とこちらに近付き、四苦八苦している墨子の武器を取り上げてしまった。
「ああっ!」
思わず片手を離した瞬間、ずるずると、高欄からずり落ちてしまう。
とすん、と軽い音を立ててお尻が地面について呆然としていると、真上から叔父に見下ろされた。
「……暗殺者として、あまりにお粗末ではないのか?」
心底から呆れ返ったように言われて、墨子はキッと睨み上げる。
「黙れ、卑怯者!」
「卑怯者?」
「お前が、当主になりたかったから、お父さまとお母さまを殺したんだろう」
許さない、と叫ぶと、叔父は軽く鼻を鳴らした。
「それは違う。私は別に、当主になどなりたくはなかった」
全く思いもしなかった言葉に、ぽかんとした。
叔父は平然と、墨子の視線から逃げることなく、こちらを見返している。
――嘘を言っているようには見えなかった。
「では、どうして……」
「どうして、お前の父と母が死んだのか?」
あれは、あの二人の自業自得だ、と融は答える。
「お前の父と母が死んだのは、若宮と、その母を殺そうとした報いを受けたからだ」
墨子は声をなくした。
「私はむしろ、巻き添えになりそうだったお前を助けてやった恩人だぞ。感謝されこそすれ、恨まれる筋合いはない」
言われている意味が分からない。
ぼんやりとする墨子に溜息をつき、融は不意に声を張った。
「逆恨みされてはかなわん。よくよく言って聞かせろ」
その言葉は、墨子に投げかけられたものではなかった。
叔父の声を受けて、その背後からもうひとり、墨子の見知った顔が現れた。
「この度は、ご迷惑をおかけして申し訳ございません」
深々と頭を下げた青嵐に、構わん、と融は静かに言い返したのだった。
「怪我をしているようだ。手当てして、さっさと連れて帰るがいい」
青嵐は、墨子が寺を抜け出したことを咎めなかった。
邸の一室で傷の手当てをし、刈り取った蘆薈の汁を、蚋に食われた手足に塗りこみながら、ただ静かに語って聞かせた。
「お前の二親は、お前を長束彦殿下の妻にしたいがために、焦り過ぎたのさ」
父は、誰にはばかることなく宗家に不敬の念を顕にし、南家の当主としてあるまじきことに、強引な手段での若宮廃嫡を目論んでいた。そして母は、後宮の貴人達を軽んじ、挙句の果てに、弟宮の母親を殺害しようとしたのだという。
「お前の母が毒となる香を贈り、その結果、弟宮の母は死んだ。これが公になれば、南家そのものの存続すら危うくなる。だから、南家を守るため、秘密裏に粛清されたんだ。流行り病ということで名誉が守られただけ、まだマシと思うべきかね」
お前も生き残ったことだしな、と淡々と青嵐は言う。
「せっかく助かった命だ。せいぜい、長生き出来るよう、賢くなることだね」
正直なところ、青嵐の言葉の意味を、墨子は正確に理解出来たわけではなかった。
だが、両親が、墨子自身が「いなくなればいいのに」と思っていた、弟宮を本当に害そうとして、その罰として殺されたのだということは伝わった。
――なあに、心配はいらないさ。弟宮なんか、その気になればどうとでもなる。
そう言ったのは、父だ。
――あの女が後宮を制した気になっているのも、今だけのことよ。
朗らかに言って、こちらに笑いかけたのは、母だった。
――墨子が、入内さえすれば――
ああ!
気付きたくなどなかった。
何気なく言っていた言葉の意味が、こうなってみて、初めて分かるなんて。
「本当は、お父さまと、お母さまが、『悪い奴』だったの?」
震える声で尋ねると、一瞬だけ、青嵐の手が止まった。
「……さあね」
アタシには、難しいことは何も分からないよ、と、そう言い添えたのが、青嵐の優しさだったのか、どうか。
わたしのために、お父さまも、お母さまも悪いことをした。
わたしのせいだ――全部、わたしの。
青嵐と共に慶勝院に戻って以来、墨子は勤行にも、寺の手伝いにも参加しなくなった。
ただ、父母の墓の傍で、ぼんやりと膝を抱える日々だ。
墓石だけが立派で、墨を流したように彩りがない、灰色の墓。
病で死んだということにはなっているが、神官達は、どういった経緯で彼らが死んだかを知っている。だから、墓守人のくせに、父母の墓には誰も手を合わせないのだ。
墨子が手ずから摘み、供えた花も、いつの間にか除けられてしまう。
殺風景な墓に、ただ、墨子だけが通い続けた。
そんな、ある日のことだった。
すっかり木々の葉が落ち、吹きつける風が冷たくなった頃、慶勝院がにわかに騒がしくなった。
上皇がやって来たのだ。
上皇の母は南家の出身であり、生前に親しかった親族の、墓参りに来るのだという。
それだけならば、別にどうでも良かった。墨子が震え上がったのは、その墓参りに、兄宮と弟宮もやって来ると聞いたからだ。
弟宮は、もともと上皇のもとで養育されるはずであった。だが、体が弱かったせいで母君が手元から離すのを嫌がり、例外的に女屋敷で育てられたのだった。その母君が亡くなったことを受けて、ようやく慣例通り、上皇のもとに引き取られたと聞く。
一目貴人を見ようと、鈴なりになった子ども達の後ろから、墨子はそっと一行の様子を窺った。
上皇と思しき男は後ろ姿しか分からなかったが、二人連れ立った、十歳くらいの賢そうな面持ちの兄宮と、とびきり綺麗な顔をした、墨子と同年代くらいの弟宮は見ることが出来た。
兄宮・長束彦のことは当然知っているが、自分が嫁入りするはずだった相手だということが、今となっては信じられない。きっちりと豪華な紫の衣をまとうその姿は、もう別の世界の住人に見えた。
一方、弟宮のほうは、いかにも宮烏といった感じの長束彦とは、いささか異なった雰囲気をしている。
兄と同様、立派な衣を身につけているが、細い体にはいかにも重そうで、どうにもさまになっていない。見ているこちらが心配になるくらい青白い顔色で、どことなく生気がなく、唯一、よく動く瞳の光だけが、生きている証のようである。
兄宮はひたすらに弟を気にかけているようだったが、当の弟宮は、興味深そうにあちらこちらを見回している。
一瞬、墨子とも目があったような気がしたが、兄宮に促されるまま、講堂の中へと入って行ってしまった。
――貴人の墓参りは、恙無く終わった。
上皇の用意した供え物のせいで、かつてなく墓所は華やいでいたが、やはり、墓所の外れにある墨子の両親の墓にだけは、何も供えられることはなかった。
上皇の隣で手を合わせている弟宮の、母親を殺した罪人の墓なのだから、それも当然である。
その晩のことだ。
いつものように、墨子は両親の墓参りに出向いた。
どうしても寂しい墓の様子が受け入れがたくて、せめて、夕餉の席で上皇からの土産として配られた飴を、供えてやろうと思ったのだ。
未だに騒がしい寝間からそっと抜け出し、冷え冷えとした墓所を抜け、墨色の二基へと向かう。
だが、そこには先客がいた。
いまだかつてないことに驚いた墨子は、それが誰かを認め、全身の血が凍りつく思いがした。
細っこい、小さな人影。
解き放たれた髪はさらさらと夜風になびき、首すじの白さがいかにも寒々しい。
煌々とした硬質な冬の月明かりのもと、護衛の一人も連れずに墓の前に立っていたのは、その墓の住人によって命を狙われ、母親を殺されたはずの弟宮だった。
思わず、木陰に身を隠してしまった。
こわごわと木の葉の間から様子を窺えば、弟宮は、きょろきょろと周囲を見回し、枝打ちされたまま放置されていた枯れ枝を拾い、墓の前に戻って来た。
胸がざわざわする。
一体、何をするつもりなのだろう。まさか、あの枝で、墓石をぶつつもりなのだろうか。
墨子自身、たとえ罪人で、その報いを受けただけなのだと分かった後でも、死んでしまった母のことが恋しくてたまらないのだ。何の罪もなく母を殺されたのだとすれば、どれだけ怨んでも怨みきれないだろう。
息を殺し、瞬きも惜しんで、弟宮の一挙手一投足を追う。
弟宮は、そっと、枯れ枝を月に掲げた。
月の中に、黒い枝の影が浮き上がる。
――その瞬間に起こったことは、まさに奇跡だった。
しゃん、と。
弟宮が枝を振ると、まるで、神楽の鈴がふるえるような、澄んだ音が虚空に響き渡った。
すると、空から零れ落ちた月光を、地面に落ちる前に掬い上げるかのように、枝の先に光が宿り始めたのだ。
それはまるで、月の光が蛍となって、枯れ枝に集まっていくかのようだった。
しゃん、しゃんと、何回かゆっくり弟宮が枝を振る度に、枯れ枝がにわかに生気を帯び、ふっくらと蕾がふくらみ、光の粉を振りまくようにして、一輪一輪が花開いていく。
それは、季節はずれの桜だった。
冷たく暗い墓に、こぼれるように咲き誇る桜の華やかさは、息を吞むほどに鮮やかだ。
満足げに、満開の桜の枝を見つめた弟宮は、それをそっと墓前に供え、手を合わせる。
それだけで、灰色の水底に沈んだように、全く色味のなかったそこが、一気に明るくなったように感じられた。
月光を弾いた花びらが、春の息吹を冬の墓にもたらしたのだ。
その光景を前に、ただあっけに取られていた墨子は、ふと、弟宮の顔を伝うものに気付いた。
――彼は、泣いていた。
こいつは、わたしの両親の死を悼んでいる。
どうして、と、頭を殴られたような衝撃が走った。
「ねえ」
衝動のまま木陰から飛び出て声をかけると、美しい少年は、驚いた顔で墨子を振り返った。
「どうして、この墓に花をそなえる」
「昼間来た時、ここだけ、何も置かれていなかったから……」
どうしても気になって、と。
その、あまりに吞気な言い分に、理不尽な怒りがひらめいた。
「馬鹿。これは、あなたのお母さまを、殺した者の墓だ!」
「それは、知っている」
あっけらかんと言い切った弟宮に、墨子の頭の中は真っ白になった。
「知っている……?」
「ああ。おじいさまに聞いた」
ならばどうして、という声は言葉にならない。しかし、そんな様子に、何を言いたいのかを悟ったらしい。
弟宮は、静かに瞬いた。
「母を殺したということが、その者の死を、悲しんではいけない理由になるのか?」
心底不思議そうに言われて、墨子は絶句した。
分からない。この少年の言うことが、何一つ墨子には分からない。
だが、弟宮は墨子の困惑に気付くことなく、ひたすら悲しそうに墓を見やった。
「母上も、ここに眠る人たちも、私は、死なないで欲しかった……」
頭がうまく働かないまま、ふと、自分以外で父母のために泣いてくれたのは、こいつが初めてかもしれないと思った。
遠くで、弟宮がいないことに気付いた侍従たちが、駆けつけてくる音が聞こえる。
「そろそろ戻らねば」
そう言った弟宮は、その、そこだけ生気にあふれた、きらきらした瞳を墨子に向けた。
「君の名前は?」
「わたしは――」
何も考えないまま答えそうになり、はたと、自分の立場を自覚する。
「おれは、墨丸だ」
初めて、墨丸と自ら名乗った瞬間だった。ぶっきらぼうに、男に見えるようにと意識もした。
「墨丸」
「そうだ。おれは、君と、もっと話がしたい」
また会えるだろうか、と問うと、弟宮は真面目くさった顔で頷いた。
「もちろん。あなたが、それを望むのならば」
その翌日、上皇は南家の本邸へと去って行った。
墓参りは、どうやら口実であったらしい。真の目的は、何やら南家当主と面談をすることにあったようで、以来、皇子二人を連れて、上皇は度々南領を訪れるようになった。
出来る限り、墨子は弟宮に会いに行きたかった。そうするためには、いちいち徒歩で南家本邸に向かうことは不可能だ。
墨子は恥を忍んで、飛び方を教えて欲しいと、初めて寺の子ども達に自分から話しかけた。
意外だったことに、彼らは屈託なく――むしろ嬉しそうに、墨子に鳥形への転身の仕方と、上手い飛び方を教えてくれた。
中には、真正面から「今までお高くとまってやがったくせに」と噛み付いてくる者もいた。
だが、罵りあいでもちゃんと言葉を交わすようになった後の方が、彼らとの距離はずっと縮まったのだ。
初めて、己の翼で飛んだ空は、青く澄んで、広かった。
そして、無事に着地した墨子を、歓声を上げて出迎えた子ども達の笑顔は、あまりに輝かしかった。
良かったねえ、と本当に嬉しそうに少女に微笑まれ、それまで憎まれ口を叩いていた少年が、お祝いにと夕飯のおかずを一品多くくれたその夜、墨子はようやく、彼らの仲間となったのだった。
そうして、墨子は弟宮が南領にやって来る度に、彼と会うようになった。
慶勝院にまでやって来る場合は待てば良かったが、南家本邸に逗留する際は、墨子から進んで会いに向かわなければならない。初めて己の翼で南家本邸を訪ねた時には、徒歩だとあんなに大変だった行程が、こんなにも簡単に来られてしまうものなのかと拍子抜けした。
弟宮は、南家本邸にやって来ると、必ず屋敷の中で三番目に大きな離れへと通される。そこには、築地塀を跨ぎ越すようにして百日紅が生えていたので、墨子は木登りをして忍び込むようになった。
大抵、弟宮は移動中に気分が悪くなったと言って、早々に床につく。しかしこれは、墨子が会いに来ると知ってから、弟宮がするようになった仮病だった。人気がなくなったのを待って、枝の中に隠れていた墨子がするすると木から下りて行くと、弟宮は既に着物を布団の下に丸めて押し込み、せっせと人の形に整えているのである。
「よお。もう出られるか?」
「うん」
待っていたぞ、と笑う顔はいとけなく、とても可愛らしい。
彼は、病弱なのに好奇心が旺盛だった。せっかく地方にやって来たのに、室内に閉じ込められているのをもったいないと言うので、こっそり外に連れ出してやることにしたのだった。
会話してみれば、弟宮は、墨子が今までに会ったどんな奴よりも賢く、同時に抜けている少年だった。
中央の政については、ずっと年上の大人のような口調で喋っているのに、饅頭を墨子が横からくすねとっても一向に気付かない。それを指摘しても、「すみは手先が器用なのだなぁ」と感心してばかりいるのだ。狡猾なようでいて、まるで赤ん坊のように、ひどく無垢な部分があった。
墨子はいつしか弟宮のことを、手のかかる弟を見るような気持ちになっていた。
だが、慎ましやかな交流は、そう長くは続かなかった。
それからいくらも経たないうちに、上皇が亡くなったのだ。弟宮は西家に居を移し、南領にやって来ることもなくなってしまった。
寂しくはあったが、たとえもう二度と会えなかったとしても、墨子は弟宮を友達だと思っていたし、きっと、彼もそう思ってくれているだろうと信じていた。
やがて、墨子の側にも変化が訪れる。
南本家から慶勝院に使者が訪れ、墨子を養女として迎え入れたいと言って来たのだ。
この頃、中央では兄宮が出家し、弟宮が正式に日嗣の御子となったため、南家には弟宮の后候補を出す必要が生まれていた。あの時、見逃してやった恩を今返せ、ということなのだろう。当然、拒否など出来るはずもなく、もったいぶった南家の使者に対し、墨子はただ「身に余る光栄です」と、殊勝に頭を下げたのだった。
南家に呼び戻される日の、前の晩のことだ。
青嵐に、話があると呼び出された。
毎日のように手を合わせた神像の前で、墨子は青嵐と向かい合った。
「こうして、ゆっくり話すのは、いつぶりかね」
「いつぶりじゃない。きっと、これが初めてのことだよ」
はっきりと言ってやれば、ああ、そうだったか、と青嵐は溜息をついた。
「……思えば、色々と、お前には辛い思いをさせちまった」
悪かったね、と言った青嵐は、以前よりも、ずっと老けて見えた。
「いきなりどうしたんだ、あんたらしくもない」
思えば、最初に会った頃の青嵐は、老婆というには若過ぎた。今になり、彼女がどういった経緯で自分の監視役になったのか、ふと興味が湧いた。
思うままに質問すれば、青嵐はわずかに苦笑した。
「今言っても、お前はもう考えなしに突っ込むことはないだろうから、言っちまおう。アタシはね、お前の両親は――はめられたのかもしれないと、思っている」
それを聞く墨子の中に、もはや、動揺は生まれなかった。
「聞こう」
青嵐は、墨子の目を見て軽く頷いた。
「耳が痛いかもしれないが、お前のお父さんとお母さんは、南家の頂点にいるということで、明らかに調子に乗っていた」
南家の末席の、下働きをしている青嵐にすらそう見えたのだ。当然、周囲の貴族連中にとって、その振る舞いは耐え難く感じられただろう、と言う。
「だからきっと、切っ掛けは何でも良かったんだ」
青嵐は、ぽつりと呟く。
「南家系列の宮烏達は、こじつけでもなんでも、お前の両親を排斥する理由が欲しかったんだろう。弟宮の母親が死んだ件に、実際、お前の母さんがどう関わっていたかなんて、アタシには分からない。けど、あの子は人殺しなんて大それたことが出来る子じゃなかった。アタシにとっては、それだけが真実だ」
しかし、疑われたのは、疑うように仕向けられたのは、墨子の母、夕虹だった。
この頃には、母の一門もその立場に乗じて、大きな顔をするようになっていた。
周囲からの静かな反発に危機感を覚えた連中は縁を切り、己の置かれている状況に気付かなかった愚かな者だけが――夕虹を裏切らなかった者達だけが、当主夫妻と共に粛清されたのだ。
その数は、悲しいくらいに少なかったという。
青嵐は見切りをつけながら、それでも、なんとか助けてやりたいと思った、半端者だった。
「夕虹を逃がしてやることは、どうあったって出来なかった。だから、お前だけでも逃がしてやりたいと思って、あんな無理やりな手段を取ったわけだ」
ちょっと息をついてから、青嵐は再び墨子の目を見た。
「お前はね、本当はあの時、夕虹と一緒に殺されるはずだったんだ」
墨子は息を吞んだ。
「……撫子の身代わりにするため、生かされたんじゃなかったのか」
「最終的には、そう判断したんだろうね」
だが、あの時点では違ったのだと青嵐は言う。
もともと、幼い姫をどうするかについては、反当主で団結していた彼らの間でも意見は割れていたらしい。一旦は夕虹の遠縁に当たる家が引き取ることに決まったものの、混乱に乗じて殺してしまえという命令が実際には出ていたのだ。
それを知ったからこそ、青嵐は一旦墨子の身を隠してから、新たな当主となった融に助命を嘆願しようとした。
もし、予定通り軟禁先に逃れることが出来たとしても、この状況ではいつ殺されるか分かったものではない。墨子を本気で守りたいならば、融に許しを得た上で、墨子の存在をすっかり隠してしまう必要があった。
青嵐にとっても、それは命がけの賭けであった。
勘気をこうむれば、きっとその場で、殺されていた。だが幸いなことに、融は、墨子の生死に全く関心がなかった。
――皇后と、南橘家に見つかりさえしなければ、勝手にするがいい。
そう言って新たな戸籍を用意し、青嵐が監視につく条件で、墨子が慶勝院に住むことを許したのだった。
「逃げたばかりの頃は、一言、お前が『自分は南家の姫だ』と言っちまえば、アタシだけでなく、協力してくれた連中も皆殺しになっちまう状況だったからね。こっちも必死だったのさ」
まあ、余裕がなかったんだね、と青嵐は嘆息する。
「教育係なんて立派なものじゃなかったが、実際に、あんたの母親の卵を温めたのは、このアタシなんだ」
ふと、青嵐は視線を己の膝へと落とした。
本当は、宮烏の礼儀などよりも、もっと大事なことを教えてやりたかった、と囁く。
「馬鹿な子だよ。本当に」
初めて、青嵐の声が震えた。
墨子は膝でにじり寄り、青嵐の顔を覗きこんだ。
「命をかけて、私を守ろうとしてくれたのに、辛く当たってすまなかった。そして、本当にありがとう」
青嵐は、無言で頭を横に振る。そしてふと思い出したように、傍らに置いてあった包みを差し出した。
「アタシからあんたに渡せるのは、これくらいだ」
「これは――」
包みを開いて、瞠目する。
そこにあったのは、つやつやとした、見事な髢だった。
「あの時に切った、お前の髪で作ったんだ」
どうしても捨てられなくてね、と言いながら、青嵐は母親のような手つきで、そっと墨子の短い髪を撫でた。
「髪が伸び揃うまで、時間がかかるだろう。しばらくはこれをお使い」
「青嵐――」
ぶっきらぼうで、恐い女だったが、それでも彼女は、ずっと墨子の味方だったのだ。
青嵐は、真剣な眼ざしで墨子を射抜いた。
「いいかい。今のお前に、選択肢なんかない。南家の宮烏に生まれちまったんだから仕方ないと諦めな。どうせ逃げ回っても殺されるだけなんだから、腹を決めて、自分の居場所は、自分で勝ち取っておいで」
夕虹は間違えた。母親の失敗に学ぶことだ、と。
「蛇の道だ。油断せず、自分の身は、自分で守るんだよ」
「ああ……分かった。心に刻む」
髢を脇に置き、墨子はまっすぐに青嵐に向き直った。そして、綺麗に手を揃え、深々と頭を下げたのだった。
「お世話になりました。どうか、お元気で」
* * *
それにしても、あの男の正室候補として宮烏に戻るなんて、何とまあ、不思議なめぐりあわせもあったものだ。
唖然とする撫子に見送られて、墨子は愉快な心持ちで外へと出る。
撫子は、可愛い義妹だ。
彼女の未来に幸せがあればいいと心から願っているが、あの子が思い描いている未来は、きっと来ない。
――私が、そうはさせない。
ふと、中央山の方を見る。
桜花宮には、見事な花見台があり、すばらしい桜の景観があると聞く。
だが、墨子にとっては、あれからどんなに見事な桜を見ても、若宮が咲かせた一枝の桜を越えて、美しいと思えるものはなかった。
今までがそうだったように、きっと、これからもそうだろう。
自分が、若宮の后になる気は毛頭ない。だが、ぼんくらのうらなり瓢箪に代わって、あの男の妻となるにふさわしい者を、見定めてやらなければならない。
叶うならばそれが、あの一枝の恩返しになればいいと、墨子は心から願っている。