全国の書店員さんから熱狂的な支持をいただいている、森バジルさん新刊『なんで死体がスタジオに!?』が、いよいよ6月26日に発売となります!
一行目からノンストップで進行するバラエティ・ミステリを、ぜひ試しに読んでいってください!
★あらすじ
バラエティプロデューサー・幸良涙花は、がけっぷち、である。
筋金入りのテレビっ子だが、不運体質(?)のせいか失敗に失敗を重ね、「次がダメなら制作を外す」と宣告されている。
進退をかけた「次」の番組は、その名も「ゴシップ人狼」。
出演者が持ち寄ったゴシップについて語りながら、紛れ込んでいる嘘つきを推理する、という人気トーク番組だ。奮闘する幸良が、本番直前に出会ったのは……
「大御所俳優・勇崎恭吾の死体」だった!
生放送開始まであと20分。果たして幸良は特番を乗り切れるのか!?
そして、この事件の犯人は?
1章 この番組には刺激の強い表現が含まれています。
 幸良涙花
幸良涙花
「いまどこにいるか分からない、と」
電話口で告げられた情報を、ばかのように繰り返す。
「連絡も、取れないと」
心臓と全身の毛穴がきゅっと引き締まる。この業界で十年以上働いていると、起きているトラブルが一発耐えて反撃に転じられるくらいの浅傷なのかプロデューサー生命まで届きうる重傷なのかの判断を、匂いで嗅ぎ分けることくらいはできるようになる。そんな私の勘が言ってる――こいつは、えぐいダメージになりうる。
生放送特番の出演者が、本番四十分前になってもまだ来ていない。連絡も取れない。それが今私に襲いかかっているトラブルだった。生放送といっても、YouTubeやインスタライブの配信ではない。地上波全国二十八局ネット、ゴールデンタイムの生放送特番である。
「幸良さん、顔色悪いっすよ。大丈夫ですか」
次郎丸くんが心配そうにそう声をかけてくれた。ちなみに次郎丸は苗字で、下の名は夕弥。次郎丸夕弥、芸名と言われた方が納得できそうなゴツい名前だが彼はスタッフ側。制作会社所属のチーフADである。ADらしくバミテを肩紐に通したADバッグを携え、ロンTとジャージ素材のズボンというゆるい服装だが、それでいて爽やかさと抜け感を感じさせる雰囲気がある。まだ二年目くらいの頃から、「ADってなぜかお洒落だったり爽やかだったりする方がDに怒られづらいんですよ」と言っていた。デキる子なのだ。
「私の顔色、どのくらい悪い?」
「昔、家の鍵とスマホと財布をなくして窓から家に入るはめになった友達が、そんな顔してました」
「私は旅先で、ホテルの鍵とスマホと財布に加えて、レンタカーの鍵もなくしたことあるけど、その時のほうがまだ元気だった気がする」
「それだけドジだと生きづらそうですね」
私は三十五歳で次郎丸くんは二十八歳。今もなお体育会系の縦社会のなごりを捨てきれないこの業界にいながら、立場も年齢も明確に上である私に対してこうやって遠慮ないコメントをくれるのが彼の良いところだ。
「最近はもう自分のドジにも慣れてきたから、対策するようになったよ。旅行で運転するときは、レンタカーの鍵は絶対なくさないようにGパンのベルト通すとこにぶら下げるようにしたんだ」
「当てましょうか。Gパンに鍵つけてるの忘れてそのまま着替えてGパンしまって、旅行二日目の朝に車に乗ろうとしたタイミングで気づいて車の横でスーツケース開け直すハメになったんじゃないですか」
「何で分かるの」
「勇崎恭吾さん、本当に間に合わない感じですか?」
次郎丸くんの淡々とした呆れ声が、現実に私を引き戻す。
本番開始まで四十分。とっくに勇崎さんの入り時間は過ぎている。メイクと衣装合わせを考えると、仮にいまこの瞬間にテレビ局に到着したとしても放送開始には間に合わない、なにしろ今回の勇崎さんのメイクは特別なのだ。なかなかシビれる緊急事態であり、まだ現場のスタッフたちへ正式に情報共有されているわけではないものの、伝聞で状況は伝わっているらしかった。
「マネージャーさん――勇崎さんの奥さんと、今話せた。勇崎さん昨日は夜通し外出されてたみたいで。たぶんどっかで朝まで飲んでたんでしょって言ってた」
「ああ、あの人奥さんがマネージャーやってるんでしたね。じゃあ、泥酔してどっかの路上で寝てるかもしれないんだ」
「そう、今どこにいるか分からない」
「凄いな、いろいろ激しい噂は聞いてたけど、まさかゴールデンの生の番組に遅刻するなんて。幸良さんも、全国ネットの生放送で遅刻者を出した統括プロデューサーとしてテレビ史に名を残せるかもしれないですよ」
次郎丸くんの軽口に、
「生放送に出演者が遅刻すること自体は、別にわりとあることだよ。千鳥のノブさんは正月のお笑いの特番で七時間遅刻してるし、フジの『ノンストップ!』だと小籔さんだったり博多華丸・大吉の大吉さんが遅刻したことがある。その大吉さんがMCの『あさイチ』にナイツの塙さんが遅刻したこともある。前例ならいくらだってあるんだから」
絶対いまこんな話なんかしてる場合じゃないにもかかわらず、早口でまくしたててしまう。次郎丸くんは目を細め、
「なんで生放送遅刻事例のデータベースが頭に入ってるんですか」
「そりゃインパクトあることだから、覚えてるよ」
「テレビを愛しすぎですよ。まあ、前例があるならそんなに焦る必要ないじゃないですか」
「いや、次郎丸くんも分かってるでしょ、今日の放送は勇崎さんマストなの。勇崎さんが縦軸みたいなもんだから。それに、予告でもかなり勇崎恭吾が出演するってことで煽ってるし」
勇崎恭吾は今年で五十二歳のベテラン俳優である。七年ほど前の映画出演(ヒロインのお父さん役)をきっかけにブレイクした超遅咲きタイプ。最近独立してタレント事務所〈勇崎オフィス〉を立ち上げており、数名のタレントが所属している。所属タレントをドラマや映画、バラエティで見かける機会も多く、社長業としても順調である。間違いなくバラエティ番組、しかもこんな超ハイリスクな番組に出るようなタレントではない。
「ねえ次郎丸くん」頭二つぶんくらい高い位置にある彼の目を見上げる。「どう思う? 出演者の遅刻は私の責任? それとも外的要因?」
「番組に関する全ての責任はプロデューサーに帰する」次郎丸くんは抑揚を削ぎ落とした声で言った。「僕はそう認識してますけど」
「なんでそんな容赦なく酷いことを淡々と言えるの」
「プロデューサーとしての幸良さんを信頼してるからですよ」
「私が担当する番組、深夜で始まった時はいいけど編成変わって時間帯が少しでも上がったら急に失速して終わるって言われてるんだけど」
番組死神とかいうひどくて語呂の悪いあだ名までつけられている。
「それでも記憶に残る番組ばかりです」
次郎丸くんはトーンを変えずに、
「僕は幸良Pの作る番組好きです。信頼できる作り手だと思ってます」
「次郎丸くんは信頼してくれてても、会社は信頼してくれてないんだよね」
「信頼してくれてるから、ゴールデンの二時間特番を任されてるんでしょ。三十五歳でゴールデン特番やれるのは期待されてる証拠じゃないですか」
「もう周りから色々言われまくりだよ、局長と寝たのかとかどうやって脅したんだとかいよいよテレビの時代も本当に終焉かとか。寝てないし脅してないし、なによりテレビの時代はまだ終わってないから!」
「酷いですねぇ」
「そもそも私、ゴールデンなんてやりたくないってずっと言ってたんだよ。ずっと深夜でがっつりお笑いの番組やりたいって言い続けてたし。だけど編成局長の山田さんがなぜか私を指名してきたの」
「指名で仕事もらえるなんて、プロデューサー冥利に尽きるじゃないですか」
「絶対、扱いやすいからだよ」私は断言した。「これが大御所の佐藤さんとか高橋さんとかだったら色々立場もあるし他の番組も任せてるから自分の意見をごり押ししづらいけど、三十代の女プロデューサー相手ならやりたい放題指示できるって思ってるんだよ。現にえぐい注文来まくったし」
本当にえぐい注文が来て、台本直したり急遽撮ったVTRの編集チェックしたり、この二週間は片手で数えられるくらいしか家に帰ってない。今時ADすら帰れ帰れ休め休め働くな働くなと言われるご時世なのに。
「でも、さすがに扱いやすいってだけで選ばれてはないでしょ。特番失敗したら山田さんだって困るわけだし。しかも記念すべき初の生放送回、ちゃんと回せるプロデューサーを立てたかったんだと思いますよ」
「この特番がコケたらさ」私は次郎丸くんをまねてなるべく淡々と言ってみた。「私制作外されることになってるんだ。営業か経理か、とにかく制作からは離される」
次郎丸くんは珍しく、目を丸くしていた。彼の脳内ではいま、スーツを着て広告代理店と打ち合わせをしたり机に向かって伝票を処理したりしている私をイメージしようと試みているのだろう。パーカーとニューバランスの私しか見たことのない彼には至難の業であるはずだ。というか私ですら想像できない。スーツなんて入社式以来着ていない。
「コケるって、具体的には」
「この特番、ツークールごとにやってて今回四周年だから……もう八回目でしょ? これまでの七回の平均視聴率を下回ったらアウト」
そもそも総個人視聴率が毎年前年割れしてる中で、これまでの視聴率を超えるというハードルは、改めて口にすると震え上がってしまうくらいに高い。
「視聴率だけじゃなくて、ネットでも話題かっさらえって言われてて。旧Twitterトレンド一位とれないと駄目って。それくらい話題にしろって」
といいつつ、これは正直クリアできると思ってる――番組の内容的にも話題になりやすい要素だらけだし、SNSとの親和性高い作りだし。
「あと、事故ったらもちろんアウト」
トーク番組の生放送というだけでうちの局では十数年ぶりくらいだし、しかも内容が内容なので、あらゆる種類の事故があり得る。全財産をどちらかに賭けろと言われたら、私は迷いなく今日のオンエアが事故る方に賭ける。
「いや、ヤバすぎでしょ。ふつうそこまで課されないですよ。何でそんなことになっちゃったんですか」
「私のドジと不器用さがついに会社にバレちゃって」
「というと」
「この間、担当してるレギュラー番組の収録でさ、たまたま養生されてなかったカメラのケーブルに引っかかって転んじゃって、しかもその流れで大御所司会者にお茶ぶっかけちゃって」
「ああ……」
「急いで謝罪しようと思ったんだけど、やらかしちゃった後悔と焦りがあまりに強すぎて、何か脳の変な回路がつながっちゃって、敢えて逆だ! の思考で『たまにはこんな感じで若手の頃の気持ち思い出してみるのもいいんじゃないでしょうか』的なこと言っちゃった」
「ええ……」次郎丸くんの顔が歪む。
「しかもそれがたまたま編成局長とかエラい人たちが見に来てる収録だったんだ」
「幸良さん」
次郎丸くんが歪んだ顔をぷるぷる震わせながらも、真顔をキープしつつ、
「“ドジ”とか“不器用”って、社会人歴十年超えてる大人が自分に対して使っていい語彙じゃないですよね。窃盗を万引きって言ったり売春をパパ活って言ったりするのと同じで、“仕事できない”を可愛く言い換えてるだけです。そういう逃げの語彙使って“私ドジだから”的な言い方でセルフハンディキャッピングしてごまかし続けてたら、いつか取り返しのつかない大失敗を引き起こしますよ」
淡々と嚙まずに言い切られた長尺の正論が私の自尊心を貫く。
「次郎丸くん。一応確認しとくんだけど」
「はい」
「君は私の部下だよね。七歳年下の」
「僕は制作会社の人間なんで厳密には取引先ですけど、同じ番組のチームという意味でなら部下ですね」
「年上の上司に正論を言うときは、絶対に芯を食い過ぎちゃいけないんだよ。立ち直れなくなっちゃうから」
本当に刺さってしまって、腰に力が入らない。今にもこの場に寝転がってしまいそうだった。
「まあいまのは冗談ということで」
「冗談じゃ済まされないくらいには真芯を捉えてたよ」
「幸良さんはドジで不器用だし現場の仕切りも甘いことが多いけど、テレビが好きな気持ちは誰にも負けないでしょう。だからこそ企画も強いし」
次郎丸くんは私から目を逸らさずまっすぐと、
「無限に湧いてくるトラブルとハプニングを飼い慣らしてこそ、テレビマンでしょ。この遅刻も鮮やかに解決して数字も取って、上の人たちを見返してやりましょうよ」
「爽やかに難しいこと言うけど……」
勇崎さん不在のセットを想像して、身体が熱くなってくる。嫌な汗が脇とか背中を伝う。
「それより、さっさと緊急の制作打ちやった方がいいんじゃないですか? 勇崎さんのパートどうするか決めて全体に指示してあげないと。副調整室も混乱してるだろうし、ちゃんと連携しとかないと事故りますよ」
的確なコメントを残した直後、次郎丸くんはADの子から呼ばれ、そちらの対応に向かっていった。
「何から何までその通りすぎて本当に」
本当はこの子はすぐにでもディレクターに上げて、VTRの一本でも作らせるべき人材なのだ。
私はスイッチを切り替え、スタジオ下手側の長机に駆け寄り、ノートPCを置いて指を走らせる。勇崎さん登場のシーンに間に合わなかった場合はそのくだりなしで行けるように、台本を切り貼りしていく。今から書き上げてプリントアウトしてカンペにも反映してもらって――段取りを脳内で組み立てながら、勇崎さん不在バージョンの台本を整える。
「勇崎さん遅刻だって? 大変だな、コーラちゃん」
この世で最も私の神経を削るタイプの野太い声が、背後から飛んで来た。
「山田さん、お疲れ様です。早いですね」
「まあ、俺が色々注文つけさせてもらったわけだし、現場見に来ないと駄目っしょ」
編成局長の山田さんは、余裕をにじませるような口調のわりに目がまったく笑っていなかった。ただ、山田さんの周囲三十センチだけ九〇年代の空気を保存してあるかのように、かつてテレビが絶頂期を迎えていた頃の輝きをまとっている。
「山田さんからも連絡取れないですか?」
「全然つながんないわ。あの馬鹿、昔から時間と金勘定にはうるさいクチだったんだけどなぁ」
山田さんは勇崎さんと同い年で、なんと中学の同級生だという。昔から悪ガキとして二人でつるんでいたらしい。その辺の武勇伝は暗唱できそうなほど聞かされていた。何しろ、今回の特番に勇崎さんの出演を取りつけてきたのは山田さんなのだ。
取りつけてきたというとお手柄のように聞こえるが、もう少し実際的な表現をするなら“ねじ込んできた”と言う方が的確だと思う。八割方固まっていた台本を勇崎さん中心に作り替えて出し直させられたときは深夜のデスクで泣き言の見本市を開いた。
自分が無理矢理入れた俳優が遅刻となればもう少し申し訳なさそうな雰囲気を出しても良さそうなものだが、彼は自分が部下に謝るという選択肢を持ち合わせていないタイプのお偉いさんだった。
「遅刻はしゃーないけど、構成はなんとか上手く元の通りにつなげてくれよ。俺と局の面子がかかってる」
その言葉に、私の胃はパティシエが握る生クリームチューブのようにきゅるきゅるに絞られた。口から生クリームを噴出しなかっただけよく耐えた方だ。
「も、もちろん勇崎さんなしでも数字が取れるように全力を尽くしますよ」
「あれ、聞こえなかった? 上手く元の通りにつなげてくれって言ったんだ。数字ももちろん重要だが、それ以上に今回は例のくだりを放送することが何より重要だからさ」
「勇崎さんが間に合えば、もちろん」
「間に合わなかったときにどうするかまで考えるのがお前の仕事だろ、統括プロデューサー」
この短い、三分にも満たないやりとりで自分の心がずしりと重くなったことに私は絶望した。さっきまで次郎丸くんと喋ってたときは、ピンチながらもなんとか頑張ろうという気になれたけど、今はもう何か台風とかとんでもない大事件とかが起きて番組が臨時ニュースに切り替わるような、そんな奇跡が起きるのを祈るモードに入ってしまいそうだった。番組を任される人間として失格の思考だ。だけど、勇崎さんが来てないのにどうやって勇崎さんがいる前提の構成をやれというのだろう。仮にもテレビ局で編成局長張ってる人間なら、それが無茶な要求であることくらい分かるだろうに。
理不尽な圧力を受けたとき、私の感情の割合は怒りや反発より恐れとか不安とか憂鬱が勝つ。その弱さが嫌いだった。何度も「この業界に向いてない」と言われる要因だった。
「幸良さん、ちょっと確認お願いします!」
何とかして山田さんとの会話を打ち切りたいという私の願いを聞き届けたかのように、次郎丸くんが私を呼んでくれた。私は軽く山田さんに会釈すると、そのままここには戻らないという意思表示も込めてノートPCを手に取り、次郎丸くんを中心にADの子たちが集まっているところへと早足で向かった。向かおうとした。視界が縦に半回転した。
早く山田さんから逃れたい一心で足を動かしていた私は、バミリ用の養生テープが足元に転がっていることにまったく気がつかず、そいつを思い切り踏みつけて前進しようとした結果、盛大に転んでしまった。
恥ずかしさで体温が十度くらい上がったんじゃないかと思った。
「何してるんだ」
山田さんの呆れた声が、私の羞恥心を加速させた。一刻も早く体勢を整えようとして起き上がるが、足首を変な角度で曲げてしまい、うまく立ち上がることが出来なかった。
自分の重心を見失いながら、「二度も転ぶわけにはいかない」という思考で脳が埋め尽くされる。私は数歩よろめきながらも、なんとかこの身体を再び床に這わせるのを防ぐために、手近な物体に手をついた。
これが、身体を支えるための物体としては考え得る限り最悪の代物だった。ADの子の「あっ」という短い声に、私は自分の運命を悟った。
私が手をついたのは、番組中の罰ゲームで使う電流椅子だった。別に、電流さえ流れていなければ何の変哲もないただの椅子であり、本番中ですらない今は絶対に電流など流れていないはずなのだが、テストしたADがスイッチをオンにしたままにしていたらしい。本来は衣服の上から流れる想定で調整してある強さの電流が、裸のてのひらを入場口にして私の身体じゅうへ駆け巡った。ドジと不幸の合わせ技一本。
痛みに身構えていない、むしろ転倒から起き上がろうとする無防備そのものの状態から全身の激痛。なすすべなく叫びながら床に倒れ込んだ。床が針の山になったのかと思うくらいに痛みが続いて手が動かない。息を吐ききるように、えぐい、という三文字の感想がこぼれる。
呻きながら床を転がっていると、徐々に痛覚以外のいたさ――スタッフたちから刺される視線に気づいた。この現場を仕切る人間が床を転げ回る姿は控えめに言っても滑稽すぎる光景だろう。若いADの子たちからおじさんのカメラマンたちまで、一様に笑いを嚙み殺すようなぷるぷるした顔をしていた。
「ちょっと、笑ってないで助け起こしてくれたらよくない?」抗議しつつも、私に気を取らせてる場合じゃないと思い、真面目なトーンに切り替えて言う。「OA三十分前だよ、仕事して!」
スタッフたちがにやつきながらそれぞれの作業に戻る中、次郎丸くんが遠慮なく爆笑しながら駆け寄ってきた。
「ちょっと芸術的すぎますって。ドジピタゴラスイッチじゃないですか。大丈夫ですか」
私はふらふらと立ち上がりつつ、所感を述べた。
「芸人さんのリアクションって、マジなんだね」
「PCぶん投げてましたよ」
次郎丸くんが指差す方を見ると、下手側の端の壁際に設営された簡易楽屋の前まで投げ飛ばされた、哀れなノートPCが見えた。電流と衝撃の二種類のダメージを受けたことになる。私の思考は電流を切り忘れていたADへの嘆きから、さっきまで書いていた台本データが生存しているかの不安へと一気に切り替わった。
「生きててくれ頼む」
あわあわと走ってPCを拾おうとする私に、次郎丸くんが「また転びますよ!」と忠告を投げてきた。失礼な、流石にもう大丈夫だから、と言い返すより早く、電流によって若干痙攣気味だった足は、壁際のPCまであと二歩という地点で見事にもつれた。思わず壁と、壁際に置かれていたでかい段ボールで身体を支えた。
誓ってもいいが、私はちゃんとすぐ壁にも手をついて体重を分散させた。箱が倒れるような力はかけていない。ここまでドジを重ねてきたけど、もうこれ以上はさすがにお腹いっぱいだ。
だけど結果として箱は倒れた。一人暮らし用の冷蔵庫くらいは入りそうな箱だったので、鈍いながらもけっこうな大音量がスタジオに響いた。
「マジでどんだけ罪を重ねるんですか」
次郎丸くんが手をとって起き上がらせてくれる。
「うっ、ドジが罪だという前提の発言……てかこれ何? 壊れ物じゃないよね?」
箱には特に何の記載もなかった。昨日私が小道具を確認しにきたときにはなかった気がする。美術関係の箱だったらまずいかも、と思いつつ、私は中を検めようとフタにあたる面のガムテープを慎重にはがして開いた。
そこから覗く中身に、私と次郎丸くんは顔を上げて目を合わせた。次郎丸くんはADバッグからカッターナイフを取り出して段ボールを素早く――それでいて慎重かつ丁寧に――解体した。
段ボールが展開され、敷き布団のようにその中身の下敷きになった。
あおむけになったその腹にしっかりと人の命に届きうるサイズの刃が刺さり、赤黒い液体がジャケットを染めている。そこまではいい。問題は、その目が白目を剝いていることと、その顔が生きている人間のものとは思えないほどに冷たいこと。
箱に入っていたのは勇崎恭吾の死体だった。
二度目の絶叫がスタジオに響いた。サスペンスによくある「きゃー」的な甲高い悲鳴ではなく、音で言うと「うおお」の三音をベースにした可愛げのかけらもない私の悲鳴。
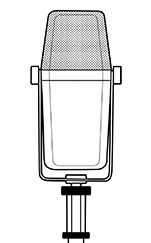 仁礼 左馬
仁礼 左馬
![]()
スタジオから前室まで届く「うおお――」という悲鳴。おれのピンマイクを調整してくれていた音声さんが、怪訝そうに首をかしげた。
「何かあったんですかね」緊張をほぐすために声をかけた。
「どうせまた幸良Pが何かドジってるんじゃないっすかね」
おそらくおれより十歳近く年下であろう音声さんは、タメ口との境界線上くらいのゆるい敬語でそう返してくれた。それだけ仁礼左馬というタレントに対して親しみを持ってくれているということだろう――おれの思考は常にポジティブに流れるよう重力を操作してある。
「幸良さん、そんなドジなんですか」打ち合わせしてるときはそんな感じなかったけど。
「ディレクター時代に、番組の最後に出すプレゼント応募用のQRコードを間違えて、なぜか国税庁がe-Taxの利便性を案内してるページに飛ぶやつにしちゃって、いわゆる陰謀論的な界隈の人たちが“国がメディアを操って納税額を増やそうとしてる!”みたいなことを投稿しまくるっていう炎上を起こしたことがあるらしいっす」
「そんな強いエピソードがすっと出てくるレベルなんですね」
これから全国ネット生放送でエピソードトークをする立場の芸人として、身が引き締まった。
「たぶん他のスタッフに聞いたらみんな違うエピソード教えてくれると思う、っす」
最後はほぼタメ口になりかけていたのをギリギリで踏みとどまってくれたらしい。だが、それよりも気になる点があった。
「そんなドジエピソード持ってるプロデューサーが、この特番仕切れるんですか。しかも生放送で」
プロデューサー批判に聞こえないよう、おどけた口調を強調して訊くと、
「幸良P、ドジだし仕切りは苦手だけど、テレビへの愛は人一倍なんすよ」
そう言ってピンマイクをしっかりセットすると、音声さんはぱんぱん、とおれの背中を叩いた。
「声、震えてますけど。頑張ってください」
一瞬、おれは自分がかけられた言葉を理解できなかった。ひょっとしてこの音声さん知り合いだったのか? と思ったがそれはない。おれの記憶にこの人の顔も声も存在しない。初対面だ。
初対面の二十代の青年スタッフに、気安く背中を叩かれて軽々しい応援の言葉を吐かれる。その行動の意味をもう一度咀嚼して、ようやく理解した。
そっか。
おれ、舐められてんのか。
「今日の衣装は、スーツなんすね」言外のニュアンスをわざとらしく込められる。やはり気を遣う相手として見なされていないのだ、と受け止める。
「まあ、トーク番組なんで。スタイリストさんが選んでくれたんです。『すべらない話』とかも、やっぱみんなスーツじゃないですか」
「えー、絶対あの衣装で出るべきでしたって。じゃないと視聴者、誰かわかんないですよ?」
最近のスタッフさんってこんなにぐいぐい来るの? という尻込みと同時に、それもおれが舐められてるからだとすぐ解答が出る。本番三十分前にしてもう精神がすり減って消えてしまいそうで、すぐにでもこのやり取りを終えたいと思っていたところに、おれとも音声さんとも響きが違う、ハリのある声が飛んできた。
「うい、仁礼。久しぶり! 元気しとった?」
この特番のMC、滝島さんだった。細長い体軀にばっちり沿ったオーダースーツの光沢と、決して顔で魅せるタイプではないのに、そこに立ってるだけで華がある濃い目鼻立ち。
「滝島さん、お久しぶりです!」
おれは顔を上げたまま、可能な限り深々と頭を下げた。メイク室でも会わなかったし、楽屋挨拶に行ったときもちょうど寝ていらっしゃるタイミングだったのでまだ挨拶出来ていなかった。
「滝島さん、ピンマイク失礼します」
「はいよろしくお願いします」
音声さんの顔からさっきまでおれに見せていた軽薄な表情が消え、引き締まった顔と丁寧な手つきでピンマイクをつけていく。おれが舐められていたという事実がより際立った気がして精神がまた一センチすり減る。
音声さんが手際よく作業を終えて立ち去っていったのを見送ると、おれは滝島さんにまっすぐ向き直った。
「滝島さんと同じ特番に出るなんて、もうマジで無理だろうなって諦めてました」
「そうよなぁ、俺もあの一件あってからほとんどレギュラー飛んだしなぁ」
滝島さんが自分でその件に触れるとは思わなかったので、焦る。数年前に暴露系インフルエンサーに抜かれたスキャンダル。そういえば、おれとは別の意味で滝島さんとの共演が珍しいあの人の名前が出演者一覧の中にあったな……と思い至る。この辺には触れてはいけないスイッチがいくつか眠ってそうな気がして急に怖くなり、とにかく明るく返す。
「いや、どう考えても滝島さんじゃなくておれ側の問題でしょ! 深夜番組とか含めても、テレビに出るの数年ぶりっすよ」
「潜ったなぁ」滝島さんは感慨深げに「お前が売れて番組出まくってたころに一回、収録終わりに飲み行ったことあったよな。あれは三年前くらいか」
「いや、七年前です。七年前の十月六日金曜日。おれが滝島さんの番組にゲストで出させてもらった日です」
「もうそんなに経つか。てか、相変わらず記憶力良すぎるやろ」
「時が止まったのかな、ってくらいスベった収録だったんで、印象深くて覚えてます」これはちょっと噓だ。時が止まったのかなってくらいスベった収録なんていくらでもあるから印象深くもなんともない。単純に、おれがあらゆることを覚えているというだけだ。
「せやせや。あまりに哀れで、俺から誘ったんよな。俺が後輩誘うの相当珍しいからな」
「スベったおかげで滝島さんと飲みにいけたって考えると、案外不幸中の幸いっていうか、逆にもう“幸い中の不幸”だったのかもしれないです」
「どういうことやねん」まだMCとしてのスイッチを入れてはいないらしく、テレビ画面越しでいつも見るようなシャープなつっこみは飛んでこない。ゆったりと微笑している。そりゃそうだ、前室でばりばり肩回してるMCは何か嫌だ。
「緊張してるんやろ」
滝島さんが悪戯っぽく言った。その視線の先には、おれが身体の前で組んだ手。小さく震えている。
「いや、そりゃ緊張しますよ。ただでさえ超久しぶりのテレビだし、生放送だし、しかも内容が内容だし……」
「確かに、ブランクあっていきなりここに放り込まれるって、無茶苦茶シビれるな」
「ほんと、今回の特番も何で呼んでもらえたのか全然分かってなくて……けど、たぶんこんなチャンスもう二度と来ないから、絶対に摑みたくて」
この特番で爪痕を残すこと――それがおれの今日の使命。
この仕事が決まったときの、相方の顔と激励の言葉が浮かぶ。
――この特番で流れ変えるぞ。ぜったいにカマせ。間違っても一ターン目追放だけは避けろ。
本当なら自分が出たかった、という思いが表情筋を支配していた。おれも相方が出た方が良かったと思う。マネージャーも相方が出た方が良かったと思ってたと思う。
「呼ばれたからには、全力でやれよ。お前が呼ばれたことにも、制作側の意図がある。俺がいくらでもフォローするから、頭使って臨めよ」
滝島さんの言葉が、震える手を包むようだった。
〈アカンパニー〉というコンビの頭脳と身体は相方が担っている。ネタはすべて相方が書いているし、MC、裏回し、ツッコミ、ロケ、大喜利、ギャグ、トーク、運動神経やリズム感、顔、華、先輩づきあい――あらゆる芸人としてのスキルで相方はおれを上回っている。おれが勝てるのはクイズとかそういうのくらいで、バラエティの平場で使える武器はなんにもない。だがそれでも、この特番のキャスティング権を持ってる人はおれを選んだ。
まあ、本命の芸人に何人か断られて、スケジュール空いてて、ギャラが合って、炎上しても構わない芸人としておれの名前が挙がっただけなのかもしれないけど。
そんなおれの内心を見透かすかのように、滝島さんがおれの両肩をがしっと摑んだ。
「この特番の成功はお前にかかってるといっても過言やない。気合い入れろよ」
「いや、過言でしょ」
おれが笑ってつっこむと、滝島さんはおれの肩から手を離し、ふらふらと手を振って「俺はちょっと早めに入るから」と言ってスタジオへと入っていった。
前室には、まだ共演者は誰もいなかった。前室での立ち振る舞い、どうしてたっけ。あの頃はいつもスケジュールに隙間がなくて、時間ギリギリに局入りしてバタバタでメイクしてもらって前室に来るのもいっつも最後の方だったから、こんなに時間を持て余すこともなかった気がする。どうしよう、ディレクターさんに話しかけてみるか……と思案しているところに、
「おはようございまーす。今日はよろしくお願いしまーす」
からっとした挨拶とともに、京極バンビちゃんが現れた。しっかり巻かれた肩までの金髪とカラフルなネイル、おそらくカラコンで増幅されている眼球と、その眼球の直径よりさらに長そうなつけまつげ、ラメできらきらしたシャドー。ギャルタレントそのもののいでたちだが、そのこてこての風采よりも笑顔の晴れやかさの印象が勝る。
今日の共演者を知らされたときに、二番目に驚いたのがバンビちゃんだった(一番は勇崎恭吾さん)。テレビで見ない日はないし、TikTokとインスタとYouTube、三つともフォロワー・登録者数が百万人を超えている売れっ子――こんなリスキーな番組に出るようなタレントじゃない。
バンビちゃんはこの空間にまだおれしかいないことをみとめると、おれの方へつかつかと歩み寄って来た。
「初めまして、〈勇崎オフィス〉所属の京極バンビです。楽屋挨拶行かせていただいたんですけど、ちょうどいらっしゃらなかったみたいで。今日はよろしくお願いいたします!」
しっかりした直立からの深々としたお辞儀。ギャルの見た目から繰り出される百点の挨拶だった。芸歴がおれより浅いとはいえ、売れに売れているタレントにここまで丁寧にされると逆に恐縮してしまう。
「よろしくお願いします。〈アカンパニー〉の仁礼です。楽屋いなかったのは、トイレ行ってたときかも。全然気にしてないっていうか、もうおれの方が挨拶行かないといけないくらいなのにごめん」
「なに言ってるんですか、あたしアカンパニー超好きですよ。ネタめっちゃ真似してました」
「うわー、ありがと。今活躍してる子にそう言ってもらえると嬉しい。京極さんこの間の『さんま御殿』見たけど、もはや貫禄あったもんね」
「バンビでいいですよ、仁礼さん」にっこり。「仁礼さんって下の名前、なんで左馬って言うんですか? 芸名ですか?」
芸歴八年目でまっすぐ芸名の由来を問いただされると少し気恥ずかしい。
「深い理由はなくて、ノリで決めちゃったんだけど。下の名前を敬称にしたいなって思ってつけただけ。MCのめっちゃ先輩の人からも仁礼さま、って呼ばれたりしたら面白いかなって」
「いや、アクセント違うし。変な人ですね、仁礼さん」バンビちゃんはけらけらと笑った。おれは単純なので、それだけで身体があったまってくる。
「ま、あたしのも響きが可愛いからつけただけなんですけど。バンビって鹿だから、鹿と馬であたしたちお馬鹿コンビですね」
出会ってまだ数十秒なのに、もうすでに打ち解けているような錯覚を覚える距離感。売れても腰が低いし、それでいて懐に入り込んでくる人なつっこさもある。そりゃ売れるよな、スタッフさんにも気に入られそうだ。
「バンビちゃん、めちゃくちゃ忙しいでしょ」
「おかげさまで、昔よりは。けどあたし、どのお仕事よりもこの番組がいちばん緊張してるかもしれないです」
「ああ……それは間違いないね」
「昨日の夜とか今日の台本の最初のページずっと写経してました」
「いや、最初のページほぼ滝島さんのMCでしょ」
バンビちゃんの距離感につられて、おれも気安くつっこみを入れながら笑う。すごくリラックスできてる気がする。
「え、でも仁礼さんも台本ちゃんと把握してますね」
「おれ、一回見たものとか聞いたもの、忘れられないんだよね」気がつくと、あまり人に話さないことまで話してしまう。「全部きれいに覚えちゃうから。台本もすぐ全部頭に入っちゃう」
「え、めっちゃ便利じゃないですか。いいなぁ」
「いや、これがもう地獄。スベった収録のスタッフさんの表情とか舞台で失敗したときの相方のテンパった顔とか、マジで全部忘れらんないの。風呂でシャンプーしてるときとか夜寝る前とかにちょっとでも意識しちゃうと、全然頭から引き剝がせなくて毎回吐きそうになる」
「そっか、嫌な記憶も忘れられないんだ。それは大変」バンビちゃんは口元に手を当てて驚きの所作を見せたのち、すぐに顔をほころばせて、
「でも、台本覚えれるのはすごくいいことじゃないですか。仁礼さん、まじあたしがテンパっちゃったら助けてくださいね。こういうときってマジ、芸人さんに頼りっきりになっちゃうんで」
助けてほしいのはおれの方なんだよな、なんて弱音は吐きたくなくて、とはいえ「任せといて」なんて口が裂けても言えなくて(おれはさっきまで緊張して手を震わせてた芸人なのだ)、少し話を逸らす。
「おれ、そもそも人狼が苦手なんだよね。おれが人狼やるといっつもすぐバレちゃうし、ほとんど初日に吊られるか嚙まれるし、占い師になっても変なとこ占っちゃうし」
「まあ、この番組のやつは人狼とはちょっと違うじゃないですか。占い師とか騎士とかなくて、村人と人狼だけだし」
「そうだけど……だまし合いとか苦手なんだよね」
「確かにお前、苦手そうやな」
新たな人物の登場――今日の出演者で、おれと滝島さん以外で唯一の芸人、市原さん。見ると、その後ろに他の三人の出演者たちもいた。廊下で一緒になったらしい。市原さん含め、この四人には楽屋で挨拶を済ませてる。
おれが立ち上がって改めて挨拶しようとしたところで、ばたばたと廊下を駆ける音がしたかと思うと、開けっぱなしのドアをノックして、ディレクターらしき女性が入ってきた。
「すみませーん、皆さん揃ってますかね? 良かったら直前告知用の動画撮らせてくださーい」
ジンバルを構えながら、ディレクターが言った。ジンバルによって、ディレクターの手が多少揺れてもカメラ部分はブレずにまっすぐ対象を捉える。なにごとも上手くいってる人の人生みたいだ。道を間違えそうになっても誰かが正しい道に戻してくれるブレない人生――どこかでたとえつっこみとして使えるかな? と考えてみたけどあまり生かせなそうだ。ジンバルってそこまで単語としての認知度がないから伝わらなそう。ちなみに、手ぶれを補正するための器具である。最近はYouTuberもよく使ってるのでわりかし認知度あるかな?
「じゃあ、バンビちゃんからお願いしようかな」ディレクターがカメラをバンビちゃんに向ける。
「外で撮りますかー?」バンビちゃんが廊下を指さす。ディレクターは首を横に振った。
「すみません、前室の中でお願いします。すぐ終わるんで、皆さんお手間かけますが、ご協力お願いいたします」
ディレクターはおれたちの答えを待たずに、ドアを閉めて撮影を始めた。余計な音を立てないように口を引き結ぶ。
「私が質問振るんで、それに答える感じでお願いします」
「オッケーです」
「じゃあいきます――はい、回った」
撮影開始が告げられると、すでにバンビちゃんは自然な笑顔を作っていた。
「今日は何時入りですか?」
「実は別の番組の収録があって、今日はお昼から今までずーっと局にいます。けど楽屋に置いてもらってた叙々苑のお弁当で元気チャージできてるんで、絶対勝ちまーす」
滑らかな答え。そこからディレクターの合図を受けて、番組名と開始時刻を正確に口にしたあと、「観てね!」と締める。鮮やかなコメント撮り。
「はいバンビちゃんオッケーです!」
すごいな、と思う。急にカメラを向けられて即座に正確な番組名と開始時刻とちょうどいいコメントを言える適応力、前室の地味な背景でも映える明るい笑顔――そのへんの技術にも驚いたんだけど、おれはなによりもバンビちゃんの楽屋に置かれていたのが叙々苑の弁当だったことに衝撃を受けていた。なにしろおれに支給されたのは小指の爪くらいの唐揚げがころころ入ってる中華の弁当だったから。全然お腹いっぱいになれてない。
とはいえ、おれにだって、「この芸人さんをもてなそう!」という意志を感じるいい弁当が出されてた時代もあった。七年前。でも今となっては、京極バンビと仁礼左馬では、タレントとしてのランクが違うということなのだ。分かってはいたけど、やっぱり悲しい。
だがおれの思考はつねにポジティブに流れるように重力を操作してあるので、思い至る。もしタレントとしての格ではなく、役割の違いで区別されていたとしたら? この番組では、明らかに人狼側の負担がでかい。人狼側がとんちんかんなムーブをすれば番組自体が成立しなくなる。そのプレッシャーは尋常じゃないはずだ。実際おれも七年前の全盛期にはスパイ系の番組とかドッキリの仕掛け人側を何度かやったことがあるが、その収録終わりは緊張と興奮が持続してまったく眠れなかった。
バンビちゃんは人狼だから、叙々苑弁当なのか?
そういえば、台本を写経してたって言ってたけど……それも、人狼だからか?
そんな風に、番組外のメタな部分にも思考を巡らせてしまうくらいには、おれは本気だった。本気だからこそ、手も震える。このチャンスを逃すわけにはいかないのだ。
「はい、それじゃあ次は仁礼さん、お願いしますね」
ディレクターにカメラを向けられ、反射的に笑顔を返す。
「はい、回った」
ディレクターの合図とともにカメラのランプが光ったのを見て、芸人のスイッチを入れる。声をしっかり張って、画面越しでも熱が伝わるくらいに大きく分かりやすい声とアクションで。
どんな質問でもばっちりちょうどいい答え返しますよ、という意気込みで身構えた。だが。
「今日は何年ぶりのゴールデンですか?」
いきなりの質問に面食らい、ちょっと間が空いてしまう。
「あー、五年ぶりくらいですかね」
しかもちょっとかっこつけて気持ち短めの数字を言ってしまう。まあ別に誰も気づかないでしょ、と自分の中で解決したものの、ディレクターはこちらの予想をさらりと超えてくる。
「実は、番組で調べたんですけど、実に七年ぶりとのことですよ」
「うわ、はっず。勘弁して下さいよ」
「この七年でいろいろ改築したりしてるんで、楽屋まで迷ったんじゃないですか? ちゃんと時間通りに着きました?」
「いや、そこまでばかじゃないですって。ばっちりオンタイムで来てますよ」
「一発屋として、芸能界の上も下も経験された仁礼さんですが、今日の意気込みを一言!」
「いや誰がパンパカパンマンだけの一発屋ですか! 二発目三発目ありますから! たぶん!」
あまりに予兆のない失礼さを、おそらく自分より五歳近く年下のディレクターに向けられて驚きながらもなお、おれの反射神経はいつものリアクションを出力した。
パンパカパンマン――相方が開発したリズムネタ。上半身は裸の上に祭り法被、下半身はふんどしで、底抜けに明るいお祝いキャラ“パンパカパンマン”に扮し、耳に残るメロディにのせてテンポ良く「めでたいこと」を言っていき、横で相方が餅つきで餅をひっくり返す人のようにタイミングよく合いの手やつっこみを入れていくというネタだ。ネタ番組のオーディションに初めて受からせてくれて、芸歴一年目という異様なほど早いタイミングでおれらを売れさせてくれたネタであり、おれらを世間に認知させてくれたネタであり、おれらの存在を食い尽くして世間を飽きさせたネタである。
ゴールデンのトーク番組やネタ番組、クイズ番組(これが一番楽しかった)、朝とお昼の帯の情報番組、BS、ローカル、インターネット番組、ドラマに本人役で出演したこともあった。ラジオも始まり、雑誌やらWEBメディアやら地元紙やらのインタビューもたくさん来たし、営業の数も爆発的に増えたし、広告代理店のコピーライターが書いたネタでCMもやった。
スタンプラリーのようにあらゆる番組を一周するうちにネタをやりすぎておれも相方も飽きてしまい、少し違いを見せようと“お祝いキャラ”を“呪い”キャラに変えてやろうとしたら呼んでくれたプロデューサーに手で大きくばってんを作られ、怒られた。マネージャーにそのことを相談したらマネージャーにも怒られた。リズムネタで流行っているときは一周するまでネタを変えないのが鉄則、なぜなら制作サイドはあくまでそのネタをさせるためにおれたちを呼んでいるから。おれは芸人って面白いことさえすれば喜ばれるんだと思っていたが、面白いにも色々種類があって、どの種類の面白さを求められるかを見極める目が必要だと知った。なんだか狭っ苦しい話だなと思いながらも、乗っている波から飛び降りる勇気はなかった。
だが、飛び降りるまでもなく、波は勝手に崩れた。リズムネタは数を作れないので飽きられる。いや、飽きられる前に“旬が過ぎた”と見なされる。リズムネタの賞味期限はレバ刺しくらい足が早い。“旬”“いま人気がある”“いま流行ってる”という理由だけで舞い込んでいた仕事は、びっくりするほどぱたりと消えた。
それでもおれらは、ふつうのネタを真面目に磨いていけば、得た知名度を元手にまたTVに出れると思っていた。違った。リズムネタや特定のギャグで流行りきってしまうと、そういう芸人の枠に入れられる。世間からも、スタッフからも。あのリズムネタの人、あの一発屋の人、という認知が植え付けられると、露骨に舐められる。いくら他に面白い漫才やコントのネタがあっても、いくら大喜利が強くても、そんなところには目がいかない。もちろん、一発屋として消費されながらも食らいついて地位を確立している芸人はいくらでもいる。ただ、芸歴一年目で身の丈に合わない売れ方をしたおれたちには無理だった。
売れると同時に大阪から東京に出てきたものの、仕事は一年で半分になり、もう一年で営業以外の仕事はすべて消えた。東京の家賃が重くのしかかってきた。
夢が叶わないことよりも夢を叶えてから底に沈むことの方が恐ろしいなんて、芸人を始めた頃は夢にも思わなかった。
「お前ら、七年は沈むぜ。でも、七年経ったらまたサイクルが変わってチャンスがくる」
そう言ってくれた先輩がいた。だいたい世の中の流れが変わって、社会の記憶がリセットされるまでにそのくらいの年数がかかるのだというのがその人の持論だった。
偶然なのか、先輩の見事な推察が当たったのか、飽きられて七年後となる今、念願の全国ネットのゴールデンに出る機会を得られた。ここで“昔リズムネタやってた印象しかないけど意外と実はふつうに力あったんだ芸人”のポジションを摑む。あの時より小さくていい、とにかくもう一度、波を起こしたい。
「それじゃあ、今日のトーク、爆発期待してます」
「でっかいくす玉、割ってやりますよ! ぱんぱかぱーん!」
言い終えたあとに数秒の無音。
「はい、ありがとうございますー」
おれのコメント撮りが終わり、ディレクターさんは次の出演者へとカメラを向ける。七年前はまだそこまで番組側がSNSに力を入れていなかったので、予告動画なんて初めてだった。勝手が分からないし、手応えも判然としない。
おれは恥を忍んで、隣のバンビちゃんにひそひそ声で訊いた。
「おれのコメントさ、大丈夫だったかな」
バンビちゃんも小さな声で「問題ないっしょ」と返してくれた。
 京極 バンビ
京極 バンビ
「おれのコメントさ、大丈夫だったかな」
「問題ないっしょ」
うるせえ話しかけんな、と思いながら、あたしは義務的にそう返した。幸い、他の出演者の事前告知Vの撮影中なので、それ以上会話を広げずにすむ。
集中したい。
人を殺すことをずっと考えてた。ぶっちゃけここ一ヶ月はほぼそれに使ったと思う。頭の中で何度もシミュレーションしたし、勇崎恭吾さんの顔を思い浮かべながら、その腹に包丁を突き立てるアクションの練習もした。例えば(したことないから雰囲気で言うけど)大学受験するなら何年も勉強してから本番に臨むわけじゃん? なら人を殺すのにもほんとはそれくらい準備が必要だと思う。人殺す子の方が受験する子よりずっと少ないんだし。本当ならもっと入念に準備を重ねたかったけど、こういうのはタイミングとか縁が大事だから仕方ない。
あたしはこの殺人を成功させてみせる。本当だったらこんなの出れば出るだけ自分の賞味期限を早めるタイプの番組なんだし断った方がいいに決まってる。けど殺人の舞台としてなら話は別だ。これで面倒事は清算して、あたしの実力も見せつけて、次のフェーズにいく。一石二鳥だ。
透明ガラスで仕切られたこの前室から、勝負は始まっている。本番まではあと三十分弱くらい。
あたしは心を落ち着けるために、いつものルーティン通りに、事前にSNSや公式サイトで確認しておいた出演者の情報を脳内で再確認することにした。
いまインタビューを終えたのは仁礼左馬、あたしより七つ年上の三十三歳。ニックネームをつけるなら“一発目が早すぎた一発屋”。直近出演は特に見当たらず。劇場出番がときおりあるくらい。
若くして売れるとろくな事がない、というのはうちの社長の言だが、それは本当にその通りだと思う。実力がないのにキャッチーさだけで売れてしまった、ある意味哀れな芸人である。何も考えてなさそうな柔和な顔と、悩みとかないんだろうなって思わせる肌つやが印象的。
仁礼は自分のインタビューの出来を心配するように、他の出演者の撮影を見守っている。
「今日は何時入りですか?」
あたしや仁礼のときと同じ質問を投げるディレクター。インタビューに答えているのは、“コンパ(笑)開きまくり芸人”市原野球、四十一歳。直近出演はバラエティ多数。ぜんぶひな壇かロケVTRでMCはなし。
「そら、指定された十八時に入りましたよ。プロデューサーから絶対に遅れないよう言われましたからね」
関西出身、芸歴十九年目のお笑い芸人で、数年前にコンビが解散して以降はお笑い芸人というよりタレント寄りの活動に軸足を置いているっぽい。その交友関係は芸人のみならずタレント・スタッフと幅広い。薄めの茶髪をソフトモヒカンに近しいツーブロックに刈り上げていて、四十を超えてもチャラさを脱臭できていないことの表明のよう。
「市原野球です、よろしく。バンビちゃん、もしよかったら今度飲もうや。将来ぜったいハネる俳優の卵とか放送作家連れて行くから」「はは、どうも」――楽屋挨拶に行った際、そんなやりとりを交わして閉口したのを覚えている。シンプルに、俳優の卵も作家も興味ない。
市原はカメラに向けてメイク室で起きたできごとを短くまとめて話し、軽くウケをとって締めていた。さすがの力量。
「次は村崎さんお願いします。今日はなんとレコーディング終わりらしいですね?」
「そうっすよ! マジ、体力全部スタジオに置いてきて空っぽなんで、一人だけハンデありで闘うみたいな感じなんすけど」
カメラに向けて甘ったるい声で文句を言う、“女優抱いてきた系バンドマン”村崎要。二十一歳。直近出演は『Mステ』『CDTV』などの音楽番組のほか『ボクらの時代』など。
ロックバンド〈幾星霜の待ち人〉のギターボーカルで、TikTokきっかけで売れたタイプ。アイドルに提供した曲がヒットしたりもしてるので金はありそう。芸人の音ネタに協力したりもしていて、市原と同じく交友関係が幅広い。色白マッシュヘアーに線の細い体軀、サブカルチャーを背負う気概の見えるルックス。可愛い顔して、インスタライブとかツイキャスで配信してるときに、言っていいラインと駄目なラインを見誤ってときおり炎上してる。曲調も顔もバンド名のセンスも、全ての要素があたしの好みとは完全に合わないので逆に清々しいくらいだった。
『初めまして。今度かなかな(村崎くんのことです)と共演されると思いますが、放送中以外は彼に近づかないで下さい。あの子四、五歳年上の共演者がいるとすぐ子犬みたいについていっちゃう癖があるから、京極さんにも迷惑かけちゃうかも(汗の絵文字)』――この特番の出演情報がオープンになってから、そういう主旨のDMが数通届いた。母親目線の痛いファンを多数擁するモテバンドマンとして理解した。心配しなくても年下には興味ないよ。
村崎は絶対観てねー、という捻りのないメッセージで締めて撮影終了。
次のインタビュイーは“平成の中女優”清水可奈。三十八歳。直近出演は連ドラ脇役多数、あとは公開を来週に控えた映画『恋の苑』。主人公の叔母役。
「清水さん、今日はけっこうメイクに時間かけられたらしいですね?」
「ゴールデン特番なんてほとんど初めてなので、ちょっとヘアセットに気合い入れたくて。皆さんより一時間早めに入らせてもらいました。ふふ」
子役時代から数えて芸歴三十六年目の大先輩だが主演は十年前のよくわからんVシネのみで、基本は脇を固めるポジション。あたしもけっこう映画とかドラマを観てる方だし彼女が出てる作品もそこそこ観たことがあったが、見終わったあとにまったく印象に残らないタイプのバイプレーヤーだという結論。ただ有名どころの役者と共演しまくってるので交友関係は広そう。
いくつか質問を受けて、当たり障りのないコメントで終了。まあ、この人には集客力、特にSNSでのパワーはほとんどないだろうから番組側も期待してないだろう。
「それじゃあ最後、もち子ちゃん。どうですか、今日はなんとフェス終わりに来てもらってるみたいですが」
「村崎さんが体力空っぽって言ってましたけどぉ、わたしもマジで声出ないかも」
最後は“大喜利ができる(という触れ込みの)アイドル”町田もち子。二十四歳。直近出演は『Mステ』『バズリズム』や『ゴッドタン』。
喋ったことはないものの、この子はよくTVで観たことがあったし印象もあった。名前だけは聞いたことあるな、くらいの位置のアイドルグループでお笑い担当、というポジらしい。グループより個人が売れてるパターンだ。
印象に残っていた理由は簡単で、大喜利ができるアイドル、という売り文句が海藤ひるねのことを想起させたからだ。ひるねのことは今でもたまに思い出す。同じ事務所の戦友。よくバラエティのひな壇で共演したし、あるいはスケジュールを仮押さえされて、結局バラしになったような仕事にひるねがキャスティングされていた、ということもよくあった。喋れる若い女の子、というポジションが同じだったのだ、当時は。
ひるねを側で見ていたから分かる。町田もち子の実力はひるねに遠く及ばない。大喜利が強いといってもたまに天然系の回答ではねるだけで打率は低いし、レスポンスも早い方ではない。だからこそ、ひるねが手を出していなかった下ネタや悪口系のコメントでフックを作っているが正直見てられない。今日も大して芯をとらえてない、上っ面だけを粗く叩くだけの悪口をいくつか言って帰るのだろう。そもそも、アイドルとしての華も、ひるねとは比べものにならない。
もち子はウィスパーボイスで「爆弾発言しちゃうかもぉ」と煽って締めた。
「皆さん、ご協力ありがとうございました! 告知VTRはすぐに番組公式の各種SNSで投稿させていただきます」そう言ってディレクターは足早に前室を出ていった。これから動画をチェックして軽く編集して投稿するのだろう。もう本番まで時間はそんなにない。忙しいことだ。
出演者を見回してみて、改めてこの中に入ってトークとだまし合いの勝負をすると思うと、気が重かった。エゴサをしてると、出演前から「え、バンビちゃんと勇崎恭吾出るの。神回じゃん」「バンビちゃん出すとかキャスティングやばすぎ」「バンビちゃん仕事選んで」みたいな投稿がいくつも引っかかった。
仕事は選んでるよ。厳選に厳選を重ねてるよ。
撮影が終わって他の出演者たちが会話を始めたので、かったるくなる。トイレに行くといって前室を抜け出した。
「おお、バンビ久しぶり。元気してるかぁ?」
振り向くと、編成局長の山田がばっちりホワイトニングされた歯を見せながら近づいてきた。この局でどの時間に何の番組が流れるか、というTV局の根幹部分の決定権を持つ人間である。めちゃくちゃ偉い人なので気をつかう。山田に対してというより、山田と話している様を他のタレントや局員に見られることに。変な誤解を生むのは避けたい。
幸い、トイレ前に人気はなかった。
「お久しぶりです、山田さん。いつもありがとうございます」
深い挨拶はせずに定型として自然な程度に留める。山田もそこは分かっているようで、微笑みながら頷いたのみだった。
「さっきのスタジオの騒ぎ、聞こえた? うちのコーラちゃんがド派手に転んで、まさかのビリビリ椅子に手ぇついちゃって。スタッフも笑いこらえんのに必死よ。その後も騒ぎながらどっかに消えちゃうし。昔っから、お騒がせ制作女子なんだよねぇ」
なにやらそれっぽい騒ぎの音は聞こえていたが、あまり気にしていなかった。身の丈に合わないゴールデン特番の統括プロデューサーの現場を前にしてテンパってたんだと思う。幸良さんはあたしがテレビに出始めたころに深夜の番組で何度か仕事したことがある。いい人・トラブル体質・この業界に十年以上いるとは思えない田舎っぽさ、という三要素しか記憶にない。またトラブルに見舞われてるのだろうが、この放送はきっちりやってもらわないと困る。
そんなあたしの心境を察してか、「大丈夫、ちゃんとやるように俺からも言っといたから」とだけ言い残して山田は去って行った。編成局長から“ちゃんとやるように”と言われるプレッシャーはサラリーマンをやったことのないあたしにも想像できて背筋が冷えたが、所詮は他人事なのですぐに背筋はぬくもりを取り戻す。短いやり取りで山田が立ち去ってくれたことへの安堵の方が強かった。
トイレから戻ると、出演者たちとディレクター数名が談笑していた。面倒くさいなと思いつつも、ここはちゃんと参加して空気を作っておいた方がいいな、と思い気合いを入れるが、あたしが入室した直後に、プロデューサーの幸良が現れた。ユニクロで売ってそうな無地のパーカーとニューバランスのスニーカーという、動きやすそうな服装をしてる。三年目のADと言われても特に疑いを持たないくらいには垢抜けていない。
「皆さん、本日はよろしくお願いします」
統括プロデューサーがわざわざ前室に来るのは、番組にもよるがわりかし珍しい。とはいえ、あたしは幸良の口から発される言葉の予想はついている。
「皆さんにお伝えしないといけないことがあります」
「何ですか、かしこまって」村崎が茶化すように肩をすくめる。
幸良は雰囲気を壊さないよう曖昧に微笑みつつとはいえ不真面目に見えない程度に真剣な目を保ちつつ、みたいなこと考えてんだろうなーって表情で、
「本日の〈語り手〉の一人である勇崎恭吾さんが、遅刻されています。到着時刻は、現時点で分かっていません」
幸良からの宣告により、場はあからさまに騒然となった。
「うっそ、冗談でしょ?」「ドッキリとかじゃなくて?」「やばいでしょ、もう本番始まるって」
うるさいな、と思いつつ、あたしもしっかりと演技して驚きを表現する。「え、社長遅刻? マジぃ?」
幸良は本当です、と短く言った。
「本番は、勇崎さんなしでスタートします。間に合い次第合流ということで、皆さんには臨機応変な対応をお願いすることもあるかと思いますが、よろしくお願いします」
遅刻じゃなくて、欠席なんだけどね――なんせ死んでるから。
あたしは脳内で笑いながらも、表情に出ないように気を張る。他の出演者たちと同じように、当惑とほんのちょっとのわくわく感――こういう自分起因じゃないトラブルには高揚してしまうのがタレントの性だ――を織り交ぜた顔で、幸良の言葉に耳をかたむける。
「ごめんなさい、時間がありません。とにかく、皆さんは元々の進行通りにやっていただいて大丈夫です。MCの滝島さんとは先程話を詰めていますので、勇崎さんまわりは彼が何とかしてくれます。スタンバイお願いします」
自信なさげながら有無を言わせない、というなかなか難度の高そうな口調で、幸良はスタジオの方を手で示した。ここでうだうだ言ってても時計を止められるわけじゃないことくらい、全員分かってる。出演者たちは素直に従ってスタジオ入りした。演者さん入られます! というADの威勢のいい声がスタジオに響く。
セットの裏に回り込む形で、待機場所まで先導される。よほど遅刻の件でぴりぴりしてるのか、幸良の表情には笑みが一切なかった。
「それでは――よろしくお願いします」
本番五分前ー、というよく通るタイムキーパーの声がスタジオに響いた。
独特の緊張感が、セット裏に漂う。
「生放送って、こんなギリギリに入るもんでしたっけ」
仁礼が市原に小声で尋ねている。市原より先にバンドマンの村崎が口を開く。
「演者を待たせないように配慮してくれてるんすよ。歌番組とかだと、ギリギリまで楽屋で声出ししてる人もいるし」
「おれはもうちょい余裕持ってスタンバイさせてくれた方が安心するんだけどなぁ」と仁礼。
「まあ、今回はさすがに緊張しますよね。歌番組の生放送はせいぜい歌詞飛ばすとかそのくらいの失敗しかないけど、この番組はマジで一歩間違えたら大炎上しちゃいますもん」
「てか、勇崎さんの遅刻もかなり話題になりそう」仁礼が勇崎さんの件に触れる。「生放送で遅刻って、なかなかえぐいよね」
「勇崎さんって時間に厳しい方ですよねぇ。前に『情熱大陸』の密着で観ましたよ、“俺は売れてからも仕事で人を待たせたことはない”って」もち子が参加してくる。「全国に遅刻がバレるの、めっちゃ恥ずかしそう。所属タレントとしてはどうなんですか、バンビさん」
煽り気味に話を振られて苛つくが、この程度のことで感情を波立たせてたら今日の生放送なんてやっていけない。あたしはしれっと、「まあ、忙しい人なんで」と内容のないコメントをした。そこでふんわりパーマのADの男子があたしのマイクを直しに入ってきたので、それ以上会話せずにすんだ。
「尺とかどうするんだろ、勇崎さんもトークする前提で二時間組んであるんだと思うけど」と清水。舞台もやってるからか、尺への意識があるらしい。
「長めにトークした方がいいんですかね。幸良さんから何の指示もなかったけど」と仁礼。お前にそんな調整するスキルないだろ、と言いそうになるのをこらえる。
「まあ、何かあったらカンペ出るやろ。こういうトラブルのときは他の演者が落ち着きつつ臨機応変にやればええねん」
市原がベテランらしくまとめたところで、「本番十秒前!」というADの声が聞こえる。
「五、四、三――」カウントは三まで。きっかり二秒後、音楽が流れ出したかと思うと、MCの滝島がタイトルコールを高らかに宣言する。
《ゴシップ人狼、2024秋ぃー!》
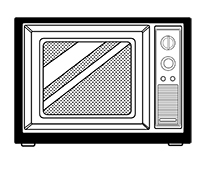 甲斐 朝奈
甲斐 朝奈
《ゴシップ人狼、2024秋ぃー!》
MCのタイトルコールで番組が始まる。テレビを見るのなんて、いつぶりだろう。なんとなく受け取る情報量を減らしたくなって、テレビの持ち主である小羽石さんに「音量下げられますか」と尋ねた。
「うるさかった、かな?」
気まずそうな小羽石さんに、首を振る。
「いえ、ただちょっと、大音量で受け止めるにはまだ心の準備が出来てないというか……これから、出演者の人が、いろんなゴシップの話をするんですよね?」
「まあ、そういう番組だから」
「すごい番組ですよね」
「そうだね。だいぶ攻めてるよ。イニシャルトークになることもあるけど、実名出すときもある。事前の許可取りもほぼしてないし。文春みたいな週刊誌ですらちゃんと事前に通達するのにね」
画面にはMCだけが映っており、番組が第八回、四周年を迎えたことへの感慨や、この番組がいかに尖ったものであるか、八回も続いていることが奇跡であるというようなことを述べていた。
「本当に、観る? 消してもいいけど」
手元の機器で音量を下げながら、小羽石さんが不安げな顔をした。
「いえ、見ますよ」
《この芸能界という村で生きる七人の〈語り手〉たちに、ルーレットで指名された順にゴシップエピソードを話していただきます。ゴシップは誰に関するものでもアリ》そこでMCはただし、と間を置いた。《この村にはわるーい噓つきの人狼がいるのです。人狼は噓のゴシップエピソードしか語りません。ですから、ここで語られたエピソードが本当なのか噓なのかは最後まで分かりませんのでご注意ください》
「ああ、最後まで視聴率を維持する狙いってことですよね」
「そうだね。番組中にネットニュースにされるのとかを防ぐのもあるかも」
《“語り手”たちは互いのエピソードを聞いて裏切り者を見つけ出し、追放することを目指します。勝利した“語り手”には賞金二百五十万円!》
賞金二百五十万。“公開の場でゴシップを話す奴”と見なされるリスクと釣り合う金額なのか、わたしにはよく分からない。単純な確率にすれば賞金を手にできるのは七分の一なので、期待値としては四十万円にも届かないと考えると、さすがに釣り合わない気がしてきた。
《そしてこの『ゴシップ人狼』、今回は四周年記念ということでまさかの暴挙に出ました――なんと、二時間まるごと生放送でお届けいたします》
生放送、に力強くアクセントを置いた言い方。
《トーク中心のゲームをやる番組としては異例、しかもゴシップを語るわけですからね。炎上を恐れない、屈強な精神を持った者しか参加できないと言えるでしょう》
「こういう、公式側が“前代未聞”とか“いかれてる”みたいなスタンスで煽ってくる感じってちょっと冷めますよね」
わたしの言葉に、小羽石さんは苦笑しながら、
「いや、まあそれは分かるよ。やたら公式側のテンションが高かったり自虐したりするのって萎えるよね。ただ、この番組は実際本当にイカれてると思うよ。最初生放送でやるって知ったとき、よく企画通ったなって思ったもん」
《さあ!》
MCが視聴者の注意を引くための間投詞を言い放ち、カメラが切り替わる。セット内に組まれた入場ゲートが映される。
《それでは、こんなクレイジーな番組のオファーを受けてくれた、クレイジーな“語り手”たちをお迎えしていきましょう。まずは一人目――》
※続きは単行本『なんで死体がスタジオに!?』(森バジル著/文藝春秋刊)でぜひお楽しみください!
※『なんスタ』グッズが当たるキャンペーン実施中!
#なんスタ #バジル推し で感想を募集しております!
詳しくはこちらをご覧ください。
















