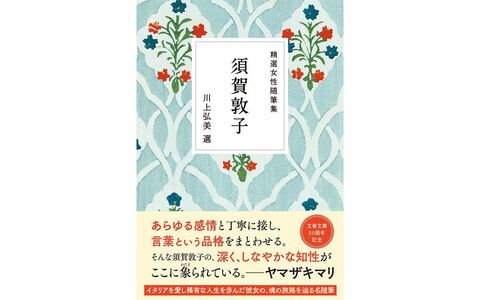白洲正子の流儀とは何か
傑出した人間と面と向かうのは心労だから、その人の凄さを感じつつも横で眺めておくようなつきあいで済ましておいて、後になってからさも近しくつきあったごとく他人に、あの人は凄い人であったと吹聴するような狡(ずる)さを、断じて許さなかったのが白洲正子だった。いつも逃げずに真正面からその人間に近づいてゆく。時に、人が普通接近する際に保つ距離を超えて。
しかし、同時に白洲さんは、面と向かうだけでは人も物も見えてこないということも熟知していた。人なら時間をかけて丁寧につきあう。物なら身辺において何年も眺め、いじる。そして風景なら同じところに何遍も繰り返し足を運ぶ。意識的に、無意識的に、さまざまな局面に接して見る。見たものを書くのではない。見えてくるものを書くのだ、というのが白洲正子の流儀である。本書を読まれた方々はその消息を理解されるだろう。そうした流儀を彼女はいかにして獲得したのだろうか。
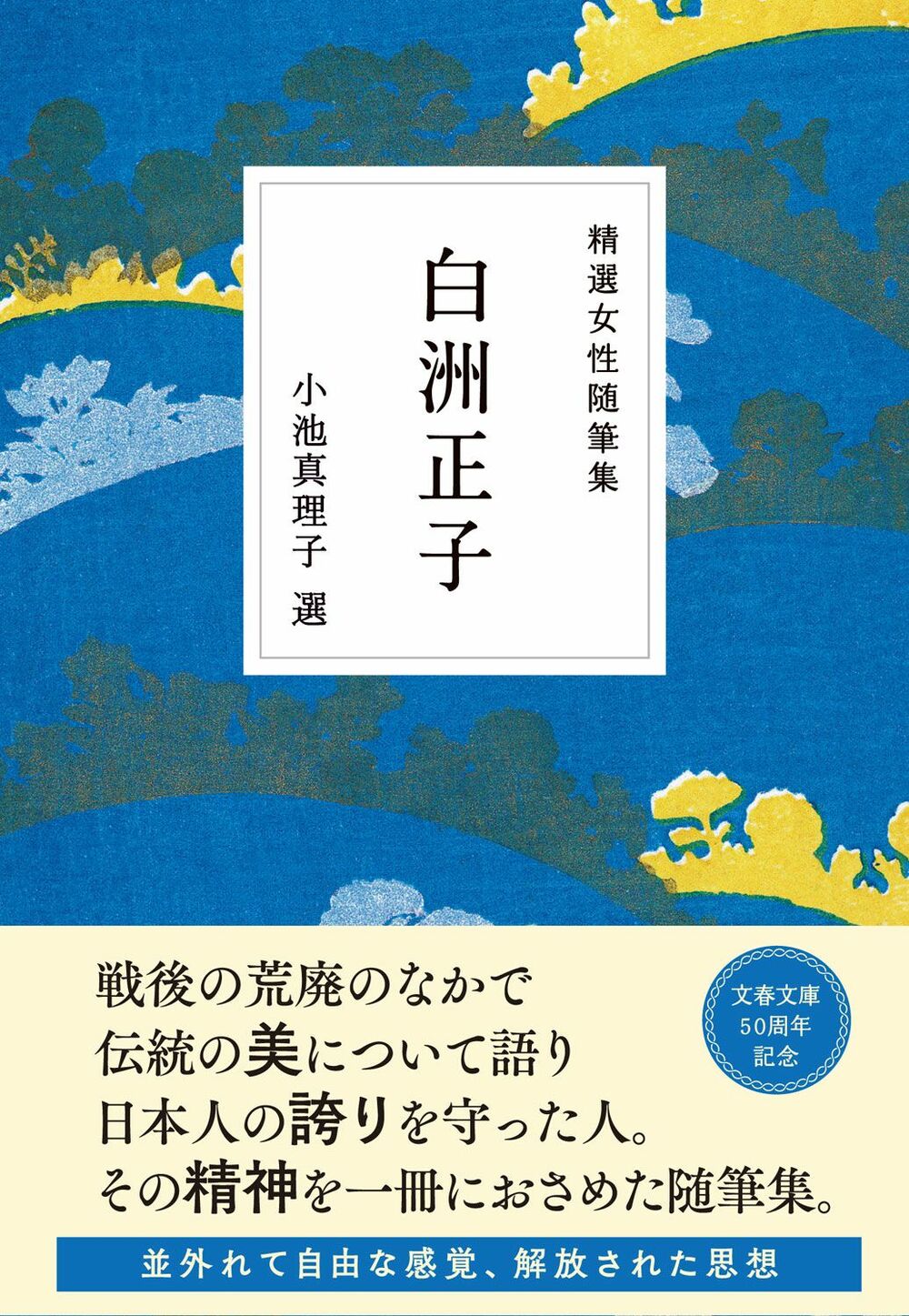
華々しい生い立ちと白洲次郎との結婚
白洲正子は一九一〇年、樺山愛輔(かばやまあいすけ)・常子の次女として東京永田町に生まれた。母方の祖父川村純義(すみよし)も、樺山愛輔の父の樺山資紀(すけのり)も薩摩藩士として明治維新を経験し、明治新政府の軍人として功績を上げた人物である。樺山資紀は若き日には薩南示現流(じげんりゆう)の使い手、軍人・政治家としては山縣(やまがた)内閣、松方内閣の海軍大臣、内務大臣、文部大臣等を歴任した(本書所収の「晩年の祖父」)。
父樺山愛輔は、若き日にアメリカ、ドイツに留学し貴族院議員や枢密顧問官を務め、国際交流、文化行政に力を尽くした。ジョサイア・コンドルの設計した永田町の洋館(「坂のある風景」)の応接間の壁には、黒田清輝(樺山家の縁戚にあたる)の「湖畔」が、食堂の壁には「読書」がかかっていたという。清輝がやって来ると、父と清輝は鹿児島弁で親しげに談笑して楽しい時を過ごした。しかし、普段は正子は広い食堂で一人ぽつんと黒田の「読書」を眺めながら食事をすることが多かったという。家族で炬燵(こたつ)に入ってミカンを食べる一家団欒とか、親父のドテラ姿も知らない、恵まれてはいても、一方で同世代の少女が当然経験していて当たり前の日常の欠落している少女でもあったようだ。おそらく日本の近代化のありようを最前線で見ていた少女であった。
十四歳のとき、アメリカの全寮制の学校ハートリッジ・スクールに入学し、十八歳で卒業しさらに上級学校に進む試験にも合格していたが、昭和の金融恐慌のあおりをうけ帰国、その直後に白洲次郎と出会い、恋愛結婚。その頃、幼い日より稽古を重ねていた能楽以外のことで、自分が日本文化にいかに疎いかということを痛感し、飢餓感をもって古典文学をむさぼり読んだり、大和路を歩き回ったりした。白洲次郎の仕事は海外を舞台にしていたから、一年の半ばは外国生活であったけれども、日本にいるときは大和を彷徨していた。
一九四〇年、白洲夫妻は鶴川村能ヶ谷に広い農地と農家を購(あがな)い、家に手を入れて一九四二年に引っ越し、結局そこがついの住処(すみか)となった(「冬のおとずれ」)。戦争中のことである。次郎は農業に挑み、正子はズボンをはいて仕舞のけいこに励んだ。夜はわずかな灯火のもとで梅若家から預かった能面の数々を眺めて暮らした。父の友人の志賀直哉や柳宗悦の勧めを受け、一九四三年には『お能』(昭和刊行会)を書き下ろす。さらに細川護立(もりたつ)の家(現在の永青文庫)に通い、古美術の講義を受け、陶磁器の魅力を知る。
西国巡礼のあと、文筆活動が本格的に
一九四五年、空襲で焼け出された河上徹太郎夫妻が白洲家に寄寓することになる。河上夫妻と白洲夫妻は軽井沢の別荘友達である。河上徹太郎は終日だまって虚空を眺めている。たまにピアノに向かうときも表情を変えずに無口で弾いているが、伊東に出かけるとなると急に潑剌とした顔になる。伊東には青山二郎がおり、そこに小林秀雄が来る。突如雄弁になる河上は青山二郎という人間の魅力を語り、小林秀雄の思考の様子、紡ぎ出される文章の魅力を語った。白洲正子はその友情に嫉妬を感じ、そこに分け入りたいと願った。彼女は能の世界では一つの達成を果たしていたが、文章を書くという行為においては未だ『お能』一冊を書き上げただけであった。
敗戦直後に白洲正子は文字通り、真正面から三人の中に分け入った。彼らに分け入る際に媒介となるのは骨董と酒である。三十六歳で酒を飲み始め、骨董を買いだした。場所は銀座、京橋、日本橋。欲望を捨象して骨董は存在しない。酒は人を修羅の世界に引きずり込む。敗戦直後の欲望と修羅の中に身を投じることによって、白洲正子は今までの殻を脱ぎ捨てようとしたのだと思う。何かを捨てないで、何が得られようか。腐心して手に入れた骨董も次から次に手放して、次なるものを求めた。拙(つたな)かろうが書いてみないことには人の批評は得られない。手ひどい批評を受ける連続であったようだが、己が批評の的になることによって、批評自体の真贋も判別する能力を身に付けたであろう。骨董が過去の世界のものだけなら、現代の工芸にそれをつなぐ仕事もしてみようという思いで銀座に「こうげい」という染織工芸の店も開いた。
一九六四年、五十四歳で西国巡礼の旅に出たのが一区切りなのであろう。以後、精力的に『栂尾(とがのお)高山寺 明恵上人』(一九六七年、講談社)、『かくれ里』(一九七一年、新潮社)、『近江山河抄』(一九七四年、駸々堂(しんしんどう)出版)、『十一面観音巡礼』(一九七五年、新潮社)、『日本のたくみ』(一九八一年、新潮社)、『西行』(一九八八年、新潮社)、『いまなぜ青山二郎なのか』(一九九一年、新潮社)、『白洲正子自伝』(一九九四年、新潮社)、『両性具有の美』(一九九七年、新潮社)等々の今も多くの人に読み継がれている本を陸続として発表した。『白洲正子全集』(二〇〇一~二〇〇二年、新潮社)全十四巻別巻一に収められている文章の大半は、中年期というよりも老年期に至って書かれたものである。
銀座の女性を偲ぶ、二つの文章
ところで、本書の選者の小池真理子さんは、むうちゃんこと坂本睦子のことを書いた文章を二編選んでいる(第一章「『いまなぜ青山二郎なのか』より」第二章「銀座に生き銀座に死す」)。第二章の文章は一読明らかなように、彼女の死の直後に書かれたものであり、第一章の方はそれから三十二年経って、三十二年前の自身の文章が書かれたいきさつにまで触れながら彼女を追想したものである。白洲正子、四十八歳と八十歳の文章を読み較べて、読者はどのような感想を持たれるだろうか。二つの文章の間には、大岡昇平の『花影』が横たわっている。
文体に多少の変化はあるが、白洲正子は変わっていないということ、三十二年間白洲さんの裡(うち)にむうちゃんは生き続けていたのだということに私は感動する。
私事ながら、あるとき「銀座に生き銀座に死す」の初出の一九五八年六月号の「文藝春秋」のコピーが白洲さんから送られて来たことがあった。前から探していたが見つからず、たまたま当時の編集長(田川博一さん)に出会ったのでコピーして貰った、あんまり辛い思いをしたし、さし障りもあったので今までどの本にも入れなかったものであること、むうちゃんは自分の唯一の女友達だったことが記されて、読んだら悪いが返送してくれろと付された手紙が付いていた。
結論を言うと「銀座に生き銀座に死す」というエッセイは、白洲正子にとって辛い思いをしたが、これで自分の腰が定まったという手ごたえを感じた文章なのだと思う。むうちゃんを語ることで青山二郎を書いたという思いもあったろう。またむうちゃんの死を自分の裡(うち)にとりこまなければ噓だという思いはもっと強かっただろう。
「無一物(むいちぶつ)」のむうちゃんは、「白洲さんて、何でも持っていらっしゃるのね」と言う。これは人生の批評の言葉である。「むうちゃんにそういわれた時、私は羞じた」と白洲正子は書く。白洲正子の愛読者は「私は羞じた」という言葉に或る切迫したリズムを感じるだろう。それは決して感情ではなく、痛みに似た肉体的な感覚である。この感覚をいかなる時に覚えるか、それがその人の感性であり、倫理でもある。その感性と倫理を白洲正子はむうちゃんとの約十年のつきあいの中で研いだという自覚の中で「銀座に生き銀座に死す」は麴町の旅館で綴られた。
一九六二年に刊行された秦秀雄の『名品訪問』(徳間書店)で、今どんなものが欲しいと思っているのかという秦秀雄の質問に対して白洲正子は「有名なものでいえば、長次郎の無一物っていうようなもの。何でもなくて、そして何もかもあるもの。平凡なものがいいね。やっぱりあきる。先にもってた志野の火入なんて、とてもいいものだけど、いま欲しいとは思わない。それで、この志野(ぐい呑みを指す)を買って、溜飲をさげたのよ。あれが手に入るまでは、毎夜のように、志野を売ったことがくやしかったの」と語っている。
白洲さんが志野のぐい呑みを手に入れた時期は、むうちゃんの死の頃のことと想像されるし、その志野のぐい呑みを眺める白洲正子の視線に、もちろん意識されることはないだろうが、むうちゃんは生きていると言ってもいいのではあるまいか。「『いまなぜ青山二郎なのか』より」の最後の数行は白洲さんにしては珍しく感傷的な文章で終わっているけれども、八十歳の老人の感傷はみずみずしい。
「私は道草が好きなのだ」
物を見る目も人を見る目も同じであるという思想は青山二郎伝来の思想だけれど、白洲正子はそれを繰り返しという方法をもって実践した。繰り返すことは時間と手間がかかるし、一見無駄のようにも思われる。が、繰り返すことによって、ものを見る人の目から、実は本質的な意味で無駄が省かれるのである。自意識も洗われ、余計なものが目に入ってこない。それを例えば本書の最後に置かれた「極楽いぶかしくは」は教えてくれる。
宇治の平等院に白洲正子は何度でかけたことであろうか。その時々で見えるものは異なる。その積み重ねの中で、見る対象は心の風景になってくる。それが歴史の風景だという信念を白洲正子は持っていたのだと思う。
白洲さんと旅行していると、ときどき突拍子もない提案を受けたことを思い出す。ルートの変更は毎度のこと、目的地の変更を移動中の車の中で提案されたこともある。「私は道草が好きなのだ」というのは定番の言葉であったけれど、それだけではないようであった。いまこの状況の中で、どこそこの景色を見ておきたいという欲求がわいてきて、そういう時に何か見えるものがあるだろうという予感のようなものがあったのではないだろうか。同行した人に「ほらね」と、予定を変更してここに来てよかったでしょ、とさも言わんばかりの嬉しそうな白洲さんの顔が目に浮かぶ。
また、景色を眺めながら言葉にならない音声を発することが多々あった。なにか口の中でむにゃむにゃ、ものを食べているような仕種をするのである。私には白洲さんが風景を食べているというふうに思われた。歴史は過去の事実の羅列ではなく、個人の心の中に再現するものであるという小林秀雄の思想を、白洲正子は自分の心の風景を描くことによって生かしていると言いたい。ちょうど室町時代の世阿弥の能に平安時代の業平が生きているように。
*こちらは2024年に刊行された『精選女性随筆集 白洲正子』(小池真理子選/文春文庫)の解説の転載です。

白洲正子(しらす・まさこ)
1910(明治43)年、東京生まれ。祖父は海軍大臣、台湾総督などを務めた樺山資紀伯爵。幼少時から能を習う。学習院女子部初等科修了後、14歳でアメリカに留学、18歳で帰国、19歳で白洲次郎と結婚、二男一女を産む。43年『お能』刊行。64年『能面』で読売文学賞(研究・翻訳部門)受賞。代表作に『巡礼の旅―西国三十三ヵ所』『栂尾高山寺 明恵上人』『両性具有の美』など。1998年12月26日逝去。